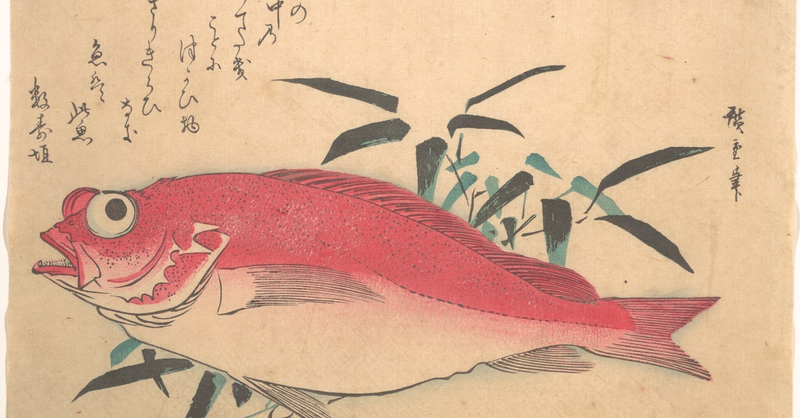
数多旅茶色の裏はふぶきかな 夏目漱石の俳句をどう読むか80
冬の日や茶色の裏は紺の山
解説は特にない。しかも宇宙全体から「ふーん」されているようで、例のひたすら無言の鑑賞にもさらされていない。つまり誰も解釈していない。
冬のある日、一面を茶色に冬枯れした山の裏側を見ると青々としていて紺色に見えたという句か。しかし山の裏に回り込むという大変な動きが詠まれた句というよりは、「きっと」が略され、「きっと紺色だろうね」と簡単に想像がされているのではないかとも感じる。
そもそも裏というからには表からしか見ていないということはないだろうか。いつも見ている面が山の面である。
それとも本当に山をぐるりと巡ったのか。
ポツンと一つ立っている山ならいいがたいていの山の裏は山の中でそうそう回り込めるものでもあるまい。紫紺の山とは山深いところの表現である。
冬枯や夕陽多き黄檗寺
この句を子規は酷く気に入ったようである。おかげさまでこの句は例のひたすら無言の鑑賞にさらされている。一度いったいどんなつもりでたすら無言の鑑賞をやっているのか訊いてみたいものだが、返事はないだろうな。実際鑑賞している本を読んでみたらひどいものだった。
この「黄檗寺」というのは解説にある通り黄檗宗の寺ということで、そのうちどれとは特定されていないようだ。
従って山寺かどうかも定かではなく、冬枯れをしているのが木立なのか山肌なのか釈然としない。
一応夕陽を集める木立、半分ぐらい明度が上がって光に溶けている景色を思ってみる。冬の早い夕陽を浴びる静かな寺のたたずまいは、漱石、子規、私がそれぞれ別の姿に思い浮かべているわけだ。
そういう意味では『鏡子の家』の夏雄の体験を待つまでもなく、世界は無意味で、固有名詞もさしてあてにはならない。
しかしどんなたまたまかで漱石と子規の間においては決してつながるはずもない画が何度も繋がっていたのではないかと疑ってしまう。今はもうなかなか寺の名前を俳句に詠み込むことが難しい時代なだけに、少し距離感を覚えてしまう句だ。
あまた度馬の嘶く吹雪哉
そのままという感じの詠み方ながら、何だか『カムイ外伝』のような寒々しい、不穏な「夜」のイメージで、改めて「夜」を意味する言葉が全く使われていないことを確認して、「あれ?」となった。
無論昼でもいいのだろうが、どうも夜の感じが消えない。嘶きも吹雪も音だから、自然と目を閉じて聞いているように感じてしまうのだろうか。そして音が気になるので寝付けないという意味を勝手に付け足してしまっているのだろうか。
しかしどうも漱石は音だけを詠んで眺めを見せていない気がする。あまた度という時間の経過、嘶く声、原因としての吹雪は馬に対しても漱石に対してもやはりヒューという寒々し気な音であろう。
視界に入るものはない。
これは寝てるな。
嵐して鷹のそれたる枯野哉
と書いたとたんに景色を持ってくる。ここには鷹がそれるくらい望洋とした枯野が広がっている。
しかし前にもあったけど天候の悪い時に鷹狩りをするかね?
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
