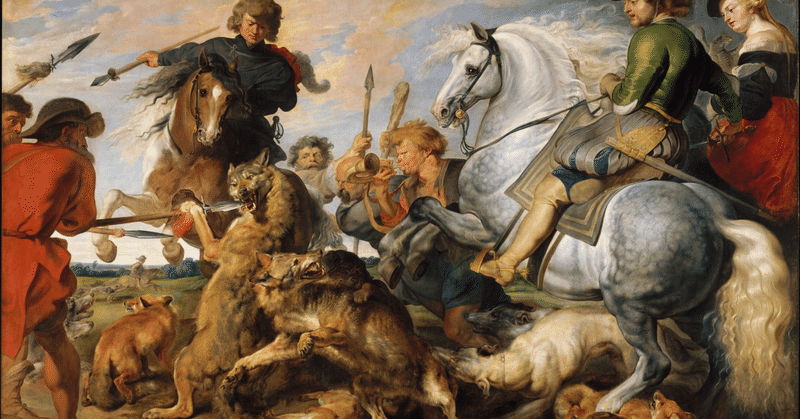
萩原朔太郎と菊池寛と南部修太郎の見た芥川龍之介
今にして、僕はこの「人間的なるあまりに人間的なる」作家――さうした作家は、今の日本の既成文壇は、全く稀有の例外である。――を考へ、愛慕の情眞に切々たるものがある。芥川君のやうな文學者は、單に天才と呼ぶべきではない。むしろ人間的生活を惱んだところの、眞の人間的作家と言ふべきである。僕は實に、日本文壇の技巧的文學に飽き飽きしてゐる。芥川君の如く、單なる才能での小説でなく、靈魂と情熱とを以て書くところの、眞の人間的文學者は、今後に於ても益々見ることが無いだらう。しかもその芥川君が、生前全く人々に理解されず、誤つて「文人」の名で呼ばれたり、甚だしきは「技巧派」の範疇で論じられたりしたことを考へると、世評のいかに妄誕であり、天才の理解されがたい眞事實を、しみじみと痛感せざるを得ないのである。然り! 芥川君は何人にも理解されず、孤獨の中に悲痛なる自殺を遂げた。
佐藤春夫に脱ぎたての猿股を貸すのだから芥川は人間的な作家である。
しかし萩原朔太郎がわざわざ「芥川君は何人にも理解されず」と書き、人間的作家だと書かねばならないのは、本人が余りに芸術的な作家を装ったためであり、実際にただ生きることよりも芸術の完成の為に命を絶ったようにさえ見えなくもないからである。
彼が、多くの作家を入れたのは、各作家に対するコムプリメントであったのが、かえってそんな不平を呼び起す種となり、彼としては心外千万なことであったろう。私が、文芸家協会云々のことに反対すると、彼はそれなら今後、印税はあの中に入れてある各作家に分配すると言い出したのである。私は、この説にも反対した。教科書類似の読本類は無断収録するのが、例である。しかるに丁重に許可を得ている以上、非常な利益を得ているならばともかく、あまり売れもしない場合に、そんなことをする必要は絶対にないと、私は言った。その上、百二、三十人に分配して、一人に十円くらいずつやったくらいで、何にもならないじゃないかと言った。私が、そう言えばその場は、承服していたようであったが、彼はやっぱり最後に、三越の十円切手か何かを、各作家の許にもれなく贈ったらしい。私は、こんなにまで、こんなことを気にする芥川が悲しかった。だが、彼の潔癖性は、こうせずにはいられなかったのだ。
この事件と前後して、この事件などとも関連して、わずらわしい事件が三つも四つもあった。私などであれば「勝手にしやがれ」と、突き放すところなどを、芥川は最後まで、気にしていたらしい。それが、みんな世俗的な事件で、芥川の神経には堪らないことばかりであった。
その上、家族関係の方にも、義兄の自殺、頼みにしていた夫人の令弟の発病など、いろいろ不幸がつづいていた。
それが、数年来萠していた彼の厭世的人生観をいよいよ実際的なものにし、彼の病苦と相俟って自殺の時期を早めたものらしい。
傑作一つ書ければ死んでもいい、あとのことはどうでもいい、というのが芸術的作家なら、三越の十円切手か何かを、各作家の許にもれなく贈るのは人間的作家である。菊池寛はこれを潔癖というが、単なる潔癖で自分の脱ぎたての猿股を佐藤春夫に貸せるものではない。なぜならいったん貸した猿股は又自分のところへ戻ってくるわけである。この芥川の猿股を人間的と呼ばないで何と呼ぶべきであろうか。
畢竟するに、私が芥川氏の芸術に対して不満を感じる根本は其処にある。即ち、私は氏が先づその智の制肘から、支配から脱する事を望みたい。書斎の外に出る事を望みたい。そして、もつと自己を裸にして芸術に、人生に対する事を望みたい。云ひ換へれば、智の境地以上の、全人間的体現を私は芸術家としての氏に求めたいのである。
菊地寛と萩原朔太郎の意見は芥川の死後のもの、南部修太郎のこの文章は大正十年四月のもの。ただしここで南部は「秋」や「秋山図」までを読んでいるので、「秋山図」が緻密な設定と知的な技巧に遊ばれているのに対して「秋」という作品が、多くのものに「転機か」と認められていることを理解しつつも、このようにいささか乱暴に突き放したことになる。
要するに、あれもこれもと当つてみてゐるやうな試みの域を脱しない、甚だ不熟な作品か、乃至は、ともすれば過去の作風の易きについた、何等の新創の無い作品ばかりだつたやうである。
私は「秋」が完成された新しい境地だとは思わない。ただもし時系列で読んでいけば、「おや?」と思わせるような作品であるとは思っている。話は現代、主人公は女、しかもこれから作家になろうかという女、そしてその女が結婚して妻になる。大事件は起きない。ただそういうこともあろうかという家庭の描かれる作品である。逆説も「あべこべ」も見当たらず、これまで個別に論じてこなかった作品ではあるが、言ってみればこういうものが人間的な作品なのではなかろうか。
間もなく信子は、妹夫婦と一しよに、晩飯の食卓を囲むことになつた。照子の説明する所によると、膳に上つた玉子は皆、家の鶏が産んだものであつた。俊吉は信子に葡萄酒をすすめながら、「人間の生活は掠奪で持つてゐるんだね。小はこの玉子から」――なぞと社会主義じみた理窟を並べたりした。その癖此処にゐる三人の中で、一番玉子に愛着のあるのは俊吉自身に違ひなかつた。照子はそれが可笑しいと云つて、子供のやうな笑ひ声を立てた。信子はかう云ふ食卓の空気にも、遠い松林の中にある、寂しい茶の間の暮方を思ひ出さずにゐられなかつた。
言われなくてはこれが芥川の作品だとは解らないのではないか、というのが『秋』である。これを「あれもこれもと当つてみてゐるやうな試みの域を脱しない」というのは少し違うのではないかと思うのだ。
その後芥川は吉田精一が「身辺雑記的私小説」と呼ぶ現代ものとして「保吉もの」と呼ばれる一群の作品をものしていく。失われたものを回顧の形式で描くというやり方で、明らかに「切支丹もの」「開化もの」「時代もの」では描かれなかった細やかな人間の感情が捉えられていく。
言ってみれば佐藤春夫に脱ぎたての猿股を渡すくらい温かく、三越の十円切手か何かを、各作家の許にもれなく贈るくらい繊細なのだ。さらにその構図は大胆にして芸術的、知的な技巧に溢れ、『芋粥』の利仁の支配が持っていた芥川独特のアニミズム的世界観が引き継がれている。
津波をあえて書かないことで日常に留まりながら、その奥に大きなドラマを仕込んでいる。
こんな傑作が一つ書けたら死んでもいい。ほかのことはどうでもいい。
【余談】
芥川は晩年に至つてはじめて自らの教養の欠如に気付いたのだと思はれます。すくなくとも晩年に於てはじめてボードレエルの伝統を知りまたコクトオの伝統を知つたやうです。その伝統が彼のものではないことを知つたのでせう。彼は自分に伝統がないこと、なによりも誠実な生活がなかつたことに気付かずにゐられなかつたと思ひます。彼の聡明さをもつてすれば、その内省が甚だ悲痛な深さをもつてゐることを想像せずにゐられません。彼は祖国の伝統からもまた自らの生活からもはぐれてしまつた孤独の思ひや敗北感と戦つて改めて起き直るためにあらゆる努力をしたやうです。一農民の平凡な生活に接してもそこに誠実があるばかりに、彼はひとりとり残された孤独の歎きを異常な深さに感じなければならなかつたものでせう。彼の生活に血と誠実は欠けてゐても、彼の敗北の中にのみは知性の極地のものをかり立てた血もあり誠実さもありました。立ち直ることができずに彼は死んでしまつたのですが、そのときは死ぬよりほかに仕方がなかつた時でしたでせう。
本来これは余談で書くようなことではないが、どうにも纏まらないので仮置きする。
この「自らの教養の欠如に気付いた」という指摘がどこぞの馬の骨なら放っておいても良さそうなものだが、相手は凡そ出鱈目に見えるが怖ろしく出鱈目な安吾である。
少なくともフランス語、フランス文学に関しては芥川が及ばない教養を持っいたことは確かであろう。その安吾から「すくなくとも晩年に於てはじめてボードレエルの伝統を知りまたコクトオの伝統を知つたやうです」と言われてみれば、一面においては確かにそうか、となる。ボードレエルを知らなきゃなんなんだとはならない。
ただそれを死と直接結びつけるのは性急だなとは思う。
伝統ねえ、と思う。
伝統、ねえ。
芥川龍之介は教養をたてなほさうと足掻いたが、その時はもう彼が足を降さうと努力しても、大地の方がむしろ足から遠のくやうな悲劇的な事態になつてゐたのだと思ふね。つまり伝統や祖国やふるさとや生活の中へ足をつけて立ち直らうと焦つたのだが、その時はもう伝統や生活や祖国の方がまるで彼を棄てるやうにあの人には見えたのだらう。あの人は死ぬ前に漸くボードレエルの伝統が分かり、コクトオやラディゲの伝統が分かつたのだ。言ふまでもなくそれは彼の伝統ではなく、おまけに彼自身は自らの伝統や生活の中に育つた眼すら持たなかつたことに漸く気付いたのだと思ふね。
この伝統の話は繰り返されており、ちょっとした思い付きではない。芥川の死の後に発表された作品群に対する安吾の直感であり、それによって芥川を発見したようなところがある。
この余談はまだ書き足されるかもしれない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
