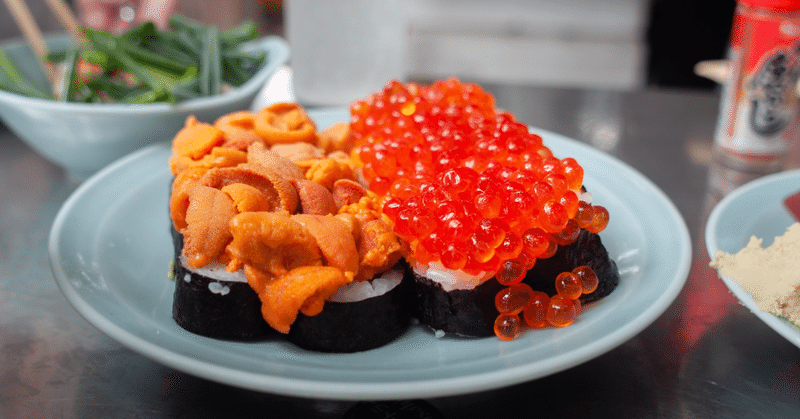
芥川龍之介の『三つの窓』をどう読むか④ 晩年
『彼 第三』
例えば川上弘美の『ぼくの死体をよろしくたのむ』に収められた『鍵』という小説を読んでみる。そうすると三十二歳なのか三十五歳なのかよく分からない鈴音という女性が六十五歳の七生というガタイの良いフリーの校閲のホームレスに初めての恋をすることに驚く。これが彼女の常套手段なのか、語り口が妙に幼いし、なにしろ三十五歳の女性が初めての恋をする話という設定に驚いてしまう。
そうしてだいたいそれくらいの年齢で芥川が自殺したのだなと考えてみる。
二万噸の××は白じらと乾いたドックの中に高だかと艦首を擡げていた。彼の前には巡洋艦や駆逐艇が何隻も出入していた。それから新らしい潜航艇や水上飛行機も見えないことはなかった。しかしそれ等は××には果さを感じさせるばかりだった。××は照ったり曇ったりする横須賀軍港を見渡したまま、じっと彼の運命を待ちつづけていた。その間もやはりおのずから甲板のじりじり反り返って来るのに幾分か不安を感じながら。……
この「新しいものにはかなさを感じる」という感覚に辿り着くほど、芥川は既に年老いていたのであろう。そしてそれは年も若いのに目の前の海に沈んでしまった△△がみせる景色だ。『三つの窓』は何物にもなれないまま死んでいった友人たちを見送る『彼』『彼 第二』に続く『彼 第三』でもあるのだ。
この三十五歳にしてはあまりにも年寄り臭い芥川を読みながら、川上弘美の『鍵』を読むとガタイの良いフリーの校閲のホームレスという滑稽な生き物が芥川の対極にはあるのだと思えてくる。あるいは六十五歳という年齢が何か悪ふざけのような馬鹿々々しいものに思えてくる。
実際川上弘美が『鍵』という小説を書いたのは五十九歳くらいの年齢の時で、その時点で描かれた三十二歳なのか三十五歳なのかよく分からない鈴音という女性は余りにも無垢で幼い。これは時代の違いではなく、単なる個人差の話だ。芥川には『ぼくの死体をよろしくたのむ』とは書けなかった。それほど無垢でカジュアルに運命を語ることはできなかった。
しかし『三つの窓』がアンニュイな死の予感漂う作品であることは間違いない。
芥川龍之介
もしも新人作家が芥川龍之介と書かれた名刺を差し出したら、誰も本名だとは思わないだろう。本名にしては立派過ぎる。若いだけあって格好つけやがってと思われるのではなかろうか。
それが本名だと知らされた後でもやはり立派な名前だなと感心する。芥川龍之介とはそんな名前だ。例えば川上弘美の『ぼくの死体をよろしくたのむ』の表題作『ぼくの死体をよろしくたのむ』には黒河内瑠理香なる人物が出てくる。
「ペンネームですか、黒河内瑠理香って?」
と、聞いたら、
「ちがうわよ、本名。ミステリー作家になるくらいしか、ない名前よね、まったく」
そう言って、黒河内瑠理香は、笑った。
芥川龍之介も作家になるくらいしかない名前だ。そんな芥川が自身のカリカチュアのようにして作り上げた名前に「保吉」がある。A中尉やK中尉、ましてや一等戦闘艦にはなれない名前だ。もしも一等戦闘艦××が一等戦闘艦保吉だと、どうも戦闘で勝てそうな気がしない。保吉ではSや下士や△△にしかなれまい。
そういう意味では二万噸の××が芥川と重ねられることを拒むように、『三つの窓』にはキャラクターとしてのありのままの芥川自身の投影はない。たとえばA中尉やK中尉にしたところが、白髪頭で俳句を詠む「ありえなかった」三島由紀夫老人のように、少し遠い未来、「ありえなかった」芥川龍之介老人のイメージであり、その時点での芥川そのものではあり得ない。
勿論芥川には大正六年に君看双眼色、不語似無愁と書くだけのひねこびた生意気もあった。しかしK中尉の君看双眼色、不語似無愁には年寄り臭い含羞がある。もしかしたらK中尉は「ありえなかった」芥川龍之介老人だったのではないかと思ってみる。
そしてそんな舞台が、夏目漱石の死後すぐに芥川の出向いた横須賀、大正五六年の横須賀なのではないかと思ってみると、『豊饒の海』がくるりと『花ざかりの森』に戻るような感覚で、昭和二年がくるりと大正六年へ、『あばばばば』の横須賀へ戻ってきたような感じがする。
何故今更そんな場所へと考えてみる。
時時私は廿年の後、或は五十年の後、或は更に百年の後、私の存在さへ知らない時代が来ると云ふ事を想像する。その時私の作品集は、堆い埃りに埋れて、神田あたりの古本屋の棚の隅に、空しく読者を待つてゐる事であらう。いや、事によつたらどこかの図書館にたつた一冊残つた儘、無残な紙魚の餌となつて、文字さへ読めないやうに破れ果ててゐるかも知れない。しかし――
私はしかしと思ふ。
しかし誰かが偶然私の作品集を見つけ出して、その中の短い一篇を、或は其一篇の中の何行かを読むと云ふ事がないであらうか。更に虫の好いい望みを云へば、その一篇なり何行かなりが、私の知らない未来の読者に多少にもせよ美しい夢を見せるといふ事がないであらうか
芥川がこんなことを書いたのが大正七年、まだ海軍機関学校時代で、自分に三千人の読者がおり全集が出ることを知らぬ時代だった。いよいよ終わりが目の前に見えた時、はじまりの場所を振り返ってみるということが誰にでもあるのかもしれない。
そういえばこんなところから私も始めたのだ。
晩年
よく言われるように『歯車』を自殺直前の精神異常者の苦悩の告白だとは読めないのだということを、私は自身の『歯車』論において徹底して述べてきた。
しかし例えば堀辰雄が、晩年は「偉大なる片輪」の一人だつた、とすれ違いざまにナイフを突き立てるように『芥川龍之介論』で述べていることを完全に無視するわけではない。
元ネタ丸パクリ問題を含めて、『古千屋』にゆるみがあるとは見受けられないし、『三つの窓』における擬人法や「ほとんど信じられないくらいだった」といった翻訳調の表現は五十年新しい。
全く芥川を知らない外国人に読ませて、これが晩年の作品だと当てさせることは困難であろう。堀辰雄が「僕は芥川龍之介の諸作品の中で最も晩年の作品を愛します」と述べるような素直さで『河童』あたりを最盛期の作品として認め、『保吉の手帖から』あたりを晩年の作と勘違いするのではなかろうか。『河童』は堀辰雄が言う通り「筋の溌剌とした小説」である。
さらに言えば「點鬼簿」は彼の晩年の暗澹たる諸作品の先驅をなしたものである、と『點鬼簿』のような小品を一個の独立した作品として取り上げるのはいささかフェアではないような気もするが、これまで小品であれなんであれ凄まじい機知とイロニーを見せていたことを考えると、確かに『點鬼簿』に「晩年」はあったと認めざるを得ないだろう。
彼の死後、續々と、彼の遺稿が發表された。僕が今それについて語つた「齒車」も、遺稿となつて發表されたものだつた。その外に重なものを擧げれば、
「西方の人」(前編は生前に既に發表されてゐたが)
「闇中問答」
「或舊友に送る手記」
「十本の針」
「或阿呆の一生」等。
これらのものは(「西方の人」を除けば)、すべて、作品と云ふよりも、もつと彼自身に近い精神的産物である。そして彼を藝術家として見る時よりも彼を人として見るために大事な鍵である。これらのものに就いて語つて行かうとすれば、勢ひ、人としての彼をもつと精細に論じなければならなくなるだらう。
おそらく『點鬼簿』はこれらのもの「作品と云ふよりも、もつと彼自身に近い精神的産物」の側に含めるべきものであろう。
しかし『三つの窓』はどうであろうか。
不幸にも大抵の作家はどれか一つを缺いた片輪である、と芥川は書いている。私は芥川でさえ最初から何か一つに欠いた作家ではなかったかと疑っている。それは厚顔さ、無邪気さである。
僕の朝ご飯は大抵十一時、いつも一人で食べるけれど、今日は母が相伴してくれた。
トーストが三枚、ミルクが一合、うで玉子と焼いたポークが一枚、野菜サラダにキャベツ、デサートが二十世紀に紅茶。一寸ぜいたくのやうだけれど夜仕事をするのと昼飯兼帯であるから仕方がない。
こんな屈託のない話は芥川にはとても書けまい。しかし最初からそうではなかった。
『調痢丸をのみてより以来の便今日を以て漸く通じ五日ぶりのうんこを時にひり出し快絶大快絶に御座候』(龍之介『書簡集』より)
芥川は『點鬼簿』から何かを欠いたのではない。作家になった時からガタイの良いフリーの校閲のホームレスのような無邪気さを欠いていた。芥川は本来おデブな二万噸の一等戦闘艦××にはなれない男だった。
見よ、一等戦闘艦××の含羞を。
芥川に晩年なんてないねん。
[余談]
ガタイの良いフリーの校閲のホームレスということは出来高制ということなのだろう。時給で貰えるわけではないので、相当腕がいる。いや、だからホームレスなのか。
「⿸疒黑」と書いて「ほくろ」、「あざ」などと読む。江戸時代の文学でかつて使われた廃字で18世紀初めから20世紀にかけて約200年間使われた例が見つかっている。#新しいプロフィール画像 pic.twitter.com/wzL4dP2mz2
— 拾萬字鏡🐦 (@JUMANJIKYO) July 26, 2023
二君、二禁で「ニキビ」だと芥川も書いていたな。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
