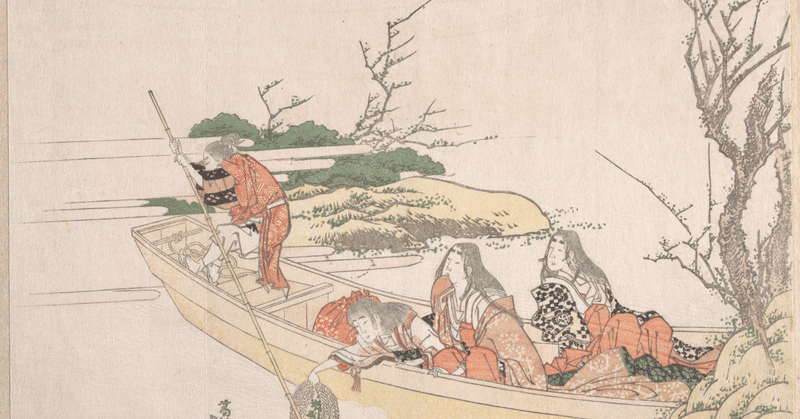
計算が合わない 牧野信一の『闘戦勝仏』をどう読むか⑩
「然し王様、金聖はどうなさるのですか。」と一人の侍女が云つた。
「あれか、あれはどうしても俺の云ふことを諾かぬ愚な女だ。」
馬鹿々々しいことを云つてゐやがると思つた悟空は滑稽で堪らなかつた。
「で、俺はもうあの女が憎くなつた。明朝は西の空へ竜車を駆つて火の鈴で焼き殺してしまふのだ。」
鈴を持つてゐる事くらゐで、己の醜さも知らずにこんな自信が持てるのか、と思ふと、悟空は寧ろ賽太歳のおめでたさが羨しい位だつた。
牧野信一は侍女をして賽太歳を「王様」と呼ばせてみる。村上龍が『半島を出よ』で書いた通り、たとえ合理的な支配でなくとも、一旦支配されてみれば、人はその支配を受け容れるしかないのではなく、むしろその支配が不合理なものであればあるだけ、積極的に支配されようとするものであることを確認するように。しかし村上龍がしたお勉強を牧野信一はしていないだろう。牧野はさして深い考えもなしに、ただ自然に「王様」と書いてみただけかもしれない。
しかし悟空は佯狂の詩人ではない。ここでは賽太歳の残忍さがむしろ単純さとして捉えられ、醜さの自覚のないことが論われている。確かに少しは揺らぎながらも、悟空には醜さの自覚はあったのだ。「鈴を持つてゐる事くらゐで」と言ってみるのは筋斗雲や如意棒では女の心を捉えられないという自覚あっての指摘であろう。
ただし悟空は醜さに対して辛辣である。醜いものに女が靡くわけもないという理屈を持っている。それでいて何とか活躍して皇后に抱き着かれたいと望んでいる。少々おめでたい。
— حملة الأسهم في الشرك (@mokuhyokabuka) April 28, 2024
そしてやはり賽太歳の残忍さに怒るわけでもなく、漫画的な正義感というものを見せない。悟空はここまで決して正義ではなかった。美しいものにもてたいと働きかけてきたにすぎない。
朝になると賽太歳は車を駆つて西の空に昇つた、さうして火の鈴を取り上げて、(二つの他の鈴は袋の儘傍の従者にその間だけ持せて置いて)――。
「如何に艶麗無比な金聖皇后と雖も、賽太歳の力の前には、風に吹かるゝ朝露のごとく滅亡するであらう。」と叫ぶやカラカラと打ち笑つて、猛火を雨のごとくに降りそゝいだ。
二つの鈴を持つた従者は、悟空が化けた従者だつた。悟空は立処に、巽の空へ飛んで、無茶苦茶に煙砂の鈴を振つた、これが自然の運命なのだ、と思ふと悟空はちよつとまた寂しい気がした。皇后を焼かうとした火は忽ち大王の群に覆ひかぶさつた、麒麟山百万の化物は一匹も残らず焼け死んでしまつた。
人間を焼いてしまおうというアイデアがいつどのように始まったのかは定かではないが、火炎放射器のアイデアは古代インド神話『リグ・ヴェーダ』に登場する火の守護神アグニからきたものであろうか。
それがギリシャの火として実用化されて以来、人は人を焼くことに執着して来た。
ここであからさまな行為者である悟空は小林秀雄のように考えてみる。
「この大戦争は一部の人達の無智と野心とから起こったか、それさえなければ、起こらなかった。どうも僕にはそんなお目出度い歴史観は持てないよ」
こう言った小林秀雄に対して平野は、
この居直りは、自国の帝国主義の責任を直視できず、全てを「歴史の必然性」の被害者という視点からしか眺められない、戦後日本の戦争観の一つの基調を成している。
このように批判したのだが、悟空は「これが自然の運命なのだ、と思ふと悟空はちよつとまた寂しい気がした」とさらに当事者意識を放棄する。平野啓一郎は悟空を批判しない。牧野信一の『闘戦勝仏』を読んでいないのだろう。
しかしこんなことをする必要が果たしてあったのであろうか。三つとも鈴を奪い、物理的に破壊してしまえば済んだことではあるまいか。「二つの鈴を持つた従者は、悟空が化けた従者だつた」という設定の影にはすでに二つの死体が転がっているのだろう。これは『西遊記』に描かれるよりもはるかに残酷で大げさな抹殺である。ここには大量虐殺という振る舞いに関する無自覚さ、あるいはやはりいい加減さとでも呼んでみたいものがある。
二つの鈴を、汚れたものでもあるかのやうに悟空は奈落の谷へ投げ棄てゝ、時を移さず牢へ走つた。金聖皇后は気絶して室の片隅に斃れてゐた。暗闇の土牢で、小さな窓が一つ空いてゐて其処からの光りが僅に薄い光線を投げてゐる。皇后は丁度その窓下に倒れてゐるので一筋の光りが水のやうに白い皇后の顔を浮ばせてゐた。金襴の衣が薄紫に漂うてゐた。
二つの鈴はもう用なしとなったらしい。となると「麒麟山百万の化物は一匹も残らず焼け死んでしまつた」という言葉の内には賽太歳も含まれていたのだろう。やけにあっさりと焼き殺されてしまったものだ。おそらくこの賽太歳こそがこの話での最大の悪役であり、賽太歳を倒すことが悟空最大の手柄である筈なのに、牧野信一は「王様」とも呼ばれた賽太歳をその他大勢と一緒に焼き殺してしまった。
この「金聖皇后は気絶して室の片隅に斃れてゐた」は牧野の凡ミスだろう。「斃れ」は死ぬことだ。いやしかし手書きで、つまりワードプロセッサーの変換ミスでないのに、わざわざここで「斃れ」と書き間違うとは、一体どんなうっかりなのであろうか。
牧野はここに「金襴の衣が薄紫に漂うてゐた」として例のドレスを持ってくる。
いやそんなこともあるまいが、
悟空には、王と皇后とが見定めが付かなかつた。たゞ王の時よりも、皇后とたつた二人ぎりで牢の中に居るのだ、といふ事が意識されただけ嬉しさも多かつた。―― ――此間王の前で感じたと同様な快感に打たれた。その時の通りになつた。
皇后の顔を拝んでしまつた悟空は、もう此上動くことすら欲しなかつた。長い間の血を見る程な悪戦苦闘も皇后を一瞥しただけで容易に報いられた。この儘野猿に帰つて、律師の破門を蒙つても何でもない、と思つた、寧ろその方が希ふところ位だつた。
さうしてゐる間に、不図また悟空の胸に新しい希望が涌いた。――直ぐに朱紫城へ帰らうとした。勿論それは王から賞与を得度い為でもなく、玄奘から智勇を賞して貰ひたい為でもなく、八戒や市民に豪気を誇りたいが為でもない。
どちらが王でどちらが鼻后であるか決して見分けのつかぬ程美しいところの恋人同士が再会を喜び合ふ姿と、到底帰らぬと思つてゐた皇后が計らずも戻つて来たのに喜ぶ市民達の笑顔が見度かつたのだ、たゞそれだけのことだつた。「皇后を迎へた王と市民の喜びの流観は、俺の方にも見せて呉れるだらう、ちよつとぐらゐ。」こんなことを思つた。
この時また悟空が王の前でしたように裸になって転げまわるのではないかと疑わせるように、牧野は「二人ぎりで牢の中に居るのだ」と書いてみる。いつ牢の鍵を壊したとも虱に化けて忍び込んだとも書かないで、悟空はもう牢の中にいる。もう一度虱に変身すれば、皇后の金襴の衣の中に潜り込み、走り回ることも可能であろうが、ここでは何か急に真面目になってしまって、本来の市民を喜ばせて歓迎されたいという無難な希望に立ち返る。何か本音で建て前を言っているようにも思えなくもないが、ここでは二つ目の冷やかすような、まぜっかえすような声は現れない。
再び悟空の全身には溢るゝばかりに勇しい血潮が涌き上つた。十日間山野を抜渉し、二十日間に十万里の空を往復して漸く烏金丸を作ることが出来た。
その一粒を皇后に含ませると直ぐに蘇生した。眼を開くや否や后は王の名を連呼して泣いた。声までが王のそれと寸分違はぬ甘味と艶と可憐さとを含んでゐた。「なんとまあ不可思議な現象であらう。」とさう悟空は思ふと、好奇心さへ浮んで来るやうだつた。
朱紫城を出てから半歳にして、皇后を伴つた悟空は城へ戻つた。
え?
皇后は確かに「斃れ」ていて、それが烏金丸を呑ませることで、三十日後にも拘らず生き返ったというのか?
その間腐敗することもなく、鼠にかじられることもなく、
それにしても勘定が合わないではないか。
風を蹴つて駆けて行く悟空は竜神の如く早かつた。間もなく如意棒の先端が麒麟山の一角に達した。早速門番の小悪魔を殺して偽門番に化けた。
こうしてすぐに麒麟山に到着した悟空は翌日には賽太歳を焼き殺している筈である。五か月ばかり勘定が合わない。
その五か月間、悟空と皇后が何をしていたのか。それはまだ誰にも解らない。何故なら、そこまでしか読んでいないからだ。
[附記]
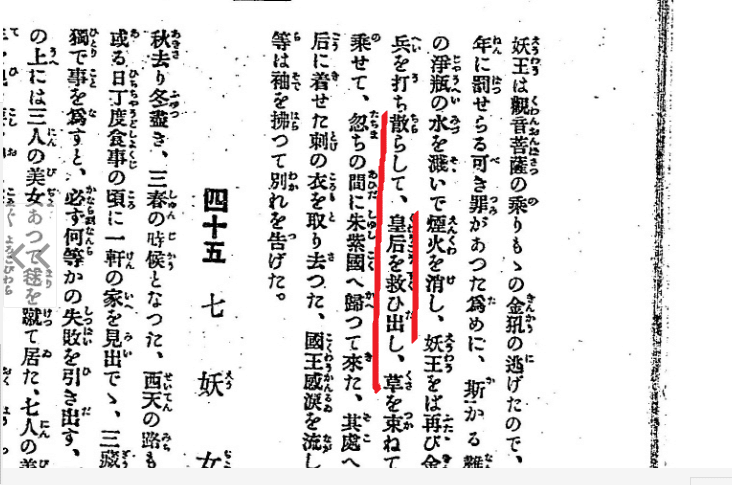
この一か月後の蘇生と半年の空白はやはり何かを意図した牧野の創意であろう。
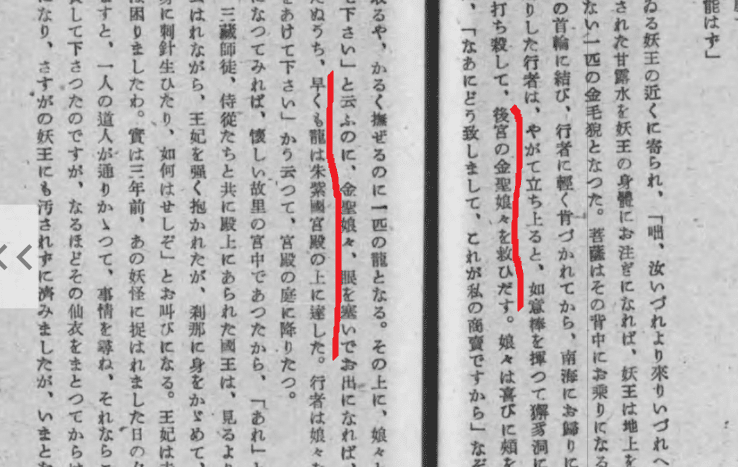
五か月。それだけの時間があれば色々なことができる。玄奘三蔵法師は貞観十三年、朱紫国に「数十日の長きに渡り」留まりながらさらに半年、悟空らの帰りを待つことになる。
いい加減に書いているものを真面目に読んでもつまらないが、ここは「悟空のきわめて個人的な目的のために貴重な任務がかなり遅らされることとなった」と読むことは可能であろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
