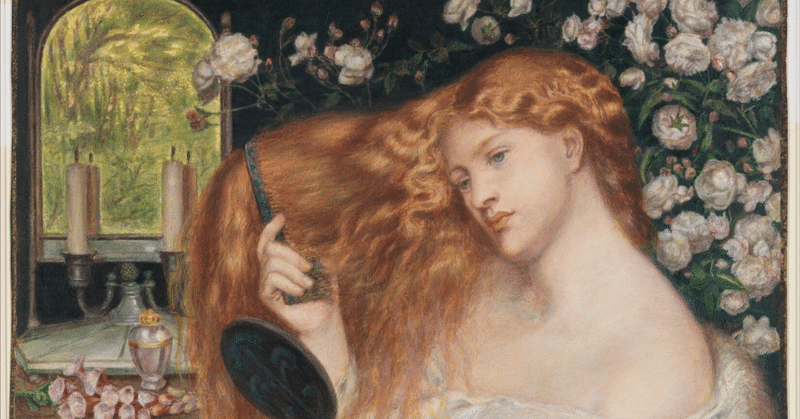
この宇宙こそが問題だ 牧野信一の『爪』をどう読むか②
昨日は「彼」が三日も本を読まないことがおかしいと書いた。よく考えると煙草と珈琲については書いていて、何も食べていないし排泄すらしていないかのようでもある。そんなこともあるまい。どうも「彼」は正直ではない。
寝るのにも化粧をする程お洒落で、お転婆な彼の従妹の道子は、丁度風呂から上つて唇や頬を塗り終へて、威勢よく梯子段をドンドン昇つて来るや、ガラリツと手荒く彼の室の障子を開けた。
「馬鹿!」若少しで彼は道子を叱り飛ばすところだつた。
部屋はどこかの安下宿ではなく実家のようだ。全然気が付かなかった。まるで一人暮らしのように騙されていた。しかも部屋は障子で仕切られた二階の和室だった。
確かに牧野は「密閉した室」と書いていた。障子ではたいして密閉もされまい。明りも漏れるはずだ。煙も漏れるだろう。
「まあ酷い煙り! 毒よ。」道子は顔を顰めて煙りを払ひ除けながら、彼の傍に坐つた。
「あ、痛い/\、どうもこう頭が痛んぢや、とてもやり切れない。」頭が痛いといふより他に病気と自称する自分の容体を発表する術はなかつたので、彼は如何にも感傷的な表情をして、道子の荒々しい態度が病人である彼に対しての順当な動作でないぞ、といふやうに、又自分が終日引籠つて居た事に勿体を付けるために、顳顬を一本の指先で突いて見せた。
-
— عزيز بن خالد (@3zoozvic) May 2, 2024
🌶️🌶️🌶️ الحرااااااااااااااااIاق 🌶️🌶️🌶️ pic.twitter.com/Qmt5ipVqxg
どうもこの話のテーマは「病気」らしい。それを「頭が痛いといふより他に病気と自称する自分の容体を発表する術はなかつた」と書いてみる。どうも「彼」が精神を病んでいるらしいことまでは解る。躁気味の統合失調症? そんなことを思ってみる。妄想はなく、鬱でもなさそうだ。考えがまとまらない感じはある。しかし考えがまとまらないと小説は書けない……ということもないか。
確かに『闘戦勝仏』は性格というものがまとまらない、ふらふらした話だった。しかしところどころに巧妙な仕掛けが設けられていた。そんなものをすべてたまたまでは片づけられない。
一本の指先とは右か左か。
食欲の減退はあったのではないか。
お洒落とはいえ風呂上りに化粧する道子もどこかおかしいのではないか。
野村Webローンで借りて年利1.5パーセントより高い利率で運用すれば丸儲けじゃないの。
と考えてみた。野村Webローンは関係ないな。
とりあえず牧野信一が精神の病気を頭の病気のように捉えようとしているところまでは解った。しかもこの書きようにはさしたる深刻さも悲観もない。
道子は空とぼけてゐるやうな顔をして両手を火に翳しながら、
「だつて時々面白さうに唄など歌つてるぢやないの。それもねえ、大きな声でさ。」仲々同情はしないよといふ風に答へた。
「紛らせやうとしてさ。」と即答はしたが明に彼はその弱点を握られたのである。口惜しいけれども事実だから仕方がない――弁解すべく余りに頼りないみすぼらしい病状なのだから。いよ/\喧嘩をしなければならないと思つた。
「僕は何も他人に同情を求めたくはないよ。まして道ちやんなんかに――。ハヽヽヽヽ。」
「おや、まあ変な兄さん。可笑しくもないのに、どうしてそんな気味の悪い笑ひ方をするのさ。」道子は彼の眼を見た。
「ハヽヽヽヽヽ。」彼は又笑つた。――考へて見れば全く其処に何の笑ふべき理由もない。彼は今道子から享けた痛手に惑はされて、自分の敗けたことを悟られてはならない、それに代ふるために鷹揚な笑ひを洩した心意りでやつたのだが、全く道子に取つたら敗けたも勝つたも考へてる訳でなし、彼の笑ひが異様に写つたのは無理もなかつたのだ。――やり損つた、と彼は思つた。
そもそも「彼」にとって当座の問題は病気そのものであることよりも、病人らしくみられないことらしい。さらにありのままの症状を告げることははばかられるらしい。読者には全部ばらしているのに?
そして少しはお道化ている? 駆け引きに失敗して困っている?
「兄さんは近頃余程変よ。母さんはあんなだから随分心配してゐるのよ。――夜中に突然大きな声を出したり、訳のわからない独り言を云つたり……全くおかしいわ。妾可笑しくて仕方がありやしない。妾兄さんがどんな挙動をしたつて、幾日寝てゐやうと平気よ。だつて余り馬鹿馬鹿しいんですもの、一体兄さんは横着で怠け者なのよ。此方こそ笑ひ度いわ。」
道子は抱へて来た折箱の中から美味さうなシユウクリームを出して盛んに喰べ始めてゐた。
やはり道子は変だ。風呂上りに化粧して兄の部屋にやってきてシユウクリームを食べる。シユウクリームを食べるとして、わざわざ煙草臭い兄の部屋で食べる必要はなかろう。それでいて自分がおかしいという自覚がない。こちらの方がむしろ本物なのでは。そう思えてくる。
仮に兄の仮病を疑っていようと、ここは握り飯でも運んでくるべきなのではないか。
そして「母さん」は「あんなだから」というのも気になる。それこそ心配なら自分で様子を見に来るなりする筈ではなかろうか。それを何もしないのは何か怪しい。
そして読者もあやしい。「おかしいわ。妾可笑しくて」と書かれてあるのに気が付かないでいる。注意散漫である。注意欠陥・多動性障害の疑いがある。そもそもこれまで牧野信一作品を読んでこなかったなんてどうかしている。
結局この宇宙で真面なのは私一人ということではないか。
「何んだい。病人のお見舞じやないのかい。」到底道子に遇つては敵はないとあきらめた彼は、寧ろ彼女に詫び度いやうな気になつた。で普段の通りな戯談味のある口調でさう云つた。と、頭の鉛りが急に溶けて、快活さと清新さとの血潮が溢り始めた。「嬉しい! やつと治つた。」と彼は独り言つた。今度こそは不調和でない笑ひをハヽヽヽヽと洩した。道子も「お気の毒様よ。」と云つて笑つた。
しかし治るということはあくまで自分の中だけの問題らしい。なんというか、昔の接触不良のテレビのように、叩いたら治るという具合で、「顳顬を一本の指先で突いて見せた」ことが幸いしたのか「普段の通りな戯談味のある口調」が功を奏したか、兎にも角にも「彼」本人は「治った」とは言うものの、道子から見れば何の変化も感じ取れまい。
今迄大概の場合、彼は道子に敵はなかつた。如何に不機嫌に、道子を叱り飛ばして居ても、それ以上冷酷な道子の態度に接すると、一撃の下に敗けてしまつた。――さうして道子の華な世界に引き込まれながら、道子が彼に浴せた冷笑に、彼は反つて追従しなければならない事が多かつた。
――憎い、いまいましい道子、と彼は思つてゐた。
彼は道子の顔を見るのも嫌になつた。彼は静に眼を閉ぢた。頭はすつかり醒めてゐた。
いや、この状態を「治った」と言って良いものであろうか?
どうも「彼」の妹に対する執着は真面でもない。兄を兄とも思わない冷たい妹などごく当たり前の存在であろうに、「追従し」憎むという精神構造が良く解らない。そして何よりも「顔を見るのも嫌になつた」から目を閉じるのがおかしい。自然な動作は余所を向くことだ。目を閉じるのは自然な動作ではない。
この「彼」が本当に治ったのか、そして本当におかしいのは道子の方なのか、それはまだ誰にも解らない。何故ならここまでしか読んでいないからだ。
[余談]
牧野信一には弟英二がいた。そういえば長男らしい名前だ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
