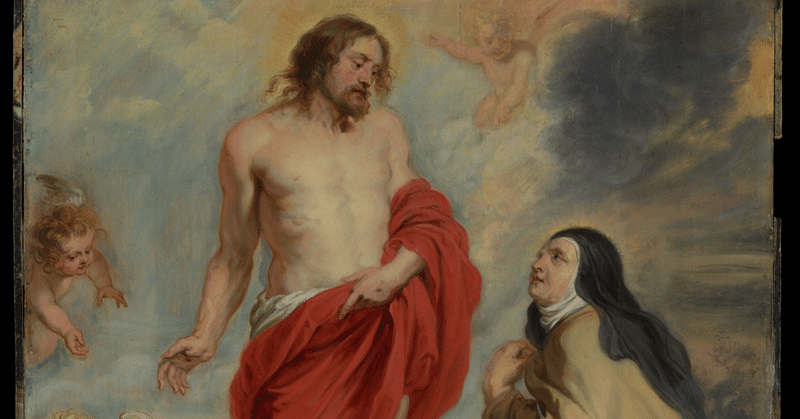
灰皿がないなら喫煙者ではないのかもしれない 芥川龍之介の『誘惑』をどう読むか⑤
昨日は芥川の映像編集技術、特に場面転換の動画の斬新さ、そして孤高さについて書いた。一日経っても類似の描写が思い出せない。そんなものは本当に芥川しか書いていなかったのではなかろうか。
20
長方形の窓を覗いている「さん・せばすちあん」の上半身。但し斜めに後ろを見せている。明るいのは窓の外ばかり。窓の外はもう畠ではない。大勢の老若男女の頭が一面にそこに動いている。その又大勢の頭の上には十字架に懸った男女が三人高だかと両腕を拡げている。まん中の十字架に懸った男は全然彼と変りはない。彼は窓の前を離れようとし、思わずよろよろと倒れかかる。――
ここが凄い。「但し斜めに後ろを見せている」でカメラ位置を決めておいてから「明るいのは窓の外ばかり」で窓を捉え、「窓の外はもう畠ではない。大勢の老若男女の頭が一面にそこに動いている」としてカメラを移動して窓の外の景色を捉えている。頭が動いているように見えるのだから、カメラが据えられた位置はかなり高いことになる。「姿」と説明しないで「頭」と描写したことがはっきりわかる。これが「靴」ならこの部屋は半地下になる。
それにしても「さん・せばすちあん」は洞穴から移動してきたのか、元々そこにいたのか、回想なのかとあれこれ考えさせる隙を与えないで、剣呑な景色が描かれる。「大勢の頭の上には十字架に懸った男女が三人高だかと両腕を拡げている。まん中の十字架に懸った男は全然彼と変りはない」とは、「さん・せばすちあん」が自らが十字架に懸かった景色を眺めていることになる。
この自分が自分を眺めるという構図もリアリズムの小説では決して現れないものだ。自分で自分の姿を眺められるようになるのは家庭用ビデオカメラが普及した後のことだ。記憶を辿り過去の自分を眺めるとき、その眺者たる自分自身はたいていほぼ身体性を失いアングルから消え、透明な眼球と化している筈だ。
そうしてその行き詰りには、大きな四角な家が建っていた。家には幅の広い階子段のついた二階があった。その二階の上も下も、健三の眼には同じように見えた。廊下で囲まれた中庭もまた真四角であった。
不思議な事に、その広い宅には人が誰も住んでいなかった。それを淋しいとも思わずにいられるほどの幼ない彼には、まだ家というものの経験と理解が欠けていた。
彼はいくつとなく続いている部屋だの、遠くまで真直まっすぐに見える廊下だのを、あたかも天井の付いた町のように考えた。そうして人の通らない往来を一人で歩く気でそこいら中馳け廻った。
彼は時々表二階おもてにかいへ上あがって、細い格子の間から下を見下した。鈴を鳴らしたり、腹掛を掛けたりした馬が何匹も続いて彼の眼の前を過ぎた。路を隔てた真ん向うには大きな唐金の仏様があった。その仏様は胡坐をかいて蓮台の上に坐っていた。太い錫杖を担いでいた、それから頭に笠かさを被っていた。
健三は時々薄暗い土間へ下りて、其所からすぐ向側がわの石段を下りるために、馬の通る往来を横切った。彼はこうしてよく仏様へ攀じ上った。着物の襞へ足を掛けたり、錫杖の柄へ捉ったりして、後から肩に手が届くか、または笠に自分の頭が触れると、その先はもうどうする事も出来ずにまた下りて来た。
健三はむしろ過去の空間に身体ごと意識を沈めて動き回る。この奇妙な回想もまた『メトロに乗って』などの映像作品を見るまでなかなか腑に落ちないものかもしれない。おそらくこうした芸当は夏目漱石ほどの一次記憶領域がなければできないことであろう。
その夏目漱石においてさえ、過去の自分を眺める自分をアングルに入れることはできなかったのだ。やはりそんなものが現れるのは少なくとも八ミリフィルムといった映像記憶装置の出現以降のことであろう。
21
前の洞穴の内部。「さん・せばすちあん」は十字架の下の岩の上へ倒れている。が、やっと顔を起し、月明りの落ちた十字架を見上げる。十字架はいつか初い初いしい降誕の釈迦に変ってしまう。「さん・せばすちあん」は驚いたようにこう云う釈迦を見守った後、急に又立ち上って十字を切る。月の光の中をかすめる、大きい一羽の梟の影。降誕の釈迦はもう一度もとの十字架に変ってしまう。……
寺を天皇のメタファと見做す人の話を読んでいたら、今度は釈迦に十字を切る人が現れた。もうめちゃくちゃである。マリア観音やデウス如来ならまだ解る。しかしいくら何でも釈迦に、しかも降誕の釈迦に十字を切るのはやり過ぎではなかろうか。
盂蘭盆会2日目。
— 金剛吉祥 (@vidyadhara_sri) August 14, 2022
釈迦法・盂蘭盆経読誦に加え、霊供作法にて新盆精霊に霊供膳をお供えしました。
箸を十字にするのは明恵上人の口伝。
本日はこのあと施餓鬼作法で終了です。
南無盂蘭盆教主釈迦牟尼如来
南無目連大士
南無大師遍照金剛 合掌 pic.twitter.com/rufIsn0koM
22
前の山みち。月の光の落ちた山みちは黒いテエブルに変ってしまう。テエブルの上にはトランプが一組。そこへ男の手が二つ現れ、静かにトランプを切った上、左右へ札を配りはじめる。
山みちが黒いテエブルに変ってしまうのはやり過ぎだ。しかし芥川はまたアングルで男の「姿」は見切れさせて、まるで真上から撮影するようにトランプと「手」を描写する。「男の手が二つ」とは左右の手であることが「静かにトランプを切った上」で解り、「左右へ札を配り」でここに三人いるのではないかと疑わせる。
ここに?
そこは「山みち」が変化したテエブルを真上から映している絵なので、そのテエブルの脚が何に支えられているのかは定かではない。もう読者が猿のことを忘れかかっているのをいいことに、ここで配られた札を手にするのは、二人ではなく二匹なのかもしれない。
しかしそれはまだ誰にも解らない。何故ならここまでしか読んでいないからだ。
[余談]
Kokoro by Natsume Soseki https://t.co/8RTAlGb0hE
— Stuart Alan Becker (@StuAlanBecker) April 6, 2024
世界に広がる漱石の『こころ』。
しかしあのことには誰一人気が付いていない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
