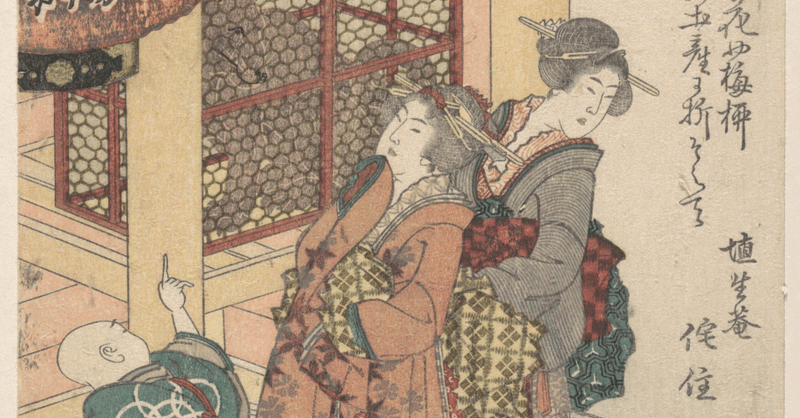
とても大きな窓だ 芥川龍之介の『誘惑』をどう読むか⑧
昨日は「幹」について書いた。
そして痛切に感じたのはそういうレトリックがありうるということだけ分かっても容易に真似ができないということだ。物まねというものは不思議なもので、誰か一人が物まねを披露すると、物まね芸人たちは上手い下手の差こそあれ誰でもがその物まねをまねることができるという。しかし「幹」は、……。この真似はまだできない。
それだけ凄いことを芥川が現にやっていて、みんながそれを無視しているというわけなので、なんともわびしい限りだ。
もうどうでもいいや、こんな世の中 pic.twitter.com/X2ZOU4dlRO
— K (@Manchukuo_1945) April 8, 2024
え?
たまたまだって? 「樟の木の無標性を指し示している」なんてただの深読みだって?
32
月の光を受けた樟の木の幹。荒あらしい木の皮に鎧われた幹は何も始めは現していない。が、次第にその上に世界に君臨した神々の顔が一つずつ鮮かに浮んで来る。最後には受難の基督の顔。最後には?――いや、「最後には」ではない。それも見る見る四つ折りにした東京××新聞に変ってしまう。
ここになんて書いてある? 「幹は何も始めは現していない」って書いてあるよね。
ここで一応この樟の木の幹は特殊な意味を始めは持っていないわけだ。件の猿の座っていた樟の木の幹だとは書かれていないのだ。それが「幹は何も始めは現していない」ということ。そこから意味を持ち特殊なものに変わる。
しかしもうなんとなくわかってきたと思うけれども、昨日の「石」のピストルへの変化のくだりで説明したとおり、特殊な意味は、それが成立しかかるとたちまちひっくり返されてしまう。四つ折りにした東京××新聞は基督のメタファにはなりえない。
ナンセンス。
そういうことが繰り返されている。
しかしすべてのことが無意味というわけではない。仮にここでも「世界に君臨した神々」の中の一人として「受難の基督」が相対化されている。相対化されているのに「世界に君臨した神々」が外に列挙されていないので、「受難の基督」と比較されるのは「四つ折りにした東京××新聞」だけになってしまう。つまり「受難の基督」自身がナンセンスなものとして放り出される形になってしまっている。
少なくとも大事にはされていない。「四つ折りにした東京××新聞」が褒められているとも思えない。
マッチポンプ。
そう思えなくもない。
33
前の山みちの側面。鍔の広い帽子にマントルを着た影はおのずから真っすぐに立ち上る。尤も立ち上ってしまった時はもう唯の影ではない。山羊のように髯を伸ばした、目の鋭い紅毛人の船長である。
今更もう驚きはない。影は独立して目の鋭い紅毛人の船長になる。鍔の広い帽子にマントルを着ていたのは船長の衣装だったのだ。なぜそんなものを影として引き連れなくてはならなかったのか、「さん・せばすちあん」と船長とはどういう関係性にあるのか。そんなことはこれまでにヒントすら出ていない。船長という言葉が使われたのはこれが初めてで、帆前船の内部には確かに紅毛人の水夫がいたけれど、彼がその帆前船の船長かどうかはまだ解らない。なぜなら彼はただ船長と呼ばれているからだ。ここでもそのとかあのとか呼びうるかどうかという点が泳がされている。
34
この山みち。「さん・せばすちあん」は樟の木の下に船長と何か話している。彼の顔いろは重おもしい。が、船長は脣に絶えず冷笑を浮かべている。彼等は暫く話した後、一しょに横みちへはいって行ゆく。
この広い宇宙のいくつもの太陽の周りをまわる幾つもの地球の一つ、その日本の南部のどこかの山道で、「さん・せばすちあん」はどこかの船長と話す。「せばすちあん記し奉る」というその「せばすちあん」が「さん・せばすちあん」なのだとすれば、ここまで固有名詞が与えられた唯一の存在が「さん・せばすちあん」であり、固有名詞が与えられているのにも関わらず、全く正体の解らないのが「さん・せばすちあん」である。
何故「さん・せばすちあん」の顔色は悪くなるのか。
こうした「さん・せばすちあん」を巡る何故という疑問は、これまで一度も解かれてこなかった。それは殆どはぐらかされていた。間違いなくここでは何かが語られているのに、意味から逃げるように話が展開していくのだ。
35
海を見おろした岬の上。彼等はそこに佇んだまま、何か熱心に話している。そのうちに船長はマントルの中から望遠鏡を一つ出し、「さん・せばすちあん」に「見ろ」と云う手真似をする。彼はちょっとためらった後、望遠鏡に海の上を覗いて見る。彼等のまわりの草木は勿論、「さん・せばすちあん」の法服は海風の為にしっきりなしに揺らいでいる。が、船長のマントルは動いていない。
手真似!
彼等は、五位に対すると、殆ど、子供らしい無意味な悪意を、冷然とした表情の後に隠して、何を云ふのでも、手真似だけで用を足した。人間に、言語があるのは、偶然ではない。
手真似は『芋粥』においては軽い侮蔑のあかしだった。おおよそ対等以上の相手に手真似はすまい。
この作品の中では猿による手真似で会話が行われていた。
船長と「さん・せばすちあん」は言葉でも話すことができるので「見ろ」と云う船長の手真似は先ほどの「さん・せばすちあん」の重々しい顔色と船長の冷笑とともに船長の「さん・せばすちあん」に対する何らかの優位性を示している。そして船長の風に揺れないマントルは、船長の出現の仕方と合わせて船長の超自然的なもの、現実に対する超越性を示している。
そして「しっきりなしに」という江戸弁は作者が江戸っ子であることを示している。
さらに我々は船長の手真似を「目の上に手をやって眺めはじめる」という猿の動作と比較してみる。そしてつい人並みであることが知られている猿の視力が人間より良い設定なのではないかと考えてみる。芥川自身は視力が良い方ではなかったので、少なくとも猿は望遠鏡なしでも遠くのものが見えるというなのではなかろうか。
36
望遠鏡に映った第一の光景。何枚も画を懸けた部屋の中に紅毛人の男女が二人テエブルを中に話している。蝋燭の光の落ちたテエブルの上には酒杯やギタアや薔薇の花など。そこへ又紅毛人の男が一人突然この部屋の戸を押しあけ、剣を抜いてはいって来る。もう一人の紅毛人の男も咄嗟にテエブルを離れるが早いか、剣を抜いて相手を迎えようとする。しかしもうその時には相手の剣を心臓に受け、仰向けに床の上へ倒れてしまう。紅毛人の女は部屋の隅に飛びのき、両手に頬を抑えたまま、じっとこの悲劇を眺めている。
水夫はナイフで殺されたのに今度は二人とも剣を使う。トランプはない。
剣は横腹にではなく心臓に突き刺され、やはりあおむけに倒れる。鼻の穴から猿は出てこない。
それにしても如何に大きな窓越しであってさえここに書かれている一部始終は望遠鏡には映るまい。つまり「何枚も画を懸けた部屋の中に紅毛人の男女が二人テエブルを中に話している」ここまでが、望遠鏡に映った第一の光景であり、後は誰かがドローンカメラで撮影した?
いやここは格別大きな窓越に本来見えるはずもない一部始終が見えたのだと考えておこう。
とにかく三人とも紅毛人で、そのうち一人の紅毛人が死んだようだ。それは馬鹿にあっけない二人目の紅毛人の死なのだが、微妙に異なる死だ。何かほんの少しずらされただけの繰り返しのような、相対的な死だ。二回目ながらもうありふれたような、さしたる通用を感じない死に方だ。
紅毛人の女は叫びさえしない。何かリアルな感情に迎えられない死だ。すべてはただ眺められている。
誰も当事者足りえない。
そんなことに気が付いたところで今日はここまで。
芥川の旧蔵書約2600冊を調査している中で見つかったとのこと。地道な作業がロマンティックな発見につながりました。素晴らしいです!
— 初版道 (@signbonbon) April 9, 2024
芥川龍之介の蔵書に“恋心”の押し花 初恋女性とのやり取りか | NHK https://t.co/0ZtY2y4JTE
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
