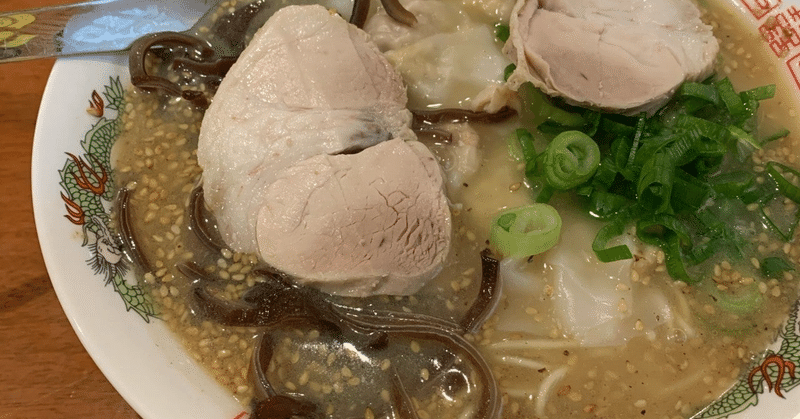
芥川龍之介の『猿蟹合戦』をどう読むか① アンチ敵討ちものとしての『猿蟹合戦』?
昨日、
昨日?
多分昨日、
『或敵討の話』(大正九年四月)
『或日の大石内蔵助』(大正六年八月)
『伝吉の敵討ち』(大正十二年十二月)
『三右衛門の罪』(大正十二年十二月)
……の四作品は「保吉もの」「開化もの」「切支丹もの」と同じ程度の緩い括りとして「アンチ敵討ちもの」と区分しても良いかもしれない、と書いたような気がする。
多分書いたと思う。
しかしどうも何か忘れているような気がする。
酒のつまみは買ってある。ビールも缶チューハイも冷蔵庫に冷えている。
なのに何か忘れているような気がする。そしてふと思い出す。

「猿蟹合戦の猿の行為は明に権利の濫用であつて不法行為であります。」という最高裁による「猿」批判に対して、芥川は『猿蟹合戦』において真逆の立場をとっているのだった。
彼等は仇を取った後、警官の捕縛するところとなり、ことごとく監獄に投ぜられた。しかも裁判を重ねた結果、主犯蟹は死刑になり、臼、蜂、卵等の共犯は無期徒刑の宣告を受けたのである。お伽噺のみしか知らない読者はこう云う彼等の運命に、怪訝の念を持つかも知れない。が、これは事実である。寸毫も疑いのない事実である。
敵討ちが罪に問われている。……ということはもしかして、この大正十二年二月に書かれた『猿蟹合戦』も「アンチ敵討ちもの」の仲間に加えてもいいのではなかろうか。
と思いきや、実は芥川の『猿蟹合戦』はお伽噺の『猿蟹合戦』から設定として「あること」を無くしているのだ。
ついでに蟹の死んだ後のち、蟹の家庭はどうしたか、それも少し書いて置きたい。蟹の妻は売笑婦になった。なった動機は貧困のためか、彼女自身の性情のためか、どちらか未だに判然しない。蟹の長男は父の没後、新聞雑誌の用語を使うと、「飜然と心を改めた。」今は何でもある株屋の番頭か何かしていると云う。この蟹はある時自分の穴へ、同類の肉を食うために、怪我をした仲間を引きずりこんだ。クロポトキンが相互扶助論の中に、蟹も同類を劬わると云う実例を引いたのはこの蟹である。次男の蟹は小説家になった。勿論小説家のことだから、女に惚れるほかは何もしない。ただ父蟹の一生を例に、善は悪の異名であるなどと、好い加減な皮肉を並べている。三男の蟹は愚物だったから、蟹よりほかのものになれなかった。それが横這いに歩いていると、握り飯が一つ落ちていた。握り飯は彼の好物だった。彼は大きい鋏の先にこの獲物のを拾い上げた。すると高い柿の木の梢に虱を取っていた猿が一匹、――その先は話す必要はあるまい。
とにかく猿と戦ったが最後、蟹は必ず天下のために殺されることだけは事実である。語を天下の読者に寄す。君たちもたいてい蟹なんですよ。
仇を取った後とあるのに、そもそも裁判にかかった蟹は猿とおにぎりを交換した当事者であり、復讐の当事者でもあるのだ。つまり猿は蟹を殺していないのに復讐されたことになっているのだ。蟹が死んでいないとしたら、やられたことは精々青柿をぶつけられた程度のことで暴行罪である。それに対して猿は臼につぶされて死んでしまうことになる。計画的な殺猿行為だ。これでは敵討ちというより確かに過剰な仕返しということになる。
敵討ちが成立するためには親ガニは死ななくてはならなかった。芥川の『猿蟹合戦』には晴らすべき親の無念がない。
その上新聞雑誌の輿論も、蟹に同情を寄せたものはほとんど一つもなかったようである。蟹の猿を殺したのは私憤の結果にほかならない。しかもその私憤たるや、己の無知と軽卒とから猿に利益を占められたのを忌々しがっただけではないか? 優勝劣敗の世の中にこう云う私憤を洩らすとすれば、愚者にあらずんば狂者である。――と云う非難が多かったらしい。
親の敵討ちは孝である。主の敵討ちは忠である。孝も忠もないところで私が仕返しをすれば、それは確かに私憤である。芥川がお伽噺の「猿蟹合戦」を知らないわけもない。しかし芥川は『猿蟹合戦』において、敢えて晴らすべき親の無念を取り除いてみたのだ。
そうすると確かに反撃の残忍さばかりが目立つ。
しかし芥川はこの作品においてらしくもないミスを犯している。卵は爆発しているので無期徒刑にはできない。逮捕しようにもぐちゃぐちゃだ。
[余談]
現在の首相公邸はかつての首相官邸であったが、それは伊藤博文が芸者やメカケにお金をつぎ込んで住居をなくすほど貧窮したので、仕方なく造られた建物。
— Hachi Ishigaki (@IshigakiHachi) May 25, 2023
その後も伊藤の女狂いは止まらず、官邸での仮装舞踏会の最中、庭で人妻・戸田極子(きわこ)を○○したと伝えられています。 https://t.co/pEOuXCIPmX pic.twitter.com/fCJTTmS3lT
こういうことは知っていたが、
こういうことは知らなかった。
何でもありの状態だったんだな。昔も今も。
初めて見るわこんなん pic.twitter.com/UsVkQyGUH4
— (アカン) (@akanbird) June 12, 2023
「「稼げないこと」を承知で、表現者になりたいなどと「ぐれた」人たちは、いつの世も身を立てることが出来ないのは当たり前のことなのかもしれない。どの社会でも、表現することが職業と結びつく僥倖を得られるのは僅かな稀人だけだ。」(鬼海弘雄『靴底の減りかた』筑摩書房、P211) pic.twitter.com/l4CqlKTilQ
— 本ノ猪 (@honnoinosisi555) June 12, 2023
うん。投資すればいいと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
