
目の前に拝むものがあるのに 平野啓一郎の『三島由紀夫論』を読む48
いくつもの天皇像がある

つまるところ平野啓一郎の『三島由紀夫論』の最大の問題は、「天皇」の複雑さを捉えきれていない点にあるのではなかろうか。それはまず三島由紀夫の「天皇」、「天皇観」と言ってもいいし、現実の天皇、或いは天皇制と言ってもいい。
「赫奕たる太陽」という言葉が、直接に天皇を指すことは既に確認した。
この飯沼勲のような純粋な表現はある意味では正しい。しかしその正しさは何故飯沼勲は宮城の前で腹を切りたいとは願わなかったのかという疑問を無理やり払いのけて成立する正しさである。何故荒ぶる神が日輪を拝して腹を切らなければならないのかという疑問を完全に無視して成立する正しさである。
しかし、東京市内の蜂起のあとで海辺へ達するのはむずかしい。
いや、ここまでわざとらしく書かれていて、宮城でいいじゃないかと思わないことはむしろ困難である。従って三島由紀夫はこう書いて遊んでみる。
もし宮城前まで落ちのびることができれば。……彼に恐れ多い空想が生れた。自分は薄氷の張る御濠を泳ぎ切つて、かなたの崖をつたひのぼり、崖上の松かげに身をひそめて朝を待ち、あるいは月島の船影がはるかにうかぶ海のしののめを望み、目前の丸ノ内のビル街が朝日の最初の一閃に浮彫りされる前に、刃に伏してゐることもできるのだ!
なんという徹底した拒絶だろうか。飯沼勲は皇居に忍び込んでさえ、それが松の生えた海が見える場所であることにしか意味を見出さない。天皇陛下では日輪の代わりにはならないとでも言いたげだ。
なんなら勲は天皇陛下にけつを向けて、敢えて日輪を拝しようとしている。何たる不敬。
飯沼勲がその場にいたら、飯沼勲が飯沼勲を誅していただろう。

それなのに平野啓一郎は、
何よりも、蔵原殺害の動機が、「聖明が蔽われている」ことへの怒りではなく、「伊勢神宮で犯した不敬の神罰」である。昭和天皇に、この「握り飯」を「必死の忠」として受け容れよ、というのは、さすがに無理があろう。彼は敵である現体制の共感を拒む行動によって、結局のところ、人格的な天皇からの理解さえ、拒んでしまったことになっている。
こう真面目に書いてみる。どうであろうか。この書き方では、勲が天皇陛下にけつを向けて日輪を拝しようとした位置関係が見えていないことにならないだろうか。これは基本的な読解力の問題だ。「もし宮城前まで落ちのびることができれば」の下りを、「あー天皇崇拝者だわこれは」と読んでしまった人は、残念ながら読解力が足らない。これではとても牧野信一は読めまい。
飯沼勲の日輪へのこだわりは、田舎の人が皇居を訪れて、ここに天皇陛下がいらっしゃるんだとお辞儀をするような、そんな素朴さを唾棄するような、現に宮城に実在するはずの「あきつかみ」、現在神に対する抗議を秘めたものに思えなくもない。無論三島は勲に何度も「陛下」といわせることで「天皇」を複雑化させ、勲の天皇に対する忠誠心を匂わせてもいる。その一方で神風連の「幽(かく)り世の遠御神(とほつかみ)に事(つか)へまつる」方式、孝明天皇の御意志に順ずる思想があるわけなので、明治天皇以下、今上天皇まで仮に「宇気比」の神慮がかなえば誅することが可能であるかのようにも思える。

この矛盾は敢えて創り出されたものなのだ。
さらに言えば立ち消えになった勲たちの計画には洞院宮を担ぐ計画もあった。今上天皇を担がなくとも皇道政府はできるのだと言わんばかりである。
複雑である。
なにしろ天照大御神陛下とは言わないからだ。
神風連の天皇には明らかに、「とおつかみ」と「あきつかみ」の二種類の区別がある。勲の天皇は「陛下」と「日輪」とが「それこそは陛下の御姿だつた」として無理やり重ねられている。しかし別の場面で日輪は「宇気比」の神と重ねられ、陛下とは乖離している。この細かい矛盾こそが三島由紀夫の狙いであろう。
何かが現はれねばならぬ。しかも、神は肯うとも否むともなく、この地上の不決断と不如意をそのまま模したように、高空の光りのなかで、神の御御足からなほざりに脱げた沓のやうに、決定は放棄されているのである。
ここで日輪は陛下とは引きはがされ、超越的な力を持った神と同化させられている。平野は『英霊の声』を巡って、「二・二六事件」で処刑された青年将校たちの霊が天皇を神と呼びながら、
彼らは決して、天皇に神であることの超人間性を求めている訳ではない。寧ろ、天皇の超人間的側面を、人間としての天皇が正しく理解することを求めているのである。
と、して特攻隊員たちの霊の、
人間としての義務において、あらせられるべきだった
という天皇観と対比する。いやたいして対比はしていないが、一応違う考え方があるという指摘はしている。
神風連にはソラリズムがない。勲には「とおつかみ」がない。この天皇観の違いを構成したのは三島由紀夫である。この複雑さが平野啓一郎には見えていないのではなかろうか。
三島由紀夫にとって天皇は〈絶対者〉であったという平野啓一郎の『三島由紀夫論』は天皇を一つにまとめることで成立しているが、平野啓一郎は様々な天皇が書かれていることには気がついている筈なのである。
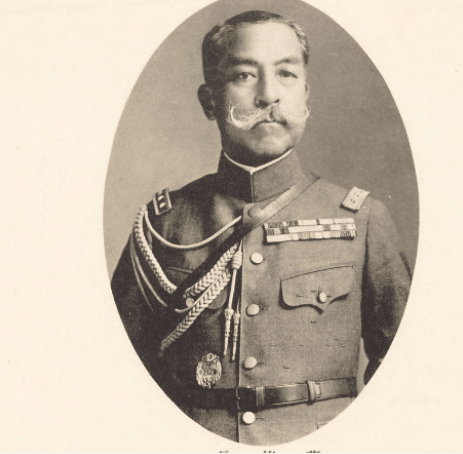
たとえば天照大御神だって「宇気比」をしているんだから、神慮は天照大神の外側にあるのではないか、とは問わない。さらに言えば神にしろ天皇にしろ特攻隊や勲が勝手に求めているものでしかなく、科学的に外在している訳ではないという当たり前の事実を指摘しない。神にしろ天皇にしろ、それが様々な形をとりうるのは、それが求める側の都合でしかないからなのだという当たり前の事実を指摘しない。それは平野啓一郎が天皇の実在性を頑なに信じているからであろう。しかしそれは平野啓一郎の天皇観であり、飯沼勲や三島由紀夫の天皇観とは明らかに異なる。
理屈の上で「宇気比」を出してきた時点で、三島由紀夫には天皇であれ神であれ「求める側の都合」であることがはっきり分かっていたことになる。三島由紀夫は自分の天皇論、天皇観自体があまたある天皇観の一つにすぎず、「あくまでもこちらの都合」であることが分かっていたのだ。
その冷静さと三島の最期の反りが合わないので、平野は「あくまでもこちらの都合」である「宇気比」の意味を掘らなかった。春日宮妃殿下に気がつかなかったのは単なるミスではあろうが、こちらはどうだろうか?
操られる勲
平野啓一郎は勲の行動に関してこう批判する。
蓮田善明に殺された中条大佐の場合と同様、どれほど勲を理解しようとしても、蔵原の殺害については、肯定的な受け止めが困難である。
それは安倍元首相の暗殺ならば肯定的に受け止められるという意味でもなく、テロというものの完全否定も意味してはいないだろう。計画通りに東京中の変電所を破壊しなくてはだめだという意味でもなく、なんか適当に殺しているぞ、という程度の意味だとして理解しておこう。
しかしたまたまながら様々な計画があったにもかかわらず最終的には市ヶ谷のバルコニーに辿り着いた三島の行動と勲の行動はよく似ている。
小説としての『奔馬』においては、勲は『神風連史話』にたまたま啓発され、たまたま親が右翼で、たまたま堀中尉、洞院宮に辿り着いてそそのかされ、たまたま堀中尉の満州転属が決まり、軍人の協力が得られないことになったから計画がねじれたわけだが、たまたまではないことがある。それは当人にとってはたまたまなのだが、作者にとってはたまたまではないのが堀中尉の軍人下宿が「北崎」であり、勲は「何だかこの家を見るのははじめてではない」と感じるのである。
つまり勲は綾倉侯爵か蓼科の生きたままの生まれ変わり?

とまあそんなこともなかろうが、人は時々そんな感じがしてしまうことがあるものだという理屈と、人はたまたまに意味を見出してしまうものだという理屈を読者には示してるのだろう。
清顕と聡子が交わった霞町の軍人下宿は蓼科に二度お手がついた北崎の家だったということが、「門も玄関もない、そのくせかなりな広さの庭に堀塀をめぐらした坂下の家」という表現の重なりで解る。
このいわば蓼科の秘密基地にたまたま勲も導かれたわけである。
なんというたまたまであろうか。堀中尉はただ腹が切りたいというだけの勲たちに、知恵をつけていく。
屈辱的な外交、農村の疲弊を救ふのに何らなすところのない経済政策、政治家の腐敗、共産党の跳梁、そして政党は師団半減論、軍備縮少を唱えて軍部を圧迫し続けていた。
綾倉伯爵と蓼科が、清顕と聡子が、あんなことやこんなことをした場所で、まるで自分たちの代わりに若者に行動させようとでもいうかのように、知識を授けてしまう。これが簡単にそのまま勲の政治思想になってしまう。これは勲が蓼科の怨念に操られていると言っていい、……いや蓼科はまだ生きてはいるのだが、やはり事情を知る読者には何か因縁めいて見えるところだ。
勲の地図はたちまち出来上がる。
洞院宮に握り飯の忠義の話をすると、宮様は「こういう若者が出てきたか」「日本の将来にもいささか希望が持てる」とやすやすと持ち上げてしまう。これは一見受け身の姿勢のようでありながら、完全に指嗾である。しかし平野はここでも指嗾とは指摘しなかった。
若者は偉い人からちょいと褒められると嫌がおうにも舞い上がるものである。握り飯の忠義の話など大人なら簡単に反駁できる筈なのに、宮様はそうしない。まさか三島由紀夫自身が握り飯の忠義の話を完璧な理屈であるなどと見做していないことは、「自分なら……」という三島自身の考えが別に示されていることから明らかである点を平野は確認済みである。しかしここではあまりに思慮に欠ける宮様の無責任な態度は批判しない。
結果として「洞院宮殿下への大命降下の事実ありたるを宣伝し、宣伝をしてやがて事実たらしめんとするものなり」などという計画が出来上がってしまう。これも良く読めば「今上天皇では何ともならん」という天皇批判に見えなくもないところだ。ここまでが報道されれば一応「握り飯」にはなったのだろうが、本多はこれを握りつぶす。思想と計画は膨らみ、軍の協力が得られない事態に陥って、勲の中には「純粋」が残った。
そこに佐和という大人が現れ、また知恵をつける。戒厳令発布の高望みを捨てさせ、暗殺一本に絞るよう計画変更させるのである。佐和の助言により、蔵原武介は佐和が、新河亨は飯沼が暗殺することになった。
この二十八章の時点で殆ど飯沼勲の行動からは、勲自身の意志というものが奪われていたわけである。二十九章の接吻も事故のようなものである。剣道の達人勲に悟られぬほどの素早さで間を詰めたのは鬼頭槙子の方だった。
三十章で勲らは逮捕され、三十一章で勲らのことが新聞に出る。
「『昭和神風連』事件の全貌判明
一人一殺で、財界潰滅を狙ふ
首謀者は十九歳の少年」
逮捕してくれたのは警察で、勲たちの思想を宣伝してくれたのは新聞社である。本人の意図せぬところで勲たちの行動は、世間に檄文を撒いたも同じことになった。しかし三島由紀夫はこんなことでは満足しない。何と本多を退官させ、弁護士にして、勲の弁護をさせてしまうのだ。
観察者と言いながら結構な行動である。
それに勲を逮捕させたのは勲の父親である。そう考えてみると勲の行動というのはいろんな人に操られてのものであることがだんだん明らかになってきたのではあるまいか。それはニラともやしと卵があればニラもやし卵炒めを作るのが明らかなくらい明らかなことの筈である。
ことが済んで聡子の着替えを蓼科が手伝うようにして、勲が知らないところで大人たちが動いてゐた。なんと洞院宮殿下までが勲を救おうと、弁護士本多を呼びつけたのである。そこで本多は勲らが洞院宮内閣を計画していたことを漏らしてしまう。それは宮様を脅し、証拠隠滅を命じさせるためだった。この大人の働きがなければ、勲たちの罪はどう問われたものかわからない。
平野は勲がした「蔵原の殺害」にだけ囚われているが、そこに至るにはなかなか複雑な経過があるのだ。それは勲の動機だけでなしうることではない。しかしそもそも勲は天皇の理解など求めていたのだろうか。天皇がどう受け止めようが腹を切るというのが理想であった筈だ。握り飯が握れたのかどうかはもう少し細かく見ていきたいので、今日のところはここまで。
[余談]
真面目な話、三島由紀夫を読むトレーニングとして、牧野信一は役に立つと思う。うっかり読むと全然意味が解らない。決めつけが出来ない。明らかに自分とは異なるものの捉え方をしている。ナンセンスながら出鱈目ではない。非論理的ながら小さな理屈はある。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
