
きっと三島由紀夫とは意見が合わないな 芥川龍之介の『誘惑』をどう読むか⑨
昨日はあらゆるものが眺められていて、誰も当事者足りえていないのではないかと書いた。
そのことは何故か現在の状況を言い当てているかのようでさえある。確かに眺められていて意味が見いだせない。
例えば『蜘蛛の糸』において蜘蛛はどの位置にいたのかと考えもしない。ありていの蜘蛛なら蜘蛛自身が垂れさがるのであり、もしも糸が切れれば蜘蛛は矢張り地獄の池に落ちるのである。
ただ文字が眺められている。
可能な限り意味からは遠ざかり、ただ眺められている。それは芥川龍之介個人の問題ではない。中島敦の『山月記』の「若くして名を虎榜に連ねた李徴が虎になる」というふりと落ち、大きな物語構造を理解できているものがこの宇宙にただの一人も存在しない。
小説を書くとは殆ど虚無と向き合うことに似ている。
ナンセンスと向き合うニヒリズム。それはトコジラミのために購入されたダニ避けスプレーに似ている。
37
望遠鏡に映った第二の光景。大きい書棚などの並んだ部屋の中に紅毛人の男が一人ぼんやりと机に向っている。電灯の光の落ちた机の上には書類や帳簿や雑誌など。そこへ紅毛人の子供が一人勢よく戸をあけてはいって来る。紅毛人はこの子供を抱き、何度も顔へ接吻した後、「あちらへ行ゆけ」と云う手真似をする。子供は素直に出て行ってしまう。それから又紅毛人は机に向い、抽斗から何か取り出したと思うと、急に頭のまわりに煙を生じる。
そこにも大きな窓があり、「さん・せばすちあん」はその一部始終を眺めたのだと確認した後、あなたはきっとこう考えている。なんだかあれ以来少しずつ、彼のニュースに関心がなくなってしまった、彼の言葉は信じたいがやはりおかしい、シーズン途中でまた大問題になって、そこで嘘がばれてけじめが必要になったら、それは何かの穴が確定したくらいの話ではなくなってしまう。その前に少しずつ彼から関心を無くしたい……と。そのくらいこのエピソードには物語性がない。
既に二人目の死にも殆ど驚いていないあなたは、もうこの子供が誰であるとか、この紅毛人の男がどの男なのかを考えもしていない。つまり二人目の紅毛人の友人であるのか、二人目の紅毛人を剣で刺した男なのかを考えない。大きい書棚には本が横向きに並んでいるのか縦向きに並んでいるのか考えない。そういえば紅毛人が阿蘭陀人かどうかということも最初から気にしていなかった。みんな紅毛人というだけで同じ顔に思える。
बीजेपी ने विदेशी राजनीतिक दलों को क्यों भेजा न्योता?- प्रेस रिव्यू https://t.co/8BlVXX3bpb
— BBC News Hindi (@BBCHindi) April 10, 2024
そしてたぶんあなたは船の中で電燈が使われていることに何も感じなかったはずだ。第一の光景は蝋燭で照らされていた。なのに帆前船だと発電装置はないだろうとは考えもしない。つまりこの船があの帆前船かどうかという問題がどうでもよくなっている。携帯電話のバッテリーの残量を見る。そもそもこの船は子供まで乗せて何をしているのだろう。とあなたは考える。いや、目的など何もありはしない。これはきっと芥川が息抜きに書いたお遊びなのだからと。
38
望遠鏡に映った第三の光景。或露西亜人の半身像を据えた部屋の中に紅毛人の女が一人せっせとタイプライタアを叩いている。そこへ紅毛人の婆さんが一人静かに戸をあけて女に近より、一封の手紙を出しながら、「読んで見ろ」と云う手真似をする。女は電灯の光の中にこの手紙へ目を通すが早いか、烈しいヒステリイを起してしまう。婆さんは呆気にとられたまま、あとずさりに戸口へ退いて行ゆく。
わざとらしく誘いながら、けして正体を見せない。まるで正体不明の変態だ。
正体不明の変態 pic.twitter.com/bPORsA0Ebz
— حملة الأسهم في الشرك (@mokuhyokabuka) April 10, 2024
もはや手紙の中身がどうかなどと考えさせもしない。そこに文字が書かれていたかどうかも怪しいものだ。
露西亜人の半身像は上半身なのか下半身なのか、そんなことももう考えられない。文学もやはり一回きりしか起こりえないものなので、物理学でも歴史学でも扱うことができない。
他でも生じうる一般法則しか原理的に扱えない物理学によっては扱えない問題であると同時に、他では生じえない一回性の出来事しか原理的に扱えない歴史学によっても扱えない問題であるという点が、非常に興味深いところですね。深く考えるとむしろ後者のほうがより興味深いかもしれません。 https://t.co/9s0L9bD3W0
— 永井均 (@hitoshinagai1) April 8, 2024
下半身像などあるわけがないという思い込みはたった一つの例外で崩れてしまうものだ。
それはそもそもただ眺めることしかできないものだったのだ。手紙はいつこの船に届けられ、それから何時間後に彼女のもとにもたらされたのか。それは誤配ではないのか。そして彼女は誤読していないだろうか。
39
望遠鏡に映った第四の光景。表現派の画に似た部屋の中に紅毛人の男女が二人テエブルを中に話している。不思議な光の落ちたテエブルの上には試験管や漏斗や吹皮など。そこへ彼等よりも背の高い、紅毛人の男の人形が一つ無気味にもそっと戸を押しあけ、人工の花束を持ってはいって来る。が、花束を渡さないうちに機械に故障を生じたと見え、突然男に飛びかかり、無造作に床の上に押し倒してしまう。紅毛人の女は部屋の隅に飛びのき、両手に頬を抑えたまま、急にとめどなしに笑いはじめる。
そして今度は蝋燭とも電灯とも書かれない。「不思議な光の落ちた」と書かれてしまう。
「舞踏には舞踏の本質的な内容がある
彫刻や絵画の内容になるものとそれとは勿論おなじではないのだから
印象派以来意味のある画が軽蔑されるように
舞踏にもきっと絵画的であったり彫刻的だったりする舞踏が軽蔑される時が来る
又来なくてはならない」と、こういうことを考えたのですが如何でしょうか。
ワイルドは印象派の生まれぬ前にはロンドンの市街に立ち罩める、美しい鳶色の霧などは存在しなかつたと云つてゐる。青と燃え輝いた糸杉もやはりゴツホの生まれぬ前には存在しなかつたのに違ひない。少くとも水水しい耳隠しのかげに薄赤い頬を光らせた少女の銀座通りを歩み出したのは確かにルノアルの生まれた後、――つひ近頃の出来事である。
又画の話を持つて来ますが、つい近頃まで生きてゐた印象派の大家のルノアルは「我々は何も新らしいことをしようとしたのではない。唯古大家の跡を踏んだだけだ。それを新らしいことのやうに言ひ囃したのは世間だけに過ぎぬ」と言ひました。単に鑑賞に止まらず、創作に志す青年諸君は一層この心がけを持つて貰ひたいと思ひます。若し諸君の万葉集を読み、或は芭蕉を読むのを見て、時代遅れと笑ふものがあれば、芥川龍之介はかう言つたと、――位のことには何びとも驚かないかも知れません、それならばルノアルはかう言つたと一撃を加へておやりなさい。その為にも甚だ便利だと思ひ、ルノアルを立ち合はせた次第であります。
三島 印象派はパリでも見たけど、ちっとも感動しなかった。加藤周一君とも話したのですが、ロマンチックまでは絵と文学が相渉っていたけれども、印象派になってからは、絵は截然と文学からわかれたでしょう。だから文学者としての立場で見たら、印象派に感心するわけはないんですよ。
中村(光夫) ほんとにそうだ。それは或る人も言っていたけど、印象派以後から絵というものが女子供のものになった。
三島 それはおもしろい。
中村 やはり感覚の世界だからね。
三島 僕がいちばん嫌いなのは感覚の世界です。なにもフランスへ行ってそんなものを見たくない。
とは云へ「話のない小説」の説をただ衰弱した体力の所産とばかり片づけ去ることは出来ないし、潤一郎と龍之介とではただ体力の相違とばかりに片づけ切れないものが何か残るやうな気がせぬでも無い。
龍之介に倣つて画に例をとつて云ふならば、潤一郎は結局、紫派(日本洋画壇で初期印象派を呼ぶ語である)以後の理解者とは云ひ難いのに反して、龍之介はゴオガンやルドンなどに対して異常な魅蠱を感じてゐたのはその自ら記してゐるとほりである。彼はその頃ゴオガンの最もいい蒐集がモスコオにある事を僕に教へて、それを見るために一緒に行く気はないかと誘つたので、僕も仮りに賛成したものであつた。これもやはり体質か、気質か、それとも趣味かはた教養のためかその原因は知らないが、ともかくもかういふ相違が、「僕等の兄」と敬まひ、また往年の深夜の自動車のなかの友情を今も忘れず感じつつも、龍之介をして
「大なる友よ、汝の道にかへれ」
と気の弱い捨ぜりふを残して見返りがちに潤一郎から遠退かせた。
そしてようやく、なるほど印象派かと合点がいく。芥川が「印象派以来意味のある画が軽蔑されるように」と言い、三島が「絵は截然と文学からわかれたでしょう」と言った意味がやっと解った。「話のない小説」というのも解った。
今解った。
何だそういうことか。蝋燭から電灯へ。
この人形はまるでロボットだ。
<巻五第一五 作人形事・於高野山>
同比、高野の奥にすみて、月の夜比には、或友達の聖と諸共に、橋の上に行合侍りてなかめ/\し侍りしに、此聖、京になすへきわさの侍りとて、情無ふり捨て登りしかは、無何、おなしくうき世を厭華月のなさけをもわきまへ(ら)んとも恋しく覚しかは、思はさるほかに、鬼の、人の骨を取集侍りて人に作りなす様に、可信人のおろ/\語り侍りしかは、其まゝにして、広野に出て、骨をあみ連らねて造て侍れは、人の姿には似侍りしかとも、色も悪く、すへて心もなく侍りき。声は有共、絃管声の如し。けにも、人は心かありてこそは、声はとにもかくにもつかはるれ。たゝ声の出へき間のことはかりしたれは、吹そんしたる笛のことし。大かたは、是程に侍るふしき也。扨も、是をは何とかすへき、やふらんとすれは、殺業にやならん。心のなけれは、唯草木と同しかるへし思へは人の姿也。
この『撰集抄』にもロボットのようなものが出てくる。しかし芥川の描く人形はロボットのようなもののレベルではない。まるでボストン・ダイナミクスのレベルである。少なくとも飛び掛かるだけでアシモくんよりは未来にある。少なくとも「機械に故障」と書かれているので、ネジと歯車だけのからくり人形ではない。
It's pretty awesome how dancing makes robots less intimidating. Looking forward to seeing more nontrivial Machine Learning on these robots. Credit: Boston Dynamics. pic.twitter.com/wnB2i9qhdQ
— Reza Zadeh (@Reza_Zadeh) December 29, 2020
彼が持っていた人工の花束、この言葉は芥川専用のようで、いわゆる造花の花束を指すようだが、むかしはこれがけして厭味ではなく、それなりのものであったようだ。
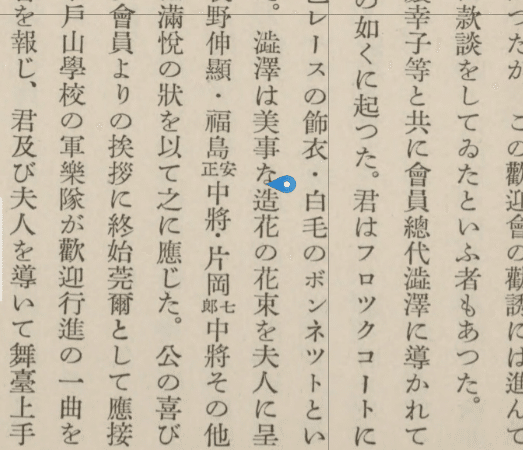
しかしここでは人形と合わせた悪戯であろう。女が笑い始めたのは、人形の殺意ではなく人工的な、しかしいかにも人間的な、しかしどこか滑稽な、腰ふりを目撃したからではなかろうか。そのホモセクシャルな景色は「さん・せばすちあん」だけに見えていて、決してあなたには見えない。紅毛人の男の人形と書かれていたのに、それがついていると認めない。
それがついていなければ男の人形ではない。
中国に帰っていったパンダのシャンシャン、日本語が聞こえるとお耳をピンとして駆け寄る「泣いちゃった」https://t.co/UaUbqARsGS.
— Togetter(トゥギャッター) (@togetter_jp) April 10, 2024
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
