
あなたがわるいのだ 本当の文学の話をしようじゃないか⑲
そして漱石が及びもつかず分らなくなつていくのだつた。怪奇で不氣味な姿に見えてくるのだつた。「漱石はいやな人間ばかりなぜ描くのだらう。」
それが漱石を身近かに讀ませ、白樺派の作品に新しい文學を成立させ、鷗外の作品に巨人的な人間像をうかがはせたのであつた。
しかも典型的なる近代人は、-たとへば漱石のごとく龍之介のごとく-その孤獨に誇りを感じてゐるのである-寂しき誇りである。
漱石や鷗外や萬葉を讀み、さらに西洋や支那の書籍を漁り、思ひの外な文學史や考古學の本などまで讀んでゐる。
文学の発生
風巻景次郎 著子文書房 1940年
風巻景次郎という人は谷崎潤一郎の解釈を巡って、ふいに気になってきた人である。その人は、
たとへば、私などの文學の發生は、あきらかに傳統詩歌の抒情の虐げからはじまつてゐた。それが漱石を身近かに讀ませ、白樺派の作品に新しい文學を成立させ、鷗外の作品に巨人的な人間像をうかがはせたのであつた。
伝統詩歌と漱石を経て、谷崎に至ったのだ。それは言い換えれば「萬葉集」から藤原俊成を経て、漱石にという話になる。しかし風巻は自身の文学の系譜を上田秋成、松尾芭蕉、井原西鶴、吉田兼好、鴨長明、清少納言、としてそれより上には遡れないと嘯く。
この欺瞞。万葉集をかじらないで古今集は読めず、そこから出ないと伝統詩歌には触れられない。
必ずしも數の問題でなく、何かしら本質的なもののみじめさと言ふ感じであつた。
どれだけ背伸びをしてみても万葉学者以上に万葉集を読み切ることはできないし、万葉学者が万葉集を読み切れているわけではない。では日本文学に連なろうとすれば誰しもが万葉集を少しだけかじり、古今集を少しだけかじり、後は何やら適当にすましてハナモゲラの根無し草で、はったりをかますしかないものであろうか。
とてもやりきれない。この無力感を風巻は「みじめさ」と言ったのではないか。
これは何かを書くことを決意した人間にとってさらに切実な問題として立ちはだかる。
萬葉集さえ読み切れていないのに、何を語る資格があるのかと。実際何も書かないで万葉集の万葉仮名による精読と註解の何週目かを終えた万葉学者は、まだ何も書いていないにせよ、金融資産が一億円超えた平社員くらいの心の余裕があるのではなかろうか。少なくとも萬葉集はなんとなくつかめてきたぞという余裕。そんなものが風巻にはない。
しかしそんなものは本来どうでもいいことなのではないか。万葉歌を一つも知らずとも中世の詩歌を一つも知らずとも、ただ目の前の作品を丹念に読み、その意味が理解できるかできないか、それだけのことなのではなかろうか。たとえ『国歌大観』をそらんじていても、目の前の作品を読めなければしょうがない。
文學が發生するといふことは、白日のもとに行はれる神秘である。それは突如としてうら若い心の奥にあらあらしい足どりをとどめる。今までかつておぼえなかったやうな深々しい印象である。
風巻景次郎 著子文書房 1940年
風巻はこう書き始めたのである。「文学の発生」とは文学史における最初の文学の発生のことではなく、若者の心の中に生じるもののことだ。
ある詩人はそこにさびしさをしか見つけられなかった。
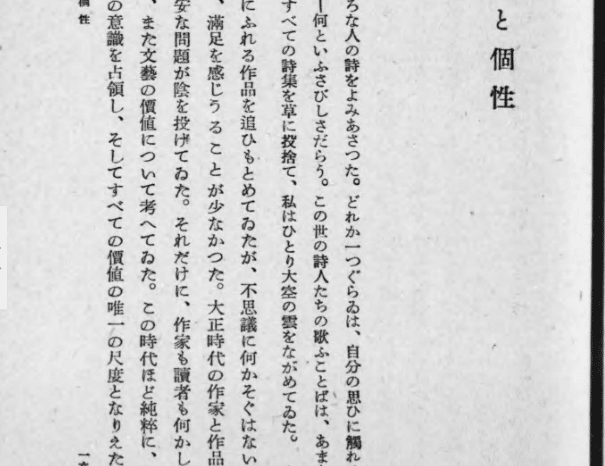
萩原朔太郎である。圧倒的なものに打ちのめされること、例えば日本語の魔術師に激しい嫉妬を覚えなかったことは、彼の天才の不幸でもある。
風巻もこんなことを言ってみる。
かゝる考を助けたのは、芥川龍之介の言である。彼は小說の命は二三十年位のものであると書いてゐる。そして明治時代は既に二十年の彼方にある。
だから明治の文藝は、感銘を私に與へ得なくともそれは私がわるいのでは決してない。そしてそれは感銘を與へぬ故に古典である。私の理窟は大體かうであつた。
個性という言葉を使う人はたいてい独りよがりのエゴイストである。「私がわるいのでは決してない」という理屈は、実は漱石と芥川に関して言えば当てはまらない。あなたが悪いのだ。
文学的な仕掛けが理解できないと感銘が受けられないようなものを、少なくとも漱石と芥川は書いてきたのだということを私はより具体的に繰り返し説明して来た。
重箱の動きが解らないと『行人』は解らないよとか、九星くらい計算しないと『道草』の面白さは解らないよとか。
あるいは位置関係や時代を掴まないと意味が解らないよと書いてきた。
解らないのは漱石や芥川の所為ではない。そのひらめきは突如発生してあなたの心をとらえる。
丸見えだったのかという驚きとともにその記憶は心に刻まれる。これが本当の文学の発生である。今にして思えば、風巻が中世の詩歌の研究に没し、漱石や芥川の価値に辿り着けなかったことは、残念なみくびりであつたというしかない。
現に芥川作品は百年後まだ読まれる可能性を秘めている。
けれどもそれ等は、歷史的なる過去の一部を、在るがまゝに把握せんとする事からは世にも遠い立場のものであつて、おしなべて、作家自身の痛切なる主題を表現する爲に過去を借用したものに過ぎないのである。
こうも言って風巻は芥川や谷崎や菊池寛の過去の時代を材料にした作品の価値を認めない。つまり『芋粥』に現在の読者が参加させられていることに気がついていないのだ。それが平安前期の把握ではなく、千年変わらぬ人間の普遍的なものをめぐる小説であることに気が付いていないのだ。しかし読者の参加を見抜くのは、言ってみれば単なる国語力であり、それを見落とすのは国語力が足りないか、集中力が足りないかで、どちらが悪いのかと問われたら、あんたが悪いというほかない。
伝統詩歌の世界に深く沈みながら国語力がない?
実はこのことは風巻の個性などではないのかもしれない。
實際僕等の詩は、明治以來の新文化が初めて生んだ新しい詩で、傳統詩歌の和歌俳句等に對立するものなのだから、正統の意味に於て文字通りの「新詩」である。今後僕は、必要の場合すべてこの名稱で書くことにした。
日本への回帰
萩原朔太郎 著白水社 1938年
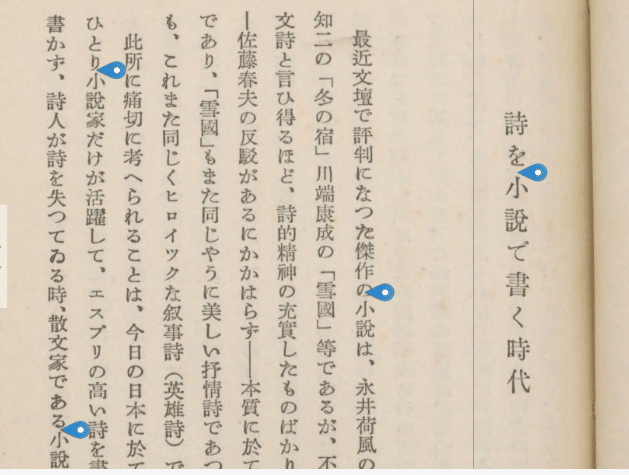
萩原朔太郎が川端康成の『雪国』に関して述べていることは間違いではない。「夜の底が白くなった」と言われれば、誰しもが詩を認めざるを得ない。しかし、その詩は芥川龍之介が二十年も前に使ってもいた詩なのである。
下人は、剥ぎとった檜皮色の着物をわきにかかえて、またたく間に急な梯子を夜の底へかけ下りた。
そして萩原朔太郎は夏目漱石を全く評価していない。まるで漱石には抒情性がないかの如く無視をする。
「死んだら、埋めて下さい。大きな真珠貝で穴を掘って。そうして天から落ちて来る星の破片を墓標に置いて下さい。そうして墓の傍に待っていて下さい。また逢いに来ますから」
ここには注意深く読まないと見落としてしまう文学的な仕掛けなどない.ただ美しいとしか言いようのない詩がある。もろくはあるがもろさも詩である。
「もう十一時だから御帰りなさい」と私はしまいに女に云った。女は厭な顔もせずに立ち上った。私はまた「夜が更けたから送って行って上げましょう」と云って、女と共に沓脱に下りた。
その時美くしい月が静かな夜を残る隈なく照らしていた。往来へ出ると、ひっそりした土の上にひびく下駄の音はまるで聞こえなかった。私は懐手をしたまま帽子も被らずに、女の後に跟いて行った。曲り角の所で女はちょっと会釈して、「先生に送っていただいてはもったいのうございます」と云った。「もったいない訳がありません。同じ人間です」と私は答えた。
次の曲り角へ来たとき女は「先生に送っていただくのは光栄でございます」とまた云った。私は「本当に光栄と思いますか」と真面目に尋ねた。女は簡単に「思います」とはっきり答えた。私は「そんなら死なずに生きていらっしゃい」と云った。私は女がこの言葉をどう解釈したか知らない。私はそれから一丁ばかり行って、また宅の方へ引き返したのである。
これが例のデマを産んだ所以ではないかと思うところ。月は美しい。
ここには少しだけ文学的仕掛けがあるが、それにしても抒情性が勝っている。何かギリギリのところでバランスを保つ人間関係の機微というものを捉えている。「私がわるいのでは決してない」という理屈は、漱石と芥川に関して言えば当てはまらない。あなたが悪いのだ。
[附記]
文学的仕掛けというのは、漱石が文字通り「送る」と言って「女の後に跟いて行った」という絵面。明治の男が女の尻を下駄の音もたてずに一丁もつけて行ったら、そりゃおかしい。
大体女の人は後ろからついてこられて尻を見られていると嫌がるものである。それを「光栄」と言わせているところが面白いれど、無理にそう茶化さないでもいいかもしれない。
以前付き合っていた彼女と家で大喧嘩をして、出ていく!と部屋を飛び出したので、勝手にしろ!とブチ切れたが、夜中に女の人が1人は不安なので必死に走って追いかけたら彼女から電話がかかってきて息を切らしつつ電話に出たら「言いづらいけど後ろ見て...多分追い越してる...」と言われたことがある。
— げんげん/Blue Mash (@_236745981_) April 7, 2024
これは私もいつも感じています。「みんな」は誇張法だと思いますが「ほとんど」そうであることは字義通り真実だと思われます。 https://t.co/Mpc0j2DQeK
— 永井均 (@hitoshinagai1) April 7, 2024
「文豪風評被害三銃士を連れて来たよ」
— 乱会 (@ransedoukoukai) April 4, 2024
「文豪風評被害三銃士?」
「力道山殺害未遂の与謝野晶子」
「うっす、よろしく」
「ハマコーに殺人犯扱いされる宮沢賢治」
「がんばります、よろしく」
「金閣寺を燃やした三島由紀夫」
「よっす、どうも」 pic.twitter.com/Kit1GKuBCu
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
