
第11回 神戸・新開地「『御堂筋いくよ・くるよ』作戦」
不思議な偶然のチカラ
前回に紹介した2本の連載を続けながら会社員から転身した人たちをテーマに書籍化を考えたが、編集者と出会える機会がなかった。
一番フィットするのは、日本経済新聞の読者層だと想定していた。日々ビジネス中心の仕事をしているものの、実際は自らの生活を充実させたい会社員に私の発信はより届くと考えたからだ。
ある日、紀伊国屋書店梅田本店で書籍を購入した際に、たまたまカウンターにあった「加藤廣先生サイン会」という小さなチラシに気がついた。サイン会の日時と場所の下段には「お問い合わせ 紀伊国屋書店梅田本店(電話番号)」と記載されていた.
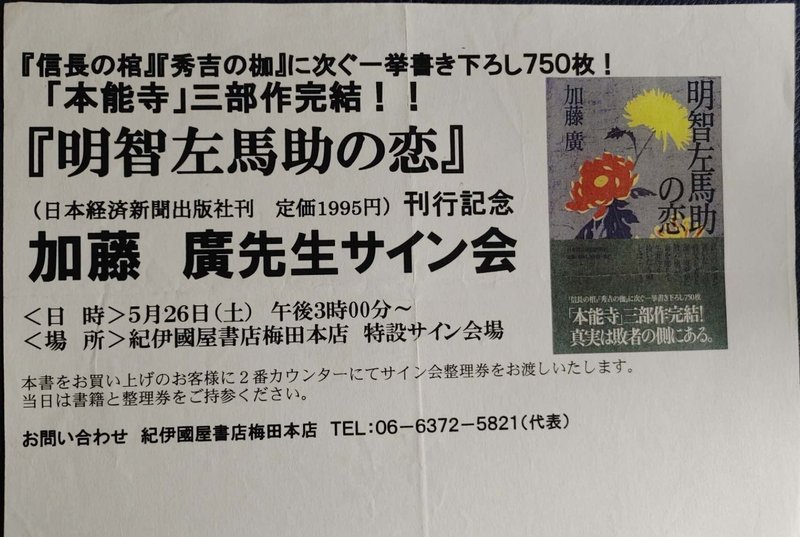
加藤先生は、中小企業金融公庫(現日本政策金融公庫)に勤めた後に作家に転じたので、以前から転身者の取材対象としてリストアップしていた。
著書の『信長の棺』(日本経済新聞出版社)は、当時の小泉総理が愛読書として挙げたこともあって大ベストセラーになっていた。
チラシを見て、紀伊国屋書店ではなく、直接加藤先生でもなく、あえて日本経済新聞出版社に取材依頼を入れた。朝日新聞で連載中の「こころの定年」に登場いただきたいと考えたのである。
当日は、講演会場近くのホテルのロビーラウンジで加藤先生から話を聞いた。その場には日本経済新聞出版社の比較的若い編集者が同席してくれた。
先生の興味ある話を聞くとともに、傍らに座っている編集者に「私は、こんな取材を続けています。面白いでしょう。私のテーマに関心はないですか?」という波動を送り続けた。
インタビューだけでなく同時に売り込みもする忙しい取材だった。
その時の編集者N氏は、その後『人事部は見ている。』をはじめ、数年間かけて私が日本経済新聞出版社から発刊した5冊の本をすべて担当してくれた人物なのである。その日は、『信長の棺』担当の編集者が随行できなくなってN氏が代理で来ていた。
偶然のチカラは不思議だ。あの時、紀伊国屋書店で本を買わなければ、カウンターにあったチラシに気づかなければ、日本経済新聞出版社を経由して依頼していなければ、その編集者が代理で来てくれていなければ、どれかが欠けても日本経済新聞出版社から何冊も本を出せなかった。
30年以上働いた生命保険会社の組織内では、こういった偶然を体感したことはない。
書籍を出しているサラリーマンを探せ
当時は編集者を探しながら、「本を書いているサラリーマンはどんな人なのか」を自らの眼で確認していた。小説や専門書を執筆している会社員は少なくなかったが、私は幅広く発信したかったので、一般書籍を執筆している著者を探した。
たとえば、当時「週末の達人」と呼ばれていた小石雄一さん(1958年~)は、通産省に在籍しながら多くの本を出版していた。
彼の共著『本を書こうよ! サラリーマンよ、立ち上がれ!〝二足のわらじ作家〟デビューへの道』(同文書院)は、私のような初心者には参考になる本だったので何度も読み返した。
2007年には彼に取材をして朝日新聞の連載に登場してもらった。
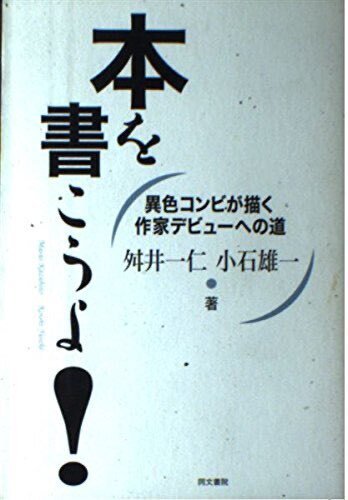
小石さんは、数多くの勉強会を主宰していて、ビジネスマンのライフスタイルや知的生産に関する書籍を数多く執筆していた。
彼がアフター5や週末を利用した活動に取り組むきっかけは「役所での先行きが見えたからだ」と話してくれた。
いわゆるノンキャリアなので昇進にも限界がある。そのため職場のキャリアアップ以外の生き方を模索したというのだ。
「通常残業省」とも呼ばれた多忙な職場なので色々な工夫も凝らした。
「逆残業」と称し、朝の7時前に出勤して仕事を片付けたり、職場の親睦会の幹事は率先して引き受けたりして自分のスケジュールと調整したそうだ。
彼にその働き方についての見解を問うと「ワークライフバランス」ではなくて「ワークライフインテグレーションだ」と説明してくれた。仕事の時間を削ってバランスをとるのではなく、仕事と社外の活動を統合すると相乗効果が生じると主張していた。
実際にも社外活動で得た人脈は、役所での仕事に役立っていると強調していた。
サントリーの元社員だった野村正樹さんにもいろいろ話を伺った。
彼は現役社員の時に、推理作家としてデビュー。50歳の時に選択定年制度によりサントリーを退社して、推理小説のほかに会社員向けのビジネス書を多数書いていた。
お二人以外にも話を聞いたが、会社員として働きながら執筆するという環境は同じなので参考になることが多かった。
同時に、彼らが書いている内容は会社員の仕事や趣味といった枠内に留まっていたので、会社員の生き方自体をポイントにすると私なりに個性を発揮できると考えた。小さい頃から、商店主や職人、アウトローの人たちに囲まれて育ち、会社員や公務員は全くいない環境だったので違った味が出せると判断したからだ。
『人事部は見ている。』がヒット
先述の日本経済新聞出版社のN編集者に意見を聞きながら執筆した『会社が嫌いになったら読む本』(日経プレミアムシリーズ)は、一定の反響があって重版となった。
しかし『就職に勝つ! わが子を失敗させない「会社選び」』(ダイヤモンド社)、『就活の勘違い』 (朝日新書)は、それほどの広がりはなかった。
当時は、大手の生命保険会社で採用責任者を務めた経験と、娘の就活では会社選びから内々定まで親子で語り合いながらルポしたこと、大学の非常勤講師を務めてゼミ生にも繰り返し話を聞いていたにもかかわらず、書籍の読み手を絞れていなかった。
漠然と学生を読者と考えていたが、彼らは全体感のある手引書ではなく、ノウハウ的な本を欲していた。
読み違いがあったのである。学生の就活支援をしている人たちや企業の採用担当者を読者対象とすべきだった。
『就活の勘違い』で私も勘違いしていたのである(笑)。
執筆する書籍は目の前にいる人に深く刺さることが大切だという反省から、それ以降は私の「顧客」を比較的大きな組織で働く中高年の男性会社員に絞り込んだ。
これが『人事部は見ている。』(日経プレミアムシリーズ)のヒットに結び付いたのだ。部数は13万部まで伸びた。

企業経営では人的資源は重要な位置を占めるので、人事関連の書籍実用書は数多く出ている。ただ実際に働いている立場から読むと、実態とは少しかけ離れた印象があった。
そのため自らの人事部での体験、社員が人事部をどう見ているかの観点、人事異動や評価に関する実際のケースを取り上げて論じるなど、できる限りリアルな内容にすることを心がけた。
定期異動日の朝から夜までの社員や人事担当者の動きを描いたりもした。また客観性を得るために、仕事で付き合いのあった他社の人事担当者からも話を聞いた。
文中では、大きな組織で課長クラス以上の「出世する条件」は、「(結果的に)エラクなる人と長く一緒にやれる能力だ」とか、「人は自分のことを3割高く評価している」など、他の本には決して書いていないことを論じた。
これが多くの人に手に取ってもらった理由であると考えている。
このような「出世する能力」は、私には決定的に欠けているものだと痛感していた。
3割増しの法則は、実際に私が体験した人事異動のケースを例に引いて述べた。また歯の浮くようなお世辞で周囲がドン引きしても、本人は普通に受け止めるのもこの法則があるからだ。
『人事部は見ている。』(最後に「。」が付いている)という奇妙なタイトルも現実感を呼び起こすためにN編集者と一緒に考えた。
松嶋菜々子主演のTVドラマ『家政婦のミタ』に乗じたという人がいたが、実際には『人事部は見ている。』の方が半年くらい早いのである。
この頃から会社員という立場を元に発信することが独自性の発揮につながるという確信を得た。若い頃から執筆している作家や物書きには個性や蓄積では到底かなわない。会社員という枠組みをうまく使うことしかないと痛感したのである。その後は一貫して会社員を対象とするか、読み手とするか、の書籍しか出さないことにしたのである。
「御堂筋いくよ・くるよ」作戦
得体の知れない人間が書いた『人事部は見ている。』がヒットしたので、各出版社の編集者から書籍のオファーが次々と届いた。おそらく20社程度はあっただろう。
出版社との打ち合わせや雑誌の取材対応などで忙しくなったので、勤めていた会社と御堂筋をはさんだ近くにレンタルオフィスを借りた。

御堂筋の東側にいる時は、生真面目な生命保険会社に勤めるサラリーマン、西側に行くと、なんとか一発当てたい著述家に変身することになった。
一人二役の「御堂筋いくよ・くるよ」作戦が始まったのである。

実際に実行してみると、著述業がスムースに走り出せれば、会社員としての仕事も充実する、逆に、会社での仕事がうまくいけば、執筆の調子も上がってくることに気がついた。
私はこれをピンク・レディーの大ヒット曲「UFO」の振付になぞらえて「ピンク・レディー効果」と呼んでいる。
右手が回ったら左手も回る、左手が回れば右手も回るという相乗効果があるからだ。
そもそも身体でつながっているので両者を分けることなどもできないのである。先述した小石雄一さんの「ワークライフインテグレーション」の主張と符合している。
会社の中にどっぷり浸かっているときは、「余裕なんてない」と思っていても、「こんなことをやりたい」と主体的な姿勢で一歩踏み出すと、会社の仕事との調整はなんとかなる。
仕事以外のことをやると疲れると考える人もいるが、人間は機械ではなく、生身の人間なのでやりたいことに取り組むとエネルギーが湧いてくる。むしろやりたいことを我慢している方がよほどエネルギーを消耗してしまうのである。
そしてこの「ピンク・レディー効果」が昂じていくと「どうにもとまらない」高揚した気分が充満する「山本リンダ状態」に至る。
二つのことを並行させていくと、各々が他のことに対する気分転換にもなるのである。
今から振り返っても、「定年退職後は著述業に専念できていいですね」「女子大の教授とは羨ましい」と言われたこともあるが、私が最も楽しめたのは、この「御堂筋いくよ・くるよ」生活なのである。
入社3年目の若い営業ウーマンから「社内でこんなに楽しそうにしている人に初めて出会った」と驚かれて、他部署の先輩からは「お前、何かやってるやろ。(役職復帰を断った)平社員なのに一番イキイキしている」と言われたりした。
副業禁止が頭に浮かぶ人もいるだろうが、
・会社の仕事をないがしろにしない(ように見せる)。
・直接の上司や同僚とうまくやっていく。
この二つをしっかり押さえておけば、会社員が取り組める範囲は大きく広がる。もちろん自分が勤めている会社のスタンスを見極めておくべきであることは言うまでもない。
40代後半の休職時の前後は、「こんな会社ではもう働けない」と思い込んでいたが、執筆を始めてからは、「会社ほどいいところはない」と変化したのが我ながら可笑しかった。会社は何も変わっていないからである。
名前を二つか三つ持とうよ
私は、執筆や講演、大学の教員も一貫して「楠木新」という芸名で通してきた。
その理由は、会社には伏せておきたかったこと、また会社の役職や立場とは関係なく自分の腕一本で勝負したい思いがあったからだ。
事実、芸名で執筆や講演活動をしてみると、もっと自由にやれたのに本名の自分に縛られていたことに気がついた。「A会社の田中」と何度も名乗ったり呼ばれたりするうちに、田中さんにとって社名は自分のアイデンティティーの一部になってしまう。私も勝手に自分に枠組みというか活動の制約を課していたのである。
「楠木」は私が通った神戸の中学校の名前から、「新」は、育った地名である神戸・新開地からとった。新たに生まれ変わるという意味も込めた。
私が会社生活に行き詰まり休職した時に脳裏に浮かんだのは、子どもの頃の身の回りにいたおもしろいオジサンたちや周囲の歓楽街で暮らしていたアウトローの人たちだった。
彼らは高い収入や安定した老後を望めなかったはずなのに、私の周囲にいた会社員よりもはるかに楽しそうな顔をしていた。
また中学時代は野球部に入って、放課後は友人と一緒に映画館を巡り、神戸松竹座の漫才や落語などをよく観に行っていた。夜になれば、銭湯で友人とだべっていた。あの頃の日々が永遠に続けばよいと思ったので、芸名すなわちペンネームに使った。
遠藤周作の『周作塾 読んでもタメにならないエッセイ』(講談社文庫)の冒頭の小見出しは「名前を二つか三つ持とうよ」である。
遠藤周作は「沈黙」や「深い河」などの重いテーマの小説を執筆する一方、狐狸庵(こりあん)とも称して、素人劇団をつくったり音痴の合唱団を結成したりした。
それによって人生の探求心と生活の好奇心を併存させて、人一倍生きた気持ちだと語っている。
狐狸庵こと遠藤周作は、社会生活用の実名のほかに、個人生活用の名前を少なくても一つか二つは作ることを勧める。同時にこの別名を本名と同じように大切にすべきだという。
名前が一つでなければならない理由はない。そもそも人は多様な面を持っているので立場に応じて名前を変えたほうが、自然体でぴったりするのである。
本名の私は、「楠木新」のプロデューサーあるいはマネージャーの役割も担っている。自身を客観的に見る別の視点が大切なのだ。
「楠木新」の芸名で活動して困るということはほぼない。電話に出るときに最初「もしもし」と言って、相手を確認してから、本名と芸名のどちらを名乗るか決めるぐらいのことだ。
ライフサイクルで考えてみれば、会社員時代の私も大切であるし、学生時代の自分や、子どもの頃の自分、定年後の現在の自分も各々価値ある人生の一部である。
二つの名前を使い分けて役割を広げることによって、日々全人格的に生きていると感じることができるとともに、二つの顔からゆとりが生まれ、自分自身の物語を作り、語りやすくなるのである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
