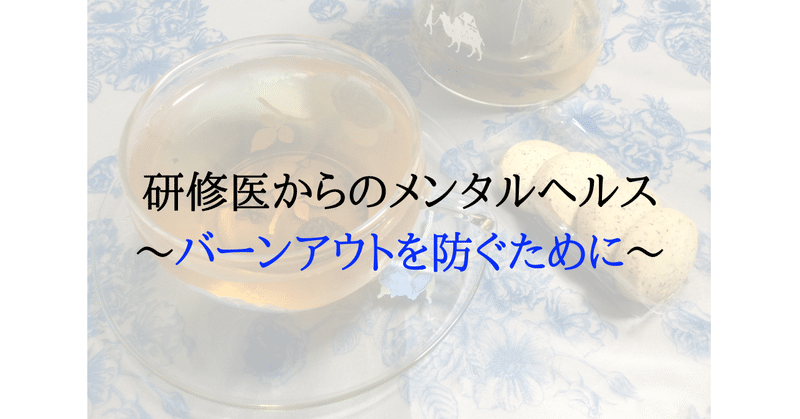
研修医からのメンタルヘルス〜バーンアウトを防ぐために〜
新研修医、新専攻医の皆さん、日々の業務お疲れ様です。
そろそろ、ストレスからの体調不良がきやすい時期ではないでしょうか。
それは、4月からの新しい生活をなんとか2ヶ月surviveしたわけですから、体調を崩してしまうのも不思議なことではありません。
実際、私は研修医1年目の時にバーンアウトを経験し、2ヶ月の休職を経験しています。
詳しくは以下の記事をご覧ください。
このnoteでは、自分の経験も踏まえて、バーンアウト予防に対して個人レベルでできることについてまとめています。
本来、バーンアウトに対しては個人・職場単位・病院ぐるみで考える必要があることです。まずは個人レベルでできることについて、考えてきたことをまとめたので参考にしていただければ幸いです。
そもそもバーンアウトとは
バーンアウトとは、それまで意欲的に仕事に取り組んでいた人が、極度の心身疲労により意欲が低下してしまった状態を指します(出典:日本プライマリ・ケア連合学会基本研修ハンドブック改訂3版 p.265)。
バーンアウトの状態かどうかは、以下の3つの症状で定義されます。
①情緒的消耗感
心がすり減り、疲れ果てている状態。3つの症状の中の中心症状。
例)「もう、本当に疲れたな・・・。辞めたいな・・・。」
②脱人格化
他人を思いやれるような、人としての温かみががなくなった状態。
例)「担当患者さん?どーでもいいや・・・。」
③個人達成感の低下
自己肯定感が下がっている状態。
例)「ああ、やっぱり私ってダメだなあ・・・。」
(出典:日本プライマリ・ケア連合学会基本研修ハンドブック改訂3版 p.266)
これらの3つの症状が現れ出したら、要注意です。
バーンアウトしている本人は気づかないことも多々あるので、周りが「大丈夫?」って声をかけることも大事です。
医師がバーンアウトする影響
医師がバーンアウトすると、もちろんその医師自身の人生への影響は多大でしょう。でも、それ以外ではないのです。
以下、ご許可をいただいて、和足先生のTwitterをご紹介します。
医師がバーンアウトするデメリットのエビデンスの蓄積 。Dr. Dr. Westの講演を聞いてめちゃ感銘をうけました。 @ColinWestMDPhD
— Takashi Watari🇺🇸M.D, MHQS, Ph.D (@wataritari1) May 19, 2023
1) Medical errorsが増加
2) 患者満足度低下
3) 離職増加
4) 勤務時間減少
5) 学習意欲低下
6) 鬱病発症
7) 交通事故増加
8)医療経済的損失🇺🇸年間46億ドル
医師がバーンアウトすると、患者さんにとっても多大な影響が出る、
その医師を雇っている病院にもマイナスになる、経済損失的に国にもマイナスになる・・・。悪いことしかありませんよ・・・。
だからこそ、バーンアウトについては個人・職場単位・病院単位で考える必要があるのです。
医師生活はバーンアウトリスクに溢れている
そもそも医師として生きるというのは、とても大変なことです。
長時間勤務、オンコール、夜勤などなど、物理的にハードワークなのですから。そして、医療は常に不確実です。
世の中には教科書通りの典型的な患者さんしかいなくて、教科書通りの治療していれば治る・・・ということはありません。
大学までは、問いに対して必ず1つの正解がある世界でした。
でも、実際の臨床現場は、患者さんごとに、それも無数の解がある世界です。
そんな世界では、今まで自分が信じてきたことも時として無力です。
だからこそ、チーム医療の中で協力して、より良い解を、その度毎に導き出していかなければならないのです。それには医師自身も悩むことも多々あるでしょう。それが大学の医学教育と、臨床現場の最たるギャップだと思っています。
さらに輪をかけて、研修医・専攻医にはまた別の大変さも加わります。
それは、ローテーションで頻繁に診療科や病院が変わることです。
1ヶ月毎に変わるローテーションだと、さながら「毎月転勤しているような」感じですよね。その診療科で必要な医学的知識や技術を深めるだけでなく、その部署毎のシステム、上級医との関係も再構築しなければいけません・・・。地域研修などでは、別の病院で勤務することにもなります。引越しも加わりますし、それが頻繁にというのは、ものすごく大変なことです。
医師の世界にも働き方改革の波が来つつありますが、まだまだというのが現状です。それに、研修医・専攻医の研修システムで必要なローテーションシステムはなくすことはできないでしょう。
つまりは、バーンアウト予防のために、個人レベルでできることの手札を持っておく必要があります。
バーンアウトしないために大事なこと
では、バーンアウトしないために個人レベルでは何ができるのか、私が考えていることをまとめてみます。

実際、どれも言われてみれば当たり前のことなのです。
でも、それらを実行することは意外と難しかったりします。
①毎日、食事と睡眠をしっかり取ること
どんなに忙しくても、食事・睡眠はしっかり取りましょう。
私たち医師とて人間です。空腹、寝不足はパフォーマンスに悪影響を及ぼします。それで一番迷惑を被るのは、他でもない、自分が診る患者さんたちです。
特に研修医や専攻医の生活は、前述のように周囲の環境も1ヶ月でガラッと変わる、非常にストレスフルな生活です。それでからだや心に変調をきたすのは、むしろ当たり前だし、正常な反応です。それなのに、空腹や寝不足の状態で無理をして「自分が弱いんだ」と思い込むのだけはやめましょう。
バーンアウトしないための基礎となる、栄養のある食事と、十分な睡眠時間の確保は、医師にとって最低限の義務です。
②自分なりのストレス解消法を持つこと
皆さんは趣味など、自分がリラックスできる術はお持ちでしょうか?
私は読書、音楽鑑賞、映画鑑賞、執筆など色々な趣味を持っています。
そして、私にとってそれら趣味を楽しむことが、しんどいな・・・と思った時のストレス解消法にもなっています。
「研修医のための人生ライフ向上塾!」によると、ストレスマネジメントの基本は3Rと言われています。
・Rest:休息や睡眠
・Recreation:レクリエーション、趣味など
・Relax:リラックス
(出典:鈴木瞬「研修医のための人生ライフ向上塾!」p12)
体に必要不可欠な睡眠や休憩(Rest)はもちろん大切ですが、仕事とRestだけでは心がしんどくなりますよね?
自分が楽しめたり、リラックスできるような時間を持つのも、バーンアウトしないためには大切です。3R、ぜひ意識してみてください。
③自分のストレスサインに気づくこと
自分にとってストレスフルな状態において、自分の心身が出すサインに注意を向けることも大切です。
・なんだかイライラしてばかりいる
・周囲に対して怒りっぽくなる
・仕事していても集中できない
・凡ミスばかりしている
例えば、上述のような症状があった場合、ストレスが溜まっているサインかもしれません。
「ああ、ストレスが溜まっているんだな」
とメタ認知できれば、②のストレス解消法に進めますし、自己嫌悪に陥ることもありません。
人によってそれぞれストレスサインは異なるので、ちょっと意識してみましょう。
④まずい、と思ったら、迷わず信頼できる誰かに相談すること
・寝つきが悪い状態が続く
・食欲がない状態が続く
・体を動かせない状態が続く
・休日もソワソワしてリラックスできないような状態が続く
上述のような症状があった場合、それはストレスが溜まっているを通り越して、心身が限界で悲鳴を挙げているサインかもしれません。
そんな時は無理しないようにし、周囲に相談してみてください。
臨床研修部の他、病院の産業医やカウンセラーなど、多くの研修病院では整備されているはずです。
自分がしんどいなーと思ったタイミングは、誰かに相談するタイミングです。
⑤自己肯定感を保つこと
前向きな状態で過ごすことも、バーンアウトしないために大事な要素です。
医療社会学者のアーロン・アントノフスキー博士が提唱した「健康生成論」では、以下の3つがストレス対処力「SOC(Sense of coherence:首尾一貫感覚)」に重要としています。
・把握可能感(わかる感)
自分の置かれている状況がある程度予測できる、理解できるという感覚。
例)「この仕事を任されたのは、自分が研修医だからで、経験を積む機会ってことだな」
・処理可能感(できる感)
何とかなる、何とかやっていけるという感覚。肯定的な意味での楽観視。
例)「この仕事はちょっと難しいけど、あの人にアドバイスをもらえれば何とかなりそう」
・有意味感(やるぞ感)
自分の仕事や置かれた状況に前向きな意味・意義づけができる感覚。
例)「希望したところじゃなかったけど、ここで頑張って、後でここで良かったと心から思えるように努力しよう」
出典)以下のリンク(最終アクセス 2023年6月18日)
https://www.earthship-c.com/psychology/sense-of-coherence/
ちなみに、私は自己肯定感を高める上で最大の敵は、他者との比較だと思っています。研修生活には、良くも悪くも、同期がいます。
比べるのは同期ではなく、常に「昨日までの自分」としましょう。
そうしたら、成長あるのみです。
一日一つでも、自分が成長したと思えたなら万々歳です!
終わりに
私は、研修医2年目の時に、今までにないほど激怒したことがあります。
同期間で、入職して来たての1年目向けにアドバイスを集めた時のこと。
同期の誰が書いたのかは知りませんが、
「死ぬまで働こう」という文字がそこにはありました。
冗談でも、「死ぬまで働こう」なんてアドバイスはしないで欲しい。
自分で高いハードルを設定して、限界まで追い込んで、文字通り「死ぬほど」頑張って「しまった」人間なら絶対にそんなことは言いません。
「死ぬ気で頑張る」スタンスは自己の成長にとって理想的ですが、健全な精神は、健全な身体あってこそです。
「死ぬまで働く」オーラで命すり減らそうとしている後輩がいたら、「ちょっと待った」をかけるのが、先輩としての私の一番の役目だと思っています。
出典)
・日本プライマリ・ケア連合学会基本研修ハンドブック改訂3版
・鈴木瞬「研修医のための人生ライフ向上塾!」
・以下のリンク(最終アクセス 2023年6月18日)
https://www.earthship-c.com/psychology/sense-of-coherence/
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
