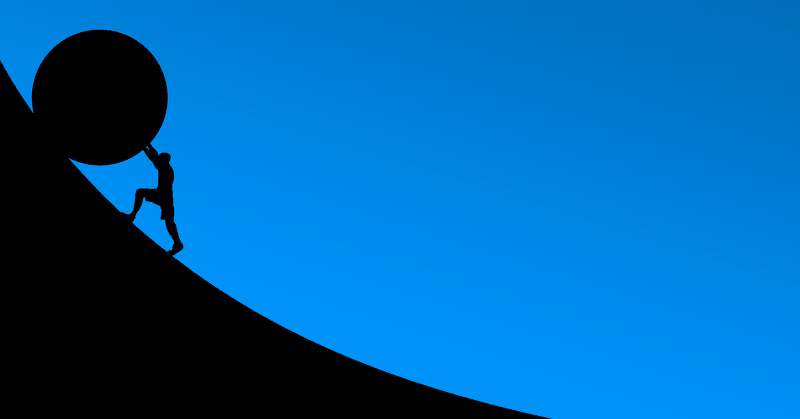
〔意志〕のパラドクス ところで、ショーペンハウアーはペシミストなのか?
ショーペンハウアーが〔意志〕という言葉を使うとき、世界は反転する。
意志という概念は、哲学の伝統用語であり、またわれわれの日常用語でもある。
例えば、「わたしは〇〇高校に受かりたいがために〇〇を勉強することを意志決定する」このように、意志という言葉は、なにかの目的や目標に結びつけられていることが多い。
しかし、ショーペンハウアーの意志は、これとはひと味違う。
そもそも「〇〇高校に受かりたいがために〇〇を勉強する」このような努力(運動)は、それ自体すでに意志の発現である。
ショーペンハウアーはこのように言う。
意志は、それ自体で原初的な運動である。
われわれは人生における個々のケースで、この意志を意識することがあるが、その時われわれは、自らの目的や目標を意識している。
もう一度言おう、「いま君が、なにかを努力しようと運動しているが、そのことは君の意志の表象である。われわれが内部から体験した意志から出発するとき、世界がわれわれの表象であることを度外視した後にも残る本質的な世界、つまり物自体としての意志の世界を、君は理解することができるはずである」
このような認識論は、意志の自由を訴える理論に対しペシミスティックであり、カントとも真っ向から対立する(カントの実践理性は、意志を規定する根拠を義務に基づく定言命法に求め、自然と自由の二律背反の上でバランスを取ることにある)
ショーペンハウアーに、簡単に言ってもらおう。
例えば、「大人になったら〇〇になる」というような目標。そんなものは全て無意味であり、「わたしが何者であるか?」と言った類の問いには、何の意味もない。
なぜなら、わたしの意志は、わたしが自由に作ることなどできないのであり、わたしの人生の中での様々な行為が、わたしが何者であるかを示すのであり、わたしという意志が、時間空間という形式において、表に出ているのである。
ようするに、人間は認識の光により自己を作り上げるのではなく、人間はあらゆる認識に先立ってすでに作り上げられていて、認識はただ出来上がったものを照らすために、後から人間に付け加わったものにすぎない。
それゆえ人間は、自分がこんな人になりたいあんな人になりたいと自ら決めることなどできず、彼はただ一回限りにあり、自分が何であるかを後から次第に認識し、自分が何を欲するのかを認識してゆくのである。
意志とは、わたし自身がそれであるところの現実であり物自体である。わたしはその世界において、世界がわたしの表象であるところとは別の世界を、自分の肉体で体験するだろう。
その人の顔や姿を見給え、性格や個性や身体つき(体形)というのもの、個体の特徴的な容貌こそ意志の客体性であり、常日頃の行動や行為や言動に、意志は発現しているではないか。
ところで、意志をもっとも発現するものは芸術である。ゴッホを見給え、セザンヌを見給え、ベートーヴェンを聴き給え、ゲーテを読み給え、あれこそ意志の表象行為である。
わたしの発言は誇大だろうか? しかし科学の説明は、物自体を超え出ることはないから、科学は物自体に関することがらを放置しているのであり、科学が放置しているその場所で、再びこのことがらを本来的に取り上げるのが哲学であり、哲学は科学と異なる方法でこのことがらを考察することである。
哲学にとっては、科学がすべてをそれに還元し満足している根拠の原理それ自体が問題なのであり、科学がみずからの説明の根底におき、説明の限界として設定しているものこそ哲学の本来の問題であり、したがってそのかぎりで言えば、科学の終わるところに哲学が始まるのだと言ってもよい。
現在の哲学は世界が「何のために」存在するのかを探究するものではなく、ただ世界が「何であるか」を探究するにとどまるものである。
世界が何であるかは、各人が認識の主観であり、世界がその表象なのであるから、誰でも格別の助けを借りずに認識していることであるが、哲学の任務はこの具体的な認識を抽象的な知にいたるまで高めることである。そのとき哲学は抽象概念のかたちで世界をもう一度完璧に繰り返し、いわば世界をこのかたちで反射することとなるであろう。すでにフランシス・ベーコンは哲学に以上のような課題を立て、こう言っている。
「世界そのものの声をもっとも忠実に復唱し、いわば世界の口述するところをそのまま写しとった哲学のみが真の哲学である。それはまた世界の模写と反射にほかならず、なにか自分自身のものをつけ加えたりせずに、ただひたすら繰り返しと反響をなすだけのものである」
われわれはしかしベーコンが当時考えることができたよりもこれを広い意味に拡張して考えたい。世界の抽象的な模写が相互に浸透し合っていれば、その力は合流し、一つの思想という統一を得るにいたるであろう。
身体は意志の現象として限定されていて、根拠の原理(時間、空間、因果律)に入ってしまっているのだから、自分を自由であると思いこみ、いつなんどきでも自由に別の生活態度を始めることができるとか、別の人間になることができるなどと考えているとすれば、それはアプリオリにそうだというだけであり、アポステリオリには、誰でも経験によって自分は自由ではなく、必然性に支配されていて、どんなに決意してみても自分の行為を変えることはできず、一生の始まりから死ぬまで、自分でも嫌だと思っている性格をもちつづけていくだろうし、いったん引き受けた役割を最後まで演じ切らなければならないのだという始末である。
カントは経験的性格と叡智的性格との区別を示し、自由と必然との間の関係を、意志と現象との関係として説明することで、みごとな業績をあらわしているが、わたしの意志すなわちわたしの叡智的性格が時間の中で現象すればわたしの経験的性格となるのであり、時間の中で存在者がなにかを意欲すること、これは存在者の叡智的性格の発動であり、叡智的性格とは意志そのものであり、物自体であり、あるいはもっと本来的にいえば、イデア(プラトンの言う)においと現れる根源的な意志の動きと一致するのである。
人間は意志によって決定された現象であり、性格は、ほかならぬ自由な意志の自由な意欲により決定づけられた現象である。
個人のうちに一定の程度で現象化する叡智的性格(意志)は、時間的に言えば行動様式となり、空間的に言えば体格となって現れ、個人の経験的性格として現象そのものとなる。
人間の個々の行為、生涯における経験的性格に自由はなく、経験的性格は叡智的性格(自由な意志)に決定づけられており、すでに子供のときから認められる決定的な素質が発展したものであり、したがって人間の行状は生まれた時点ですでに定められているのだというキリスト教の予定説にわたしは同意する。
するとわれわれの人生に残された問題はあと一つだけである。
われわれはこの意志を、肯定すべきか? あるいは否定すべきか?
「生きんとする意志の肯定および否定」という概念は、ひとつの行動様式である。
わたしがもっぱら目的とするところは、生きんとする意志の肯定と否定という双方の概念を説明し、これを理性によって明晰に認識することであり、どちらか一方をとるよう指図したり、人に勧めたりすることではけっしてない。
さて、ショーペンハウアーをペシミストという一言で片づけるのはあまりにも浅学である。
四巻を読むだけでも、彼の「一つの思想」の輪郭が見えてくるだろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
