
第6回 先人の肩に乗って(1)
若いビジネス・リーダーの人たちと一緒に本を読む機会がありました。選んだ本は、本多勝一『アムンセンとスコット』(朝日文庫)です。

いまからおよそ100年前、1911年から12年にかけて、人類初の南極点到達一番乗りを競ったノルウェーの探検家ローアル・アムンセン(38歳)とイギリスの海軍大佐ロバート・スコット(42歳)との、国の威信と名誉を賭けた、熾烈な対決の物語です。
結果は周知の通り、アムンセンの圧倒的な勝利に終わります。かたや大成功を遂げて祖国に英雄として帰還したのに対し、一方は敗れた上に帰途で全員が遭難死を遂げるという悲劇的な最期を迎えます。
なぜ、このような「圧倒的大差」が生まれたのか? この本は、アムンセン隊とスコット隊の行動を逐一同時進行ドキュメントの形で描き、比較検証を試みます。「解説」の山口周さんが、
<本書は、「組織とリーダーシップ」という問題を考えるに当たって、最も深い示唆を与えてくれる最高のケーススタディだ。>
と述べているように、本を読んだ若いビジネス・リーダーたちも、アムンセン、スコットという2人の個性、マネジメントのあり方の違いなどを、それぞれの関心にそって読み取っていました。
その意味ではとてもおもしろい読書体験でしたが、同時に私は、この本を久々に読み返し、改めて新鮮な感動にとらえられました。今回はそれについて、やや雑感ふうに述べてみたいと思います。
まず南極という場所についてです。最初に意識して地図帳を眺めた時、ただ真っ白に描かれた南極大陸は、不思議な神秘の世界でした。厚いところで4㎞にもおよぶ分厚い氷に覆われ、中心部を横切る山脈も、本来の大地もすべてその氷の下に隠されている、と言われても、想像を絶するばかりです。
大河内直彦さんの『地球の履歴書』(新潮選書)によれば、南極点は平均気温がマイナス49℃という、地球上でもっとも寒い場所です。ドライアイスができる温度(マイナス79℃)より低いマイナス82.8℃を記録したこともあるそうで、「外出するだけで命取りになりかねない」というのは、まぁそうだろうなと思うのです。
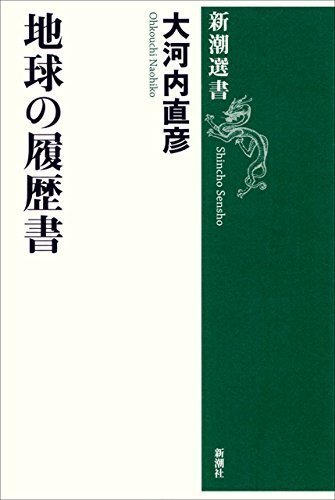
<その一方で、南極点の気候は大変乾燥しており、一年にわずか二〇センチメートルほどの雪しか降らない。これは降水量に換算すると七〇ミリメートルほどで、東京の年降水量のおよそ二〇分の一にすぎない。南極点は、極寒の砂漠なのである。>
となると、もう絶句するのみです。そもそも南極点に立てば、「すべての方角は北となる」というのが、わかりません。「南極点には東も西も南もないのである」と言われても、ボーゼンとするばかり……。
地球の誕生以来、わずか100年前まで、人類をまったく寄せつけなかった最後の空白地帯。
そこに何があるのか、そこで何が起きるのか。まったくもって不透明な前人未到の極地に、交通手段、通信技術、装備、防寒対策も、いまとは比較にならないほど未整備な状態で、天候も、細かい地形も、待ち受けるリスクの把握も十分できない条件のもとで、「それでも未知の領域を探求したい」と驀進した人たちの屈強な精神、断固たる意志にただただ圧倒されてしまいます。
映画「南極物語」のタロ、ジロの物語で、ずいぶん身近なイメージになりました。かつては、大晦日の「NHK紅白歌合戦」といえば、決まって「南極の昭和基地からの応援電報」が読みあげられ、「遠い地球の果て」を象徴するものでした。いまではインターネットが通じています。スマホの画面には、映像をいつでも呼び出せます。
エベレスト登頂と同じように、南極も観光地化している時代です。
2018年1月、日本人として初めて無補給単独徒歩で南極点到達を果たした荻田泰永(おぎたやすなが)さんによれば、民間会社のお膳立てで、南極大陸まで飛行機がツアー参加者を案内し、現地にはキッチン、トイレの完備したキャンプが用意され、お土産用のTシャツ、マグカップなど南極グッズも揃っているとか。



<一〇〇年前に南極点からの帰路に氷上で死んだスコットは草葉の陰で何を思うか、隔世の感である。>


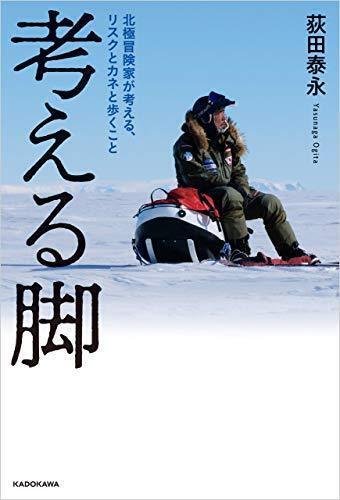
アムンセンとスコットの探検は、第1次世界大戦(1914~1918)の直前でした。列強が覇権を競った時代精神が、「極地探検史」のピークをもたらし、両雄を「史上最大の冒険レース」へと向かわせます。
アムンセンはといえば、そもそもは北極点到達の一番乗りをめざしていました。ところが、北極行きの準備をしていたその時に、アメリカのピアリー、クックによる北極点初到達成功のニュースが入ります(これが5ヵ月遅れで届いたというところに“時代”を感じます。その後、ピアリー、クックの両者は「到達証明」をめぐって醜い泥仕合を演じ、クックの北極点到達は認められず、ピアリーについても不審な点が指摘されます)。
ともあれ、この時点でアムンセンは、もはや「北極探検はその意義を失った」と判断し、急遽、行先変更を決意します。かくして運命のいたずらが、2人を世紀の対決に導きます。
一路、南極をめざして航海していたスコットは、オーストラリアのメルボルンに入港したところで、一通の電報を受け取ります。
「われ南極に向かわんとす。マディラにて、アムンセン」
これを読んだスコットの衝撃は、想像するにあまりあります。
アムンセン隊は北極をめざしていたのではなかったか! これまで世界で最も熱心に南極大陸に歩を進めてきたイギリスに対し、バイキングの血を引くノルウェーの探検家が、いきなり“殴り込み”をかけてきたのです。
探検家同士の礼儀にしたがってしたためられた親書とはいえ、まったく予期せぬ“参戦”です。「われ、なんじに先立って南極点にいたるべし」という予告のように思えただろう、と本多氏は記します。
ところで、世界広しといえども、イギリスとノルウェーの2国だけが、この「人類史的な冒険レース」に挑んでいたのか、といえば、実はそこに明治維新からわずか40年後の、日本の白瀬南極探検隊も名乗りを上げていたのです。この話は、また後で触れたいと思います。
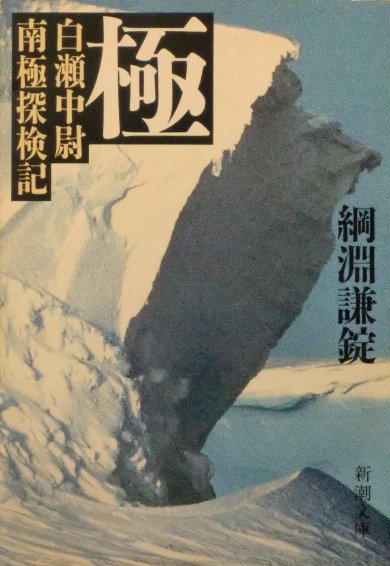
本多氏は「あとがき」の冒頭に、アムンセンの言葉を紹介しています。
「探検家は誰でも冒険をもつ。そして冒険をきりぬけることにスリルを感じ、それをかえりみて楽しみとするが、しかし探検家はけっしてかような冒険を捜し求めているものではない」
まさにアムンセンは、潜在的なリスクを回避するために、探検家を志して以来の知見や技術、過去の探検での経験、教訓を総動員し、当時としては最善と思われる、周到にして合理的、科学的な準備に徹します。極地体験での蓄積、寒地での訓練、心構えの違いが、スコット隊との決定的な実力差を生み出します。
もっとも象徴的な例が、探検隊の物資を運ぶソリは馬が引くか、犬が引くか、という選択です。イギリスの「伝統」にしたがって馬を主力に選んだスコット隊に対し、アムンセンは寒さに強く、危険な氷のクレバス(氷の割れ目)をも予知するエスキモー犬を多数揃え、迷うことなく犬ゾリを活用します。
しかも、先人の例にならい、極点到達レースに勝ち抜くための非情な計画を立案します。
<このときアムンセンがたてた大探検家らしい精密な計算は、のちのちまでも驚嘆の目でみられるようになる。それは、ソリ犬自身も食糧として計算するような徹底した作戦だったからである。前人未到の、どんな障害がまちうけているかわからぬきびしい南極大陸の中心まで、ここからあと往復で一〇九二キロ。東京―札幌の間よりも長いのだから、成功した上で確実に生きて帰るためには、感傷的な甘い考えはいっさい許されない。アムンセンはノルヱーにいてもふだんから犬好きで、その点では普通以上に犬をかわいがっていたが、真の探検家として欠かせぬ決断力もまた並はずれた人物だった。>
そこから南極点まで往復するのに必要な日数を算出し、そのために必要な人間と犬の食糧60日分をソリにのせ、余剰分は帰途のためにそこにデポ(食糧貯蔵所)を設営します。その上で、荷をさらに軽量化し、少数精鋭チームで目的地到達をめざします。
大量のマグサをエサとして運ぶ必要のある馬に対し、犬はアザラシやペンギンなど、エサを現地調達することが可能です。さらに「いざとなれば犬の肉自体がエサになる」――現代ならば、大論議を巻き起こす話でしょうが、南極点到達というきわめて不確実で難度の高い目的を達するために、あえて冷徹な判断をアムンセンはくだします。
スコット隊との「圧倒的大差」の詳しい分析は本に譲りたいと思いますが、スコット隊とてインディ・ジョーンズのような綱渡りの冒険を「捜し求めて」いたのでも、無謀な精神論で突き進んだわけでもありません。
イギリスの王立地理学協会会長、マーカム卿の期待を一身に背負ったスコットにとって、これは2度目の南極探検でした。前回の苦い教訓をふまえ、アクシデントは「何も起きないように、起こさないように」万全の準備を心がけたはずです。ただ、アムンセンに比して、計画の緻密さ、冷酷なまでの合理性の追求などで、随所に甘さがあったことは否めません。
いずれにせよ、探検が人類史上もっとも輝いていた時代の両雄は、同じ最終目的地をめざしながらも異なるコースを辿り、お互いの様子は何ひとつ知らないまま、それぞれの戦略、状況に基づいて進んで行きます。結果、両者の命運は、大きく明と暗に分かれます。
さて、見事に目的を果たし、祖国に錦を飾ったアムンセンですが、その後の人生が穏やかなものであったかというと、決してそうではありません。
<その後アムンセンは、一九二六年には飛行機に乗って北極点に到達し、人類で初めて両極に達した探検家となる。探検家としてこれほどの偉業を成し遂げたにもかかわらず、探検に要する資金繰りのトラブルや、北極点到達に絡んだ醜聞に悩まされ続けるのである。それは死をもって永遠の名声を得たスコットとは対照的な姿でもあった。>
1928年、北極探検に出たイタリア隊の遭難救助に向かったアムンセンは、大型飛行艇に乗ってノルウェーを出発したまま、消息を絶ちます。各国の大がかりな捜索にもかかわらず、彼の遺体は見つかっていません。56歳の誕生日を前にした事故でした。
いま南極点には、アメリカが建設した「アムンセン・スコット基地」があります。

<偉大な二人の探検家の名を冠したこの基地では、極地の気象観測や特有の環境を利用した天文観測などが常時行われており、夏場になると二〇〇人ほどの人々が滞在する。(略)スコット隊、アムンセン隊、そしてわが国の白瀬隊などが数々の苦難を乗り越えて南極大陸を旅した時代は、いつの間にか遠い過去のものとなった。一世紀あまりの間に、時代はすっかり様変わりしてしまった。その代わりに、新しい時代の南極大陸には新たな役割が芽生えている。>
すぐに思い浮かぶのは、地球のまわりにあるオゾン層——太陽光に含まれる有害な紫外線を吸収し、私たち生きものを守っている――を、フロンガス(エアコンなどに使われている)が破壊しているという衝撃の発表です。この脅威を伝えたのは、1982年、日本の南極観測隊が世界で初めていわゆるオゾンホール現象を発見したのがきっかけです。
また、南極氷床から採取される氷床コアが示す過去の気候変動は、将来の地球温暖化への警鐘を鳴らします。このようにいまの南極大陸は、
<炭坑のカナリアのごとく、地球の変化の兆しを敏感に感じ取り、人類に情報を発信し続けてきたのである。これも南極探検に命を捧げた先人あっての成果である。私たちは、巨人の肩に乗ってはじめて遠くを見通すことができるようになったのである。>
王立地理学協会の期待を背に、学術調査にも比重を置き、10人の科学者を帯同したスコット隊の貢献も偉大です。動物学者チェリー・ガラードの『世界最悪の旅——スコット南極探検隊』(中公文庫)は、スコット隊基地を出て約1ヵ月、別動隊としてペンギンの発生学研究のための冬季科学探検を行った3人の隊員のうち、生還を果たした著者による凄絶にして貴重なその記録です。
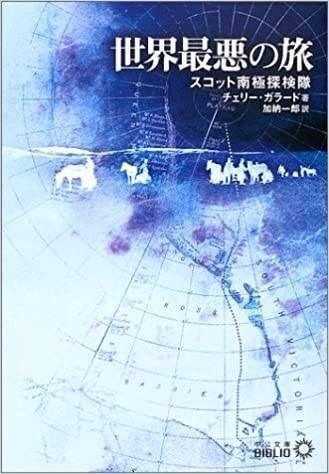
さて、ここまで書いてきたところで、実はもっとも触れたかった白瀬南極探検隊の話にまだ至っていないことに気づきます。駆け足で「付け足し」のように書くのも不本意です。次回に譲って、続きを述べたいと思います。
*南極の写真はすべて荻田泰永さんに提供していただきました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
