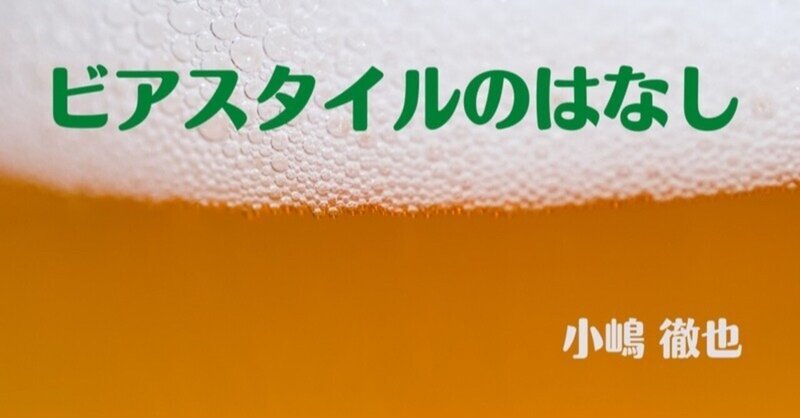
Episode 04: ケルシュ〜街の名を誇りに〜
ドイツ発祥のビアスタイルには地名のついたものが多い。すでに紹介したものの中にもデュッセルドルフスタイル・アルトビアやミュンヒナー・デュンケル、ミュンヒナー・ヘレスなどがある。ただし、これらは街の名前だけではなく、ビールの特徴を表す言葉、すなわち、「アルト」だったり「デュンケル」だったりというワードを伴っている。
そこで、今回取り上げる「ケルシュ」だ。ケルシュはベルギーとの国境に近い街、ケルンで作られてきたビールである。

「ケルシュ」(Kölsch)という言葉には、このビアスタイルの名前という意味の他に、ケルンで話されている方言というような意味もあり、まさにこの街自体を表す言葉であるとも言える。しかし、ビールの特徴がこの名前からはまったく浮かび上がって来ない。では、ケルシュとはどのようなスタイルなのか、掘り下げていくことにしよう。
ケルシュ協定
実は、ケルンで作られているケルシュしか、ケルシュを名乗ることはできない。シャンパーニュ地方で伝統的製法によって作られたスパークリングワインだけがシャンパンと呼べるというような原産地統制呼称制度がケルシュにも適用されている。
もっと正確には、ケルン醸造者協会(Kölner Brauerei-Verband)によって定められたケルシュ協定(Kölsch Konvention)に基づいて、ケルンから50km以内の地域で作られたケルシュだけがケルシュの名を関することができるという地理的表示保護制度が定められているのである。
あれ?と思う方もいるだろう。アメリカや日本でもケルシュは普通に作られているよね?と。特に日本では、1995年の地ビール解禁以降、ピルスナー、アルト、ケルシュ、それにときどきヴァイツェンというようなドイツ由来のスタイルを作る地ビールメーカーが非常に多かったし、現在も数多くの銘柄が生産されている。実は、上の制度はEU圏内で適用されているもので、EU圏外ではケルシュの名を使用することは問題ない。決して非合法ではないので、ご安心あれ。
歴史の名残り
後でも述べるが、ケルシュはドイツの中では数少ない上面発酵酵母で醸造された「エール」である。ドイツ由来のエールとしては第2回で扱ったアルトが知られている。アルトは濃色のエールであったが、ケルシュは黄金色に輝く淡色のエールである。
前回のピルスナーのところで書いたとおり、黄金色のビールは1842年のボヘミアスタイル・ピルスナーが最初だったので、ケルシュもそれ以降に定められたスタイルである。麦芽もピルスナーと同様、ピルスナーモルトが使用されている。
初めてケルシュの名をもつビールが世に出たのは1918年と言われているが、当時のケルシュは現在のものとは違っていたようである。現在用いられている製法が正式に定められたのは、先に述べたケルシュ協定によるものであり、これは1986年のことである。私が高校生の頃の話なので、ついこないだのことである。
さて、ケルンでは、古くからビール造りが行なわれてきたが、ケルシュの原型のようなビールとして重要なものが17〜18世紀頃から作られていたヴィース(Wieß)という小麦を用いたものである。現在でもドイツで小麦を用いたビールと言えば、ヴァイツェン(Weizen)が知られており、小麦由来で色が淡いものは白ビールを意味するヴァイス(Weiß)が用いられることもあるが、ヴィースというのはヴァイスのケルン訛りの呼び方のようである。
このヴィース、小麦を使用したエールで、しかも無ろ過のものであったと言われている。そうすると、後にこの連載でも取り扱う酵母入りの小麦エール、へーフェ・ヴァイツェンと非常に似た特徴をもつように思われるかもしれない。しかし、ヴァイツェンとは異なり、ヴィースはホップが非常に効いたビールだったようである。
現在のケルシュでも、必須ではないが、小麦麦芽の使用が認められている。このことも、歴史的にはヴィースの名残りなのかもしれない。さらには、現在でも無ろ過のケルシュをヴィースと呼ぶことがあるようであるので、古くからの伝統がその名前にも刻まれていると言えるだろう。
ちなみに、17世紀頃、ケルンの街でもラガービールがポピュラーになり、それまでエールを作り続けてきた醸造所の経営を圧迫するようになった。ケルンでは伝統的に作られてきたエールを守るために、ラガーの販売を禁止するような法制化も行なわれたようだが、醸造士たちは別の方法で抵抗を試みた。それは伝統的なエールの製造法に基づくが、熟成だけを低温で行なう、いわゆるエールとラガーのハイブリッドな醸造法でビールを作るというものであった。まさにこの製法が現代のケルシュでも採用されているわけである。アルトと同様、ラガーリングを行なうことでシンプルでスッキリとした飲みやすいビールに仕上がっているというわけだ。
香りが命
既に述べたとおり、ケルシュは黄金色のエールである。淡色麦芽を使っているので、麦芽由来の香りは決して強くない。スタイルガイドラインによれば、ホップの香りも強くないとされている。また、上で述べたとおり、アルトと同様、低温による熟成(ラガーリング)が行なわれるため、酵母由来のフルーティーなエステルの香りも比較的抑えられている。つまり、モルト、ホップ、エステルの香りが低いレベルで絶妙なバランスをとっているのがケルシュである、と説明されることがある。
これはこれで間違っていないのだが、私はあえて異論を唱えたい。あえてケルシュはフルーティーなエステルを楽しむべきビアスタイルであると言いたい。黄金色のラガーであるピルスナーでは、発酵温度が低いため、エステルはほとんど生成されない。一方、ケルシュの場合は、レベルは低いがエステルのアロマはしっかりと存在している。モルトやホップの香りが控えめであるため、強い香りでなくても、リンゴや白ブドウのようなフルーティーなアロマがはっきりと感じられるはずである。
ケルンの街の中心部にある大聖堂の付近には今でもケルシュを醸造するブルーパブが何軒か存在する。それぞれ使用している酵母の株や発酵温度などに微妙な違いがあるため、感じられる香りにもそれぞれの個性が出ていると思われる。これこそがケルシュを楽しむ醍醐味ではないだろうか?
ちなみに、日本で醸造されているケルシュは、必ずしもケルンでケルシュ醸造に使われている酵母と同じものが使われているとは限らないため、本場ケルンのものとはエステルのアロマに違いがあるものもあるだろう。一方で、本場に勝るとも劣らない素晴らしいフルーティーさを感じられる銘柄も少なくない。
独特な提供法
既に述べたとおり、ケルシュはエールではあるが、ラガーリングによってスッキリと飲みやすいビールに仕上がっている。ピルスナーは大きなジョッキで提供されることも多いが、ケルンでケルシュを注文しても、ジョッキで提供されるなどということはありえない。ガブガブと飲むものではないのである。
ケルンの酒場では、100〜200mLのシュタンゲと呼ばれる細長いグラスで提供される。ウェイターはクランツという独特なトレイ(下写真)に何本ものシュタンゲに入ったケルシュを載せて運んでくる。まるでリボルバー銃の回転式弾倉のように見えないこともない。

一杯の容量が小さいので、簡単に飲み干せてしまうのだが、グラスが空になったのを見ると、ウェイターは新しいケルシュが入ったシュタンゲを置いていく。しかも何杯飲んだかわかるように、コースターにチェックを付けていく。
この方式で、自ら断らない限り、永遠にケルシュがサービングされることになる。もちろん、永遠に飲み続けられるはずはないので、へべれけになって帰らないためには、どこかでストップをかけなければならない。ストップをかけるためには、空のグラスにコースターを重ねなければならない。
機会があれば、ぜひケルンの街で由緒正しいケルシュを由緒正しい提供法で楽しんでもらいたい。私は10年ほど前、ドイツからベルギーへと向かう途中、ドイツ鉄道のストライキのため、計らずもケルンで一泊することになり、思う存分、ケルシュを飲み歩くことができた。旅のスケジュール変更はめんどうだったが、これはかけがえのない思い出である。
代表的銘柄
Früh Kölsch(ドイツ)
Gaffel Kölsch(ドイツ)
Thornbridge Brewery Tzara(英国)
麗人酒造・信州浪漫麦酒・しらかば(長野県/IBC2021金賞*)
壽酒造・國乃長ビール・蔵ケルシュ(大阪府/JGBA2021金賞**)
ブリューパブテターレヴァレ・ケルシュ(大阪府/IBC2021銀賞*)
宇奈月ビール・十字峡(富山県/JGBA2021銀賞**)
横浜ビール・道志の湧水仕込(神奈川県/IBC2021銅賞*)
One's Brewery KLS(大阪府/IBC2021銅賞*)
OKINAWA SANGO BEER・ケルシュ(沖縄県/JGBA2021銅賞**)
黄桜酒造・京都麦酒・ケルシュ(京都府/JGBA2021銅賞**)
ブリューパブセンターポイント・ケルシュ(大阪府/JGBA2021銅賞**)
田沢湖ビール・ケルシュ(秋田県)
* IBC: International Beer Cup
** JGBA: Japan Great Beer Awards
ケルシュは繊細なビールだが、そのフルーティーなアロマを堪能していただきたい。
さらに知りたい方に…
さて,このようなビアスタイルについてもっとよく知りたいという方には、拙訳の『コンプリート・ビア・コース:真のビア・ギークになるための12講』(楽工社)がオススメ。米国のジャーナリスト、ジョシュア・M・バーンステインの手による『The Complete Beer Course』の日本語版だ。80を超えるビアスタイルについてその歴史や特徴が多彩な図版とともに紹介されている他、ちょっとマニアックなトリビアも散りばめられている。300ページを超える大著ながら、オールカラーで読みやすく、ビール片手にゆっくりとページをめくるのは素晴らしい体験となることだろう。1回か2回飲みに行くくらいのコストで一生モノの知識が手に入ること間違いなしだ。(本記事のビール写真も同書からの転載である。)
そして、今なら2022年1月30日(日)までの期間限定で30%オフでご購入いただけます!割引購入をご希望の方は、小嶋まで直接メッセージをいただくか、または、
楽工社のウェブフォームからお申し込みください。
また、ビールのテイスティング法やビアスタイルについてしっかりと学んでみたいという方には、私も講師を務める日本地ビール協会の「ビアテイスター®セミナー」をお薦めしたい。たった1日の講習でビールの専門家としての基礎を学ぶことができ、最後に行なわれる認定試験に合格すれば晴れて「ビアテイスター®」の称号も手に入る。ぜひ挑戦してみてほしい。東京や横浜の会場ならば、私が講師を担当する回に当たるかもしれない。会場で会いましょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

