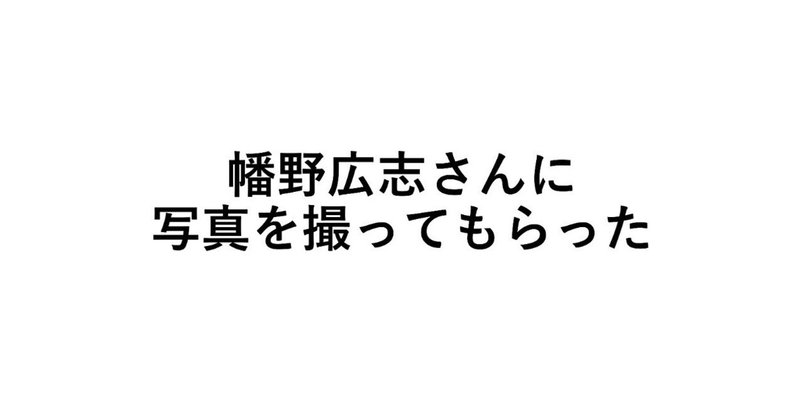
幡野広志さんが写したかった、妻と私と、その娘。
幡野広志さんに、家族の写真を撮ってもらった。
依頼したのは、自分ではない。妻だった。
ぼくは編集者という仕事柄、そしてtwitter民として幡野さんを知っていたし、幡野さんの『ぼくが子どものころ、ほしかった親になる。』という本も読んでいた。でも、それとは全く別ルートで、妻は、幡野さんの写真や発信をずっと見ていたらしい。
ある日、妻は突然、「ねえ、幡野さんにあたしといっちゃん(娘)の写真撮ってもらいたいんだけど、いいかな? よかったら良介くんも」と言ってきた。
オーケー、もちろんだ。
ある寒い休日の正午、幡野さんは、うちにやってきた。妻が指定した撮影場所は、ぼくらの家だった。インターフォンのカメラ越しに見えた初対面の幡野さんは、ファー付きのジャケットのフードをかぶっていて、雪山からきたクマさんみたいだった。
35歳の幡野広志さんは、「数年のうちのガンで死ぬといわれている写真家」だ。もう少し正確に言うと、「自分が数年のうちに死ぬだろうことを公に発表し、それを自覚して写真を撮っている人」だ。
ぼくの死の原体験の1つは、それほど仲良くもなかった高校の同級生が急逝した、その葬式だった。
彼の遺体を見て思ったことは、「あ、もうこいつとしゃべれないのか」「ん? ってことは、この先のこいつと俺の関係は、俺の解釈の中で変化していくしかないんだな」だった。
当初、これは「絶望」なのかな、と思っていた。
でも、今はぜんぜんそんなこと思っていない。むしろ逆だと思っている。そもそも、あんま仲良くなかったのだ。彼が死ななければ、もしかしたら一生、彼のことを思い出さなかったかもしれない関係だった。
すごく極端なことを言えば、彼が生き続けていたら、俺と彼の関係は実質上、死んでいたかもしれないわけだ。でも、彼が早く死んだことによって、彼の存在は死ぬ前よりも強く俺の中に刻まれ、たまに同級生との話題に上ったりして、こうして今も思い出すことになっている。
もし、自分の周りにいる人と、自分の記憶に生きている人だけが「生きている人」だとするなら、「実際は生きているけど二度と思い出さない人」は、自分の中では死んでいる人と何が違うんだろうと、あの時、思ったのだ。彼が死んだ後のほうが、彼は、俺の中に生きている。彼の肉親にとっては決してありがたくないことだろうけど、ぼくにとっては、それが事実なのだ。
そして幡野さんの話だ。
ぼくはおそらく、幡野さんが「数年のうちに死ぬらしい」と公表しなければ、幡野さんにそれほど大きな興味を持たなかったかもしれない。そして、妻が撮影を依頼することもなかったかもしれない。
幡野さんが撮ったぼくらの写真は、幡野さんが死を宣告されたからこそ、実現する写真だ。
撮影は、「幡野さんが好きな場面を、好きなように撮る」という条件で行われた。実際、一度も「構図」を指定されなかった。「そこに立ってこんなポーズとってください」とか、もう、まったくなかった。
他愛もないことや、子どもの話や、ちょっと重い話もしたけど、特に肯定も否定もせず、幡野さんはほとんど同じトーンですべての会話を交わした。「そうかー」とか「なるほどねー」と、何度言っていたかわからない。
そんな会話の中で、幡野さんは、不規則にシャッターを切っていた。
あの3時間で、ぼくは少し幡野さんのことを知れた気になっているけど、僕は幡野さんの人柄を知りたかったわけじゃない。いい人だなと思ったけど、それよりも、あの他愛のない会話の中で、彼はどの場面を切り取ったのか。まあ、少しは緊張してたけど、かなりいつも通りに過ごした妻と娘とぼくの、どの瞬間を、彼は写したいと思ったのか。
それが知りたいし、仕上がりがめちゃくちゃ楽しみだ。
唯一、幡野さんから要求されたことがあった。一番最後に撮影された、ぼくと、妻と、娘の3人の家族写真だ。
構図を指定されたわけではない。
「できれば、15年後も残っている家具の前で撮りたい」と、幡野さんは言った。
「娘さんが大きくなって、この写真を見返すことがあったときに、まだ残っているものと一緒に写したい」と。
ぼくらはみんなでちょっと考えて、新品で調達したナショナルメーカーの高性能エアコンと、最近買って、長く使えそうなトトロ柄の時計が映る場所を選んで、その前でポーズをとることもなく、じゃれた。
幡野さんは、何度かシャッターを切った。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
