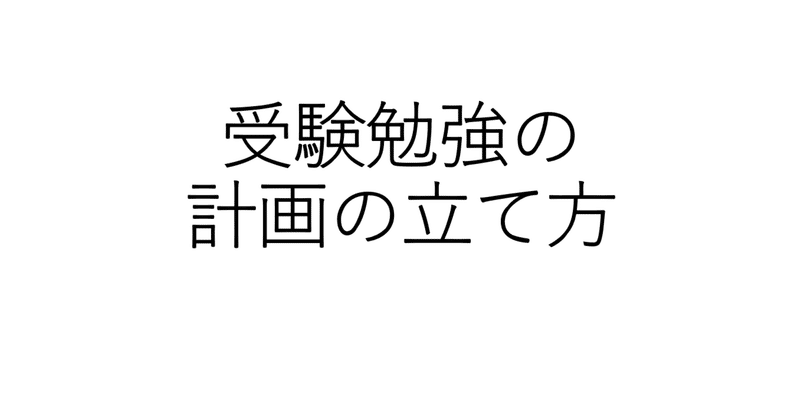
勉強計画の立て方と実施
勉強計画の重要性
自分の行ったことのない目的地まで行くのに何も調べず、何も手掛かりなしで行きますか?
事前に道を調べたり、ナビやグーグルマップで案内してもらいながら目的地に向かう人がほとんどでしょう。
なにも使わないで行く人は、目的地がそもそもない人や何度も行ったことのある場所に行く人でしょう。
しかし、「受験の合格」、「資格の取得」に関しては明確な目的地があるにも関わらず、事前に調べたり計画を立てないでいることが多いですよね。
それでは思ったような結果にはつながりません。
勉強の計画の立て方と、その計画をその通りに進められるか否かによって志望校の合格や資格の取得の可能性が格段にあがります。
計画を立てていない、計画の立て方がわからない場合は早急に計画を立てましょう。
計画の立て方
目標の明確化と計画の具体化
具体的に計画を立てるときは最終的なゴールと期日を設定しましょう。受験であれば、来年の共通テストで〇〇%、資格であれば、いつまでに何級といったことです。それを把握したうえで、参考書や過去問をいつまでに取り組んで、どのくらいの精度で正答できるべきかを計画します。
過去問や合格平均点の把握
過去問やその他のデータを得られるのであれば早めに集めましょう。これによって自分自身の取るべき点数や取り組む問題のレベルの把握が可能になります。ここで、問題のレベルは自分自身でわかるぐらいのレベルでなければ、合格レベルには程遠い位置にいることになります。したがって、この場合は定番の問題集や参考書を用いて基礎レベルの徹底が必要になります。
参考書や問題集の選択
近年はネット上でおすすめの参考書などの発信が多くなっていますので、調べればおすすめの参考書は山ほど出てきます。しかし、ほかに同じレベル帯の参考書や問題集を持っていて、まだその参考書を解ききっていないにも関わらず、新しい参考書を買い加えるのはやめましょう。
新しく参考書を買って成績があがるというのは間違いです。まずは目の前の問題を解けるように、そしてどのような着眼点を持てばよいのかを養っていきましょう。
参考書の選び方は、まずは解説が豊富で自力で進めることができるかどうかを見極めましょう。このとき、参考書の初めの方だけでなく、まんべんなくチェックしましょう。
また、できる限り書店で参考書や問題集を見てから買いましょう。
レイアウトや解説の手厚さの好みは個人差があります。かならず自分の好みのものをやりましょう。
一度、やると決めた参考書は他のものに目移りせずにしっかりとやり切りましょう。
参考書の8~9割程度が完璧に解くことができ、残りの1~2割は答えを見れば理解できる程度になっていれば、次のレベルの参考書に進んでも良いでしょう。
計画の立て方(実践編)
まずは受験生の場合、過去問から逆算して、どの程度の問題レベルまで仕上げるのかを決定してください。これは科目ごとに設定しましょう。
受験までの日程を考えて、いつまでにどれを行うのか、おおまかに計画を立てましょう。
次にそれを月ごとに計画を割り振っていき、週ごと、日ごとに細かく切って考えていきましょう。
その時々の精神状態や個々の性格によってどこまで細かく予定を立てるべきか変わってきます。しかし、月ごと、週ごとに関しては必ず立てるようにしましょう。適当に受験期間を過ごしても良い結果につながる可能性は低いでしょう。
計画の例(数学編)
受験生の7月から計画を立てるとして、1月の共通テスト、2月の国立大2次試験を受験する想定します。
各大学の公開している受験者平均点から、必要と予想される自分の点数やレベルを想定して計画を立てます。
たとえば、共通テストで数学80%、2次の問題レベルが地方国立標準レベルで6割程度必要であると予想される場合の予定を立てます。
7~11月:記述重視
12,1月:共通テスト重視
とおおまかに予定を立てます。
そのあと、実際に行う予定を立てていきます。このとき、自分自身の今現在のレベルを知っておくことが非常に重要になります。理解していないで難しい問題ばかり解いても、単なる暗記となってしまい学力の伸びが鈍くなってしまう可能性が高くなります。
例えば、この段階で数学Ⅲの履修が完了していればそのまま受験勉強を中心に行うべきですが、数学Ⅲがまだ完了していない場合は早急に数学Ⅲを完了させましょう。
そして次のように計画をたてます。
使用する参考書を先におおまかに決定しておきます。
これにより、いつまでにどの問題集を終了させ、どの勉強に移るかを科目別に整理しておきます。
ここにあげる参考書はあくまで一例であり、推奨しているわけではありませんので注意してください。
7、8月:基礎問題精巧(1a~3c)
9、10月:標準問題精巧
11月:志望校の過去問(私立併願含む)
12月~1月:共通テスト対策(過去問と各予備校の予想問題集)
1月~2月:志望校の過去問+志望校レベルの問題集
といったようにおおまかに予定を作成しましょう。
そのあとはさらに細かく予定を立てていきます。
7月~8月で基礎問題精巧を終わらせるには、3冊を2か月で習得する必要があります。ここで、1aなどすでに学習が進んでいて、時間がかからないのであれば、復習の時間などを削ってどんどん進みましょう。
逆に数学Ⅲの分野など演習不足であれば、復習時間や演習に時間がかかることを想定して計画を立てましょう。
例:
7月中の第1週、2週で基礎問題精巧1aを習得すると目標を立てます。
第1週で数学Ⅰ、第二週で数学Aとなり、週ごとにやるべきことが決まります。
そうしたら、週のタスクが決まり、日ごとのやることを決めていくと必要な勉強時間が自動的に決まっていきます。
1週間のスケジュールは週でまとめて立ててください。日ごとに予定を立てるときは、始める時間やシチュエーション(場所)等もできるだけ書きましょう。そして隙間時間に進めるものも予定として立てておきましょう(例:英単語、化学の無機の暗記など)
例:
月曜日
6:00~7:00 基礎問題精巧1A 15~19
16:00~18:00 基礎問題精巧1A 20~28
18:30~21:00 化学の新研究(〇章)
21:30~24:00 基礎問題精巧1A 29~40
隙間時間:システム英単語
このように科目ごとにやるべきことを明確化し、必要な知識を習得するのに必要な時間を算出し、計画を立ててください。
計画を立てる際の注意点
計画を立てるとき、自分自身の現実と、これだけやりたいという願望が混ざってしまうことが多くあります。
そのときの精神状態や各々の性格によりますが、どのような計画の立て方が良いのかは自分自身をよく分析しましょう。
・多い課題を自信に課すことによって、やる気が起きて勉強が進むタイプ
・課題が終わらないことによって自己嫌悪に陥り、やる気を失うタイプ
など多くのタイプが存在し、その時々の精神状態にも大きく左右されるでしょう。これにより、自分自身や身の回りのサポートによって大きく変わってくる部分でもあります。
計画の立て方のバリュエーションは別途記事にまとめたいと思います。
塾によっては、この計画の遂行までサポートしてくれるものもありますが、ほとんどは授業をするのみでこの部分のサポートは行っていません。
ここで、個人の家庭教師としてこの部分を私は提供し、なおかつ、ノーマルな家庭教師としての指導も承りたいと思っています。
お気軽にご連絡ください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
