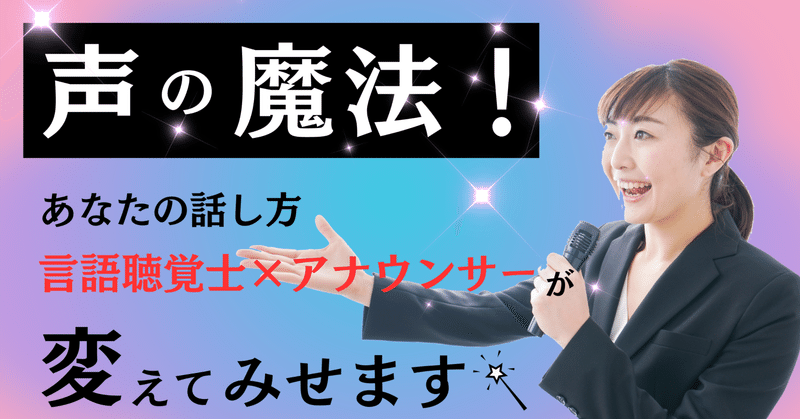
声の魔法!🪄 vol.1「声の高さ」を変えてみる
手っ取り早く声を変えたいなら「高さ」の調節
ひとつ前はこちら。
声の高さを変えてみよう
人の声の種類は千差万別。なぜそんなに十人十色なのかは、また別の記事で述べますが、とにかく、いろんな声があります。私たちはその声を聞き分け、「この声は○○さんの声」と判断しているわけです。何千何万の種類の声の中からその人の声がわかる、というのはある意味すごい能力です。
あなたの声も私の声も、大好きな推しの声も、一種類ではありません。その日の調子によって微妙に変わることだってあります。もっと言えばそれだけ「変えられる幅がある」ということにもなります。
手っ取り早く「自分の声を変えたい!」と思ったとき、一番簡単にできる方法が「高さ」を変えることです。高さのことをピッチと言うこともあります。
高さを変えると声がどう変わるのか。ダウンロードファイルで恐縮ですが、以下の音声ファイルを聞いてみてください。
音声の順番は、①普通の高さ、②高めの高さ、③低めの高さです。
なお、違いを際立たせるため、高さと低さをより強調するような話し方をしています。
いかがでしたか? 3種類の高さ、違いがお分かりいただけたのではないでしょうか。これだけでずいぶん雰囲気ががらりと変わりますよね。
高さに関する理論の話
人間の声の高さは、声道の長さと声帯の長さで調節されます。イラストで言うと、左の側面像のうち、唇の先から声帯までが声道、右の円の中に描かれているのが声帯です。薄い黄色の部分が震えて声が作られます。

このうち、声道は骨格とほぼ同義なので、長さを簡単に変えることはできません。変えられるのは声帯の方。声帯が伸びると声は高くなり、縮むと声は低くなります。
ではそれをどうやって伸び縮みさせるのか。声帯自体は粘膜でできており、自力では動きませんが(肺からの呼気の流れによるベルヌーイ現象は別とします)、その声帯を動かす筋肉というのが存在します。有名なのが輪状甲状筋(りんじょうこうじょうきん)と甲状披裂筋(こうじょうひれつきん)。歌声で高音域を出したい、低音を響かせたいと練習されている方々にはお馴染みの筋肉です。この記事では歌の話ではなく、普通の話声の話をしていきますので、これらの筋肉をがんがん鍛える必要はありません。理論として、これらの筋肉が動くと声の高さが変えられるということを、頭の片隅に置いておいていただければ大丈夫です。
さて、ここからが声の魔法をかけるお時間です。
声の高さは意識的に変えられます。今、ちょっと高い声を出してくださいと私がお願いすれば、あなたの声は高くなりますね。この瞬間、あなたの声帯はいつもより少し伸びています。
もうひとつ、声の高さを調節する方法として、首を少し伸ばしてみるというのがあります。顎を少し上に突き出すイメージです。この瞬間、首が伸びるのに合わせて、物理的に声帯周りの筋肉が伸びて、結果的に声帯も少しだけ伸びています。
逆に顎をぐっとひいて、喉を詰めるようにすると、声帯は短くなり、結果的に声は少しだけ低くなります。「あーーーー」と声を伸ばしながら顎を上げ下げしてみると少しわかりやすいかも。
とはいえ、意識して顎を上げ下げしながら生活している人はいないでしょう。
では無意識にはどうでしょうか。
普段のあなたは、背筋をぴんと伸ばして、胸を張って生活していますか? 背筋が丸くなって、前屈みになったままお話ししていないでしょうか。そうするとのどを詰めるような話し方になり、結果的に声は少し低くなります。
先に紹介した音声ファイルですが、普通と高めと低めの声、どれが一番聞き取りやすかったでしょうか。私はプロですので、どの声でも聞き取りやすく伝えられるよう訓練しています。でも、毎日滑舌練習をしているわけではない一般のみなさんが、低めの声でぼそぼそと話したとき、相手に届く話し方になっているかというと、どうでしょう。
あなたの声が伝わりにくいのは、姿勢に関係している可能性もあります。胸を張って胸郭を広げ、のどを締めつけない姿勢で発言するだけで、伝わりやすい声になります。
高さに関する感覚の話
「そんな簡単に声の上げ下げなんて、意識してもできないよ」とおっしゃるあなた。目の前で3歳の子どもが泣いているとき、あなたはどんなふうに声をかけるでしょう。きっといつもより少し高めのゆっくりした声で話しかけていることと思います。
目の前に大好きな芸能人が現れたとしたら? 上擦った少し高い声で興奮するのではないでしょうか。
意識的なのか無意識なのかは人によりますが、声の高さ、あなたも意外と使いこなしているんですよ?
こう考えると、魔法をかけるのは私ではなく、あなた自身かもしれませんね。
声にだってあるTPO
T(Time:とき)、P(Place:場所)、O(Occasion:場面)の考え方は、服装でよく使われますが、声にだってTPOはあります。
もしクレーム対応をしている場面だったら。高めの声は好まれるでしょうか。弔辞を読む場面、前年度割れした決算報告の場、低く落ち着いた坦々とした声の方が相応しい場面だってたくさんあります。
あなたが自分の声をより良くしたい理由を、もっと深く考えてみるといいでしょう。「この場面でこんなふうにしたいんだ」という具体的な場面が思い浮かぶなら、そこに合わせた高さをまずは選ぶ必要があります。
高くしたいなら胸を張り、のどを広げ、伸びるイメージで。
そのとき声帯が少し伸びているはず。
低くしたいなら、ゆったりと力を抜き、少し俯くイメージで。
そのとき声帯は少し縮んでいます。
そのときどきに相応しい魔法を駆使していきましょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

