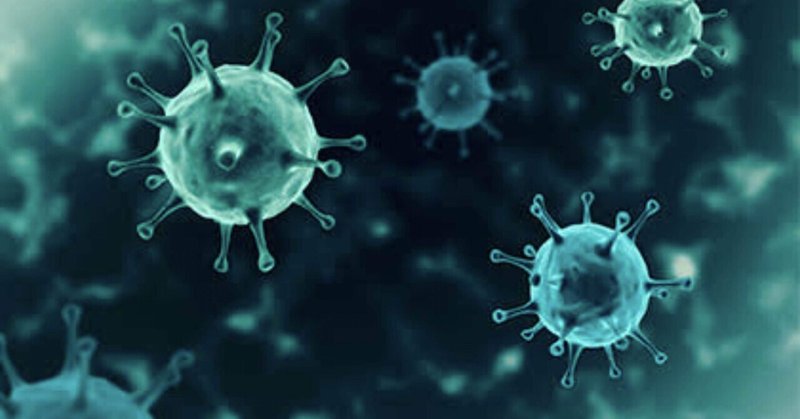
短編【ささやかで不確実な完全殺人】小説
監禁状態から解放された時、ぼくは首相が凶弾に倒れた事を知った。
体調の異変に気がついたのは猪烏さんから連絡をもらって二日後の事だった。
「ごめん、春馬くん。俺、コロナ陽性出てしまった。もしかしたら、キミに感染してしまったかもしれん」
その日のうちに病院へ行った。すぐに検査をしてもらえるのかと思ったら唾液収集の容器を渡され、明日の朝九時に病院に提出して下さい、と看護師から言われて帰された。
ぼくは、その唾液収集のポリ容器をポケットにねじ込んで、五日ぶりに実家に帰った。あの男が棲んでいる家に。
玄関を開けた瞬間、湿ったような実家の匂いが流れてきた。その匂いで、ぼくの左手の小指が疼いた。
ぼくは実家で父親と二人暮らしをしている。二人暮らしと言っても、ぼくが実際に家にいるのは、せいぜい三日が限界で、五、六日は友人の住まいを転々としている。一週間以上、家から離れる事もざらにある。
実家に戻るのは泊めてくれる友人が見つからなかった時だけだ。
久しぶりに会った父親はリビングのソファに横たわりテレビを見ていた。ぼくの気配に気づいた父親はテレビから目を離さずに、おう、と一言だけ言った。
特にぼくも、それに反応することもなくリビングを抜けて自分の部屋へ行った。家の中心のリビングが最も匂いの濃い場所だった。その分だけ左手の小指の痛みも増した。左手の小指は虐待の記憶を今も鮮明に覚えており、ときどき叫び声をあげる。
ぼくは、この家のリビングで父親から虐待を受けていた。左手の小指が折られたのもリビングだった。箸の持ち方が綺麗じゃない。というのが小指が折られた理由だった。母親は見ぬふりをしていた。母は十年前に他界した。
虐待は、父親にとっては教育だった。
そして、ぼくもそれが虐待だという認識はなかった。それが日常だった。
翌日、ぼくは溜めた唾液を持って病院へ行った。その日の夕方、結果が出た。
陽性だった。
保健所からの指示で十日間は外出を禁じられた。耐えられないと思った。十日間も父親と過ごさなければならないなんて。それはコロナに感染したという事よりも恐ろしい事だった。
そんなに辛いなら宿泊療養を利用するといいよ。そう教えてくれたのは綾部くんだった。
ぼくはコロナ陽性の連絡を受けて直ぐに関係を持った男たちに連絡をした。猪烏さんがしてくれたように。
ぼくは愛に飢えた男たちに身体を売って生活をしている。客のほとんどの連絡先は知っていた。綾部くんはその一人だった。綾部くんは客ではないけれど。彼はどう思っているのだろう。ぼくの事を。
電話で保健所に宿泊療養の申し込みをして二日後に宿泊先のホテルが決まったと連絡があった。
そしてぼくは保健所から派遣された送迎車に乗ってホテルへ向かった。
父親は、たいして心配している素振りもなく自分で自分の食事を作っていた。
父親は七十を超えているが歳の割には頑健で身の回りの事はなんでも自分でこなす。
ぼくは来年で三十になる。いまの父親の様子を見ていると長生きしそうで怖い。父親が九十になった時、ぼくは五十だ。その時になっても父は生きているのだろうか。それまでに何とかしなければ。そして、ささやかで不確実な計画を思いついた。
ホテルでの生活は快適だった。食事は朝七時と正午と、そして夕方六時の三回。日替わりで弁当が出た。一日二回の検温と酸素濃度のチェックが義務付けられているだけで、あとは自由だった。部屋から出てはならないという制限の中での自由ではあるけれど。
ホテルの部屋は無臭で左手の小指は安らいでいる。
宿泊して二日後、ぼくは計画が順調に進んでいるか確かめるために実家に電話をした。
六回のコールで父親が出た。
「春馬だけど」
「どうした」
父親の声が少し皺がれている。それは老化によるものではなかった。明らかに喉の炎症によるものだった。
「どうしたの。声が変だけど。体調わるいの」
「んん。ちょっと、喉が」
「熱は?」
「ん。ちょっと熱っぽいけど。まあ、大丈夫だろう。心配するな」
ぼくは、さも心配気な口調で話しをしながら口元は笑っていた。
洗面所に掛けられた湿ったタオルに、ぼくは念入りにウイルスを付着させていた。自分でも気持の悪い行為を思い出して口元がゆるんだ。
「もしかしたら、コロナに感染したかもしれない。ぼくが保健所に連絡するから、父さんは心配しないで。ぼくからの連絡を待って。外にも出来るだけ出ないで」
「そうか。悪いな。助かる」
もちろん保健所への連絡はしなかった。父親の食事は、ぼくがウーバーイーツを使って自宅に届けさせた。できるだけ脂っこい消化に悪そうな物を選んで。
「体調はどう?」
「うん。熱が38度から下がらなくて」
「いま、保健所に連絡してるから、もう少し待って」
「そうか。出来るだけ早く、何とかするように」
言ってくれ、そう言い終わると父は咳き込んだ。
ぼくは毎日、毎日、父親に電話をして病状のチェックをした。
八回目のコールで電話に出るようになった父は、いつしか十回以上のコールで受話器を取るようになり、ついには電話に出なくなった。
「春馬、息苦しいんだ。何とかしてくれないか」
それが最後の会話だった。
父親と連絡が取れなくなったのは宿泊療養を始めて五日目、陽性になって七日目の事だった。
あと三日、ぼくはホテルで療養しなければならない。
父親の様子を見にいけないのがもどかしかった。
異変に気づいた近所の人に救出されたのかもしれない。いや、あの忌まわしいリビングで倒れているのかも。
そのことばかりを考えて、気がつけばテレビも見ずに完全に世間から取り残されたまま十日間の療養を終えた。
監禁状態から解放された時、ぼくは首相が凶弾に倒れた事を知った。
ぼくはタクシーを捕まえて、急いで実家に戻った。タクシーのラジオから痛ましい首相の事件のあらましが流れていたが、そんな事はどうでも良かった。
ささやかで不確実なぼくの殺人計画の結果が早く知りたかった。
目の前にある実家の玄関が一年ぶりに立ちはだかっている。そんな錯覚を覚えた。実際は十日ぶりなのだけど。
ぼくは玄関のノブに鍵を差し込んで回した。
開いた玄関から実家の匂いが漏れてきた。
そして、ぼくはリビングへ向かった。左手の小指がきつく疼くのを感じながら。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
