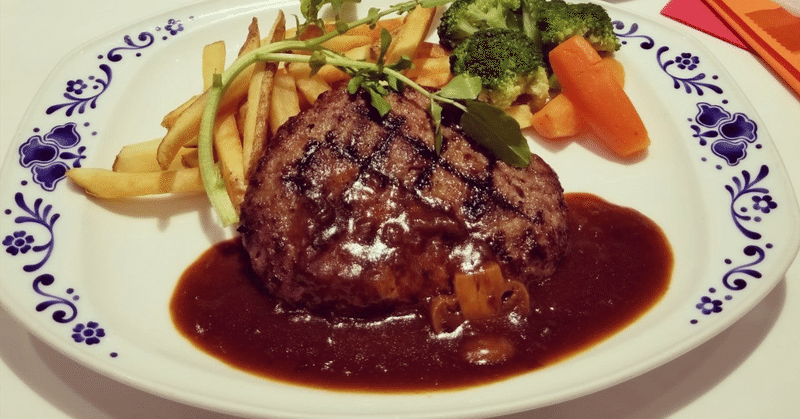
ハンバーグの歴史その4 戦前のアメリカにおけるハンバーグ・ステーキの特徴(前編)(東洋経済オンライン記事補足)
東洋経済オンラインにおいて、ハンバーグの歴史記事(前編、後編)を公開しました。
例によって字数の関係で情報量を圧縮した記事となっているので、説明が足りない部分をnoteで補足していきます。
前編/その3においては、戦前のハンバーグ・ステーキの多くはフランス料理ではなく、アメリカ料理であったことに言及しました。
それでは、日本にやってきたころのアメリカ料理ハンバーグ・ステーキとは、いったいどのような料理だったのでしょうか?
戦前のアメリカ料理書におけるハンバーグ・ステーキレシピを17ほど抽出して、スプレッドシートにまとめました。ここから、その特徴を書き出してみます。
特徴1.タマネギを使用する
ご覧の通り、ほとんどのレシピにおいてタマネギ(あるいはその汁)を生地に混ぜ込んでいます。
ハンバーグ・ステーキとよく似たアメリカ料理にソールズベリー・ステーキ (Salisbury steak)があります。
上記アメリカ料理本のうち、3つにおいてハンバーグ・ステーキとソールズベリー・ステーキ両方のレシピが記述されていますが、ハンバーグはタマネギを使う、ソールズベリーは使わないというのが両者の主な違いです。



戦前のアメリカ人からすると、タマネギを使用しないパティを焼いた現在のハンバーガーは、はたしてハンバーガーといえるのか、ということになると思います。
何らかの理由で、タマネギがパティから分離され、パティに乗せる方向に変化していったのでしょう。
特徴2.使用する肉は牛肉100%
豚肉との合いびき肉を使う習慣は、日本で生まれた習慣のようです。
特徴3.鶏卵、パン粉、パンを混ぜることがあるが、一般的ではない
鶏卵をつなぎに使ったり、パン粉やパンで増量する手法は存在しましたが、必ずしも一般的ではなかったようです。
アメリカ海軍ではパンを混ぜ込んでいましたが、閉鎖的な船上では他に使いようがない、余ったパンの有効利用法でしょうか?
戦前はハンバーグよりも、ハンバーグとよく似たイギリス料理「メンチボール」のほうがメジャーでしたが、こちらは鶏卵とパン粉を混ぜ込むことが一般的。タマネギは使ったり使わなかったりです。
メンチボールにおいて鶏卵とパン粉を混ぜ込むことに慣れていたので、戦後挽肉料理の主役がハンバーグ・ステーキに交代した後にも、その手法が受け継がれたのでしょうか。
特徴4.軍隊で食べられていた
アメリカ海軍やアメリカ陸軍料理学校の料理書にハンバーグ・ステーキレシピが存在しました。おそらく兵食に採用されていたのでしょう。
このことが、戦後日本でハンバーグ・ステーキが普及する鍵となります。
“ハンバーグステーキは、日本では太平洋戦争後、さかんに食べられるようになった”
“太平洋戦争中までは挽き肉の西洋料理といえばメンチ(ミンチ)ボールだった。”
“太平洋戦争後、占領軍としてきたアメリカの兵隊たちが、ハンバーグを好んで食べたのを日本人がまねて、メンチボールにとって代るハンバーグの全盛になった”
長くなったので後編に分割します
