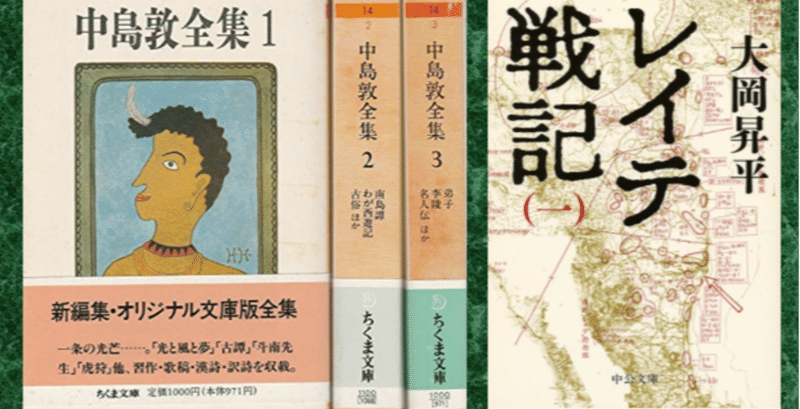
重なる通奏低音:『李陵』と『レイテ戦記』 第1回 『李陵』
書かれた時代と書いた作家が異なり物語世界を全く異にする2つの小説に、同じ感情が通奏低音として流れている。小説が人間の営為を描くものである以上、つねに起こりうることである。私は、長年の愛読書である中島敦『李陵』と大岡昇平『レイテ戦記』に共通の通奏低音が流れていることに、ごく最近になって気づいた。この連載では、その気づきを語りたいと思う。
第1回のテーマは、中島敦『李陵』と、その通奏低音である。
1.作家、中島敦
『李陵』は中島敦(1909年~1942年、享年33歳)の最高傑作と言われる作品である。私は筑摩文庫の中島敦全集全三巻を読んだが、やはり『李陵』は最も優れた作品のひとつであると思っている。
中島敦は、わずか14年の作家生活の間に実に多彩な作品を残した。『山月記』のように中国古典に想を得た作品が有名だが、日本の植民地であった朝鮮半島と南洋の島々を舞台にした短編、さらにはイギリスの作家で『宝島』の作者ルイス・スティーヴンソンが主人公の中編『光と風と夢』も書いており、その作品世界は実に幅広い。
本題からはそれるが、私は朝鮮半島を舞台にした中島敦の作品に深い愛着を抱いている。中島は旧制の小学校から中学校までを朝鮮半島で過ごした。彼は『虎狩』で日本人である主人公「私」と朝鮮人・趙大煥との屈折した友情を描き、『巡査の居る風景』では日本警察で働く朝鮮人警察官の屈折した心境を描いた。
実際に日本の支配を受けた朝鮮半島の人々からは「そんなもんじゃなかった」と言われてしまうかもしれないが、中島敦は支配する側でありながら支配される側の心情を想像しようとした作家であった。
話を『李陵』に戻す。
2.小説『李陵』
『李陵』は前漢と匈奴(きょうど)の抗争に巻き込まれ数奇な運命をたどった李陵、司馬遷、蘇武の3人(いずれも実在の人物)を描いた作品である。
偉大な将軍を祖父に持つ気鋭の軍人李陵は、少数の精鋭部隊を率い匈奴勢力圏での陽動作戦に赴くが、衆寡敵せず戦闘中に昏倒し捕らわれる。李陵の勇武に感銘を受けた匈奴の王は、彼を捕虜ではなく客人として扱う。
前線の事情を知る由もない君主・武帝は、李陵が匈奴に降伏したものと決めつけ、懲罰に李陵の家族を殺そうとする。
家臣たちは武帝を恐れ、心ない者は李陵を誹謗中傷し、心ある者も沈黙するのみだったが、ただ一人、李陵を弁護した家臣がいた。それが、歴史記録係の司馬遷だった。
武帝はますます怒り、李陵の家族は殺され、司馬遷は極めて屈辱的な刑罰とされていた宮刑に処されてしまう。つまり、男性機能を奪われたのである。
一時は自死を思った司馬遷だが、武帝に至るまでの中華帝国の史書を完成させよとの父の遺言を支えに生きることを選ぶ。執筆に己のすべてを捧げた彼が完成させたのが、『史記』である。
李陵は匈奴王の人柄と厚遇に感じ入り、また、漢に残してきた家族が武帝に殺されたことを知り、匈奴の中で生きることを選ぶ。匈奴の妻をめとり、匈奴王の息子の指導役を引き受け友情を培っていく。
このころ、捕虜交換のための平和使節として蘇武が送られてくるが、行き違いから匈奴に捕らえられてしまう。蘓武は自死を図るが匈奴の手当てで生き延びる。蘇武は匈奴の王から降伏を勧められるが、これを頑として拒み、北方の僻地に追放される道を選ぶ。蘇武は19年間、飢えと酷寒に耐え抜き、ついに漢への帰還を果たす。
この物語のハイライトは、2つある。
ひとつは司馬遷が現生の欲をすべて捨て、執筆に打ち込む姿である。私は、ここに中島敦の作家としての覚悟が現れていると思う。
もうひとつは、李陵が蘇武に対して感じる「後ろめたさ」である。これが『李陵』と『レイテ戦記』に共通する通奏低音でありこの連載のハイライトであるから、次の3で、作品からの引用を中心に述べていくこととする。
3.李陵の「後ろめたさ」
李陵が匈奴の王からの依頼で蘇武に降伏を勧めに行く場面から引用する。
李陵自身、匈奴への降伏という己の行為を善しとしている訳ではないが、自分の故国につくした跡と、それに対して故国の己に酬いた所とを考えるなら、如何に無情な批判者と雖も、尚、その「やむを得なかった」ことを認めるだろうとは信じていた。所が、ここに一人の男(楠瀬注:蘇武のこと)があって、如何に「やむを得ない」と思われる事情を前にしても、断じて、自らにそれは「やむを得ぬのだ」という考え方を許そうとしないのである。
飢餓も寒苦も孤独の苦しみも、祖国の冷淡も、己の苦節が竟(つい)に何人にも知られないだろうという殆ど確定的な事実も、この男にとって、平生の節義を改めなければならぬ程の止むを得ぬ(原文ママ)事情ではないのだ。
中島敦『李陵』ちくま文庫 中島敦 全集3 2010年第9刷 P103~104
李陵は蘇武に降伏を勧めることなどできず、悄然として立ち去るしかなかった。
そして、ついに、蘇武が漢に帰る日がやってくる。その報に接したときの李陵の胸の内である。
再び漢に戻れようと戻れまいと蘇武の偉大さに変わりは無く、従って陵(原文ママ)の心の笞たるに変りはないに違いないが、併し、天は矢張り見ていたのだという考えが李陵をいたく打った。やっぱり天は見ている。彼は粛然として懼れた。今でも己の過去を決して非なりとは思わないけれども、尚ここに蘇武という男があって、無理ではなかった筈の己の過去をも恥ずかしく思わせる事を堂々とやってのけ、しかも、その跡が今や天下に顕彰されることになったという事実は、何としても李陵にはこたえた。
中島敦『李陵』ちくま文庫 中島敦 全集3 2010年第9刷 P107~108
ここで李陵が吐露している「後ろめたさ」は、単に「やましい」というにとどまらず、自己不信の域にすら達していると、私は考える。
では、大岡昇平が『レイテ戦記』の中で吐露した「後ろめたさ」は、どのようなものであったのか? それは第2回にゆずる。
〈第2回につづく〉
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
