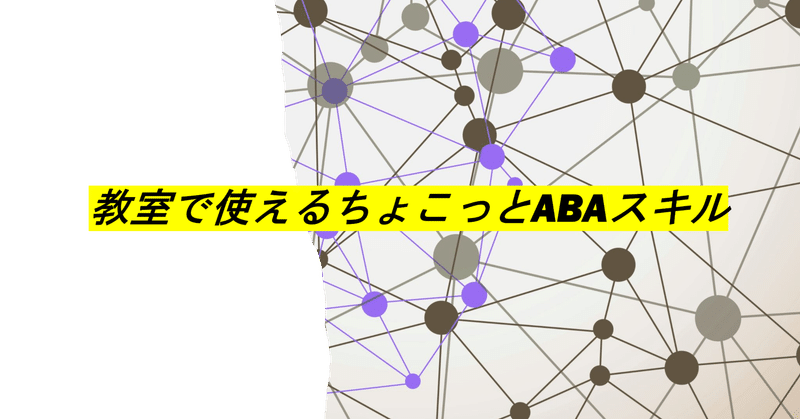
①応用行動分析学における行動の捉え方
応用行動分析学はApplied Behavior Analysisの略で頭文字をとってABA(エービーエー)と呼ばれます。ABAの特徴は、行動の理由を個人の性格や障害などの内的な要因ではなく、環境との関係で捉えていくことです。「友達をたたく」という子どもの行動を目にしたとき、一般的には「何かイライラすることがあったのかな?」「あの子は意地悪だからね」等と説明されることがあると思います。一見、納得できる理由のように思えますが、問題解決の点から言うと、「友達をたたく」行動にラベル付けしたにすぎず、具体的な対応策は見いだしにくくなります。
ABAでは、行動の前後の状況から理由を読み取っていきます。行動(B:Behavior)の前の状況を(A:Antecedent 先行条件)、行動の後の結果を(C:Consequence)とし、その頭文字をとって、ABCの枠組み(フレーム)と呼びます。
行動をABCの枠組みで観察してみると、「友達をたたく」行動は、直前のきっかけ(A)「仲間から無視され」、叩いた結果、(C)仲間から「やめろ」と言われた、という状況が繰り返されていたとします。

「行動が増えたり、減ったりする原理」
ABAでは、行動が増えたり、減ったりするのは、行動の直後の「C結果」が影響していると考えます。行動した結果、その人にとってメリットがあると、その行動は将来、増えたり維持されたりします。そのことを「強化」と呼びます。反対に行動した結果、その人にとってデメリットがあると、その行動は将来、減ったり、起こりにくくなったりします。それを「弱化」と呼びます。
つまり、例に当てはめて考えると、友達をたたくことが増えている(もしくは続いている)のであれば、それは「やめろ」という友達の反応がその人にとってメリットとなっていると考えられます。友達はたたくのをやめて欲しくて「やめろ」と言っていたのが実は逆効果だったということになります。
<教室で使える「ちょこっと」スキル>
「掃除をさぼるタカシくん」 ABCの枠組みで行動を観察して、何がタカシくんのメリットになっているか考えてみましょう。
【ポイント】行動の結果を観察すること
掃除の時間になると、クラスの子どもたちはほうきや雑巾などの掃除道具を取りに行き、それぞれ担当の場所を掃除し始めます。タカシくんは掃除道具を取りにいくことなくその場をウロウロしています。友達から「さぼるなんてずるい」、「はやくやって」等と注意を受けますが、タカシくんはそのままウロウロし続け、やがてチャイムが鳴り掃除の時間は終わります。

↓
回答例

タカシくんの行動は、結果の状況から掃除をやらずに済んでいること(逃避/回避)、友達のからの注意(注目)がメリットとなっていると考えられます。
このように行動をABCの枠組みで観察すると、行動が続いている理由(メリット)が推測できるようになります。日頃、教室で上手くいかない行動を見かけたとき、一歩引いてこのABCの枠組みで行動を観察してみるとヒントが得られるかもしれませんね。
では、次回、タカシくんの行動を改善していくために、ABCの枠組みを使ってどのように考えるか解説したいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
