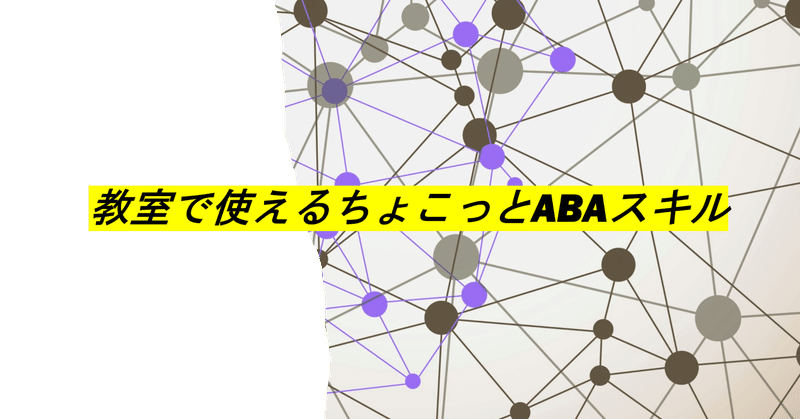
⑤ 上手な手助け(プロンプト)の仕方(Ⅱ)
ABCのつながりを成立させるために、手助け(プロンプト)を効果的に行うことが大切です。図に表すと以下のようになります。

プロンプトはAとBをつなぎ、Cに導くための役割であることが分かります。プロンプトを使いABCのつながりを繰り返し経験できるようにし、最終的にはプロンプトをなくしていきます。これまでは絵カードマッチング等の机上課題を例にABCをつなげていくことを説明してきましたが、手洗いや着替え等、複数の手順がある行動を教える場合はどうでしょうか。
複数の手順がある行動でも、基本的な考え方は同じです。手洗いを例に考えてみます。手洗いには、以下のような手順があります。
①蛇口をひねる
②石鹸をつける
③手をこすり合わせる
④手についた石鹸を水で流す
⑤蛇口をしめる
複数の手順がある行動の場合、Aにあたる指示は、前の手順(行動)のC結果になります。つまり、①蛇口をひねって水がでたことがA(指示)となり、②石鹸をつける行動が起こらなければなりません。そして、石鹸をつける行動の結果Cが次の③手をこすり合わせる手順のAになる・・のように数珠つなぎになっていきます。この数珠つなぎを「行動連鎖」と言います。行動連鎖を成立させるためには、手順ごとに「~して」と口頭で指示していてはなかなか進みません。口頭で指示をするのではなく、前の行動の結果Cが次の手順の指示になるようプロンプトしていく必要があります。
例えば、蛇口をひねった後、石鹸をつけるのを忘れている場合は、指さしや身体プロンプトで石鹸をつけることを教えます。この場合もタイミングが重要で、蛇口をひねった直後にプロンプトする必要があります。失敗(エラー)をさせないよう次の手順に導き、徐々にプロンプトを遅らせたり、減らしたりしていくようにします。プロンプトはさりげなく確実に、まるで黒子のように子どもの行動を手助けし、いつの間にかいなくなるのがポイントです。
<教室で使える「ちょこっと」スキル>
スズキ先生は、エリさんにエプロンをたたむことを教えています。エリさんは、エプロンをたたむ複数の手順のうち、できない箇所はないのですが、なかなか一人で続けて最後まで行うことができません。スズキ先生のプロンプトの仕方について改善を考えてみましょう。
エプロンをたたむ手順は、①エプロンを広げる、②両袖を折り曲げる、③縦に半分に折る、④横に半分に折る、⑤袋に入れる、でした。エリさんは一つ一つの手順はできるようです。スズキ先生は、エリさんの行動が止まっていると「エプロンひろげて」、「はんぶん」、「もうはんぶん」「袋に入れて」と指示をしたり、手を添えて手伝ったりしていました。
プロンプトをどのように改善しますか?
↓
回答例
エリさんは、スズキ先生の口頭での指示を待ってエプロンをたたんでいることがうかがえます。そのため、前の手順の終わり(C)が、次の手順のA(指示)としてうまく機能しなくなっています。行動連鎖が成立するよう、一つの手順が終わった直後にプロンプトをし、できるようになってきたら、プロンプトを出すのを少し遅らせて徐々になくしていく必要があります。最後の手順が終わったらしっかりと褒めることもエリさんのやる気を向上させるのに大切ですね。
今回はすべての手順ができるという場合でしたが、そうでない場合もあります。この手順はできるけど、この手順はできない、少し手助けすればできそう、等と細かく実態を把握する必要があります。時系列に沿って手順を分解してアセスメントすることを「課題分析」と呼びます。
次回は、課題分析について解説します。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
