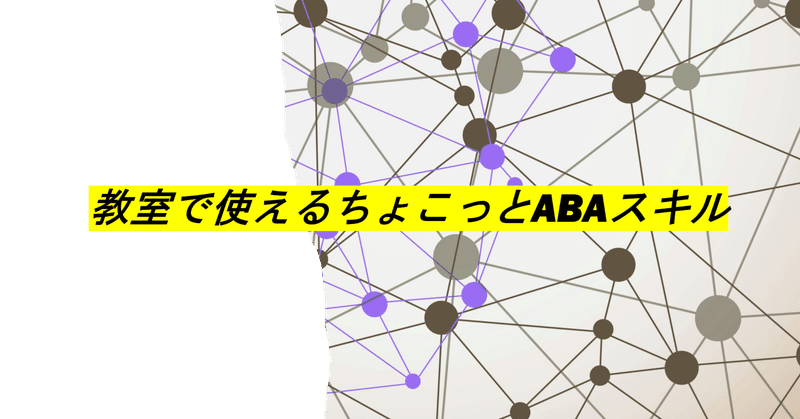
④上手な手助け(プロンプト)の仕方
ABCの枠組みで未習得のスキルを教える場合、指示を出した後(もしくは同時に)、指示に応じれるように手助けをする必要があります。その手助けをプロンプトと呼びます。プロンプトには種類があり、子どもの行動(反応)を手助けする「反応プロンプト」と、環境を分かりやすくする「刺激プロンプト」に分かれます。
「反応プロンプト」は、言語プロンプト、モデリング、ジェスチャー(指さし等)、身体プロンプト、があり、順に間接的なものから直接的なものとなっています。
「刺激プロンプト」は、色や大きさ、形を強調すること(例;なぞり書きの補助線)や、位置を変えること(例;正解の選択肢カードを子どもに近づけて置く)等があります。
プロンプトは、補助的な手助けであるので、最終的は指示のみでできるように、段階的になくしていき、ABCのつながりを成立させていく必要があります。
色の名称を命名する課題を例に説明すると以下のようになります。

先生が色カードを見せて「何色?」と聞いた後、プロンプトで答えの「あか」のヒントを出しています。それでできるようになったら、「あ」と語頭のみのプロンプトに減らしていき、最終的にはなくしていきます。
コツは、できるだけ失敗(エラー)をさせないように、プロンプトを焦ってなくなさないことです。十分に身に付いてないときにプロンプトをなくしてしまうと、先生の顔色をうかがって正解を判断したり、プロンプトが出されるのを待つようになったりと、いわゆるプロンプト依存の状態(指示待ちとも言います)に陥ります。
また、「指示」と「プロンプト」、「強化」を明確に意識しておくことです。どの言葉が「指示」で「プロンプト」なのか、子どもにとって分かりやすくします。「指示」は明確に、「プロンプト」はさりげなく、がポイントです。何度もプロンプトを繰り返し、指示と区別がつかない状態にならないように気を付けましょう。
<教室で使える「ちょこっと」スキル>
サトウ先生は、ひろしくんに「絵カードのマッチング」課題を教えています。指示を明確にすることを心掛けましたが、ひろしくんの正答率は上がりません。サトウ先生のプロンプトの出し方について改善しましょう。
サトウ先生はひろしくんの注意をこちらに向けてから、絵カードを3枚並べ、ひろしくんに一枚、絵カード手渡して「いっしょにして」指示しています。ひろしくんは絵カードを違うカードの上に重ねます。サトウ先生は「これこれ」と指さして答えを教えると、ひろしくんは正しいカードの上に置きなおします。
サトウ先生の教え方をABCの枠組みで捉えると以下のようになります。

プロンプトをどのように改善しますか?
「 」
↓
回答例
サトウ先生のプロンプトはひろしくんが間違えた後に行っています。そのため正答率が上がりにくくなっています。プロンプトは「いっしょにして」の直後、もしくは同時に指さしで出して正解に導き、成功体験を繰り返す必要があります。できるようになったら、徐々に指さしのプロンプトのタイミングを遅らせていくようにしましょう。
また、正答の絵カードをひろしくんの近くに配置して(刺激プロンプト)正解しやすくする方法もあります。この場合は、徐々に選択肢の並べ方を通常に戻していくようにします。
次回は複数の手順がある行動を教える場合のプロンプトについて解説します。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
