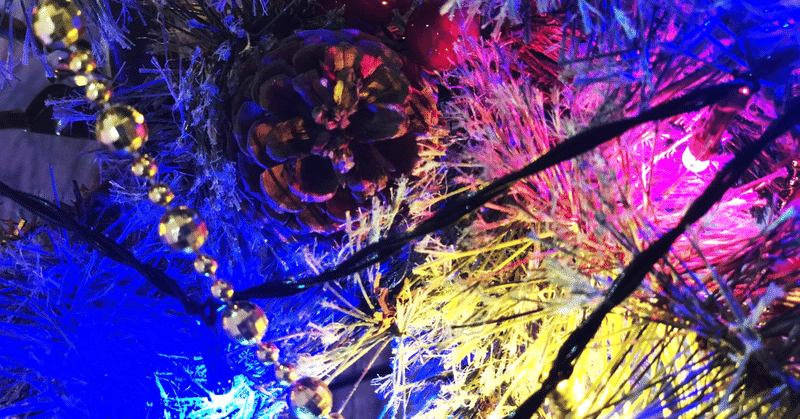
緑と赤い雨 #パルプアドベントカレンダー2022
1
冬が到来し、気温は随分と下がっていた。この寒さであれば外にいる人は凍えてしまうだろう。雪が少し降り始めた、北米にある小さな町のバーでは外灯が点いていた。そこには仄かな温かさがあり、人が生きているということが感じられた。そのバーの店内は十分な広さがあり、音質の悪いクリスマスソングが流れていた。あのあまねく人々に祝福を贈る神の日が近づいていた。リズミカルなトランペット音が人々の心を跳ねさせる。もしも、その場に人々が居たのなら、靴底でリズムをとってクラップを打っているかもしれない。陽気な気持ちが自然と沸いてくるのは、我々の遺伝子にこの日を祝うことが刻まれているからかもしれない。
しかし、このバーの雰囲気はクリスマスソングと対照的に随分と暗い。それもそうだ、店には賑わう客も居なければ、暖かい暖炉の火も無い。電気も点いてはいるが奥のカウンター以外には光は灯っておらず、四人掛けのテーブルも、奥まったところにあるソファー席にも光は差し込まれていない。テーブルは黒く焦げており、ソファーも所々破れて中の綿がはみ出ていた。椅子はてんでバラバラにひかれており、お客が暫く来ていないどころか、まるで何かが起こりそこに居た人々が慌ててその場を逃げ出したような物々しさが残っていた。
バーカウンターには独り男が座っていた。茶色いロングコートを羽織り、彼の隣のスツールにはつばの大きいハットが置いてあった。裾の破れたジーンズを穿いており、ブーツの紐はきつく縛られていた。大昔の西部劇のような出で立ちだった。ただ、腰につけているのは銃ではなく、日本刀であったが。
彼の碧い瞳とは違い、白目は濁っていて黄ばんでいた。三〇代だろうか。無精ひげを蓄え、ハットもコートも使い古されており、清潔と言い難い見た目であった。その店にバーテンダーは居ないが、彼は琥珀色のバーボンが入ったグラスを持っていた。カウンターの後ろにはお酒の瓶が並んでおり、栓の空いているものも新品のものもあった。そこから引っ張り出したのだろう。蓋の開いたブラントンのシングルバレレルバーボンの瓶がカウンターに置いてあった。その横にはスマートフォンが転がっており、どうやらそこからクリスマスソングが奏られているようだった。
男の名前はAiden(エイダン)。ブロンドの髪に黒い髪が混じっており、頭のトップで団子状に結んでいた。額がひろく、年齢のわりに横皺が多く走っていた。瞳には思慮深さを備えられていた。エイダンは何かに悩んでいるみたいに、眉間に深い皺を寄せてバーボンを傾けていた。鼻に抜ける香りが香ばしく、甘いトウモロコシを想像させる。エイダンは味わいながらも、夏のトウモロコシ畑を目に浮かべた。
エイダンは農家の息子だった。エイダンの父は身体の大きな男でジーンズの似合う人だった。いつも太陽の匂いのする服を着ており、蓄えた髭の隙間から見える白い歯はいつも笑っていた印象しかない。その記憶も曖昧だ。それ以後に起こった世界の出来事があまりに悲惨すぎたせいだ。父もエイダンも、そして皆が巻き込まれた。
次の曲の前奏が始まった。トランペットがリードし、ドラムスがビートを下支えして、クリスマスの夜を想起させた。前奏だけですぐになんの曲かと答えられるほど、キャッチーで陽気で幸せな楽曲だった。
Oh, the weather outside is frightful
But the fire is so delightful
And since we`ve no place to go
Let it snow, let it snow, let it snow!
窓から外には雪がしんしんと降りそそいでいた。外は零度を下回り、朝には氷が張って、土の上には白い絨毯が敷き詰められているだろう。エイダンは窓の外を恨めしそうに眺めている。なのに、フランクシナトラは軽やかに、雪よ降れと連呼した。
It dosen`t show signs ov stopping
And I brought some corn for popping
The lights are turned way down low
Let it snow, let it snow, let it snow!
ガガッと風ではない何かで無理やり扉が開く音が聞こえた。外気が吹き込んできて寒さが肌に染みる。エイダンは横に置いておいたハットを頭にかぶり立ち上がった。それから扉の方を正対で向いて、僅かに腰を落とした。腰のさやに左手を添えて鯉口を切る。右手で柄を軽く握り、右足をすり足で前に出した。扉は大きく開き、風を受けて揺れていた。街灯の無い外の景色は真っ暗で、扉からの景色はただの黒い長方形に見えた。エイダンはそこを見据える。黒い虚空から、嫌な香りがしてきた。汗が垂れる。鼻先から白い息が漏れていた。碧い瞳の奥が開く。
何度目かのフランクシナトラのサビが聞こえたときだ。見計らったみたいに、奴らは中に侵入してきた。エイダンの匂いを嗅ぎつけ、そして殺すために。一本、いや、二本、いや、三本と開いた扉から茶色糸状の太いモノが侵入する。子狐が駆ける程度のスピードでそれらがエイダンめがけて進んできた。エイダンは素早く抜刀し、刀身を中心に置いた。右側に進んだ二本は真っすぐこちらに向かう。もう一本が視界の端に見切れるも、向かってくる二本に集中した。一本が跳ねるような動きをしたかと思うと、エイダンのめがけて飛び込んできた。エイダンは素早く逆袈裟切りをする。伸びてきたそれの切り口から勢いよく赤い体液が飛び散った。断末魔などを叫ぶ生き物であれば、さぞかしうるさいであろうが奴らは何も言わない。赤い体液がでているのを気に留める様子も無く、もう一本が間髪入れずにエイダンの腹部へめがけてくる。しかし、それを予期していたエイダンは袈裟切りで振り上げた右手の柄を左手で迎えにいき、そいつを一刀両断した。またも切り口から赤い体液が流れ出る。足場がそれのせいでぬるぬるとしてきた。しかし、エイダンは振り下ろした刀を鞘に納めることなく両手で持ち、刃を立てた。切り落とした二本からは鼻の奥をつく生臭い臭いが流れ続ける。わずかにその二本が動いているが、もうエイダンを襲ってくる様子はない。息を殺して、エイダンは残り一本を探す。身体を無駄に動かさずに首を振り、左右を確認した。光の届かない部屋の陰にいるのかもしれない。目を凝らす。丁度間奏に入ったのか、トランペットのメロディが店内に響き渡る。エイダンの息は少しずつ静かになる。フランクシナトラはやたらとポップコーンを買ってしまったことを強調していた。バカみたいにそれが外に出ない正当な理由のように。
左側の奥手の椅子が音をたてて動いた。一瞬、顔をそちらに向ける。しかし、エイダンは目の端で違和感を感じる。視界のどこかに嘘が紛れ込んでいる。そう思った瞬間、頭上から風を切る音が聞こえた。音が耳に届くのと同時にエイダンは何も考えず、前に向かって前転をする。残りの一本が天井からエイダンが居た地面をくり抜いていた。受け身と共に身体を回転させて、膝たちになる。すぐに刀身を前にし、今しばた自分の居たところを見る。ひやりと背中に走るものを抑え、エイダンはその土埃の立ち上がったところを凝視した。奴がタイミングを見計らって、エイダンに突っ込んできたところを水平に刃を動かし切り割いた。そいつは切り口から真っ赤な体液をまき散らしながらのたうち回った。店内は赤い体液が飛び散り、元の色が何色か分からないほどに汚された。エイダンは辺りを見渡し、殺気が無いのを感じ取りようやく納刀した。
それから、煙草に火をともし、肺に煙を入れた。そして煙草をバーに投げ入れて、雪の降る夜の中に消えていった。
2
随分と昔の話だ。人類は増え続ける温室効果ガスに頭を抱えていたらしい。地球を暖め気候変動リスクをもたらす原因であると分かっているにも関わらず、有効な手立てを打てずにいた。社会が発展すれば必ず出るという文明の排泄物であったからだ。あがりを迎えた先進国だけが声高にそれを減らせと言い、これから発展しようとする国々に強要した。幸福の果実と分かっている成長を鈍化させる方針に断固として反対を表明し、地球全体の問題であるにもかかわらず、何年も人類は足並みをそろえることが出来なかったという。まあ当たり前だ、食べ物とクソは人間にとって必要で、文明も同じというだけのことだ。俺からしてみれば、こんな当然のことに頭を悩まさず、もっと楽しいことに時間を費やすべきだったと思う。少なくても、どこかのバカ博士が植物を人工的に生み出して、この問題を解決しようとすることより、何倍もマシに思える。今ならな。あるバカ博士は長い研究の末、自律して生命力が強く繁殖に優れた植物「レッドミクロカーパ」を産み出した。
そして、それを切るのが俺の仕事となったわけだ。俺はエイダン。巷ではスレイヤーズと言われている。雑草を切るのことが仕事で、とても骨が折れるのだが、実入りはそれなりだ。まあ死ぬかもしれないがな。
何故かというと、レッドミクロカーパは哺乳類の血を栄養分としたガジュマルだからだ。単為生殖植物で、時には交配による繁殖も可能らしい。つまり女がいなくても分裂するメガネをかけた気持ち悪いナードみたいなやつらということだ。奴らは北米のあらゆるところでみるみると繁殖していったわけだ。そして、気づくと植相を塗り替えて人間が入れない森を作り出した。もう、この国の国旗は緑の縞々しなきゃならないレベルだ。日に日に進化した奴らは、自ら養分を刈り取る因子を強めていき、家畜を食すまでに進化した。人類がその邪悪な生態に気づいた時には北米の農場を片っ端から襲っていた。
当然人類は自衛をするべく、軍を出動させた。燃やせば雑草処理ぐらいすぐに終わると思ったわけだ。しかし、あいつらはまさに雑草で、しぶとく根を地中深くに張り巡らせて、単為生殖でじわじわとその数をもとに戻し続けた。2057年十二月二十四日、奴らは初めて人類を突き刺しその味を覚えた。その後レッドミクロカーパは人類だけを異常に襲うようになった。人間の血が一番純度が高く栄養価が高かったことが要因と言われている。
奴らにとって人類が集まっていた都市部は格好の餌場だった。ワシントン、ロサンゼルス、ニューヨーク、ヒューストン、シカゴ、フェニックス等、都市は一瞬にしてレッドミクロカーパの森に飲み込まれた。そこは人間が立ち入ることが許されない神聖な森へと塗り替わっていった。人類はフロリダの都市を首都とし、なんとか水際にて生活した。そんな風になってもう二五年も経っていた。
「あんた、その刀。もしかして、スレイヤーズか?」
フロリダの海辺を眺められるカフェで、久々のビールを煽っていたら横からこちらの気分を配慮せずに男が話しかけてきた。垂れ目の男で、今までどんなことにも頭を下げてきた生き方が染みついているようだった。俺にもおもねるような声をかけているのに、どうにも信用したくない顔だった。俺はそいつを一瞥してビールの残りを飲み切った。
「待ってくれ。頼む、村を助けて欲しいんだ」
「悪いが他を当たってくれ。しばらくは奴らとは関わりたくない。今は休暇中なんだ」
俺は乾いた声でそう言った。心の底からそう思っていた。
「お金はある。本当だ。頼むよ」
「いや、それなら、なお受けることできないな。こんな偶然のように出会った男に金を用意しているわけがない。見たところ、見当をつけていたスレイヤーズに断られたんだろう? どうして俺がその代わりをしてやらなきゃならない?」
そう投げ捨てて、俺は近くに置いておいたハットに手をかけた。何も言い返してこない男を見て、それが答えだと確信を得た。誰かの代わりで死ぬのはごめんだ。
「でも、黄色い花の咲くやつなんだよ。このままじゃ、村が無くなる」
ぼそっと、俺の耳に放り込まれたその言葉が引っかかった。黄色い花が、なるほどな。
「あんた、名前は? 話だけなら聴くぜ」
その男の名はケイレブと言った。アラバマ州のビケット・サモンズという村の役場の人間だそうだ。数週間前からレッドミクロカーパの群がじわじわと村の周辺を襲い始めた。村の役人たちは中心地から離れたところに家畜を集めた。生贄をささげ、満腹にさせて奴らを引かせるためだ。下手に人間が多くいることを悟られてならない。普通のレッドミクロカーパの群であれば、満足すれば自然と森に引き上げていくものだ。しかし、今回村を襲ったレッドミクロカーパは黄色い花を咲かせていたという。母体樹だ。母体樹はそこに根をはり、森の中心となり、森を拡げる原因そのものだ。
「母体樹であれば、スレイヤーズ以外は排除できない。うちの村は森になってしまう」
そう言ってケイレブは俺に嘆願をした。
スレイヤーズ。切るモノたち。レッドミクロカーパは燃やしても根が地中に残り殺すことが難しい。だが奴らは血を飲み過ぎた。栄養価の高いエネルギーが急激になくなることはショッキングな状況を産み出すことができる。生命力が一瞬落ちたときに燃やすことで、土の奥深くの根から再生することができずに殲滅させられる。それをするのが、スレイヤーズだ。俺たちは日本刀という、鉄を純粋に凶器に磨き上げた刃物をつかい、レッドミクロカーパを切りつけて出血多量に追い込む。日本刀を扱えるようになるには修業が必要ではあるが、今のところ唯一やつらを殲滅できる手段であった。
「それで、どこに向かえばいい?」
俺は結局、その仕事を受けることにした。
3
ビスケット・サモンズはいい村だった。中心にはちょっとした町もある。俺はこういった古き良き時代のアメリカが好きだった。国道からだいぶ離れてはいるが、広大な農地が広がり、昼間の景色はさぞ美しいだろう。ケイレブと一緒に村に着いた俺は、村から人々を避難させた。そして夜になったところでバーで奴らを殲滅させたというわけだ。今回は母体樹が相手だから、これで御終いではないが、母体樹のサイズは十分に予想できた。恐らくⅠ型だろう。切り落とした根からの血の量でなんとなく分かった。母体樹はサイズごとに型数を決めている。Ⅰ型であれば高さ五メートルぐらいだ。Ⅱ型は一〇メートルぐらいになる。Ⅲ型もあるらしいが、俺は一度も見たことがない。Ⅲ型はビルみたいなサイズになるという。このまま一度も拝まずに済む人生でありたいものだ。
「冷えるな。冬は好きになれない」
口に煙草をもう一度咥えて火をともす。あったかい空気が肺に入る。それから、中腰になって前進した。町のあちこちに奴らの根が張りめぐらされていた。どれも硬化していて先ほどのように襲ってくる気配はない。レッドミクロカーパといえど全ての根を動かすわけではなく、動かない根は土の中に潜るために硬化する。普通の根として土を掘り始めるのだ。そいつらの近くを通っても襲われることは無い。
それにしても母体樹がなかなか見つからない。何かが変だ。あの大きな母体樹を見逃すようなことはない。さっき切った根から、すでに数十メートルは進んでいる。想定よりもサイズが大きいのか?
更に数メートル進んだところに一輪の綺麗な黄色い花が咲いていた。この雪の中でも、枯れることなく自らの生命を証明するため、その花は凛としていた。花弁の大きさは大人が膝を曲げて寝ているのと同じぐらいだった。花はユリ科のようにラッパ調になっていて、中心部はすぼまっている。花弁の黄色さとは違い中心部は白と赤の斑点模様になり、大きな雌蕊とそれを囲う雄蕊が五本伸びている。雄蕊の先には黄色い花粉があり、揺れるたびに黄色い粉が風に舞った。花からは強烈な匂いがして、哺乳類が嗅ぐと酩酊する。俺はもう酔っているから問題はない。
普通であれば、黄色い花は母体樹の元に咲く。しかし、今咲いているところは硬化した根の上だ。そんなところに咲く花は無いはずだ。まるでここが母体樹に育とうとしているみたいじゃないか。俺は徐に花に近づいた。良く見ると根本の方でどくどくと脈打っていた。俺は抜刀し、この花の根元を切り落とした。柔らかい感触が手に伝わり、まだ若い生命を殺めたと感じた。切り口から勢いよく血潮が噴き出る。これで終わりか……
「危ないナリよ」
人の声が聞こえたので、振り向いたがそこに人の影は無く、小さな犬のロボットがあるだけだった。銀色のロボットで、目のところには黒い電光掲示板が入っており、瞳をアニメの様に表現していた。サッカーボールぐらいのサイズだったので、話かけたのがすぐにソレだとは分からなかった。
「前を見るナリよ。お前バカなのか?」
随分と口の悪い犬だ。育ちが悪いんだろう。
「人間様に向かって口の利き方が分かってないみたいだな」
吸っていた煙草をを犬に投げて、もう一本を咥えたときだ。後ろに殺気を感じた。振り返ると先ほど切り落とした花の後ろに、巨大な影があった。さっきまでここに建物は無かったぞと思ったが、違う。あほみたいなサイズの母体樹だ。全長が二〇メートルを超えるサイズ——
「ホーリーシット」
俺は煙草を落としてしまう。
「おい、こっちナリよ。今、そいつは動けないから逃げるナリよ」
目の前の刀がやけに震えていると思っていたら、自分の握っていた力が強すぎたせいであった。血の気が引いた自分の顔を想像して笑った。決して犬を信用したわけではないが、確かにその母体樹は動かなかった。俺は納刀して、すぐに駆け出した。
「おい、犬! どこに逃げるんだ」
犬は、足先についているタイヤを高速で回しながら俺の横まで来た。
「犬と呼ぶな。博士と呼べナリよ」
そう言って俺の前を走り、瓦礫や木の根っこを避けて走りだした。ロボットなのに奇妙に生き物の感覚を覚えた。犬のしっぽはリズミカルに揺れていて、足元のモーター音と比べれば随分と不釣り合いだった。
俺と犬は十数分走り、丸太で組まれたバンガローに着いた。町から少し外れたところにある、誰かの住まいだろう。頑健な木で組まれた扉を押すとすぐに洒脱な玄関が見えた。一瞬見ただけでも人が生活していた匂いが残っていやがる。人の生活に土足で入るのは気が引ける。しかし、犬は居心地の悪さなど分からないかのようにリビングへと入って行った。リビングには気持ちのいい大きな窓があり、そこからそのままテラスに出れるようになっていた。窓の向こう側には夜になって見えないが、農園が広がっているのだろう。その窓の前に大量のアロエが置いてあった。奇妙に思いながらも、癖で周囲を見回した。奥に二階へ続く階段があり、天井には天窓がついていたが、今は閉ざされていた。それから、暖炉があった。暖炉のまわりにもアロエが置かれている。
「ここなら安全ナリよ。ワシが色々としておいたから」
犬はいつの間にかリビングの真ん中の赤と白で編み込まれたラグの上でお座りをしていた。
「ここが安全かどうかは俺が決める。それから最初にお前が何者かを答えろ」
俺は警戒心を解かずにロボットに命令した。見るに武器らしい武器はなさそうだ。最速で動いたとしても先ほどの速さだろう。目や、口から発出されるものがあるかもしれないので、真正面に立たずに斜に入った。相手に悟られないように、左手を鯉口においた。
「あ、そうだった。ワシが何者かを話していなかったナリな」
犬はそう言って、後ろ脚になっている足を器用に耳のところに持ってきた。どこかが痒いわけでもないのに、そんな仕草をするということはコントロールのみのロボットではなさそうだった。かといってAIってわけでもなさそうだ。
「ワシは、ヤスモト博士ナリ」
それを聞いて、俺の血が沸き立つ。ヤスモトだと? そんなはずはないと分かっているのに、俺は抜刀していた。そのまま叩き切ろうとした。
「待て待て待て‼ 話ぐらい聞くナリよ」
辛うじて理性が働き、刃が犬の顔の前で止まる。目の前のそれがヤスモトではなくロボットであることを思い出せた。
「お前……生きていたのか?」
恐らく人を呪うというのはこういう気持ちなのだと、今理解した。
ヤスモト博士。レッドミクロカーパを生んだバカ博士。世界をどん底に落としたマッドサイエンティスト。そのくせ、早々とレッドミクロカーパに生き血を吸われて死んだと聞いていた。
「まあ厳密には死んでるナリな。肉体はもうない。メモリーをバックアップしておいたから、こうやって話すことができるナリよ」
「お前、肉体が無くて良かったな。アテネ時代であれば、お前に向けて市民が石を投げて殺しただろうし、中世であれば十字架にかけて火で燃やしただろうし、少し前の時代であれば、手を後手に結んで……」
「ああ、分かった分かった。人類の敵と言いたいんだろう? 良いよ、良いよそれで」
「ずいぶんと投げやりだな」
言いたいことはあるが、一旦この状況を鑑みて冷静になるべきだった。それにすでに死んでいる人間に恨みは届かない。目の前のロボットが壊れるだけだった。
「それで色々と訊きたいことはあるが、まずは今のお前の状況を説明しろ」おれは切っ先を引っ込めて、刀を肩に担いで言った。
「お、なんじゃ。猿みたいな顔して、冷静な奴だな。気に入ったナリよ」
「早くしゃべれ。いつ母体樹が来るか分からんだろう」
「おお、クレバーだな。ますます気に入ったナリよ。良いじゃろう。手短に話してやろう」
ヤスモトは、西海岸の有名な大学の博士だったそうだ。気候変動問題は世界にとってのっぴきならないリスクだったそうだ。そんなか、世界の緑化に関する指導的な役割を担い、レッドミクロカーパを研究し人類を救う手立てとして大成させたそうだ。
「ワシは確かに大量の人類を殺したと言われる。しかし、終末時計はレッドミクロカーパが氾濫したおかげで伸びた。地球の延命措置には成功しているナリよ。もともと頼まれていた仕事をしただけなのに、なぜここまで言われなければならないナリ。酷いナリ」
「吐き気がする言い分だな。が、正論ではあるな。確かに気候変動は留まった」
「おお、本当にクレバーだな。論理的な思考が出来るタイプか。あのな、地球は人類を生かす大地なんだよ。人類がコントロールするには限界がある。そもそも増え過ぎた。ただな、それは分かっていたが、ワシが開発したレッドミクロカーパは、都市を破壊するなんて凶暴ではなかったナリよ」
「どういうことだ?」
「さっきのあれをワシは開発していない。あれはそのあとの成果というか、もっと過激な思想が完成さえた悪魔ナリよ。その思想は人類を半分にすべきという過激なものだったナリよ」
ヤスモトが開発したのはレッドミクロカーパが家畜の血を吸うところまでで、人類を攻撃する因子はその時点では無かったそうだ。しかし、合衆国の上層部が研究を無理やり引き継ぎ、ヤスモトから研究を奪ったそうだ。そいつらは、人類皆が一緒に成長しながら、さらに地球環境を守りながらという理想は、穏やかに地球を殺しているに過ぎないと結論ずけた。過激なやつらは「人間より上位の存在を造り、人類を間引きすべき」だと考えた。そして、レッドミクロカーパは進化し人の生き血を吸い、町を破壊する母体樹が産まれたという。
「まあ、でも元を作ったのはワシだからな」
ヤスモトはそう言ってクーンと鼻を鳴らした。
「で、あのアロエはなんだ?」
「おお、そうそう。アロエが出す臭いが苦手なんだよ。それを克服させようとしていたのに、急に研究をとりあげたのでその性質が残っている」
「で、どうして逃げた」
「矢継ぎ早だな。黄色い花の後ろにいた巨大な母体樹はな、母体樹のさらに母体樹だ。で、黄色い花は奴らにとって出産だった。それを切ったお前を恨んでいるはずだ」
「意思は無いはずじゃなかったのか?」
「脳が無いだけだ。感情も意志もある。それが必ず脳でやらねばならぬというのは哺乳類のおごりだよ」
「分かった。で、俺はこの村からどうやって逃げればいい」
「それは無理だろう」
ヤスモトは神妙そうにそう言った。この村の周囲にもう根が回っているはずだという。あのバカでかい母体樹は、最初の段階で人類の逃げ場を無くすために地中から根で囲む。次の母体樹が育ったところで、自分の根から幹を伸ばし、人類を閉じ込め、我が子に人を食べさせて独り立ちさせるそうだ。
「もうすでに囲まれているということか」
「すまんな……」
ヤスモトの目が漫画の様に垂れ下がった。
「それで……これは新しい依頼と思えば良いのか? あいつの殺し方、分かるんだろ?」
俺はヤスモトが生かしてくれた理由を考えた。恐らく何か手立てがあるから、生かしたに違いない。どうせ死ぬんだ。それなら一番危ない橋を渡ってやろう。
「良く言ってくれた。ワシからはなかなか言い出せなくて。だって、下手に闘っても、あのバイオロジカル母体樹とは消耗戦になり、かなり分が悪い。それに死に方もえぐいことに……」
それからヤスモトは丁寧に奴の倒し方をレクチャーしてくれた。自分のボディを開けて重要なパーツを渡してくれた。これがあれば大丈夫だというのだが……
4
「ああ、それから——」
博士が何かを言い足そうとしたタイミングで、博士のいる地面が浮き上がった。同時にレッドミクロカーパの鋭い根が博士の頭をくりぬいて天井に張りつく。博士の片目が完全にくりぬかれ、その残骸が天井でぶら下がった。その根のすぐ傍から違う根が入り込んで、ヤスモト博士を包んでしまい完全に握りつぶした。俺は急いで抜刀をした。どうやら本当に感情があるらしい。自分の足元が膨らむ気配を感じ、何も考えずに後ろに飛び込んだ。目の前に大きな根が噴き出てくる。すぐさま、半分座った状態のまま身体をひねってそれを両断した。その切り口から血潮が噴き出る。汚れたリビングに詫びを言いながらも、テラス前のガラス窓へ向かい刀の柄でそれを割った。コートで肌が出るところを隠しながら、外に飛び出す。瞬間、後で轟音が鳴る。振り向くとバンガローが根で持ち上げられていた。そして巨大なバイオロジカル母体樹が聳え立つ。夜のしじまに似合わぬ巨木。意思のある植物。木の主幹にあたる部分は複数の幹が絡まり合って出来ており、直径一〇メートルはあった。その上には拡げた広葉の傘があり、幅二〇メートルほどある。一際目立つのが天頂に咲いた一輪の赤い花だった。そして花や葉を支える枝からは何本も気根が降りており、一〇〇本以上はあった。良く見ると、いくつかの気根には人間や家畜がぶら下がっていた。
「まるで死のメリーゴーランドだな。さぞかしいい景色が見えるんだろうな」
俺は腰に付けたベルトバッグにスマフォを固定し音楽をかけた。QUEENのThank God Its`s Christmasが流れた。フレディの声が聞こえる。そうだな、賛同を示すよ、フレディ。神様、ありがとう。このクリスマスを。俺は曲のボリュームを上げて、さっき博士がくれた重要なパーツ、Bluetoothスピーカーを柄に取り付けた。爆音が夜の農村に響き渡った。目の前のあいつはぶら下げた百本近くある気根をこちらに一本、二本、三本、いや数えられないほど、俺を殺すために波を打たせて発射してきた。一つ五〇センチほどある太い根だ。このひ弱な身体で掻い潜っていかねばならないとは、何とも骨の折れる仕事だ。やれやれだぜ。真正面の一本が俺を貫こうと向かってきたので目の前で刃を立てた。一瞬衝撃が両腕に響くが、グリップを弱めずにいるとそのまま根を両断してくれた。が流石に重い。この一本に全ての力を集中せざるを得ない。これじゃ今、他の根に攻められたら——
しかし、周りの根からの攻撃は無い。俺は切り裂いた根を払いのけて周りを見た。そしたら根がのたうち回っていた。
——そう。音楽のビートを直接血に送れば勝機はあるナリ。そもそも彼らに筋肉があるわけじゃない。血のめぐりを使って根を動かしているナリよ。だから音楽の震動が直接駆け回れば、動きを狂わすことができる。麻痺状態をつくれる時間は短いが有効ナリよ——
博士があんな姿になる前に口にしていた言葉だ。なるほど本当にその通りのだ。にわかには信じ難かったが、これならバカでかい母体樹にも勝てるかもしれん。俺は切った根の峰を歩きながらそう思った。
「どうだ、QUEENは良かっただろう? 魂に響くだろう」
俺は曲のチューニングしてジャクソンファイブのSanta Claus is coming to townを選曲した。ビートに乗ったギターのカッティング音が聞こえる。マイケルがサンタが来ると唄いあげる。そう、この街にもね。
「だから、お前もいい子でいないとな」
復帰した気根が俺を狙って来る。さっきの麻痺のことを覚えているのだろう。一本だけでは来ず、数十本が同時に俺めがけてきた。
O! You better watch out!
You better not cry.
Better not pout, I'm telling you why.
Santa Claus is coming to town.
鼻歌を歌いながら、身体を翻して前転する。すぐ後ろで砂塵が舞い、突っ込んできた根が地面を突き刺すのを感じた。自分の頭上に伸びきった根が見えた。三日月の逆を描くように頭上に半円を描いて、突っ張った根を断ち切った。そのまま左手で柄をとり、切り口から唐竹切りをする。
そのまま縦に切り続けて、長い間マイケルを聞かせてやったおかげで死のメリーゴーランドから人や家畜が落ちていった。
「マイケル嫌いか? 次はその赤い花にもっといい曲を聴かせてやる。お前もクリスマスが楽しみだろう」
乱れに乱れている根の一つを切り落とし、俺は幹に飛び乗った。両手を使うため、刀を一旦納刀して登っていく。幹は一本でできているのではなく、数本の太いものがグネグネと絡まり合って上に伸びている。一〇メートルぐらいまではほとんど足だけで上ることが出来た。葉が広がるようなところまで来ると、流石に両手を使いながら上がっていかないといけなかった。俺は両手を葉のなっている枝に手をかけた。
だが、両手をかけたところ手の甲に激痛が走った。手を引いてみると、まだ成長途中の気根が複数、手の甲を突き刺していた。俺はすぐに引っこ抜いた。若々しいその根っこは弱いのだが、確実に人の皮膚を突き破れる。俺は思わず天を仰ぎ見た。木々の間を抜けて天頂の花にたどり着くまでの間、この気根が永遠に俺を襲う。どれほど針の地獄の中を突き進まなければならないかと気が遠くなった。やれやれだぜ。
「天頂にたどりつくまでに俺の血が尽きればお前の勝ちだな」
俺は懐にいれておいたグローブを手にかぶせた。自然と口の端がひきつる。周囲の気根の乱れがおさまりつつあるのが分かった。ここに居てもそのうちあいつらに殺されることになる。
「グリム童話のいばら姫か……さぞかし麗しい姫がいるのだろうな?」
覚悟を決めてその暗い森の中に入っていった。入ってものの数秒で後悔をしたことは勝手に想像してくれ。
5
ミドルスクールのときだったと思う、一度だけダディに叱られた。同級生と喧嘩をしてボロボロになって帰った玄関先での事だったと思う。そう言えば、そいつの名前を忘れたが、碌な奴じゃなかった。関わるだけ面倒ごとが増えるやつだった。その日、同級生の女の子の教科書がビリビリに破られていた。恐らくそいつがやったんだろう。どっかで手に入れたナイフで切り裂いたに違いない。家で野菜でも切っていればいいのに。そいつは自分が犯人だと言われると不利だと思ったのか、俺を名指しで犯人扱いしやがった。面倒だが、自分では無いと教員に伝えたが、知らないナイフがロッカーに入っていたので、犯人確定となったわけだ。クソみたいな説教を数時間も聞かされて、憮然として時間を過ごした。その後、あいつを見つけて殴りつけてやったら、喧嘩になったってわけだ。喧嘩の跡がある状態で家に帰ったらダディが仁王立ちして待っていた。
「エイダン。話は聞いたぞ」
ダディのその表情を見て俺は碌な話を聞いている気がしないと決め込んだ。そして、地上で一番残念な顔をしたはずだった。ダディはその時、大声で叱った。
「ヘイ、エイダン。お前は俺のことを何だと思っているんだ? あの死んだような先生の話を聞くとでも思ったのか? お前からの言葉を聞く前に? 俺はお前のダディだぞ。何よりお前を信じている。賢くてタフなお前をな」
俺が何よりも信じなきゃならない人。それがダディだった。だから俺が残念そうな顔をしたことを叱ったんだろう。偏屈な人だったが、真っすぐなところがあった。レッドミクロカーパが農場を襲ってきた時にもまっさきに立ち向かったのはダディだった。俺はハイスクールにいた。ダディはあっけなく胸を貫かれて、血を吸われてしまった。ダディ。誰よりも俺はあんたを信じていたよ。その死の報を聞いた時でさえ、帰ったら目を覚まして、「どうした、エイダン。俺を信じてなかったのか? 簡単に死ぬわけがないだろう」と言うに決まってる。そう信じていた。ダディ——
俺は手を上に伸ばして、伸ばして、届かない日々を掴もうとしていた。
6
俺の手が空を掴んだ。ああ、まだダディとお酒を飲むのには早いってことか。俺は残りの力を振り絞り、地獄の針の洞穴を抜けた。体中に気根が刺さっていた。血が吸われ過ぎて朦朧としていた。激痛が体中を走る。だが、息を吸ってこうやって天の下にたどり着いた。
「もう少しで、お前の腕の中で眠るところだったよ。どうも寝つきの悪い方でね。スッキリ寝るにはちょっと高級なベットが必要だったな」
足場を見つけて立ち上がる。自分から数メートル先には、あの赤い花がある。大きさは約三メートルぐらいだ。雪がちらちらと降っていて、葉の上には雪が積もっていた。赤い花の上には雪が積もっていない。温かい血が巡っているのが分かる。俺は抜刀して、正眼の構えに入る。前の敵に集中を固めるための構えだ。花の影からじゅるじゅると奇妙な動きをしながら根が顔を出してきた。表情でも読めれば奴の気持ちが分かるはずだが、少し気分が乗っているんじゃないか。俺も気分がいいぞ。お互い死が傍にいるからな。そのうち一本が俺をめがけてきた。正中線に切り落とす。が、他の根がそのまま同じ場所にいた。先ほどまでの錯乱は見て取れない。俺は自分のスマフォを見た。さきほどの葉の森を抜けるときに、若い根が絡まり、バキバキに壊れていた。もう音楽は流せない。やつらの血を狂わせる方法はない。雪降る中で、次の根が来ると思われた静寂が俺を締め付けた。
「お? なんじゃトラブルか?」
博士の間抜けた声が響く。
「博士、生きていたのか?」
声の元は、さっきもらったBluetoothスピーカーだ。
「ああ、あのロボットは一時的にインストールしただけの存在だったしな。本体は別にある。自分で預けたスピーカーのくせに繋ぐのに時間がかかってしまった。すまんすまん」
博士との涙の対面も許してもらえないのか、すぐに二の矢が飛んできた。半身になってよけながら、右手を振り上げた。開いた身体で腕の力を抜きながら、刀を落として、根を切り落とした。赤い血が雪を染めていく。
「おい、博士。そこから、飛び切りの曲をかけてくれないか。この赤いクソみたいな花にもオシャレな曲を教えてやりたいんだよ」
「なんだ、そういう事か。わしの生前の美声を披露してやりたかったが、このスピーカーでは表現しきれん。しかたないので、世界で二番目に素敵な曲を教えてやろう」
博士が軽口をたたいたあと、あの男の子の声が聞こえた。
Oh, happy day. Oh, happy day
悪くないね。もう少し声を出せボーイ。いや、違うな。最高の唄を聞かせてくれ
When Jesus washed
He washed my sins away
Oh, happy day
クラップが聞こえてきたところで、根の二つを袈裟切りで切る。垂れ下がった、根を足場にして、空中に身体を翻し、ひねりながら身体を前に倒す。左右に伸びていた二本の根の傍を通るときに、ひねりの勢いのまま刀の花を拡げていく。そのまま二本を切り落として着地を決めた。後ろで血が噴き出た。そのまま前に足をだして、そして天頂の花を勢いよく走り抜けるときに胴を打ち払うように刀を通す。その感触が手に感じられた。
He taught me how to wash
Fight and pray, fight and pray
And live rejoicing day
Free day, every day
血の噴水があがる。神よ。神よ。私たちの罪を洗い流したまえ。この血の雨で。そして、喜びに満ちた日を、自由で信頼に足る人としての日々を。
ぽたぽたと緑の牧場の上に赤い雨が降り続けていた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
