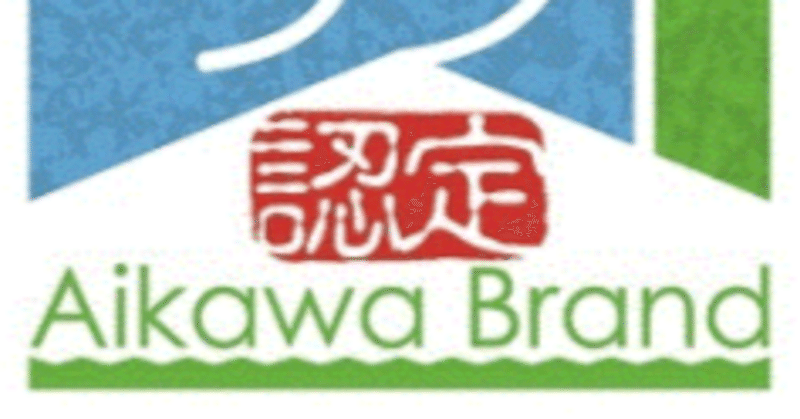
愛川ブランド認定審査委員会 (愛川町日記 2017年4月5日より転載)
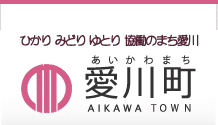
愛川ブランド認定審査委員会
開催日:(すでに二回開催)
担当課:総務課
会議録を見る
1回目
2回目
審議委員、終了。
先月3月31日、つまり昨年度を以て。
「愛川町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会」の公募委員の任期2年を終了しました。
いつもは傍聴のみ(最近はなかなか忙しくてそれすらできていないのが残念無念でなりませんが)だった審議会の委員となり
いつもと違う風景からこの町を見ることができ非常にいい経験でした。
ま、「愛川町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会」が少し特殊でしたので、一概に「これが審議会!」とはいきませんが
審議会の性質上、俯瞰的に様々な職種の人々と愛川町を視れたことは大きな収穫でしたね。
次の審議会へ・・・、と思いましたが
すべて募集締め切り。
というわけで、次年度の審議会入りはなしです(笑)
「町議会」と「審議会」
どちらも「傍聴」はできますが、それぞれの性質は大きく違います。
ですが、僕は「審議会」こそ愛川町の現在進行形が見えてきます。
想定問答が台詞としてある現代劇のような「町議会」。
それに対して「審議会」は公募委員や町に近い有識者が口語体で細分化された話し合いを進めていく。
時には白熱する議論に。
時には大きく脱線する町の話に。
丸テーブル上での意見の交し合い(議会はどちらかというと明確に質問者と回答者がわかれた二車線の話し合い)だからこそ
そこに「町に直結した指針」が生まれる。
・・・ような気がします。
審議会は「今」がわかり、愛川町の現在地が見えてくることがあります。
だからこそ、審議会傍聴は僕のおすすめです。
僕も今後も時間を見つけて審議会傍聴を続け、少しでも愛川町が進もうとしているベクトルを見ていきたいです。
「ブランド」

ブランド(英: brand)とは、ある財・サービスを、他の同カテゴリーの財やサービスと区別するためのあらゆる概念。
当該財サービス(それらに関してのあらゆる情報発信点を含む)と消費者の接触点(タッチポイントまたはコンタクトポイント)で接する当該財サービスのあらゆる角度からの情報と、それらを伝達するメディア特性、消費者の経験、意思思想なども加味され、結果として消費者の中で当該財サービスに対して出来上がるイメージ総体。(「国語辞典」より)
つまり。
「ブランド」という言葉は、「周辺の評価や評判の醸成」の顕れ。
よくよく考えるとそうです。
自ら手を挙げて「我こそはブランド」と言うことや、一人二人の人物が指さし「これがブランド」ということが
まわりが納得する「ブランド」として残ることは、まず、ないでしょう。
「長い年月と多くの人々の想い」があって「ブランド」という言葉が重く輝きを増します。
「愛川ブランド」
この言葉に私が妙な違和感を感じるのはそのためかもしれません。
昨今は「ブランド」という言葉の意味すらが揺らぎつつありますが。
しかし、その本質は変わりなく、「ブランド」という言葉にまだ重量感がある為に、どうも「愛川ブランド」という言葉をみるとむずかゆくなる。
「認定された商品」はすばらしいものです。私もそれらを知っているし、「愛川町を代表する商品・食品」ばかりです。
ただ、もし本当の意味で「ブランド」を選ぶならば、果たしてこれらの商品・食品が選ばれたのでしょうか?
先ほどの国語辞典を開いてもわかるように、本当のブランドが持つ意味である「長い年月愛されていると大多数の人々が認めるもの」。
多分に自然発生である「ブランド」という言葉を、そのまま大きく反映し、安易に数値化できるものは「アンケート」や「売上」などです。
「今の認定品を否定するのか?」と聞かれそうですが、そうではありません。
「住民アンケート」や「売上」でも今の認定品は素晴らしい結果をもたらすでしょう。
ブランドを語る上でひとつのカギとなるのは「認定方法」です。
愛川ブランドの認定方法は、「事前に業者から「申請」されたものを町の審議会で決める」
となっています。
(詳しくは一回目の審議会議事録を)
なんだか「密室性」を感じるような・・・
つまり、文字通り「ブランド」の言葉を使うならば、「長い年月愛されていると大多数の人々が認めるもの」の意味を当てはめるなら、「愛川ブランド」には「ブランド」が誕生するその条件と大きく異なるということです。
「愛川ブランド」の「ブランド」では「ブランド」ではない。

誤解を恐れずに言うのならば、「愛川ブランド」は「官製ブランド」です。
今回の認定品の多くがあらかじめ持つ「長い年月愛されていると大多数の人々が認めるもの」を、町の規定に当てはめていく。
当然、ブランドとして認定された側としては「町による販路拡大」を期待するし、町としては「愛川町をPRする製品を期待する」という構図ができます。その辺の両者思惑のやり取りの終着点はいかがなものでしょうか。
そこが今一つ見えません。
「愛川町外の物産展で愛川ブランドを販売しました」
それは単発の売上結果であり、「愛川町をPRする」という根本が薄れています。
長年愛川町で息づいてきて、「愛川ブランド」という錦の旗印がなくとも「長い年月愛されていると大多数の人々が認めるもの」と自力でなってきていた製品たちを、「愛川ブランド」という硬く狭い枠に入れ込み、その商品が持つ魅力を削るようなことにはならないでほしい。
愛川ブランドが、角を矯めて牛を殺すという結果を産んでほしくないです。
そして、議事録にもでていますが、「28」という数字は多すぎる気がします。
ただ単に認定すればいい。ではないのですから。
しっかりとブランドとして立ち上げてから、認定数を増やせばいい。
数が増えることにより「ブランド性」が薄れるのではないでしょうか?
他の「ブランド」が構成される中で、長い年月を必要とされてきました。
愛川ブランドはそれらを割愛して生まれました。
ここまで書いてきて、ふと筆を止めてみます。
「ブランド」
この言葉に思考の淵を留めているのです。
もう一度話を整理してみれば
「愛川ブランド」の「ブランド」は純然たる本来の意味しか持ちえない「ブランド」という言葉でない。
どちらかといえば
「愛川オールスターズ」
の方がしっくりくるような気がします。
ただ語呂や言い易さから「ブランド」という言葉になっただけなのかもしれません。
行政が監督なりコーチとなり、品物やお店が選手となる。
こういうビジネス的要素の色合いを強めればなんとなくこの「愛川ブランド」が見えてきます。
なら、それでいいのではないか。
と、結するのも少し蟠りがありますので。
「愛川ブランド」の「ブランド」が「ブランド」になる為にはどうしたらいいのか?
を考えてみましょう。
認定品はそれだけで愛川町を代表するものが多いです。
その上で敢えて「ブランド」という言葉を使うのならば。
まずは「認定方法」を考えてみましょう。
今の「審議会決定方式」ですと、町民としては「あれ?いつの間に?」と思う人も多いでしょう。
(この審議会のメンバーに、申請者がいるというのも少しどうかな、と思いますが)
ブランドの持つ「多くの人が認める」という点です。
今後いくつの「愛川ブランド」が誕生するのか、わかりませんが、
「最後の1枠」は「住民アンケート」にしてはいかがでしょうか?
愛川町といて新しい特産品の掘り起こしとなるし、住民意識により近い認定品が生まれると思います。
「審議会決定方式」が前提としてあるのならば、数品だけでもそういう方式ならば町民も「われらがブランド」となるのでは。
とにかく「ブランド力」をあげる事。
これに尽きます。
そのためには「多くの人が知る事」「利用する事」。
「自分たちの町のブランド」にすること。
祭りやイベントの場ではなく、「愛川ブランド」専用の市を定期的に行う。
「愛川ブランド」を一括して購入できる場所を作る。
試食会や製品説明会など町民が愛川町ブランドに接する機会を多くする。
まずは町外ではなく、町内のアピールを行うことが優先ではないかと思います。
まずは町の人々が消化し、町外へのお土産やSNSで拡散していく方が
PR効果は大きいはずです。
そして、ブランドとしての競争力をつくることがブランド内の向上になります。
ブランド市での、評判や売り上げで認定品からはずし、あたらしいブランド認定品を加える。
ブランドを維持するためには厳しい競争も必要です。
新しく町にできたお店が、「愛川ブランドに認定されたい」というくらいの力が必要です。
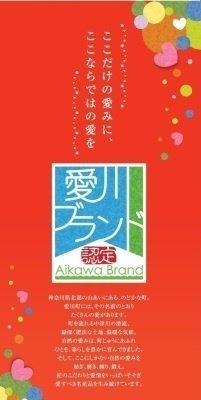
「ブランド」の行く末
「愛川ブランド」の「ブランド」が本当の意味で「ブランド」になってほしい。
先ほど、僕の考えを述べたように「愛川オールスターズ」です。
今は、「愛川ブランドだから」で買い物をしている人は少ないでしょう。
「いつも買うところだから」「知っているお店だから」で買い物をしているひとが多いです。
「ブランド」とは?
それを考えさせられました。
この「ブランド」の行く末は?
それは、「認定品」側でなく、「認定した」側である愛川町にかかっているでしょう。
「愛川ブランド」の「ブランド」が本当の「ブランド」になる。
「愛川ブランド」認定品のお店が、胸を張って「愛川ブランド」を威張れることになる。
その日は、いつか必ずくると思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
