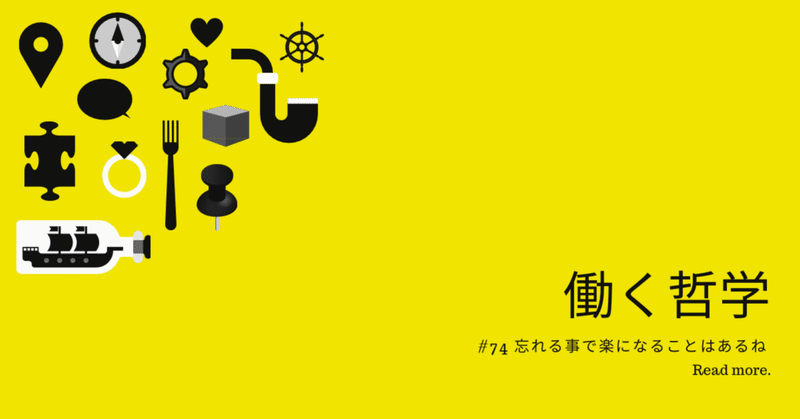
人間は忘れるから生きていけるという話
人間は忘れる生き物だ。
記憶に関する研究者として知られているドイツの心理学者ヘルマン・エビングハウスは人が学習した情報は指数関数的に失われることを示す忘却曲線を発見したことで知られる。
エビングハウスによると人の記憶は最初の20分で急激に失われ、その後緩やかになっていくという。
(最初の20分で記憶したことの42%を忘れ、1時間後には56%、1ヶ月後で79%の情報を失う)
因みに、エビングハウスの忘却曲線は学習に関する事柄(陳述的記憶)で人がそれまでに経験した出来事に関する記憶(自伝的記憶)とは少し異なる。
だが、脳科学者である中野信子氏も著書『サイコパス』の中で「脳は頻繁にエラーを起こす、バグだらけの不完全な臓器」と述べ、特に「高次脳機能」、意識や思考、 意思決定などを司る「前頭前野を中心とした部位」がエラーを起こしやすいと言及している事から、脳に依存している人の記憶は結構いい加減なものであることが分かる。
では野生動物の場合はどうか。
実はコレは比較が難しい。
野生動物の情報量と、人間が社会生活を送っていく中で蓄積する情報量とでは雲泥の差がある。
野生動物の情報は、それが無いと生きていけないギリギリのものだが、人間が得る情報には余計なものや生きていく上で必要がないものも多く含まれる。
だからこそ人間はある程度ものを忘れることが、生きていく上で大切になることだと学習していく。
身内や親友などの死に接した悲しみ、出産や骨折などで経験した痛みをなどを全てそのまま引きずっていたとしたら、とてもではないが堪えることはできない。
同じように人を嫌い続けたり、怒り続けることも難しい。その時、どんなに腹が立っても当時の怒りを当時の熱さで思い出すことは出来ない。
憎いと思っていた人が、本当は自分にとって重要な人になったということもあるだろう。
悲しみや憎しみはいつか薄れていくものだ。
そうでなければ、人間は一生悲しみの中で生きていくことになる。
ちょっとしたケガならば、数日で跡形もなく消えて痛みも忘れてしまう。
同じように、心の負った傷もいつかは消え行く。
今、人生や仕事、家族の問題で苦しい思いをしているとしても、それは一時の問題だ。
喉元過ぎれば熱さを忘れると先人はよく言ったものだが、大切なのはいつか解決の日が来ると思うことだ。
全てはうつろいゆくものだ、ということが分かれば、前向きになれる。
どんなに耐え難い苦しい道を歩んでいても、時は流れていくので人は前へ歩き続けなければならない。
いつかは忘れていく昨日。
新しい明日に向かってそれぞれの道を歩き始めよう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
