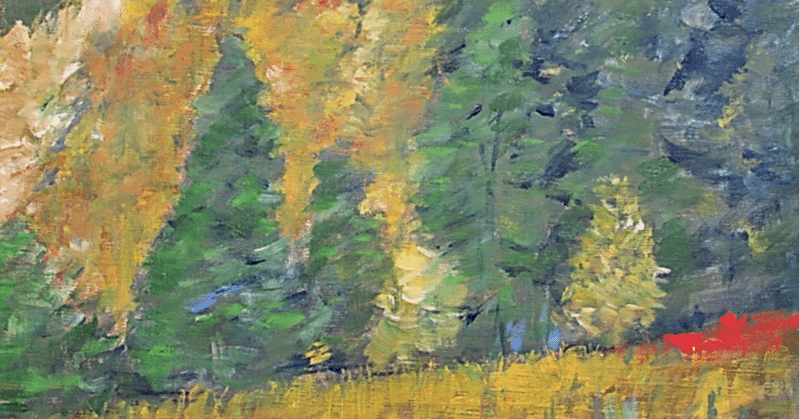
適塾 緒方洪庵 1 駒敏郎

かつて塾は日本と日本人の知性をつくりだす精神的な基盤だった。はるか遠くに消え去っていく我らの国をつくった塾を、この森に植樹していこう。木は二度生きる。ウオールデンの森でぐんぐんと生育していくはずだ。魂は不滅である。
![]()
適塾 緒方洪庵 1 駒敏郎
適塾は青春の塾である。
塾生たちの年齢はいうまでもない。その挫折を知らぬひたむきな追究、贅沢なほどの熱情の浪費、傲岸ともいえる反俗の矜持、幼稚と老成、無軌道と使命感の混淆、すべてが青春の属性であり、人生のまばゆい一時期にだけ発散されるものだ。
そうしたものをふんだんに抱かえこんで、日本の全国から三千人もの青年たちが集まってきた。彼らはみな「蘭学の虫」であり、一種の勉強馬鹿だった。ただがむしゃらに、人に負けまいとして、蘭学という大きな岩にくらいついていったのだ。
大阪の北浜過書町。緒方洪庵の適塾は、明治日本の青春が育った塾だったのである。
適塾の特色は二つの点でいちじるしい。一つは、多数の人材を世に送り出したことで、もう一つは、勉学のきびしさである。この二点は、実は塾とよばれるほどのものなら、どの塾にも共通していえることで、珍しい現象ではないのだが、それをあえて特色としてあげ得るほどに、適塾はきわだっているのである。
時代の転換期をまえにして、適塾は多くの人材を用意したが、それはみな、当座に間にあう人材ではなくて、新しい時代がはじまったときに、真価を発揮する人材ばかりだった。世俗的成功への近道は、当時、他にいくらでもあったわけだが、適塾の信念はゆるがなかった。これは、指導者である緒方洪庵の見識である。
塾風がまた猛烈だった。徹底して、努力と独力とで学問にぷっかってゆくことを教えた。「蘭学の虫」にならなければ、一日として塾内に暮らしてゆけないような雰囲気につつまれていた。アクの強いことでは選り抜きの青年たちが、こうした塾風をつくり、かつ喜んで受け入れた。これは洪庵の教育者としての力の大きさを示すものである。
![]()
ところで、このような適塾をつくりあげた緒方洪庵という人物だが、塾風とはおよそうらはらな感じがするほどの、温厚な蘭学者であり、熱心な町医者だった。塾生と接するときはいつも微笑をたたえて、言葉づかいも客に対するときと変わらなかった。これがまた塾生たちには何よりも恐ろしくて、洪庵に笑いながらよびつけられると、叱責を覚悟してシュンとしながらかしこまったそうである。
もともと洪庵は医者になることを目標に勉学をした人だ。その人生の目標は、すぐれた医者になって、よく口にしたごとく「世のため国のため」につくすことにあった。適塾は、どちらかといえばサイドワークであって、洪庵自身は町医者としての務めを専一に考えていた。
備中足守の藩士の家に生まれた洪庵が、武士を捨てて医者を志したのは、一八六二年(文政九)十七歳のときである。この年、出島開館の医師ドクトル・フォン・シーボルトが、カピタンの江戸参府に随行して、大阪を二度通過した。医学を志した洪庵が、蘭方医を選んだ理由の一つには案外こうしたできごとの影響があったのではなかろうか。
洪庵は大阪に出て、蘭方医であり蘭学者である中天游の門にはいった。蘭学にかけては、大阪には伝統があって、そのさかんなことは江戸を凌ぐほどだった。名よりも実を尊ぶ町人の町の気風は、蘭学の根底を流れる合理性と共通するものをもっている。本質的に蘭学の育ちやすい精神風土をそなえた町だったわけである。輩出した蘭学者も毛いろが変わっている。質屋の主人である間長涯。商家の番頭だった山片蟠桃、傘屋の職人だった橋本宗吉など。いかにも大阪らしい町人学者があらわれている。
洪庵は橋本宗吉の流れを汲む中天游について関学の手ほどきを受け、一八三〇年(天保元)からまる五年間、江戸へ遊学した。江戸での師は、坪井信道と宇田川榛斎だった。この坪井の深川の塾で、洪庵は、青木周弼、黒川良安といった人びとを識るわけだが、青木も黒川も、長崎の鳴瀧塾でシーボルトから親しく教えを受けた人だった。
洪庵がもう二、三年早く蘭学に志していたら、おそらく鳴瀧塾へ駆けつけていたことだろうが、ほんの少しのことでシーボルトとはすれちがいになっている。だが、新鮮な嗚瀧塾の学問をもって帰った人びとと接触したことは、洪庵の心を長崎へ駆哄立てた。
![]()
一八三六年(天保七)。二十七歳の洪庵は、長崎へおもむく。鳴瀧塾はすでになかったが、さすがは長崎で、そのつもりになれば勉学の方途はどのようにもつく。洪庵はそのころオランダ商館長だったニーマンについて、オランダ語と西洋医学を学んだようだ。長崎でも良友を得た。シーボルト門下の柴田方庵や、のちに順天堂の創始者となる佐藤泰然である。
洪庵の長崎遊学は、意外と短く、二年間で終わっている。当時、シーボルトに匹敵するすぐれたオランダ人医師がいなかったせいかもしれない。一八三八年(天保九)大阪に帰って来た洪庵は瓦町に住居を定め医師として開業をすると同時に、蘭学の塾をひらいた。こうして、洪庵の半生の大事業となった「適塾」(適々斎塾)が生まれたのである。
当時洪庵は二十九歳。同じ年に、京都では鳴瀧塾に学んだ日野鼎哉が開業しており、翌年は新宮涼庭が、順正書院をひらいている。また大阪では洪庵より二年早く、高良斎が北久太郎町に開業している。この時期に、関西の蘭学は新しい基礎をすえたわけである。それは、蛮社の獄のおこる寸前の、蘭学にとってはつかの間の平安な時代でもあった。
洪庵の蘭学者、蘭方医としての名声は、開業の当時からかなり高かったようだが、それを具体的に示す愉快な資料がある。格付けの好きな江戸時代の人は、なにかにつけて相撲番付に見立てた一覧表をつくっている。その大阪の町医者番付、「当時流行町請医師名集大鑑」というのがのこっている。
一八四〇年(天保一一)、開業して三年目の洪庵は、前頭四枚目である。それから四年たった一八四五年(弘化二)には、早くも関脇の位置をしめ、小結の高良斎とならんでいる。さらに三年たった一八四八年(嘉永元)には、堂々たる大関になっている。きわめて世俗的皮相的な評価ではあるが、塾の消長というものは案外そうした評価に左右される。
![]()
洪庵は、その前頭四枚目のころ、一八四三年(天保一四)に、北浜の過書町へ移った。塾生がふえて、瓦町の小さな家ではどうにもならなくなったのだ。師走の寒風のなかのあわただしい移転がやっと一段落ついて、年が改まる。洪庵は、新しい塾舎の発足と同時に、入門帳をつくらせた。これが現在ものこっている貴重な記録、「適々斎塾姓名録」である。瓦町時代からの塾生有馬摂蔵にはじまって、洪庵没後の一八六四年(元治元)まで六百三十七名の名がならんでいる。
その多くは、古びた半紙に一行の姓名を青春の記録としてのこし、ふるさとへ帰って蘭方医としての静かな一生を送ったのだろう。生没も業績もたどることのできない人が多い。だが、そうした寡黙な姓名にまじって、するどい光芒をはなついくつかがある。
北浜に移って三年目の一八四六年(弘化三)、村田蔵六のちの大村益次郎の名が見える。翌年は伊東玄朴の養子だった野中玄英が入門している。佐野常民、杉享二、箕作秋坪。そして一八五〇年(嘉永三)には、越前福井藩士橋本左内が登場する。左内から二年おくれて、大鳥圭介もはいってきた。かつて洪庵の師だった坪井信道の息子坪井信友も、江戸からはるばるとたよってきている。
安政という年は、さらにみのり多い年だ。まず長与専斎があらわれ、翌年には福沢諭吉が入門する。安政の六年間でこの入門帳に名をつらねた者は、二百三十六名、適塾の黄金時代である。
蘭学の勉強が一年くらいで目鼻のつく道理はない。最低三年はかかる。かりに一人の塾生が三年間いるとすると、この安政の六年間の二百三十六名という数字はたいへんなものである。いつも七十人から百人近い塾生がいたという計算になるのだ。適塾は過密現象を起こしていた。どの程度の過密かということは、北浜三丁目にのこる適塾の塾舎内へはいってみるとよくわかる。
表通りに面した二階の大きな部屋が、塾生の起居にあてられていたのだが、これが二十八畳敷である。もう一つ十畳の小部屋がくっついているが、これを入れたとしても三十八畳だから、一人の占有できる空間は、畳半畳分にしかならないのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
