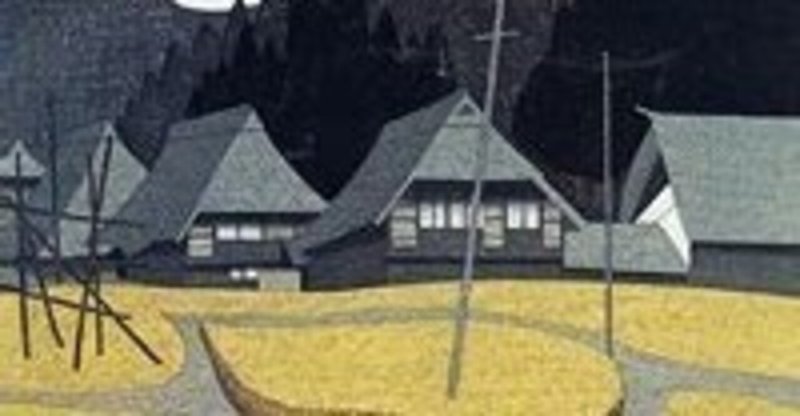
森の男は威張りすぎる 帆足孝治

山里子ども風土記 帆足孝治
私かいつまでも玖珠を懐かしがる理由のいちばん大きなものは、玖珠の景色やお祭りや行事や学校やそんなものではなさそうだ。敢えて言うなら、それは玖珠の文化というか風習というか、そこに住む人達が形成した社会の仕組みや人情に格別の親しみを覚えるからである。ことが無形なだけに、それが気づかないうちに少しづつ姿を消していっているのが気になる。
例えば玖珠の人たち、特に男の人たちは笑うことが大好きで、自分で面白いことを見出だして笑うばかりでなく、何ごとにつけても人に面白ろおかしく伝えて共に笑い合う。私が感じる東京の生活と一番ちがう点は、実にこの一点であると言っても差し支えないくらいである。田舎では、一緒に笑うことで一体感を確かめ合うという生活の知恵がそれだけ発達しているのだろうか。
私の家系では男は概して身体が小さい。おじいちゃんがそうだったし、父も叔父もみんな小柄である。叔父は初めて中学の先生になったころは、生徒が大体自分より大きいので、子供を怒るときにはいつも、この子らに本気で反撃されたらとても体力では適わないだろうなあ、という恐怖心があったそうだ。その叔父も年をとって引退してしまったが、そんなとき、子供時代から叔父を知っている年寄り達は、「ありゃありや、あん先生もとうとう定年へ? とうとう子供んときからあんまり大きゅうならんままじゃったのオー」とジョークを言って人を笑わせるのである。
![]()
田舎では昔から男の子はあまり無駄口を叩くものではないといって躾けられてきた。大勢人が集まっているときなど、つい興奮して口数が多くなったりすると、「男の癖に、まるで女の子のようによく喋る!」といって軽蔑されたりした。それなのに、普段はおとなしい大人の男連も、大勢が集まるととたんに良く喋るようになる。
何かの用で集まった男達が、代わりばんこに冗談を言って笑い合うときの表情は実に生き生きとしている。そこに婦人たちがいれば、女の人達をも笑わせるような冗談が実に上手に次々に飛び出す。その間の取り方、惚けた言い方、笑わせ方は実に巧妙である。だいたい次に誰かが言う冗談や駄洒落はことごとく予想できるのに、それが見事にタイミング良く、また上手に間をとって言われると、つい笑いこけてしまうのである。これがポンポン続くと抱腹絶倒せずにはいられない。
民話として伝えられている「吉四六さん話」や、昔から伝わる 「漫才」や「ドンタク」などとといった笑いの文化や伝統は、どうも九州地方に色濃いように思われる。東京のような都会の生活では、もう余り意味を成さなくなったこういった習慣や風習が、生活共同体の農村である田舎には、まだまだ役立っているのであろう。
田舎では、そして特に力仕事が多い農家では、家庭でも仕事のことでも何か大事なものごとをきめる場合は昔から男が主役を演じてきた。女は黙って何でも夫のいうとおりに慎ましくしていることがいいことだと褒められた。とくに森町は昔の城下町であるから、あるいは多少はそういった武家のしきたりや風習が伝わっていたのかもしれない。
だから、戦後の男女平等思想が急速に普及していった時代にあっても、この田舎では男が横暴とおもわれるほど威張っている家庭が多かった。私の家でも叔父がややそういった傾向があって、妻のマル子おばさんに対してはなかなかの腕白亭主だった。大分の町で育ったマル子おばちゃんにとっては、全く身寄りのないこんな田舎町に嫁いできたからには叔父、つまり彼女の亭主しか味方はいないわけだから、何かむずかしいことなどで相談を持ち掛けたりしても、その亭主がいざという時にすぐ怒鳴ったり、怒ったりするのでは頼るべき人はいなくなってしまう。叔父もだんだん年をとって子供が増えてきてからは随分柔らかくなっていったが、若いころはなかなか気難しい人だったから、マル子おばちゃんはずいぶん苦労したはずである。
![]()
昔は、とくに他人が見ているところなどでは亭主たるもの女房に優しくするなどというのは恥とみなされていたから、きっと叔父もおじいちゃんやおばあちゃんの前ではわざとマル子おばちゃんに冷たくしていたのだろうが、わたしは中学の先生までやっている叔父がなぜ奥さんにもう少し優しくしてあげられないのだろうかと、いつも悔しく思ったものである。
それに比べると祖父母は大変仲が良く、私が幼かった頃を振り返ってみても、おじいちゃんがおばあちゃんに対して威張ったり怒鳴ったりしたのは見たことがない。どうやら若い時からお互いに尊敬し合ってきたという感じだった。それでもおばあちゃんに言わせると、まだおじいちゃんが若かった頃に何かのことで怒ったことがあるらしく、おばあちゃんが笑いながらそのことを言うと、おじいちゃんは照れ笑いしながら[さア、そんなことがあったかなア?]ととぼけて見せた。
おじいちゃんは、若いころから意思の強いしっかり者で知られていたそうで、不正や狡いことが何よりもきらいだった。だから村で田圃の水権や山の境界線問題、親子や夫婦間の喧嘩、他の部落とのいざこざなど、もめごとや困った問題が起きるとおじいちゃんはすぐ相談を持ち掛けられたり、引っ張りだされたりした。きっとアメリカ・インディアンのシッティングーブルやレッドグラウトなどといった大酋長たちもきっとこうだったにちがいない。何ごとによらず部落の者が協力しあって生活しなければならなかった昔の農家の寄り集まりでは、部落の首長の役割をしなければならなかった本家の主人の責任は、そうでなければ勤まらなかったのであろう。
戦後、玖珠の田舎でもだんだん農家が減っていき、とくに農地改革が行われてから以降は、本家も小作もそんなことは関係なくなってしまったので、上ノ市でも昔のように農作業はもちろん冠婚葬祭などですべて部落の人達がなかよく共同作業でやるという風習は薄れてしまって、別に賢い首長のような存在は不要になってしまったが、私が子供だったころは、おじいちゃんは、きっと昔の首長たちがそうだったように部落の人達皆んなの尊敬を集めていたように思う。だから、とくにそのような立場にいなければならない人は、弱い立場の人に対して威張ったりすることなどは絶えてなかったはずである。
わたしはそんなおじいちゃんを見て育ったので、よその家庭で亭主が奥さんに対して乱暴な言葉を発したり怒鳴ったりするのを見ると、どうして強い男がこうも威張るのだろうかと不思議に思った。そんなに威張らなくても、もともと男なら力が強いのは当たり前なのだから、弱い人に対してはもっとやさしくしたらいいのになア、と残念に思ったものである。
私は強い者が平気で威張っていられるような仕組みの社会が嫌いである。強い者は引っ込んで控え目にしているくらいの気持ちがなければ、ただ存在するだけで他人に威圧感を与えるわけだから、それが威張って得をするような社会では、ライオンやサルなど野獣の世界となんら変わるところがない。私は大きくなって誰かと結婚することになっても、決して威張ったりすることがないように気をつけようといつも思っていた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
