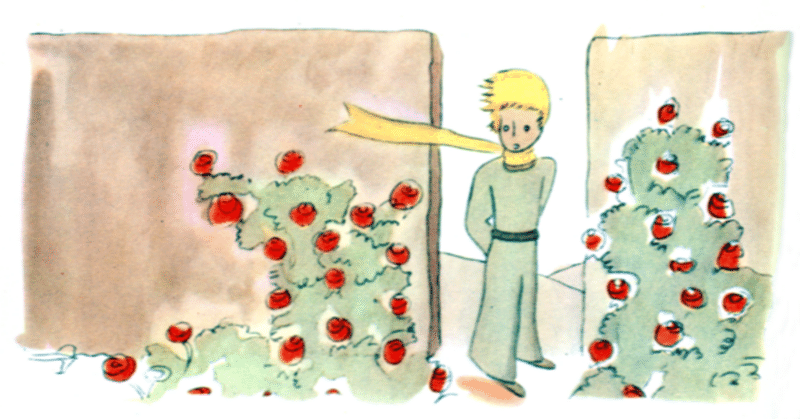
あのときの王子くん from11to20
あのときの王子くん
LE PETIT PRINCE
アントワーヌ・ド・サン=テグジュペリ Antoine de Saint-Exupery
大久保ゆう訳

レオン・ウェルトに
子どものみなさん、ゆるしてください。ぼくはこの本をひとりのおとなのひとにささげます。でもちゃんとしたわけがあるのです。そのおとなのひとは、ぼくのせかいでいちばんの友だちなんです。それにそのひとはなんでもわかるひとで、子どもの本もわかります。しかも、そのひとはいまフランスにいて、さむいなか、おなかをへらしてくるしんでいます。心のささえがいるのです。まだいいわけがほしいのなら、このひともまえは子どもだったので、ぼくはその子どもにこの本をささげることにします。おとなはだれでも、もとは子どもですよね。(みんな、そのことをわすれますけど。)じゃあ、ささげるひとをこう書きなおしましょう。
(かわいい少年だったころの)レオン・ウェルトに
11

ふたつめの星は、みえっぱりのすまいだった。
「ふふん! ファンのおでましか!」王子くんが見えるなり、みえっぱりはとおくから大ごえをあげた。
というのも、みえっぱりにかかれば、だれもかれもみんなファンなんだ。
「こんにちは。」と王子くんはいった。「へんなぼうしだね。」
「あいさつできる。」と、みえっぱりはいう。「はくしゅされたら、これであいさつする。あいにく、ここをとおりすぎるひとなんていないわけだが。」
「うん?」王子くんは、なんのことかわからなかった。
「りょう手で、ぱちぱちとやってみな。」と、みえっぱりはその子にすすめた。
王子くんは、りょう手でぱちぱちとやった。みえっぱりは、ぼうしをちょっともち上げて、そっとあいさつをした。
「王さまのところよりもたのしいな。」と王子くんは心のなかでおもった。だからもういちど、りょう手でぽちぱちとやった。みえっぱりも、ぼうしをちょっともち上げて、もういちどあいさつをした。
5ふんつづけてみたけど、おなじことばかりなので、王子くんはこのあそびにもあきてしまった。
「じゃあ、そのぼうしを下ろすには、どうしたらいいの?」と、その子はきいた。
でも、みえっぱりはきいてなかった。みえっぱりは、ほめことばにしか、ぜったい耳をかさない。
「おまえは、おれさまを心のそこから、たたえているか?」と、その男は王子くんにきいた。
「たたえるって、どういうこと?」
「たたえるっていうのは、このおれさまが、この星でいちばんかっこよくて、いちばんおしゃれで、いちばん金もちで、いちばんかしこいんだって、みとめることだ。」
「でも、星にはきみしかいないよ!」
「おねがいだ、とにかくおれさまをたたえてくれ!」
「たたえるよ。」といって、王子くんは、かたをちょっとあげた。「でも、きみ、そんなことのどこがだいじなの?」
そして王子くんは、そこをあとにした。
おとなのひとって、やっぱりそうとうおかしいよ、とだけ、その子は心のなかで思いつつ、たびはつづく。
12

つぎの星は、のんだくれのすまいだった。ほんのちょっとよっただけなのに、王子くんは、ずいぶん気もちがおちこんでしまった。
「ここでなにしてるの?」王子くんは、のんだくれにいった。その子が見ると、その男は、からのビンひとそろい、なかみのはいったビンひとそろいをまえにして、だんまりすわっていた。
「のんでんだ。」と、のんだくれは、しょんぼりとこたえた。
「なんで、のむの?」と王子くんはたずねた。
「わすれたいんだ。」と、のんだくれはこたえた。
「なにをわすれたいの?」と、王子くんは気のどくになってきて、さらにきいた。
「はずかしいのをわすれたい。」と、のんだくれはうつむきながら、うちあけた。
「なにがはずかしいの?」と、王子くんはたすけになりたくて、たずねてみた。
「のむのがはずかしい!」のんだくれは、そういったきり、とうとうだんまりをきめこんだ。
どうしていいかわからず、王子くんは、そこをあとにした。
おとなのひとって、やっぱりめちゃくちゃおかしい、とその子は心のなかで思いつつ、たびはつづく。
13

よっつめの星は、しごとにんげんのものだった。このひとは、とってもいそがしいので、王子くんが来たときも、かおを上げなかった。
「こんにちは。」と、その子はいった。「たばこの火、きえてるよ。」
「3+2=5。5+7=12。12+3=15。こんにちは。15+7=22。22+6=28。火をつけなおすひまなんてない。26+5=31。ふう。ごうけいが、5おく162まん2731。」
「なに、その5おくって。」
「ん? まだいたのか。5おく……もうわからん……やらなきゃいけないことがたくさんあるんだ! ちゃんとしてるんだ、わたしは。むだ口たたいてるひまはない! 2+5=7……」
「なんなの、その5おく100まんっていうのは。」また王子くんはいった。なにがあっても、いちどしつもんをはじめたら、ぜったいにやめない。
しごとにんげんは、かおを上げた。
「54年この星にすんでいるが、気がちったのは、3どだけだ。さいしょは、あれだ、22年まえのこと、コガネムシがどこからともなく、とびこんできたせいだ。ぶんぶんとうるさくしたから、たし算を4回まちがえた。2どめは、あれだ、11年まえ、リウマチのほっさがおきたせいだ。うんどうぶそくで、あるくひまもない。ちゃんとしてるんだ、わたしは。3どめは……まさにいまだ! さてと、5おく100……」
「……も、なにがあるの?」
しごとにんげんは、ほっといてはもらえないんだと、あきらめた。
「……も、あのちいさいやつがあるんだ。ときどき空に見えるだろ。」
「ハエ?」
「いいや、そのちいさいのは、ひかる。」
「ミツバチ?」
「いいや。そのちいさいのは、こがね色で、なまけものをうっとりさせる。だが、ちゃんとしてるからな、わたしは! うっとりしてるひまはない。」
「あっ! 星?」
「そうだ、星だ。」
「じゃあ、5おく100まんの星をどうするの?」
「5おく162まん2731。ちゃんとしてるんだ、わたしは。こまかいんだ。」
「それで、星をどうするの?」
「どうするかって?」
「うん。」
「なにも。じぶんのものにする。」
「星が、きみのもの?」
「そうだ。」
「でも、さっきあった王さまは……」
「王さまは、じぶんのものにしない、〈おさめる〉んだ。ぜんぜんちがう。」
「じゃあ、星がじぶんのものだと、なんのためになるの?」
「ああ、お金もちになれるね。」
「じゃあ、お金もちだと、なんのためになるの?」
「またべつの星が買える、あたらしいのが見つかったら。」
王子くんは心のなかでおもった。『このひと、ちょっとへりくつこねてる。さっきのよっぱらいといっしょだ。』
でもとりあえず、しつもんをつづけた。
「どうやったら、星がじぶんのものになるの?」
「そいつは、だれのものだ?」と、しごとにんげんは、ぶっきらぼうにへんじをした。
「わかんない。だれのものでもない。」
「じゃあ、わたしのものだ。さいしょにおもいついたんだから。」
「それでいいの?」
「もちろん。たとえば、きみが、だれのものでもないダイヤを見つけたら、それはきみのものになる。だれのものでもない島を見つけたら、それはきみのもの。さいしょになにかをおもいついたら、〈とっきょ〉がとれる。きみのものだ。だから、わたしは星をじぶんのものにする。なぜなら、わたしよりさきに、だれひとりも、そんなことをおもいつかなかったからだ。」
「うん、なるほど。」と王子くんはいった。「で、それをどうするの?」
「とりあつかう。かぞえて、かぞえなおす。」と、しごとにんげんはいった。「むずかしいぞ。だが、わたしは、ちゃんとしたにんげんなんだ!」
王子くんは、まだなっとくできなかった。
「ぼくは、スカーフいちまい、ぼくのものだったら、首のまわりにまきつけて、おでかけする。ぼくは、花が1りん、ぼくのものだったら、花をつんでもっていく。でも、きみ、星はつめないよね!」
「そうだ。だが、ぎんこうにあずけられる。」
「それってどういうこと?」
「じぶんの星のかずを、ちいさな紙きれにかきとめるってことだ。そうしたら、その紙を、ひきだしにしまって、カギをかける。」
「それだけ?」
「それでいいんだ!」
王子くんはおもった。『おもしろいし、それなりにかっこいい。でも、ぜんぜんちゃんとしてない!』
王子くんは、ちゃんとしたことについて、おとなのひとと、ちがったかんがえをもっていたんだ。
「ぼく。」と、その子はことばをつづける。「花が1りん、ぼくのもので、まいにち水をやります。火山がみっつ、ぼくのもので、まいしゅう、ススはらいをします。それに、火がきえてるのも、ススはらいします。まんがいちがあるから。火山のためにも、花のためにもなってます、ぼくのものにしてるってことが。でも、きみは星のためにはなってません……」
しごとにんげんは、口もとをひらいたけど、かえすことばが、みつからなかった。王子くんは、そこをあとにした。
おとなのひとって、やっぱりただのへんてこりんだ、とだけ、その子は心のなかでおもいつつ、たびはつづく。
14

いつつめの星は、すごくふしぎなところだった。ほかのどれよりも、ちいさかった。ほんのぎりぎり、あかりと、あかりつけの入るばしょがあるだけだった。王子くんは、どうやってもわからなかった。空のこんなばしょで、星に家もないし、人もいないのに、あかりとあかりつけがいて、なんのためになるんだろうか。それでも、その子は、心のなかでこうおもった。
『このひとは、ばかばかしいかもしれない。でも、王さま、みえっぱり、しごとにんげんやのんだくれなんかよりは、ばかばかしくない。そうだとしても、このひとのやってることには、いみがある。あかりをつけるってことは、たとえるなら、星とか花とかが、ひとつあたらしくうまれるってこと。だから、あかりをけすのは、星とか花をおやすみさせるってこと。とってもすてきなおつとめ。すてきだから、ほんとうに、だれかのためになる。』
その子は星にちかづくと、あかりつけにうやうやしくあいさつをした。
「こんにちは。どうして、いま、あかりをけしたの?」
「しなさいっていわれてるから。」と、あかりつけはこたえた。「こんにちは。」
「しなさいって、なにを?」
「このあかりをけせって。こんばんは。」
と、そのひとは、またつけた。
「えっ、どうして、いま、またつけたの?」
「しなさいっていわれてるから。」と、あかりつけはこたえた。
「よくわかんない。」と王子くんはいった。
「わかんなくていいよ。」と、あかりつけはいった。「しなさいは、しなさいだ。こんにちは。」
と、あかりをけした。
それから、おでこを赤いチェックのハンカチでふいた。
「それこそ、ひどいしごとだよ。むかしは、ものがわかってた。あさけして、夜つける。ひるのあまったじかんをやすんで、夜のあまったじかんは、ねる……」
「じゃあ、そのころとは、べつのことをしなさいって?」
「おなじことをしなさいって。」と、あかりつけはいった。「それがほんっと、ひどい話なんだ! この星は年々、まわるのがどんどん早くなるのに、おなじことをしなさいって!」
「つまり?」
「つまり、いまでは、1ぷんでひとまわりするから、ぼくにはやすむひまが、すこしもありゃしない。1ぷんのあいだに、つけたりけしたり!」
「へんなの! きみんちじゃ、1日が1ぷんだなんて!」
「なにがへんだよ。」と、あかりつけがいった。「もう、ぼくらは1か月もいっしょにしゃべってるんだ。」
「1か月?」
「そう。30ぷん、30日! こんばんは。」
と、またあかりをつけた。
王子くんは、そのひとのことをじっと見た。しなさいっていわれたことを、こんなにもまじめにやる、このあかりつけのことが、すきになった。その子は、夕ぐれを見たいとき、じぶんからイスをうごかしていたことを、おもいだした。その子は、この友だちをたすけたかった。
「ねえ……やすみたいときに、やすめるコツ、知ってるよ……」
「いつだってやすみたいよ。」と、あかりつけはいった。
ひとっていうのは、まじめにやってても、なまけたいものなんだ。
王子くんは、ことばをつづけた。
「きみの星、ちいさいから、大またなら3ぽでひとまわりできるよね。ずっと日なたにいられるように、ゆっくりあるくだけでいいんだよ。やすみたくなったら、きみはあるく……すきなぶんだけ、おひるがずっとつづく。」
「そんなの、たいしてかわらないよ。」と、あかりつけはいった。「ぼくがずっとねがってるのは、ねむることなんだ。」
「こまったね。」と王子くんがいった。
「こまったね。」と、あかりつけもいった。「こんにちは。」
と、あかりをけした。
王子くんは、ずっととおくへたびをつづけながら、こんなふうにおもった。『あのひと、ほかのみんなから、ばかにされるだろうな。王さま、みえっぱり、のんだくれ、しごとにんげんから。でも、ぼくからしてみれば、たったひとり、あのひとだけは、へんだとおもわなかった。それっていうのも、もしかすると、あのひとが、じぶんじゃないことのために、あくせくしてたからかも。』
その子は、ざんねんそうにためいきをついて、さらにかんがえる。
『たったひとり、あのひとだけ、ぼくは友だちになれるとおもった。でも、あのひとの星は、ほんとにちいさすぎて、ふたりも入らない……』
ただ、王子くんとしては、そうとはおもいたくなかったんだけど、じつは、この星のことも、ざんねんにおもっていたんだ。だって、なんといっても、24じかんに1440回も夕ぐれが見られるっていう、めぐまれた星なんだから!
15

むっつめの星は、なん10ばいもひろい星だった。ぶあつい本をいくつも書いている、おじいさんのすまいだった。
「おや、たんけん家じゃな。」王子くんが見えるなり、そのひとは大ごえをあげた。
王子くんは、つくえの上にこしかけて、ちょっといきをついた。もうそれだけたびをしたんだ!
「どこから来たね?」と、おじいさんはいった。
「なあに、そのぶあつい本?」と王子くんはいった。「ここでなにしてるの?」
「わしは、ちりのはかせじゃ。」と、おじいさんはいった。
「なあに、そのちりのはかせっていうのは?」
「ふむ、海、川、町、山、さばくのあるところをよくしっとる、もの知りのことじゃ。」
「けっこうおもしろそう。」と王子くんはいった。「やっと、ほんもののしごとにであえた!」それからその子は、はかせの星をぐるりと見た。こんなにもでんとした星は、見たことがなかった。
「とってもみごとですね、あなたの星は。大うなばらは、あるの?」
「まったくもってわからん。」と、はかせはいった。
「えっ!(王子くんは、がっかりした。)じゃあ、山は?」
「まったくもってわからん。」と、はかせはいった。
「じゃあ、町とか川とか、さばくとかは?」
「それも、まったくもってわからん。」と、はかせはいった。
「でも、ちりのはかせなんでしょ!」
「さよう。」と、はかせはいった。「だが、たんけん家ではない。それに、わしの星にはたんけん家がおらん。ちりのはかせはな、町、川、山、海、大うなばらやさばくをかぞえに行くことはない。はかせというのは、えらいひとだもんで、あるきまわったりはせん。じぶんのつくえを、はなれることはない。そのかわり、たんけん家を、むかえるんじゃ。はかせは、たんけん家にものをたずね、そのみやげ話をききとる。そやつらの話で、そそられるものがあったら、そこではかせは、そのたんけん家が、しょうじきものかどうかをしらべるんじゃ。」
「どうして?」
「というのもな、たんけん家がウソをつくと、ちりの本はめちゃくちゃになってしまう。のんだくれのたんけん家も、おなじだ。」
「どうして?」と王子くんはいった。
「というのもな、よっぱらいは、ものがだぶって見える。そうすると、はかせは、ひとつしかないのに、ふたつ山があるように、書きとめてしまうからの。」
「たんけん家に、ふむきなひと、ぼく知ってるよ。」と王子くんはいった。
「いるじゃろな。ところで、そのたんけん家が、しょうじきそうだったら、はかせは、なにが見つかったのか、たしかめることになる。」
「見に行くの?」
「いや。それだと、あまりにめんどうじゃ。だから、はかせは、たんけん家に、それをしんじさせるだけのものを出せ、という。たとえば、大きな山を見つけたっていうんであれば、大きな石ころでももってこにゃならん。」
はかせは、ふいにわくわくしだした。
「いやはや、きみはとおくから来たんだな! たんけん家だ! さあ、わしに、きみの星のことをしゃべってくれんか。」
そうやって、はかせはノートをひらいて、えんぴつをけずった。はかせというものは、たんけん家の話をまず、えんぴつで書きとめる。それから、たんけん家が、しんじられるだけのものを出してきたら、やっとインクで書きとめるんだ。
「それで?」と、はかせはたずねた。
「えっと、ぼくんち。」と王子くんはいった。「あんまりおもしろくないし、すごくちいさいんだ。みっつ火山があって、ふたつは火がついていて、ひとつはきえてる。でも、まんがいちがあるかもしれない。」
「まんがいちがあるかもしれんな。」と、はかせはいった。
「花もあるよ。」
「わしらは、花については書きとめん。」と、はかせはいった。
「どうしてなの! いちばんきれいだよ!」
「というのもな、花ははかないんじゃ。」
「なに、その〈はかない〉って?」
「ちりの本はな、」と、はかせはいう。「すべての本のなかで、いちばんちゃんとしておる。ぜったい古くなったりせんからの。山がうごいたりするなんぞ、めったにない。大うなばらがひあがるなんぞ、めったにない。わしらは、かわらないものを書くんじゃ。」
「でも、きえた火山が目をさますかも。」と王子くんはわりこんだ。「なあに、その〈はかない〉って?」
「火山がきえてようと、目ざめてようと、わしらにとっては、おなじこと。」と、はかせはいった。「わしらにだいじなのは、山そのものだけじゃ。うごかんからな。」
「でも、その〈はかない〉ってなに?」また王子くんはいった。なにがあっても、いちどしつもんをはじめたら、ぜったいにやめない。
「それは、〈すぐにきえるおそれがある〉ということじゃ。」
「ぼくの花は、すぐにきえるおそれがあるの?」
「むろんじゃ。」
『ぼくの花は、はかない。』と王子くんはおもった。『それに、まわりからじぶんをまもるのは、よっつのトゲだけ! それに、ぼくは、ぼくんちに、たったひとつおきざりにしてきたんだ!』
その子は、ふいに、やめておけばよかった、とおもった。でも、気をとりなおして、
「これから行くのに、おすすめの星はありませんか?」と、その子はたずねた。
「ちきゅうという星じゃ。」と、はかせはこたえた。「いいところだときいておる……」
そうして、王子くんは、そこをあとにした。じぶんの花のことを、おもいつつ。
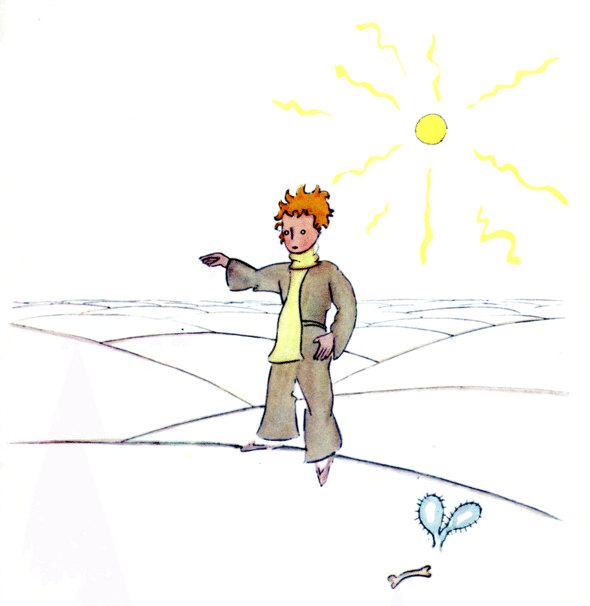
16
そんなわけで、ななつめの星は、ちきゅうだった。
このちきゅうというのは、どこにでもある星なんかじゃない! かぞえてみると、王さまが(もちろん黒いかおの王さまも入れて)111にん、ちりのはかせが7000にん、しごとにんげんが90まんにん、のんだくれが750まんにん、みえっぱりが3おく1100まんにんで、あわせてだいたい20おくのおとなのひとがいる。
ちきゅうの大きさをわかりやすくする、こんな話がある。電気(でんき)がつかわれるまでは、むっつの大りくひっくるめて、なんと46まん2511にんもの、おおぜいのあかりつけがいなきゃならなかった。
とおくからながめると、たいへん見ものだ。このおおぜいのうごきは、バレエのダンサーみたいに、きちっきちっとしていた。まずはニュージーランドとオーストラリアのあかりつけの出ばんが来る。そこでじぶんのランプをつけると、このひとたちはねむりにつく。するとつぎは中国とシベリアのばんが来て、このうごきにくわわって、おわると、うらにひっこむ。それからロシアとインドのあかりつけのばんになる。つぎはアフリカとヨーロッパ。それから南アメリカ、それから北アメリカ。しかも、このひとたちは、じぶんの出るじゅんを、ぜったいまちがえない。
でも、北きょくにひとつだけ、南きょくにもひとつだけ、あかりがあるんだけど、そこのふたりのあかりつけは、のんべんだらりとしたまいにちをおくっていた。だって、1年に2回はたらくだけでいいんだから。
17
うまくいおうとして、ちょっとウソをついてしまうってことがある。あかりつけのことも、ぜんぶありのままってわけじゃないんだ。そのせいで、なにも知らないひとに、ぼくらの星のことをへんにおしえてしまったかもしれない。ちきゅうのほんのちょっとしか、にんげんのものじゃない。ちきゅうにすんでる20おくのひとに、まっすぐ立ってもらって、集会みたいによりあつまってもらったら、わけもなく、たて30キロよこ30キロのひろばにおさまってしまう。太平洋でいちばんちっちゃい島にだって、入ってしまうかずだ。
でも、おとなのひとにこんなことをいっても、やっぱりしんじない。いろんなところが、じぶんたちのものだっておもいたいんだ。じぶんたちはバオバブくらいでっかいものなんだって、かんがえてる。だから、そのひとたちに、「かぞえてみてよ」って、いってごらん。すうじが大すきだから、きっとうれしがる。でも、みんなはそんなつまらないことで、じかんをつぶさないように。くだらない。みんな、ぼくをしんじて。
王子くんはちきゅうについたんだけど、そのとき、ひとのすがたがどこにもなくて、びっくりした。それでもう、星をまちがえたのかなって、あせってきた。すると、すなのなかで、月の色した輪っかが、もぞもぞうごいた。
「こんばんは。」と王子くんがとりあえずいってみると、
「こんばんは。」とヘビがいった。
「ぼく、どの星におっこちたの?」と王子くんがきくと、
「ちきゅうの、アフリカ。」とヘビがこたえた。
「えっ、まさか、ちきゅうにはひとがいないの?」
「ここは、さばく。さばくに、ひとはいない。ちきゅうは、ひろい。」とヘビはいった。
王子くんは石ころにすわって、目を空のほうへやった。
「星がきらきらしてるのは、みんなが、ふとしたときに、じぶんの星を見つけられるようにするためなのかな。ほら、ぼくの星! まうえにあるやつ……でも、ほんとにとおいなあ!」
「きれいだ。」とヘビはいう。「ここへ、なにしに?」
「花とうまくいってなくて。」と王子くんはいった。
「ふうん。」とヘビはいった。
それで、ふたりはだんまり。
「ひとはどこにいるの?」と、しばらくしてから王子くんがきいた。「さばくだと、ちょっとひとりぼっちだし。」
「ひとのなかでも、ひとりぼっちだ。」とヘビはいった。
王子くんは、ヘビをじっと見つめた。

「きみって、へんないきものだね。」と、しばらくしてから王子くんがいった。「ゆびみたいに、ほっそりしてる……」
「でもおれは、王さまのゆびより、つよい。」とヘビはいった。
王子くんはにっこりした。
「きみ、そんなにつよくないよ……手も足もなくて……たびだって、できないよ……」
「おれは船よりも、ずっととおくへ、きみをつれてゆける。」とヘビはいった。
ヘビは王子くんのくるぶしに、ぐるりとまきついた。金のうでわみたいに。
「おれがついたものは、もといた土にかえる。」と、ことばをつづける。「でも、きみはけがれていない。それに、きみは星から来た……」
王子くんは、なにもへんじをしなかった。
「きみを見てると、かわいそうになる。このかたい岩でできたちきゅうの上で、力もないきみ。おれなら、たすけになれる。じぶんの星がなつかしくなったら、いつでも。あと……」
「もう! わかったよ。」と王子くんはいった。「でも、なんでずっと、それとなくいうわけ?」
「おれそのものが、それのこたえだ。」とヘビはいった。
それで、ふたりはだんまり。
18

王子くんは、さばくをわたったけど、たった1りんの花に出くわしただけだった。花びらがみっつだけの花で、なんのとりえもない花……
「こんにちは。」と王子くんがいうと、
「こんにちは。」と花がいった。
「ひとはどこにいますか?」と、王子くんはていねいにたずねた。
花は、いつだか、ぎょうれつがとおるのを見たことがあった。
「ひと? いるとおもう。6にんか7にん。なん年かまえに見かけたから。でも、どこであえるか、ぜんぜんわかんない。風まかせだもん。あのひとたち、根っこがないの。それってずいぶんふべんね。」
「さようなら。」と王子くんがいうと、
「さようなら。」と花がいった。
19

王子くんは、たかい山にのぼった。それまでその子の知っていた山といえば、たけがひざまでしかない火山がみっつだけ。しかも、きえた火山はこしかけにつかっていたくらいだ。だから、その子はこんなふうにかんがえた。『こんなにたかい山からなら、ひと目で、この星ぜんたいと、ひとみんなを見とおせるはず……』でも、見えたのは、するどくとがった岩山ばかりだった。
「こんにちは。」と、その子がとりあえずいってみると、
「こんにちは……こんにちは……こんにちは……」と、やまびこがへんじをする。
「なんて名まえ?」と王子くんがいうと、
「なんて名まえ……なんて名まえ……なんて名まえ……」と、やまびこがへんじをする。
「友だちになってよ、ひとりぼっちなんだ。」と、その子がいうと、
「ひとりぼっち……ひとりぼっち……ひとりぼっち……」と、やまびこがへんじをする。
『もう、へんな星!』と、その子はそのときおもった。『ここ、かさかさしてるし、とげとげしてるし、ひりひりする。ひとって、おもいえがく力がないんじゃないの。だれかのいったことをくりかえす……ぼくんちにある花は、いっつもむこうからしゃべりかけてくるのに……』
20
さて、王子くんが、さばくを、岩山を、雪の上をこえて、ながながとあゆんでいくと、ようやく1本の道に行きついた。そして道をゆけば、すんなりひとのいるところへたどりつく。

「こんにちは。」と、その子はいった。
そこは、バラの花がさきそろう庭だった。
「こんにちは。」と、バラがいっせいにこたえた。
王子くんは、たくさんのバラをながめた。みんな、その子の花にそっくりだった。
「きみたち、なんて名まえ?」と、王子くんはぽかんとしながら、きいた。
「わたしたち、バラっていうの。」と、バラがいっせいにこたえた。
「えっ!」って、王子くんはいって……
そのあと、じぶんがみじめにおもえてきた。その子の花は、うちゅうにじぶんとおなじ花なんてないって、その子にしゃべっていた。それがどうだろう、このひとつの庭だけでも、にたようなものがぜんぶで、5000ある!
その子はおもった。『あの子、こんなのを見たら、すねちゃうだろうな……きっと、とんでもないほど、えへんえへんってやって、かれたふりして、バカにされないようにするだろうし、そうしたら、ぼくは、手あてをするふりをしなくちゃいけなくなる。だって、しなけりゃあの子、ぼくへのあてつけで、ほんとにじぶんをからしちゃうよ……』
それからこうもかんがえた。『ひとつしかない花があるから、じぶんはぜいたくなんだとおもってた。でも、ほんとにあったのは、ありきたりのバラ。それと、ひざたけの火山みっつで、そのうちひとつは、たぶん、ずっときえたまま。これじゃあ、りっぱでえらいあるじにはなれない……』そうして、草むらにつっぷして、なみだをながした。
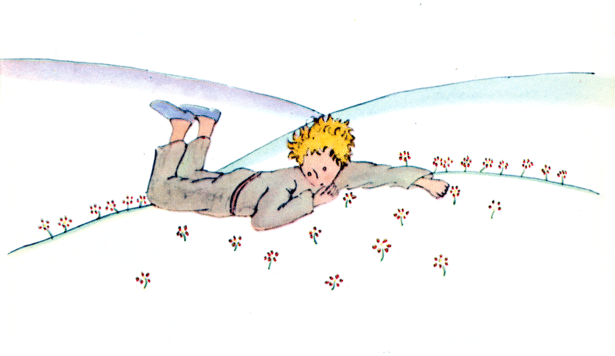

あのときの王子くんについて 大久保ゆう
4 翻訳について
前項でも書いたように、この翻訳は朗読のために作られています。そのため、文体は読むに適したものでなければなりません。また、フランス語では8歳ほどの子どもなら、ただ読むことは何の支障もないというふうにも聞いております。そうであるなら、翻訳の文体も、日本の同じ年齢の子どもが読んだり、聞いたりすることのできるような文体にする必要があります。
とりわけ、語彙には注意しなくてはなりません。小さい子どもでも、目でわかり聞いてわかる言葉。この翻訳では、できるだけ漢語や熟語を廃し、やまと言葉を使うようにしました。しかし、その言葉がやさしいからと言って、内容を簡単にしたということではありません。私は、むずかしい内容だからむずかしい言葉でなければならない、というふうには思いません。特に、この "Le Petit Prince" がそうであるように、たとえやさしい言葉で書かれていても、むずかしいことというのは存在しえます。ですから、私はたとえこの作品の内容が大人向けであっても、言葉の上ではやさしくある以上は、やさしい言葉で訳そうと思います。
平易な言葉を選びつつ、読みやすい文章になるよう心がけました。ときに意味より、リズムや音楽性を優先した部分もあります。そしてなおかつ、もうひとつ文体について配慮した点があります。それは、文章の長さです。
一般に、欧米の書物を日本語に翻訳すると、原典の1.5倍になるというふうに言われます。しかし、この意見に私は納得できません。そのような訳文は、ときに語りすぎの場合が多いからです。
なぜなら翻訳というのは、こなれた日本語を意識しすぎると、わかりやすい文、わかる文が必要であるというふうに思い始めます。それは悪いことではないのですが、原典には余計な説明を付して、文章を膨らませてしまうこともあります。たとえば、原文では一度しか使ってない動詞を反復してみたり、または何でもないところに凝った表現を使ってみたり。あるいは単純に、一言の台詞なのに、長々と語ったりする。もしこれが吹き替え翻訳であれば、すぐに尺が合わなくなるでしょう。
そこでこの翻訳では、原文の長さにできるだけ配慮して、訳文が同じくらいの長さになるよう作られています。それは原文へ可能な限り近づきたいという欲求であると同時に、自分が作品について語りすぎることを抑えるための枷でもあります。
翻訳者に限らず、人はわかっていることをすべて語ろうとします。"Le Petit Prince" であれば、その作品についてわかっていることを、その作品について読み込んだことを、翻訳にすべて出したくなってくるのです。しかし、そのなかには作品に書いてないことも含まれています。それをすべて書けば、また元の作品とは変わってくるでしょう。そういったことは、翻訳ではなく研究書や別の文章として書くべきものであり、翻訳に書き込むものではありません。原文に書いてあることを書き、書かれていないことは書かない、というのが原則であるように思います。
文体をうまく制御し、自分を律することが、翻訳には必要です。どのような条件で、どのような相手に向かって書くのか。そういった措定のようなものが、翻訳には欠かせません。まず書くべきところを抽象し、そうでないところを捨象する。つまり書くべきでないところを想定し、その場所を消去するのです。そしてそのあとに残ったちいさな場所に向かって、精神を統一して訳出していく。こういう厳密な措定を意識しなければ、たちまち翻訳のエクリチュールはぼろぼろに崩れていくことでしょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
