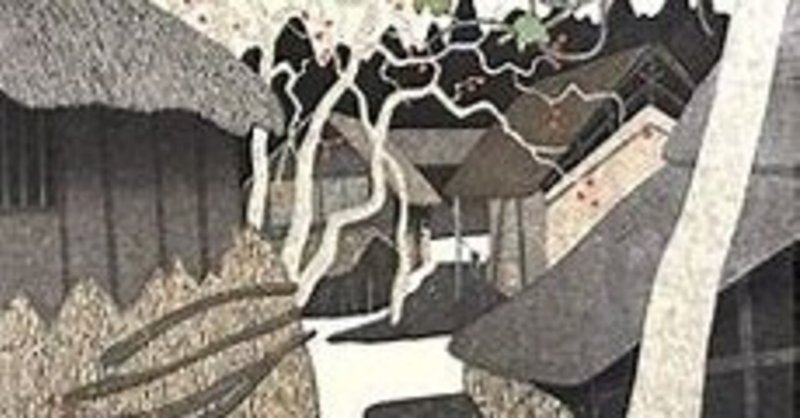
田舎の生徒の修学旅行 帆足孝治

山里子ども風土記──森と清流の遊びと伝説と文化の記録 帆足孝治
江戸時代から長い閧、玖珠地方の商工業の中心地として栄えてきた森の城下町は、昭和四年に久大線が閧通して、森町のずっと南の方に豊後森駅ができると、十文字と呼ばれる四辻には、今はもうなくなったが大丸百貨店というのが開店し、旧森からは役場や郵便局、税務署の地方事務所など多くの公共施設や商店などがどんどん駅周辺に移っていって、とくに戦後になってからは森町は急速に寂れてしまった。
豊後森駅には機関庫が設置され、ここでは機関士や機関助手の教育訓練も行われるようになった。それにつれてたくさんの国鉄職員が配備され、駅周辺には新たに鉄道関係の官舎ができて、俄かに鉄道村が形成されてきた。これに加えて、さらに宝泉寺温泉を通って肥後小国まで伸びる宮之原線(みやのはるせん)が通じ、森駅は久大線では日田と並んで駅弁まで売る主要駅となった。
こうなってくると、かつては森町が中心だった商工業は駅周辺の南部地区にすっかりお株を奪われてしまい、それまでの主要交通機関だった路線バスも次第に豊後森駅を中心として再編成されるようになっていった。駅前には、こんな田舎には不似合いなほの洗練された商店街が形成された。
新しい情報や文化はどうしても駅を中心に伝わってくるようになるため、取り残された森町はいつのころからか、誰かれとなく「旧森」と呼ばれるようになり、駅周辺の活況を呈する新興商店街地区とは対照的に、旧森は昔の城下町の面影をとどめる歴史的な町並みがひっそりとたたずむ、静かな町に変わってしまった。
いま試みにかつて栄えた本町や横町などを昼時に歩いてみると、人通りも少なく静まり返った旧森の城下町は、交通量が多く喧騒と殷賑(いんしん)を極める駅周辺や塚脇の町並みとは別世界である。私が小学校に通っていたころですら、すでに旧森の山奥から通ってくる子供たちは、駅周辺の商店街で育った子供たちには情報文化で遅れがちであった。
森谷の奥から通ってくる子供たちは駅まで出かける機会も少なかったから、白帯のついた進駐軍専用列車が走っているのを知らなかったし、ましてアメリカ軍の戦車や大砲などを見ることもなかった。もちろん汽車に乗る機会も滅多になかったから、機関車や客車の構造や仕組みなど知る道理もなく、シリンダーなどという言葉を知っている子もいなかったろう。
![]()
こんな山国では海を見たことのある子供も少なかったので、昭和二十五年の夏に初めて大分、別府に修学旅行に行った時のみんなの興奮は格別だった。森駅から二時間半の長旅の後、大分駅についたわが森小学校の六年生たちは、駅前広場に整列して引率の先生たちからいろいろ注意を受けたが、私たちは背中の後ろを亀川方面からやってくる路面電車が駅前で折り返して行くのが珍しく、嬉しくて堪らなかつた。
豊後森の田舎から出てきた私たちにとっては、大分市は大都会で、見るもの、聞くものすべてが驚きだった。向こうの方にはトキワ百貨店の高いビルディングが聳え、その向こう隣りには赤レンガの大分合同銀行が見える。田舎では見たこともない水色のモダンなフォードやシボレーが走っており、商店街からは「大分商工まつり」を盛り上げるスピーカーの騒音が聞こえて、大変な活気だった。
四輪の小さな市内電車や亀川行きの大型ボギー電車がやってきて止まると、運転手が降りてきてトロリーポールの紐を引っ張って架線から外す。その時スパッと大きな音がしてびっくりするほどの大きな青い火花が出る。時にはそれがボウっと人魂のように燃え上がることもある。私たちがみていると、運転手は紐を引っ張ったままそのトロリーポールをぐるっと後ろまで持って行き、再び架線に嵌めると車掌室の後ろの窓にその紐を結び付ける。
電車は今まで走ってきた先頭が今度は後ろになり、連転室は車掌室にはや変わりするのである。そうして車掌が紐を引っ張ってチンチンと威勢のいい音を鳴らすと、電車は勇ましい韻々たる轟音をのこして発車していく。「ツーツ、ツウーツ」というようなかすれた聞き慣れない電車の警笛が私たち田舎の山猿たちを驚ろかせて、大都会の雰囲気をいやが上にも高めるのである。
先生からいろいろの注意があってから、私たちはまず大分城址にあった県庁を見学に行き、次いで裁判所を見学した。そこでは実際の窃盗犯を裁判するところを見学したが、入廷してきた被告たちが皆んな一升瓶に被せるような編み笠をかぶっているのには驚いた。あまりはっきりとは聞こえなかったが、たしか裁判官が被告に向かって「おぬしが……」といったようで、ずいぶんひどい言葉を使うものだなアと嫌な気持ちがしたことを覚えている。
そのあと大分合同新聞社を見学、輪転機やB巻き取り紙、活字などについて説明を受け、いろいろ初めて見るものに驚いたが、そのあとに訪れた富士紡の工場では見学を断られるというハプニングもあった。先生たちは果たして事前に見学を申し入れてあったのかどうか、ずい分いい加減なアレンジだったように思う。私たち一行をつれてぞろぞろと工場の正門までやってきたのに、先行した先生は門番と二こと三こと話をしただけで私たちのところへ戻ってきて、「今日は見学でけんようです」といい、長ながとその理由を説明した。誰れも文句を言わない小学生だったからいいようなものの、田舎の小学校のこととはいえ、この修学旅行で先生たちがどんなアレンジをしてくれていたのか、私は少々心配になった。
![]()
私たちは大分の町を、くたくたになるまであちこち引き回されたあと、亀川行きの電車で別府へ向かった。電車が大分の町並みを抜けて「かんたん」から海岸に出ると、車窓の右側に明るい青々とした別府湾の素晴らしい景色が開けて、私たちは喚声をあげた。
電車は別大国道の左端に敷かれた専用路線を快適に走り、やがて左側の一段と高い所に日豊本線が寄り添ってくる。[ただ今OO匹]で有名な高崎山の下を大きく迂回して行くと向こう遥かに別府市街が光って見えだした。左の一段高いところを長い汽車が私たちの乗った電車を軽々と追い抜いて行く。
東別府を過ぎ、別府海岸通りに着いた私たちは、そこから歩いて竹瓦温泉に近い松阪屋という旅館に入った。今夜はここで宿泊だ。夕方、先生に連れられて希望者だけで竹瓦温泉に風呂に入りに行った。夕方の温泉は混雑しており、私たちは開放感が嬉しくて、熱い風呂にもぐったり犬掻きで泳いだりしたので、先に入っていた近所のおじさんらしい人から「風呂で泳いではいかん!」と怒られたりした。それでもやめないで泳ぎ続けた小野君などは、しまいにとうとうそのおじさんに頭を叩かれてしまった。
びっくりした私たちはそれで気まずい思いをしながら風呂から上ったが、まだ晩御飯には早かったので先生にくっついて少し商店街を散策した。今と違ってあの頃の大人たちは、悪さをしたり言うことを聞かない子供がいたりすると、よそのこどもでも平気で怒りつけたりした。
竹瓦温泉は別府随一の繁華街「流川通り」や別府銀座に近かったので人通りも多く、私たち田舎の小学生が珍しかったのだろうか、通りがかった進駐軍の若い兵隊がチューインガムを五~六枚、トランプのように広げてみせると、路上にパッと撒いた。皆んなはアッと言う間にこれを拾って、半分づつにちぎって分け合い口に入れたが、先生と一緒に歩いていた私にはついに回ってこなかった。
夜になると旅館の軒下には食べ物をねだる乞食や浮浪者がいっぱい集まってきた。皆んなが面白かって夏ミカンやお菓子を投げるので、ついには旅館側から「ものを投げ与えないように!」という注意を受けたほどである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
