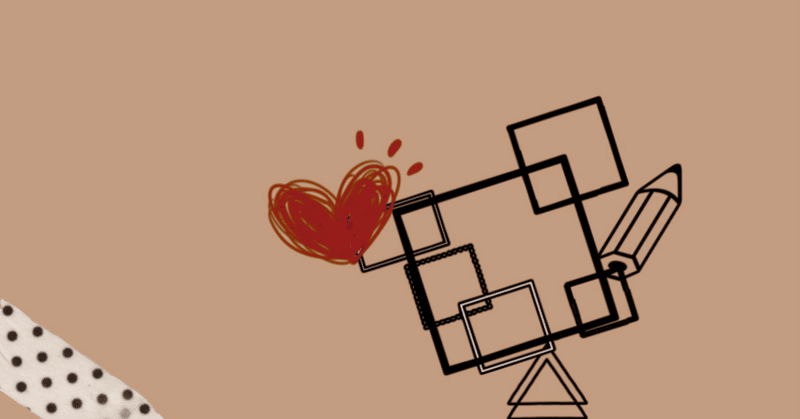
患者さんのことは、診断名と症状から思い出す。
先日、花見に誘われた。声をかけてくださったのは、かつてリハビリを担当した方のご家族だった。患者さんはご主人で、毎日奥さまが一緒に訓練室に来られていたのが印象に残っている。
既婚者男性が患者さんの場合、結構な割合でパートナーが毎日訓練室にご一緒される。そういえば父が入院したときも、毎日母が病院に通い、リハビリに付き合っていた。お父さん、ひとりになるのが嫌なんだって。本当はクタクタで、家でゆっくり休みたいんだけど、毎日夕方まで帰れないと母がよく愚痴っていた。
そんな事情で、担当した患者さんのなかにはご夫妻おふたり一緒に覚えているもおられる。たくさんのご夫婦とお会いしたが、今回お会いしたご夫婦をよく覚えているのは、素敵なご夫婦だったからだ。おふたりの会話が優しくて、お互いを労わりつつも甘え過ぎない感じだった。訓練中のお喋りがいつも面白くて、私が楽しい時間でもあった。結婚が決まった頃だったから、将来自分もこんな風になりたいと密かに思っていたので、余計覚えていたんだと思う。
退院された後も、毎年年賀状をくださる方がいるのはありがたいことだと感謝している。退職してからは仕事上の関係という縛りがなくなったので、私も一個人として毎年年賀状を出している。
最初に浮かぶのは、診断名と症状
かつて担当した患者さんを思い出すとき、顔と名前の次に浮かぶのは診断名だ。そして症状やハンディキャップの程度。リハビリの内容や退院後の生活に関わってくるので、職業や家族構成についてもすぐに思い出す。そしてお人柄については、そのあとになることが多い。今回お会いした方は入院中もよくお話を伺ったし、退院後にも連絡をいただくくらい、よく存じ上げている方々だ。そんな方でも思い出すときはまず診断名と症状、身体の状態だということに気づいた。
医療従事者と患者さんとの関係で考えると自然な流れではあるが、人と人とのつながりと考えると、不思議な関係かもしれない。
出会いは1枚の処方箋から
医師がリハビリが必要だと判断した患者さんに対して、処方箋が作成される。リハビリ科がそれを受け取ったとき、担当のセラピスト(理学療法士・作業療法士)が決められる。
担当となったセラピストは、渡された1枚の紙(=処方箋、指示書)にある名前・性別・年齢と、その下に記載されている診断名や現時点までの経過等に目を通す。
これが担当患者さんとの出会いである。
入院中は、退院後の生活に向けてひたすら観察
リハビリが開始されると、最初に身体の現状について調べる。目視で確認したり、実際に身体に触れて検査したり、現時点で困っていることや退院後にできるようになっていたいこと、できないと困ること等を口頭で聞きとったりしていく。
現在できなくなったことが、リハビリを行ったらできるようになるか。
できない場合は、代替手段を用いたらできるようになるか。
それは道具で解決できるか、それとも家のリフォームや職場の環境調整が必要になってくるか。
もしくはご家族や周りの方の協力や見守りが必要となるか。
退院後に不安を感じることのないように、
ご自宅で困ることがないように
入院前と同じ生活形態にはならないかもしれないけれど、
満足度や充実度は入院前により近づけるように、ゴール設定をする。
ここでのゴールは身体の動きや耐久力等について、
主に「何ができるか、できないか」を明確にしていくもの。
そして医師、看護師、言語聴覚士といった他職種の見解も併せて、
患者さんの生活全般のゴール設定も行う。
ここでのゴールは社会的な立ち位置も考慮したもので、
主に「これからどんな人生を歩んでいくか」につながっていくもの。
おひとりおひとりの人生それぞれが
事故やご病気をきっかけに不本意なものに変わってしまわないように、
毎日の訓練を通して、身体の変化を観察し、到達度を測り続ける。
観察を続けるうちに生じること
患者さんのゴールに向けて、
ハンディキャップに対して真摯に向き合おうとすればするほど
症例として見てしまうことがある。
症例:疾患や症状に注視してる状態(case の意に近い)
患者:疾患や症状がある人と捉えている状態(patient の意に近い)
※便宜上、このような意味合いで使い分けることにします。
担当している複数の患者さんを、
息つく暇もなく診ていくなかで、一生懸命になればなるほど
患者さんのからだの現状が変化していっているかのみに注視し、
機能的な変化に囚われていきがちになる。
患者さんを順番に診なきゃ。
変化を出さなきゃ。
時間までに終わらさなきゃ。
こころの余裕がなくなっていって
時間との闘いになってしまっているときに
こころの中で思っていることは
「せめて変化だけは出したい。」
もちろん、医療従事者として
症状を診ることは当然のことだが、
人間にはこころもある。
患者さんの思いに本当に耳を傾けられていたか。
いやいや当然でしょ。
会話で、問診で、
ちゃんとコミュニケーションとってますよ。
患者さんとの関係は大切にしていますよ。
と思っていたけれど。
こんな風に感じるようになったのは、退職したあとに
母の診察の付き添いに行ったときだった。
診察時にわかりやすく説明してくださったあと、
私は何か言おうとしたのだが(何を言いたかったかは覚えていないが)、
なんとなくやめてしまったことがあった。
説明された内容に不満があったわけじゃない。
内容は十分によくわかったし、丁寧に対応してくださった。
だけど、説明が終わった時点で「終わり」を感じてしまった。
もう次の患者さんの準備に入りだした場の雰囲気に、
母の診察は終了という区切りが、事実上なされていたのだった。
あのとき、自分も同じことをしていたかもしれないと感じたのだ。
患者さんにお伝えしたいことは丁寧に、できるかぎりわかりやすく。
笑顔で、患者さんの方を向いて。
でもそれって、自分がお伝えしたいこと(だけ)であって、
患者さん側が知りたいことや聞きたいことにも配慮していたのだろうか。
「症例」と「患者」とのバランス感覚
機能の変化に特化すれば問題なく、
業務としてはスムーズに遂行されたのかもしれない。
しかし、患者さんのこころは置き去りにしていっているかもしれない。
機能面は問題なくても、患者さんの不安が解消されていなかったなら。
不満が生じたままの退院になったとしたら。
このとき、患者さんが求めているのは
専門的な説明でもなく、高度なリハビリの技術でもなく、
人間味ある、たわいもないひとことだけなのかもしれない。
症状に対しては、症例として俯瞰して診る。
患者としてはいち人間としての尊厳を忘れずに。
どちらかに偏ってしまうとお互いの思いがすれ違ってしまう、
このバランス感覚を忘れないようにしたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
