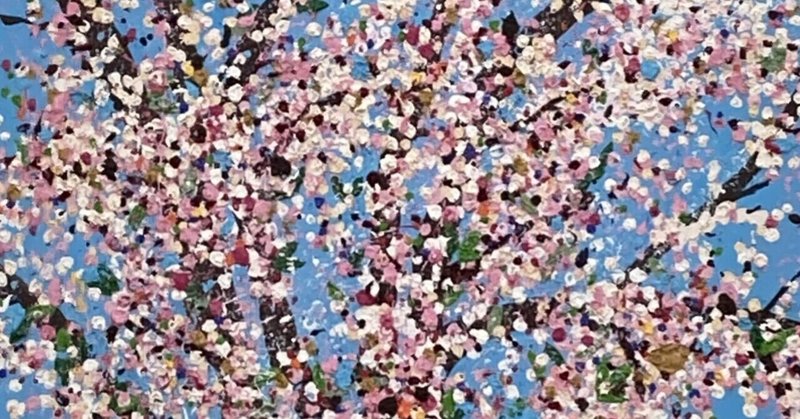
授業時数1
新学期が始まりましたね。
昨年度末は、落ち着いたかに見えたコロナの感染者数が増え、
学校現場は様々な対応に追われました。
延期を重ねてきた行事の実施、規模や方法、またオンライン授業の実施など
試行錯誤することが多かったです。
忙しくこなす事で精一杯でしたので、このことはまた改めて振り返れたらいいなと思っています😊
さて、新年度の児童数イコール学級数の目処が立つと、専科は次年度の担当学級数、授業時数が決まります。
学級数によって自動的に決まることが多いですが、週22時間前後のラインは管理職との攻防があるのではないでしょうか。
専科の週のもち時数は18〜22時間が平均のようですが、18時間以下だと評価のない図書や少し重めの校務などを担当する場合が多いようです。
私も24時間になることが決まりそうだったので、交渉をしましたが負けました😢
(と言っても異動だったので、残す音楽専科と後任の方のため。なんでムキになってるのとも言われましたが…)
こうした話をするたびに、必ず担任ともち時数や大変さを比較し、
こんな理由でできるでしょ、こんな理由でできません、の水掛け論になります。
そして、現実的な職員数、学級数は決まっている中で、徐々にそうするしかないんだな、無理だと拒否することは駄々を捏ねているだけなんだな、しかし授業を大切にしたいという専科のプライドはどうしてくれよう…という虚無感に襲われるの方も多いのではないでしょうか。
そして頑張ってこなして、内容はともあれ、消化できちゃったという実績を残す悪循環…
(または破綻して心身共に犠牲になる…)
ただ、冷静になって考えると、
授業に限らず誰がどの仕事を担当するのかを決める際に、基準は大変かどうかではないのでは?と思います。
そして担任も、専科も、管理職も、学校教職員1人残らず
みんな大変です!!
学校現場で大変じゃない人はいません!!
平等ではないかも知れませんが、それぞれの能力、キャパ、ライフステージに応じて、それ相応以上の負担を抱えています。
なので、どちらが大変、だからそっちがやってよ!と首を締め合うのではなく、
みんな大変なこの状況を変えなきゃね、と
そっちで力を合わせていきたいです(切実😢)!
学校現場の職員が増え、事務仕事の負担が減ったり、副担任のように常時ピンチヒッターがいてくれたりしたら良いのに!!
教科担任制になるならば、職員増にして欲しいし、しばらくならない低学年には、低中を担当しがちな新人教員補佐をつけて欲しい!
(立場に関わらず、新卒者、新規採用者には指導者以外に、1人ずつメンター的なサポーターが欲しいです)
そもそも意味のない調査や、学校が関わらなくても良いイベントや諸々がなくなりますように!!
ちょっとスケール大きめな心の叫びになってしまったので、もう少し学校規模、現実的な話に戻して、次回続けます☺️
