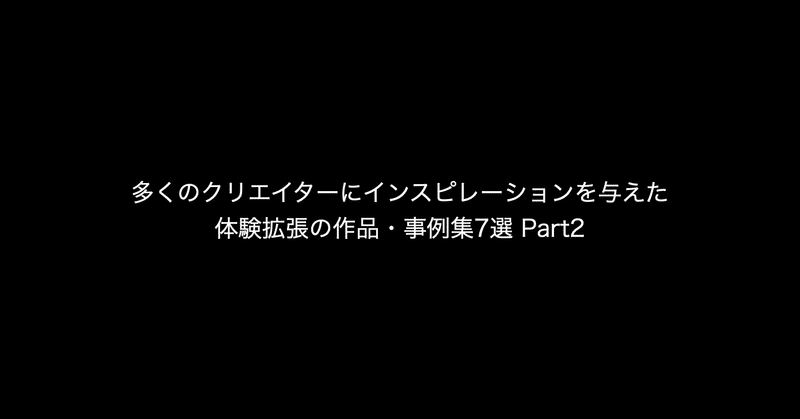
多くのクリエイターにインスピレーションを与えた体験拡張の作品・事例集7選 Part2
10月22日に弊社MESON主催のオンラインイベント「MESON WAVE LIVE 03 体験拡張プロデューサー対談 」を開催します!
今回のテーマは『WOWと考える空間と映像が交じりあう時代の体験デザイン』。
WOWのプロデューサーの松井氏と佐伯氏をお呼びし、MESONのCEO梶谷と共に空間や映像の特性を活かした体験のつくりかたについて議論を深めていきます!!
前回は、10年ほど前の作品から今に至るまで体験拡張を具体的にイメージできる作品をご紹介いたしましたが、今回も前回同様に体験拡張を具体的にイメージできる作品を7作品ご紹介いたします!
それぞれどんな作品か私の主観で感想をかいていきたいと思います!
(※ちなみに前回ご紹介した作品はこちらになります!)
1. Light Field Theater(2018)
"《Light Field Theater》は、現実の光と,コンピュテーショナル・ライトと呼ばれる,コンピュータで複雑な計算を行なうことによって実現可能となる光の表現のひとつである、ライトフィールド(Light Field)技術によって再構成された光を用いて制作された,光のパフォーマンス作品です。肉眼で見ることのできる立体映像技術を用いて、特別なデヴァイスを用いずに、実像と虚像があいまいになった、もうひとつの現実が体験されます。"
引用:https://www.ntticc.or.jp/ja/archive/works/light-field-theater/
ICCは、新宿の初台のオペラシティー内にある国内有数のメディアアートに特化したギャラリーです。
Rhizomatiksさんが展示された時は来場者数がとても多かったそうです。
実像と虚像の境目の中で、浮遊するこの美しい作品を眺めながら「実体」とは何かを考えさせられました。
2. discrete figures
"数学的・集合知的な方法を通して身体表現をつくり出すダンスパフォーマンス。AIと機械学習によって身体像や動きを捉え直し、その数値データと分析結果をコレオグラフィに反映させた。2018年よりモントリオール(カナダ)、サンフランシスコ(アメリカ)、東京、バルセロナ(スペイン)など、世界各都市を巡回している。"
引用:https://j-mediaarts.jp/award/single/discrete-figures/
スポットライトに照らされ、舞台が立ち現れる。
その瞬間、目の前に異空間が広がりました。
実存するダンサーとテクノロジーを用いた演出が一体化した空間は、独特な違和感を放ちながら、別世界の入り口に立っているようでした。
赤外カメラと再帰性反射素子を用いてリアルタイムにモーションを動きを取得し、そのデータを元に演出を作り出していたようでしたが、その技術的な難易度とそれを感じさせない洗練された演出の完成度は圧巻でした。
3. Drawing Operations Unit: Generation 1
"作者と、作者が開発したロボットアームが協働して同時にドローイングを行なう作品。ロボットアームは、天井に設置されたカメラとコンピュータの映像から得られる情報をもとに、人の動きを模倣するように設定されている。その結果、人とロボットが同時に相互の動きを解釈しあうかのようなパフォーマンスが生みだされる。"
引用:http://archive.j-mediaarts.jp/festival/2015/entertainment/works/19e_drawing_operations_unit_generation_1/
この作品は、ロボットが人間の振る舞いに同期する訓練によって、ロボットの自動化、自律性、人間とロボットの共同制作についてのアイディアを探求している作品です。
人がロボットと一緒に考えながら絵を描く。しかし、ロボットと一緒に制作した作画の完成図を、自分の意思では予測できない....
そんな体験に脳の混乱を感じる作品です。
4. Playback
"パフォーマンス《Pleasure Life》(1988 年初演)をベースに、展覧会「Against Nature」(1989)のために制作されたインスタレーション《Playback》に基づいて制作された、リモデル版作品。16台のターンテーブル・ユニットの上で、本物のレコード盤が、当時の音源(80 年代初期ダムタイプの山中透・古橋悌二による音楽、英語教材の滑稽で風変わりな声、NASA の惑星探査機ボイジャーに搭載されていたレコードに記録された55 言語の挨拶)に加え、新たにフィールド・レコーディングした音素材をミックス再生するサウンドスケープ・インスタレーション。"
参考:https://www.mot-art-museum.jp/exhibitions/dumb-type-actions-reflections/
空間内に、整列されたレコードが16台並べられている。
ほのかに、レコードが光り、様々な場所から異なる声、音楽が流れだす。
それはレコード同士がおしゃべりしているようで、そこに生命感と存在感を感じる。
昔と今の狭間にタイムスリップしたような懐かしい空間をレコードの佇まいが作り出していました。
そんな作品を眺めながら、ダムタイプの歴史の重みを感じました。
5. furumai
"超撥水加工を施された12枚の紙皿。その上で転がる水滴。ありふれた存在であるはずの水は、紙皿の上でまるで命を得たかのように、思いもよらない動きを見せます。時には尾を振りながら歩く不思議な動物のように、また時には分裂を繰り返すアメーバのように、また時にはせわしなく競技場を転がるサッカーボールのように。「ふるまい」はその語のなかに、振(behavior) と舞(dance)ということばを含んでいます。これは、社会生活を営む上での行動(振)と、遊び心のあるうごき(舞)といった両面を表しています。"
引用:https://ja.takram.com/projects/furumai/
10年以上前に見た作品で、心に残ったこの作品。
ころころ転がる水が様々な形に変化していきます。
その様が、新種の生きものを見ているかのようで、愛おしく、かわいかったです。
人の模型などの様々な形や子供の写真と重なった水滴は新たな意味をまといながら、いつまでもじっと眺めていたくなる作品でした。
6. Amazon Fashion Week TOKYO 2017 S/S
"ファッションショーのキービジュアルである、White Cube(=白い箱)をモチーフに、ステージ上の壁面に125個の箱を幾何学に配置。一面に並べられた箱へのプロジェクションマッピングから始まり、中盤からはさらにデバイスとプログラミングによって、箱のふたを実際にアニメーションさせた。「プロジェクションマッピング」「箱のアニメーション」「照明」を組み合わせることにより、生まれる錯視を利用。驚きのある空間と体験を作り出し、オープニングパーティーを盛り上げた。"
引用:https://www.w0w.co.jp/works/afwt_2017ss
リアルの箱の蓋の開閉、プロジェクションマッピング、照明がすべて同期されていることの技術的難易度に加えて、技術を感じさせない演出の美しさ...
本物の箱にプロジェクションマッピングをすることによって2Dの映像では感じることのできない奥行きを感じました。
さらにその箱が動くことで、実存感が強くなり、鑑賞体験が拡張されていると感じました。
7. WOW AR|AR + Motion Graphics(2020)
"AR(拡張現実)とモーショングラフィックスを使った作品をおさめたアプリ。あらゆる環境をアートインスタレーション化することを目標としている。第一弾リリースでは、以下モーショングラフィックス3作品を公開。"
引用:https://www.w0w.co.jp/art/wowar
WOW ARを通して見ると日常生活の中でいつも見ている街並みが、急にアート作品に変化しました。
場所によってシュールになったり、エモくなったり同じMotionでも作品の様々な表情を試しながら味わえるところがとても良かったです。
最後に
先程ご紹介したAmazon Fashion Week TOKYO 2017 S/Sと WOW AR|AR + Motion Graphicsは、「MESON WAVE LIVE 03 体験拡張プロデューサー対談 」で対談されるWOWのプロデューサーの松井氏と佐伯氏が手掛けた作品です!!
このイベントでは、これまで幅広い映像表現などのデザインワークをおこなってきたWOWのメンバーとARなどを用いて人類の体験と可能性を拡張を目指すMESONのメンバーが、空間と映像が交じり合うの時代の体験デザインについて考えていきます。
ご興味ある方はぜひ以下のイベントページから参加申し込みお願いします!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
