沈溺に、失速
「私、やめるから」
彼女が零した言葉は、真っ直ぐに伸びた背筋に見合うように落ち着きを纏っている。その姿に、悲しさや悔しさみたいな感情を一緒に詰め込んで煮詰めたような、なんとも言えない言葉が込み上げて、今にも泣いてしまいそうに震えた唇を隠すように食んだ。
夢と見切りをつけたから、掲げた目標へと走り切ったからだとか、そんな言葉の方が良いかのように先へと進む上でのことだと解からなければ、泣き叫ぶように声を上げたのにそれをさせない強さを眸に宿している。
だから、泣き出して、しまいたかった。泣き出せたら良かったのに。
此方を一途に射抜いてくる双眼は以前とも変わらない眩さに満ちた強い輝きを放っているからぐっと喉まで出かかる言葉を呑むしかなかった。
強い一途さに濡れた意志を覆うだけの言葉を私は未だ見つけられないままでいる。
*
ラジオを知らせるオープニング曲の出だしと遅れて入る番組名。そして、流れるようにお決まりの開始を知らせる挨拶を口にしたパーソナリティーの掛け声に、「嗚呼、やっと始まった」感が抜けていく。肩や腕に力むように入っていた力は、何時になったら抜けるのだという気が気でない緊張感から解放されたように重力へと沿うように落ちていった。
画面に映るメーター印を確認しながら、ヘッドフォンを遠退ける。首に微かな音を立てて、落ちるヘッドフォンよりも、オープニング曲が恰も鳴っていたけど消えていたと自然になっていたかの方が気になる。
急にぷっつりと消えないような線を引くことが大事であると、この仕事に就いたからこそ判る。見えないことが見えるなんてゴロゴロと他の仕事でもあるけれど、手を伸ばさずにはいられなかったのだ。あの時は。
「マイクテストどうだった」
「ゲストの?」
「そう」
「ちゃんと、大丈夫」
マイクが拾わなくてもよく通る声はブース越しのここからでも聞こえてくるパーソナリティーが紡ぐ言葉はいつも通りに滑り出し好調で、淡々とテンポ感を掴んでいる。それどころか、今週も楽しげに、何も問題なく声を張っている。
それの餌食になるであろう、今回のゲストに肩を竦めた。
「心配?」
「何が」
「だって、可哀想ってよりも心配って感じで見てるからさ」
「まるで母親みたいだね」と、続け様に口にした高橋に頭を抱えたくなった。どんな言葉を並べてもたぶん、恥ずかしさや照れを隠すように弁解していると思われるだけで、微笑ましいように流されるだけだ。けれど、このままでは分が悪い。
ぐるり、と脳の引き出しを引きまくるがいいような言葉や行動が見つからずに、思考の波へと溺れてしまう。
「ふはっ、必死すぎ」
眩しいね、とでもいうように笑みを浮かべた高橋の方が随分眩しく映る。笑う度にさらりと揺れる一度も染めたこともないような黒髪と、その髪から覗くピアスのアンバランスさにきゅっと口を結んだ。
細身で華奢な身体つきの割に高い身長と、顎上で切りそろえられた髪から、よく彼女は性を間違われる。けれど、彼女は苦ではないかのように「よく言われます」とだけ返す。莫迦にするわけでも、何かを吐き出すわけもなく只笑みを浮かべて返していく高橋の人格の良さに羨望を抱いてしまうくらい、その時は格好良さの方が勝ってしまうケド。
中性的な顔立ちにより一層間違えてしまうのかもしれない。けれど、よくよく見れば、高橋は女であることがわかるのに。
「奇麗で格好良いなんて最強だ」
「え?」
「勿体ないって、思っただけ。高橋が綺麗な女の子だってこと解らないなんて、ほんの少し勿体ないだろ」
「……よく、そんな恥ずかしい言葉は言えるのに変なところでは焦るってどうかしてる。そしてに、奇麗で格好良いのは彼の方だと思うけど?」
頬杖を付きながら、高橋が顎をしゃくったように視線を向けた先を追うように視線を向けた。きらきらとした色素の薄い髪とゆるりと緩められた目元。繊細で洗練された美を詰め込んだような顔立ちからは儚さが漂う。まさに百合の花のような人だと思った。
『なんと、今週はモデルのSUMIさんにお越しいただきました!』
モデルのSUMI。それは、世間一般的には知っているであろうこと。知っているであろう名前で、ある一定層か、将又それ以上に響くほど威力を発揮するようにも思える。けれど、私にとっては特に何も思わない相手であることには変わりなくて、昔の面影よりもずっと危うさを纏って、その場に立っているとしか思わなかった。
知り合いという間柄でも、気が許せるという関係性でもない。只の友達の友達で二度目ましての人か、友達の友達である初めてに近いけど顔見知りの人という程度の薄い関係性で一方的には知っているけれど知らない人だ。
『どうも皆さん、SUMIです。よろしくお願いします』
にこやかな笑みと、爽やかな挨拶。マイクテストと変わりのない音量と、変わらないゲージ数。抑揚一つもない淡白さを覚える声質なのに、それをカバーするパーソナリティーの声かけに「流石だな」と、感嘆してしまった。
それと同時に、抱えている陰が少し、ほんの少しだけ似ているとも思った。
『間近で初めて見たけど、こんなにも美だって感じることあるんだね?』
『そうですかね?』
『めっちゃ、作りものみたいだなって思ったわ~』
『ははっ、有難うございます』
長年ラジオ番組でパーソナリティーを務めているだけあって、培った力や間の開け方などが絶妙にうまい。どちらともが空気を掴んだように、するりと雑談へと持っていき、和気藹々としたように展開と発展で盛り上がりを見せている。
初めましての感覚など、最初からないように馴染んでいるからこそ、SUMIという人間は侮れなくて、絶妙なほどに掴めない、読ませないところが気持ち悪さを覚えてしまうのに、それをさせない愛想の良さで出来ている笑みにある種、圧を感じた。
『さて、今週のテーマは夢。リスナーの皆さんからいただいたお便りやメール等をもとに、ゲストであるSUMIさんに色々聞いていきたいと思います!』
『では、SUMIさん準備はよろしいですか~?』
ニヨニヨ、と隠しきれていない笑みが此方からでもわかる。想像がついてしまうくらい好奇心や愉快さが滲んだような物言いだなと少し肩を落とした。
こうなるとわかっていたけど、止めなかった。止められなかったわけじゃないのに、巻き込まれることから逃げ出して、背けたということに罪悪感を勝手に抱いて、勝手に負い目を感じている。何処までも、勝手だなと自分に呆れてしまうくらいには。
「(――――――……でも、勿体ないって思ったの。)」
全開に開けきれない窓から吹き込む風の生温かさにどっと体力が削られていくような感覚。熱風や無風よりも、なんとも言えないような生温さは返ってぶるりと身体を震わせてしまうくらい気持ち悪い体感だ。
背中に伝う汗と対抗するように照り付けるような強い日差しが、今は梅雨明けの昼であることを厭って程知らせてくれる。そして、それを煽るように一斉に鳴き喚く煩わしさが一押しとなって、私へと襲い掛かってきて、溶けるように机へとなだれ込んだ。
「……あっついんだけど」
「今日も一段と元気に溶けてる」
「これが、元気に見える?」
べたりと頬を机に当て、突っ伏したような体勢のまま、窓側の隣に腰を下ろしている生徒へと視線を向けた。癖や傷みなど知らないかのような、艶がかる黒髪はさらりと腰まで伸びている。ぱちりとした二重の眸を縁取る長い睫毛が頬へと陰を作るくらい透き通った乳白色の肌は、焼けたことを知らないようで、羨ましい。
崩すことなく真っ直ぐに伸びた姿勢と流れるような手つきの仕草、頭の上から足の先まで手入れが行き届いているのは、それら全てこの生徒の努力の賜物の証でしかないのだ。三日坊主の私と違い、積み重ねを、反復を毎日繰り返している。それが、私との圧倒的に違うワケ。
「今日は、大変ご機嫌がよろしいですこと」
きっちりと崩さずに制服に身を包む姿は、まるで学校のお手本か、模範的になりうる生徒。学力や運動においてもトップ成績を収める優等生というのがこの生徒……――――――保栖夕貴だった。
汗一つも掻かずに涼しげな顔をしていられる保栖の精神力が私は怖いわ。と呟いてしまいたくなるくらいには少しだけ、ほんの少しだけ腹立たしいとも思っていたりもする。言わないだけで。
「そう見えるなら、良かった」
「……何、それ」
「いい感じに出来上がったの」
細い指先で捉えているシャーペンをきゅっと持ち直してから、此方に視線を向ける。シャーペンを持つ簡単に折れてしまいそうな細い指や袖から除く真っ白な肌に微かについた色彩と髪から香る独特な匂いは、似合っていて似合っていないと途方もなく、思ってしまう。でも、それ以上に此方を見つめた保栖に私は目が離せなかった。
それは、まるでふわりと華が綻ぶかのような綺麗な笑みを浮かべたから、余りにも眩しいと、ぎょっとして目を見開いてしまった。
「ね、最高に良いものに仕上げたら見てくれる?」
ふわりと笑い、緩ませた眸に反射して映る私の顔は迷子になった子どもみたいだった。泣きそうな私はいつだって、この風のような生温い空気に浸って勝手に悲しんで勝手に後悔して、勝手に置いてきぼりを喰らったと思ってしまうようなヤツだ。
自分でも判っている。解っているけど、そう思ってしまうんだ。どうしようもなく。それは、さぞ滑稽なのかもしれない。けれど、保栖にはどう映っているのだろうかと問いたいくらいには、嫌いじゃなかった。
それだけは、本当だった。
『この番組は、―――――……の提供で、お送りしています』
スピーカー越しに聞こえた一区切りの締め台詞で、ふと醒める。今日もよく通る声は、泥濘のような思い出(きおく)の靄をシャボン玉のように一瞬にしてぱちんと弾け飛ばした。微睡から醒めたみたいにクリアになった頭でも、微かにでも視線を泳がせてしまう。
脳裏に纏っていた陰を追いかけずにはいられないかのように、ぐるりと一周した視線の先は、何の変りもないような飄々さで笑みを浮かべている彼がいた。
「峰元、さっき挿したCDチェックは?」
「流しても問題なかった」
「じゃあ、このままいくか」
地方のローカルラジオ局、そこが私たちの居場所で、小さな世界だ。活気で満ちて、賑やかさのある観光地や煌びやかなライトを照らしているビル街とも少し離れたモダン的で落ち着きさが並ぶ商店街に馴染み、一部となった仕事場が今を構成していた。
けれど、私はあの時からぶれないまま、頑張れずにいる。動けないわけじゃないのに、動くことを忘れてしまったかのように停止したままでいる姿を見たら、厭きてしまうかもね、と自嘲する私は変わっていない。
変われないで、いる。
CDの曲が流れだしたと同時に録音に入る。起動させた機械がくるくると回りだすのを確認して、視線を上げた瞬間、今日一度たちとも交わることのなかった視線と搗ち合った。此方をじっと見つめる視線にドキリと跳ねた。
「やっと合ったね」と、でもいうかのように、にこりと笑みを深めた彼にぶるりと身体を震わせてしまう。まさに蛇ににらまれた蛙のような気分だ。
儚く、誰にでも優しいような顔をする印象を与えるSUMIは、ある意味博愛主義的にも思える。誰にでも優しいのは、優しくされたいわけじゃなくて、誰にも興味ないという証で、淡泊で軽薄さで満ちているのと一緒で、厭だと思った。
「SUMIと、知り合い?」
「え?」
「結構、峰元のこと見てたからさ。彼」
「長い時間ってわけじゃないけどね」と、言葉を続けてから、ポケットから取り出したセブンスターの箱を軽く揺らした。その箱を馴染ませるように左手に握りながら、頬杖をつく横顔は、この仕事場ならではの出来る関係性の近さを表していた。だけど、それはとても扱いやすくてとても扱いにくいものでしかないのだ。
誰でもが自由に、そして対等に立てるようなシステムで成り立っているからこそ、関係性は築けやすく、簡単に入り込むほど皆強くないことを汲み取って、ぶつからないように流れのまま身を寄せ合っている。
声を届ける、多彩に発信していく仕事をしているのに、不器用すぎるのだ。私を含めて、空気を読んで互いが潰れないように接しながら、まるでここが居場所かのように構築するようにしている。誰もが、一ミリもこぼれないように。
「ねぇ、峰元」と、高橋は瞬く合間にできた静寂を切るように言葉を紡いだ。消えそうになるような煙を纏って。
「ずっと前から不思議だったんだけど、何で夕貴だったの」
「好きだから、かな」
「え?」
好きだったし、苦手でもあった。けれど保栖の人間性に強く惹かれたのだ。
自分が描いている理想を走り続けられるような人間(ヒト)で、何度躓いても、転んでも起き上がって前向きに地道に進んでいくから眩しくて、私が持っていないものばかりで構築されていた。それが羨ましくて、眩しくて、目を離したくても離せないくらい、魅入られた。
「保栖ほど、頑張っている人間なんて知らなかったから」
「……狭いね」
「今思えば、そうかも」
セブンスターの表面をゆっくりとなぞるように指先で優しく撫でる高橋の横顔は、どこか悲しげに憂いていた。
「置いて行かれる気持ちなんて、置いていく人間には解らないのかもしれないって思ったけど、置いていく側もそうなのかもね」
同情するとでも言いたげに、弱弱しく笑う高橋の姿は、一段と綺麗に発色した。淵をなぞるだけだった。奥深くにあるものを重ねて触れてくることなど一度もなくて、直向きに見せないように繕っていた綻びを珍しく見せた彼女の姿に、鼻の奥がツンと痛くなった。
まるで、ガラス越しに伸びた二つの影が、あの時のように重なったから。
「えっじゃあやっぱり、芸大いくんだ?」
「うん」
「すごっ!」
目先で盛り上がって、人だかりが出来ている原因なんて、考えなくても判る。高校三年間、それよりもずっと前からちゃんと見てきたようなものだから解かってしまう。
周りの感嘆とした声に、ゆらりと手持ち無沙汰のようにその場で足踏みを繰り返すのも、莫迦らしくなってしまうくらい随分と慣れてしまった。
ぼんやりと、宙に視線を飛ばせば、申し訳なさそうな顔をした保栖が見えた。周りの生徒とは頭一つ分も違う身長と華奢すぎるほどの体型。そして、周りの生徒が揺らめかせているスカートとは別のスラックス姿に、嗚呼保栖だなと思った。根拠もなく、証明することなどできない確証みたいで、保栖らしさに笑みが零れる。
「芸大かぁ、才能って感じ」
ざわりと奏でる周りの音たちに「全然、才能なんかじゃないよ」と、声を上げて否定できたらいいのに。「最後くらいは、私が作り上げた普通というものを壊せたらよかったのに」、「才能で違う人間って片づけられるのも、片づけられる悲しくないの」と、言葉にできないで勝手に悔しさやいらつきを滲ませながら、タラレバを積み重ねていく。
才能って言葉だけで終われば、まだ良かった。そしたら、割り切って「上手だね」で終わるだけなのに、そうじゃないから余計に腹立たしくて、歯がゆくて、どうにもできない感情に一瞬で吞み込まれてしまうのだ。
保栖夕貴という人間は、私や周りが思うよりもずっと努力家で、我儘で、一度決めたらそれを最後まで突き通すほど頑固で、聞き分けが良く優しく、柔和な笑みを浮かべているだけでは終わらないと、叫べたらよかったのに。
「(……ただ、我が強いだけの努力家だよ)」
莫迦なやつ、と暖かな風に乱れ舞う桃色を見つめながら、吐き出した。
「そうかも。でも、最初に見つけてくれたのは峰元だったらうれしかったよ」
「……聞いてたの」
「聞こえただけ、それに私も峰元も芸術莫迦でしょ?」
くすりと、晴れやかに笑う姿に「ああ、敵わない」と思うと同時に、ふわりと舞う桃色のコントラストの中で一回転をしてから此方に振り返った保栖はまるで軽快に踊りを披露したおどけない少女のようで、はっとした。
「ね、峰元! 一緒に飛んで」
くっきりと、けれど何重ものフィルターをかけたカメラ越しの映像を見ているように見える美しい鮮やかさを纏っているから、粒子が弾けたよう。
生温い風を纏う梅雨明けも、この桜に交じる瞬間も、保栖は真っ直ぐに前を向いていた。追いかける側の気持ちなんて知らないかのように前だけを突き進んでいってしまう、向いていくと思ったら、唐突に吐き出された言葉にきゅっと喉の奥が詰まった気がした。
どうしようもない、言葉だけど、どうしようもなくはなくて、伸ばされた手をつかみたくなるくらい、甘えたかった。だけど、それと同時に怖いと思った。
いつか、壊れてしまうんじゃないかってくらい脆さのある硝子で出来た世界から保栖はまた自由に飛び立ってしまうのではないかって、気が気じゃなくて、引き留めてしまいそうになる自分がいて。ぐっと押し込めた気持ちが一瞬で破裂するんじゃないかってくらい、危うくて、複雑に絡み合っているからこそ、壊れればいいとも思う。
壊したくなるくらい、一直線上に伸びた関係性は交わることのないという現実は痛く私へと突き刺さったままだ。
「ね、アイス」
「え?」
「アイス、食べてかえろーよ」
「そしたら考える」と、言葉を続けたら、きっと彼女は「もう仕方ないなぁ」とゆるりと眦を緩めるのだ。それは私だけに与えてくれる特権のようにも思えて、今はまだ私の特権のままであって欲しいと思ったの。
眩しい保栖に残した言葉も続きも今になってはもう思い出せないけれど、揺らめいた感情のことは覚えている。
「―――――ね、聞いてる?」
「え?」
「もう、上の空になるのもいいけどさ」
「……嗚呼、うん。ごめん」
久しぶりに出会った保栖はあの頃の保栖のままだった。真っ白な雪のように白い肌と黒曜石のような双眼と同じ色の髪。統一したコーデの配色も変わらない。そして寒々しい空気のコントラストに溶け込むように佇んでいた。
自由に飛び立った保栖はこちらを相も変わらず強い瞳をして、向き合うくせに区切るように言葉を零したのだった。
それが保栖なりの向き合い方で、真摯に受け止めて、前に進んだ。たったそれだけのことだけど失速したのだという事実に衝撃を覚えた。誰よりも美しく咲いていて、誰よりも描いていたから、コートの裾をぎゅっと強く握りしめた。
「……そう」
「峰はどうするの」
「なに、を?」
「ここでもう諦めるの」
そう、保栖が零したその言葉は、ずっと私の中で反芻している。
余りにも淡々とした、抑揚一つもない声で吐き出された言葉は呪いのように私に巻き付いて、呼吸の仕方など忘れて窒息してしまいそうくらいの威力を持った言葉に逃げ出して、沈んだままだ。
指先だけで、ゆっくりと流れ出すエンディング曲。
それは、収録の終わりを知らせると同時に、泡沫の夢から醒ますような、醒めていくような感覚に浸っていた。ブースから聞こえた終わりの合図とともには弾けていく淋しさは、まるで、もう二度と追いかけられないものを見つめるよう。
「高橋のさ、夢って何だった?」
「……夢、か」
手元で、くるりと煙草箱を何度か回転させた後、ふと思い出したかのように「ライターだった、かな」と、小さな声でぽつりと落とした。そして、それが合図かのように、キャスターチェアから立ち上がり、ディスクに乱雑に並べた資料を手際よく片付けていく。
「休憩?」
「ちょっと、少しだけ。出てくるから」
「ほどほどに」
自身が喫煙者というわけではないのに、その手には箱を握っている。その握られる箱の中身など随分と空なのに。だけど、それを手放せないかというように時折優しく撫でている。 たぶん、それは高橋にとってのお守りで。ずっと捨てられずに大事に持ち歩いてしまうほどもう高橋の手には馴染んで離せなくなっているくらいのものなのだろうと思う。
そう、それはまるで昔の私みたいに。
ゆるりと、箱を握る手を軽く振りながら外を出ていく背を視界の端で捉えてから、輪郭から私は手放した。
夢の終わりは、夢の始まりだった。そして、疾うに私は放していた。一緒に並んでいくことを最初から諦めていたのも、いつか跡形もなく消えてしまうと思っていたのも私のほうで、私だけだったのだと今更にも思う。
「じゃあね」と行った保栖を、もう私は追いかけられないのだ。
記事を書いた人
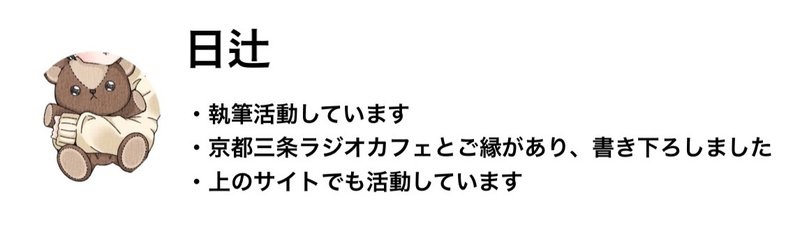
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
