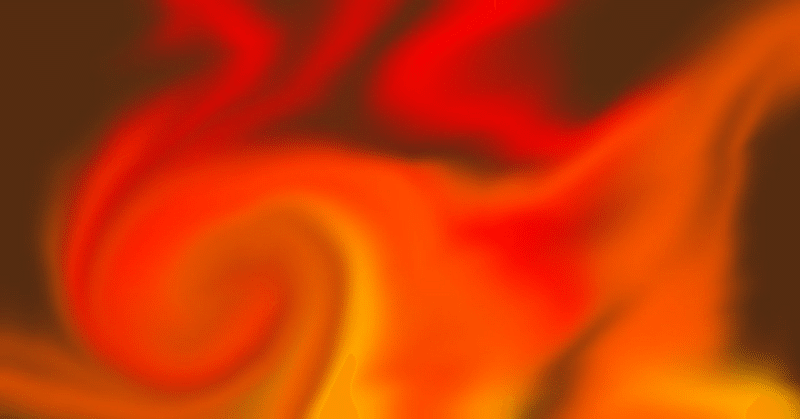
戦闘が終わっても、戦争は終わらない ~映画「ほかげ」~
今月になって漸く、塚本晋也監督作品「ほかげ」を観た。
100分弱の上映時間にも関わらず、登場人物一人一人に対する描写や挿話、いずれも密度が濃く、(軽く聴こえるが)痛々しく、生々しいものだった。
シリアスな主題の作品だと、描写や表現の方向が「悲惨」「哀切」に強調されることもあるが、「ほかげ」はむしろ、とても抑制した表現を選んでいた。
映画の時間は、戦後少し経った(と推測できる)頃で、前半は、バラックの居酒屋に住み働く「女」(趣里)が、後半は、何かの目的を持つ「男」(森山未來)が中軸となり、そして、孤児の「少年」がこの男女に関わり、進んでいく。
「女」は、ポン引きの男に居酒屋を当てがわれ、客に体を売る。
何故、この店にいるのか、身寄りがないのか、といった説明はされない。
「少年」は、居酒屋の食べ物を盗むのを繰り返しているが、やがては逆に食べ物を持ち込むようになる。
同じ頃に復員姿の「文無しの男」が来店し、酒を呑み、「女」の体を求める。
そして三人は、夜だけ、共に過ごすようになるが…。
後半は、「少年」が「男」と出会い、居酒屋のある町を出て、二人で野宿をしながら、移ろって行く。
「男」には、探す人物があり、ある目的を果たすために、「少年」が持つ拳銃が必要だった。
そして「男」は、その人物を探し当て、ある行動を起こす。
「ほかげ」は、戦争を描いた、戦争が主題である映画だが、戦闘行為の場面はない。
戦闘を「火」とすれば、その「影」は戦争全体がもたらすもの、全てだろう。
全ての人物、建物、背景に戦争は存在し、影のように全てに覆い被さっている。
確かに戦闘行為は終わっているが、一人一人に戦争はまだ生き残っていて、その顔を露わにする。
この「ほかげ」で描かれる戦争の顔は、「戦争神経症」、また、戦時中の「罪」としても現れる。
「文無しの男」は風雨の音に怯え、「女」が「そこを開けるな!」と怒鳴る、襖の奥の部屋には、大きな焼け跡がある。
「男」は野宿での眠りの中で慟哭し、「少年」と「男」が旅の途中に出会った、座敷牢から顔を覗かせる男は、何ごとかを叫ぶ。
私は、これらの登場人物を見ながら、昨年(2023年)の夏にTV放送された「NNNドキュメント でくのぼう~戦争とPTSD~」を思い出した。
「でくのぼう」とは、息子が見た父のことで、戦争から復員した父は仕事をせずに家に閉じこもり、会話もろくに成り立たない、感情を露わにすることもない人だった。
しかし、父の没後に息子は、父の兵隊服姿の写真を見つけ、やがて、父の「でくのぼう」は戦地での経験が原因だったのではないか、と思い至る。
この息子はその後、自宅に「PTSDの日本兵と家族の交流館」という資料館を開き、日本で殆ど知られていない、兵士の心的外傷などに関する展示を行っている。
このドキュメンタリーでは、戦後数十年が経った時期、ごく近しい家族から話しかけられても、目を少し遣るばかりで、返答が困難な状態にある父親を写したビデオ映像も紹介されたが、言葉を失うばかりだ。
また、同番組では、国は公に認めなかった「戦争神経症」の専門病院に、戦時中に入院していた患者たち(戦争に起因する精神疾患を負った兵士たち)の写真も紹介された。
この患者たちは戦後、どのように生きたのだろう、と思わずにいられなかった。
「ほかげ」の「男」も「文無しの男」も、座敷牢の男も、戦争神経症を患う人たちなのだろう。
次に、戦時中の「罪」について。
「男」が探す人物は、戦時中に「罪」を犯した、と「男」は考えている。
「男」が、その人物の「罪」を断じた後に呟く言葉に、シンパシーを抱かない人はいないだろう。
探し当てた人物の「罪」にも、当然ながら、戦争中だった、という大きな理由がある。
しかし「男」には、その「罪」の災いが今でも及んでいるのだ。
だから「罪」を断じなければならない、と。
この二人の「男」と異なり、「女」の過去に関する具体的な説明は為されない。
戦争によって、失った人、失った物があるのか、ないのか。
どのような酷い経験を重ねたのか。
言葉での説明はないが、「女」は居酒屋の外に足を踏み出すことはない(できない)。
しかし、「少年」と過ごすうちに、「少年」の身への案じ方が膨れ上がっていく(膨れ上がってしまう)。
この移ろいの描写によって、言葉にせずとも、どれだけ惨い経験をしたのか、その度合を想像するのは容易である。
戦時中に神経を病み、社会と関わらずに過ごすことで自らを保っていたのが、「少年」たちによって「開かれ」、自身の闇に直面してしまったのかもしれない。
映画は、このような人たちを描き、”出口無し”とも言える筋書を語っていく。
観る者を僅かにも安堵させるかもしれないのは、最終盤での「少年」の立ち振る舞いだと思う。
決して安堵ばかりではないのだが、大人たちの暗く疲れた表情に対し、「少年」の、力の込められた口元、意を決した眼差しには、希望を抱いて良いと感じた。
見終えてみれば、よくよく練られた脚本と、それを表現する撮影(いずれも塚本晋也)が見事であればこその作品だった。
塚本さんは「野火」と、この「ほかげ」と、戦争映画の佳作を(ほぼ自主製作で)作り続けていて、世間や映画社会の評判が不当に低いと思う。
(対抗として、「ゴジラ-1.0」は面白かったし、戦争(とゴジラ)の新たな見せ方も良かったが、全体にクリーンかつ綺麗に過ぎた。これは悪い意味ではなく、エンターテインメント作品には不可欠な要素だとは思う。)
塚本さんの映画は、近年の邦画では感じることの少ない、「におい」が漂っている。
よい匂いも、よくない臭いも。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
