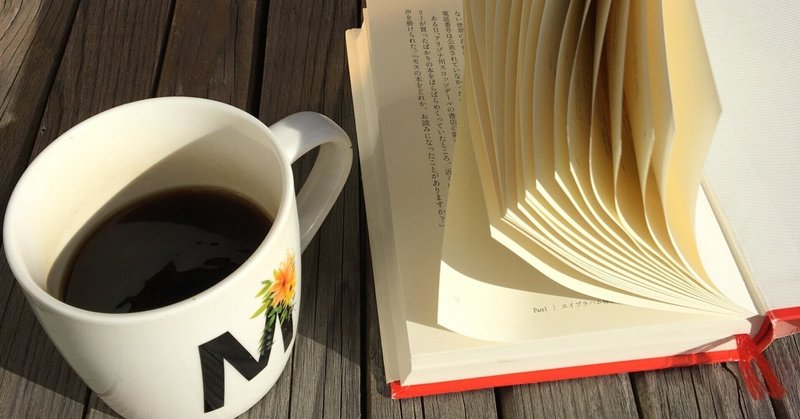
税法大学院入試 税法科目過去問 解答例 「大阪経済大学大学院 経営学研究科 修士課程【税法】 2022年度秋季」(全4問掲載,一部一般公開中)
2022年2月10日現在,全4問の解答例を掲載し,記事が完成致しました!
以下,(1)から(2)まで一般公開,(3)から(4)は購読となります。
1.大阪経済大学大学院 経営学研究科 修士課程【税法】
2022年度 秋季
【問題】(以下,問題文部分は引用となります。)
次の設問(1)から(4)のうち,2問を選択し解答せよ。なお,解答は,それぞれ記載された字数によること。
(1)所得税法において,所得を10種類に区分する趣旨と意義について述べよ。
資産所得,勤労所得の性質についても触れること(500字程度)。
【解答(例)】
一. 趣旨
所得税法が所得を区分する理由は,源泉や性質によって担税力が異なるからであり,また,典型的には,①資産所得は担税力が高いから重課するべきであり,②勤労所得は担税力が低いから軽課するべきであると考えられてきた。また,資本家は①と②の両方を得られるが,労働者は②しか得られないという社会観察が伝統的にあった。さらには,物的資本に比して人的資本の減耗部分は控除できず,労働所得が過大計上され,その補足率も高いことや,預貯金の利子や株式の譲渡などの税務執行の便宜の観点からも,所得を区分する必要性が指摘される。
二. 意義
昭和22年税制改正は,分類所得税と総合所得税の二本立てをやめ,一本の超過累進税率で課税することとした。以後シャウプ勧告の内容を含む課税所得の包括化を経て,現行所得税法は,居住者の「すべての所得」に課税するとして総合所得税の建前を採りつつ,その所得を利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡・一時・雑の10種類の「各種所得」に区分し,いずれの類型に当たらない所得を雑所得として拾い上げる一方で,退職と山林を他所得と切り離して税率を適用する,部分的に損益通算を認めないなど,分類所得税の要素を多く残している。
(514字,スペース入れて518字)
(【解答】終わり)
(1.2022秋(1)終わり)
(2) 法人税法においては,同族会社につき,定義規定を定めた上で,特別な税制を設けている。その内容について,趣旨・目的を踏まえて説明すること(500字程度)。
【解答(例)】
税務署長は,同族会社その他これに準ずる内国法人に係る法人税につき更正又は決定をする場合において,その法人の行為又は計算で,これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果(〈補足1〉)となると認められるものがある(※1)ときは,その行為又は計算にかかわらず,税務署長の認めるところにより,その法人に係る法人税の課税標準若しくは欠損金額又は法人税額を計算することができる(法法132条1項)。
包括的否認規定であるが故に個別否認規定の要件を備えておらず,この規定で個別案件を否認することの可否が議論される中,判例は,納税者の選択した行為計算が実在して私法上有効なものであっても,租税負担公平の原則の見地からこれを否定し,通常あるべき姿を想定し,その想定された別の法形式に課税当局がひき直すことにより,同族会社と非同族会社の間の税負担の公平を維持しようとする法132条の趣旨・目的に照らした上で(趣旨目的基準),当局の「客観的・合理的」な範囲内での課税処分権限を認めた(光楽園旅館事件(最判昭和53年))。
※1 専ら経済的・実質的見地において当該行為計算が純粋経済人の行為として不合理・不自然なものと認められるか否か(〈補足2〉)を基準として判定する(経済合理性基準)。
(521字,スペース入れて524字)
((2)【解答】終わり)
【解説〈補足〉】
〈補足1〉「目的」の文言削除
昭和25年度改正において現行法の文言となり,法人税の負担を免れる(逋脱の)「目的」の文言が削除された。これにより,租税回避の「意図」は必須要件でなくなったとされるが,主観性が強い概念として,もともと必要十分の要件ではなかった。最近の判例では,必須ではないにせよ,「結果」を重視する客観的・合理的基準が優先され,その上で「状況証拠」により「意図」が推定されるようになりつつある。
〈補足2〉経済合理性基準について
経済人として不合理,不自然なもの,即ち,経済的合理性を欠く場合には,独立かつ対等で相互に特殊関係のない当事者間で通常行われる取引(独立当事者間の通常の取引)と異なっている場合が含まれるとされ,このような取引に当たるか否かについては,個別具体的な事案に即した検討を要する(日本IBM事件(東京高判平成27年))。
この基準となるのが,①その具体的な行為・計算が異常・変則的であると言えるか否か,及び,②その行為・計算を行ったことにつき租税回避以外に正当で合理的な理由又は事業目的(cf. 上記「意図」)があったと認められるか否かである(ヤフー事件(最判平成28年))。
((2)【解説】終わり)
(1.2022秋(2)終わり)
2022年2月10日現在,続きの(3),(4)の解答例を購読できます。
ここから先は
¥ 100
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
