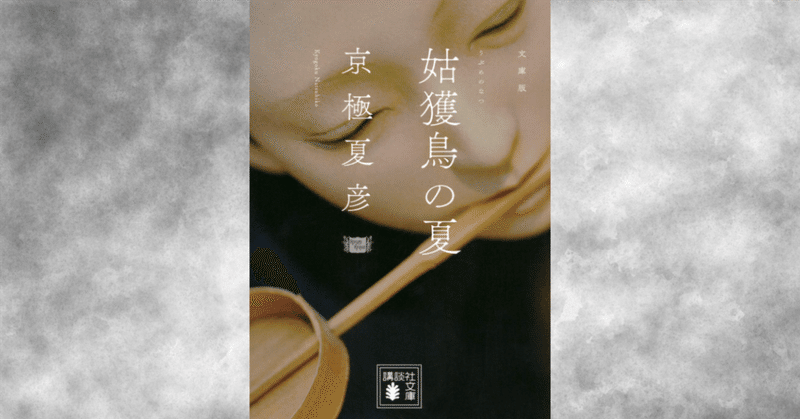
”沼”の始まり、『姑獲鳥の森』|読書感想文
全身の筋肉が弛緩した。
身動きが取れなくなるほど、小説に意識を吸い込まれていた。
綴られた言葉や文字から投影されたイメージに自意識を潜り込ませていただけで、実際には椅子の上から一歩たりとも動いていない。
もしかしたら脳から足が生えて、勝手に周辺を走り回っていたのかもしれない。
疲労困憊して横たわる体と脳に、確かな充実感と恍惚感が満ちる。

1️⃣百鬼夜行シリーズ
京極夏彦先生といえば、その圧倒的な文章を書くことで有名だ。読書クラスターの人間でなかった私でさえ、その話はよく耳にする。
本作、「|姑獲鳥《うぶめ》の夏」は彼のデビュー作として有名な作品だ。
意外に世の漫画家さんたちは京極先生の作品を好む人が多い。
赤坂アカ×横槍メンゴ「推しの子」のワンシーンで主人公のアクアが何気なく手にしていたのも、京極先生のサイコロ本だったりする。
サイコロ本とは、文庫本のこんじまりとした表面積に比べてそのページ数があまりにも多いため、本というよりもはや「立方体」に見えるからそう呼ばれる。あるいは「煉瓦本」なんて呼び方もあるが、どちらにせよミステリーの凶器に仕立て上げられてもなんらおかしくない質量と様相を呈している。(言い過ぎ)

「私がモテないのはどう考えてもお前らが悪い!」通称「わたモテ」の作者、谷川ニコさんもファンの一人。
谷川ニコさんがツイ4というプラットフォームで連載をしていた作品「クズとメガネと文学少女(偽)」では、主人公が京極先生に憧れるところから始まる。といっても、先生の抜き手袋を着用した強烈なビジュアルと、文庫本の信じられない厚さがネタにされただけで、内容にはほとんど触れられない。
だから私にとって先生の印象はといえば「分厚い本を書く小説家」といったものでしかなかった。しかし、今回の京極夏彦先生のデビュー作「姑獲鳥の夏」を読んで、世界が一変してしまった。
百鬼夜行シリーズは、こちらで紹介する「姑獲鳥の夏」をはじめとした京極夏彦作品郡であり、シリーズに共通して登場する京極堂という舞台にちなんで京極堂シリーズなんて呼び名もある。
分類としては推理小説であり、全てのタイトルに「怪異」や「妖怪」といった伝承を冠しているのが特徴的。はじめ「ゲゲゲの鬼太郎」で知られる妖怪の第一人者「水木しげる」作品を連想していたが、とんでもない。
鬼太郎もねこ娘も、ねずみ男もでてきやしない。生身の人間が生身の事件を解決する、どこまでも現実のお話だ。
2️⃣私達に、まず現実は何かを分からせる。
「モノが見えるとはどういうことか」
本編の目玉とも言える京極堂店主「中禅寺 秋彦」が私達に問うメッセージは難解極まりない。彼が本作の主人公に向かって語りかける言葉は、まさに本を読んでいる私達へも投げかけられている。私達がどれだけ世間を漠然と捉えているか、そしてその漠然をどれだけ信じ切っているのかを、冒頭から長尺セリフに皮肉をたっぷりとトッピングして浴びせられる。
まず、この時点で「ただの小説」だと認識することが難しくなる。
その深い考察と観念の因数分解は並大抵のものでなく、おおよそ普通に生きてしまえば考える間もなく忘れ去られてしまうことばかりなのだ。しかし中禅寺の言葉は、どれも現実的で説得力をもっていて、まるで袋小路に追い込まれていくように解答から目が逸らせなくなっていく。第一段階の意識の吸引だ。この小説は後半いくほどに吸引力が増していき、自分の中にあった偏見という名の斥力が事ごとく打ち壊されていく。
まるで学術書か、人によってはどこか宗教的な感覚すら湧いてくるだろう。例えば濃度を高めるためそのほとんどの記述が既知の専門用語で綴られた専門書なんかであれば、多くの人は単語の難解さで挫折する。だが、京極先生の操る日本語はすべて紐解かれているもので、だれにでも理解可能な丁寧な言葉で説明されているのだ。
本の分厚さは、まさに「要約」の反対である「敷衍」の結果なのだ。本の分厚さにとっつきにくさを感じた私の第一印象とは裏腹に、この小説はどこまでも「懇切丁寧」
不思議な反比例を描いている。
逆に、要約され薄くなってしまった本を読む時、私達がいかに自分の無意識と常識に頼り切りであったかを、否応なく分からされてしまうようであった。この本の分厚さは「モノが見えるとはどういうことか」を私達に伝えてくれている。このシンプルな題材を解説するのに、どれだけの言葉を要するか。そしてこれだけの文章量で語られる脳や意識のメカニズムを、私達が素気なく一瞬の内にこなしてしまっている事の異常さに、改めて気づかせてくれる。
このサイコロ本に匹敵する情報処理を人間は一人ひとり行っているし、なんでもないように手繰っている。どうしてこのサイコロ本を避けて、人間達と対等に向き合えると思うのだろうか。ごくごく短い「常識のものさし」などであれば人間など容易く測れると思っているのだろうかと。
まるで目の前に中禅寺が居て、彼から心底飽きられてしまったような感覚すら湧いてくる。
3️⃣ものがみえて、しかし幽霊や怪異がいる。
本作はどこまでも写実的な推理小説の部類に入る。
だが、それだけには納まらない。どの要素一つとっても十二分すぎる見識と見解を秘めている。
主人公の心情描写は限りなく深い。中禅寺の言葉を受けて、読者同様に苦悩し真実を叩き込まれ認識のずれに囚われ始める。
古書店の店主を営む中禅寺は、たびたび妖怪奇談を持ち出す。「モノはどう見えるか」と、どこまでもリアリスティックに因数分解していく彼が、どうしてそのような分野に熱心なのか。それは彼が宮司であり、陰陽師の家系の人間だからだ。
そんな人間が「この世に不思議なことなどない」とお決まりのセリフを吐くことの意味を、今一度考えさせられる。通常であれば、胡散臭さであったり論証の甘さが目立ってしまう題材だろう。ミステリーのタネは全てが現実的で反証可能なトリック。一方で陰陽道や怪異などというのは一見すればオカルティックで、人智の及ばない神秘までを考慮にいれてしまう。
主義主張は真っ向からぶつかり合うか、交わらないことで不可分領域を造り、ゆるやかな共存かの道しかないように思えるが、この作品群は違う。
それぞれの分野を因数分解した果ての最小共通点を結びつけ、そうして実存的な部分もオカルティックな部分も点と点でつなぎ合わせてしまう。そんなことがどうしたら可能なのかと、疑問に思われるかもしれないが、その緻密で圧倒的な知見を表現するために、サイコロ本、あるいは煉瓦になっている。
「相反する」などと安易にひとまとめにできる言葉を使わずして、大いなる説得力をもたせるために必要なのがこの分量であり、それだけ連なった言葉たちなのだ。
「相反していない」を証明するために用意された垂涎の630頁。
読んで見れば、すぐにあなたも囚われる。
いないはずの怪異を目にし、夢も現もぼんやりと交わり、そうして気づけば袋小路の先。そこで叩きのめされる。
文章の濁流と情報量という暴力に、もはや抗えなくなっている。
※特に言い回しが強烈なものは⇓こんな感じ⇓にまとめられている。妙な中毒性を秘めているのも、没入させられる要因かもしれない。
4️⃣なんど物語をひっくり返せば、気が済むのだろうか
目次でいうところの、4項目にして初めて本編にふれることを許してほしい。「文章のはじめに概要をかけ」とは口をすっぱくして言われてきたが、本書籍もこれの倍以上時間をかけて本題に入っているのだ。読書感想文でありながら変なオマージュのつもり。それだけ前提をまず整えることが第二の吸引力につながっていく。
本作は、たまたま探偵事務所を訪れていた文士「関口 巽」がある病院で起こった失踪事件を解決するため訪れた依頼者「久遠寺涼子」と会話することから物語は動き出す。そうして魅力的なキャラクターたちがあれよあれよと病院に終結し、そこで起こった事件の真実に近づいていく、と概要だけ説明すれば王道もののミステリーに聞こえるかもしれない。とんでもない。この小説はいわば超ハイブリッド小説なのだ。
心情描写、知見、学術的観点、トリック、文章構造、ホラー、パニック、怪異。
どれをとっても一線級。うろんな要素など一つもなく、芸術的なまでの構造をもって物語に厚みを持たせている。
本作は、動き自体は限りなく少ない。もう起こってしまった事件を証拠と照らし合わせながら紐解くストーリー形式なので当然そうなのだが、前述した要素が散りばめられるどころかひとつひとつ煮込んで配膳されるので、結果としてあの厚みにつながっている。だからといって決して味が薄いわけでなく、どれも濃密な味わいがする。だから私の脳はすぐにお腹いっぱいになってしまって、全てを堪能しきるにはキャパシティが足りなくなる。
そうしている内に物語が二転三転と動いていくから、ここで第三の吸引力が遺憾なく発揮されるのだ。脳が休まらない。ただただ興味と面白さに惹かれてどこまでも深く深く、穴に詰め込まれたピザ生地を求めて潜っていってしまう。冒頭で書いた、筋肉が弛緩しただの、うつ伏せで動けなくなっただのは、読書慣れをしてまだ日が浅いわたし程度の人間が深みに入ろうとしたらこうなりますよ、といった一種の警告文なのだ。
正直なところ、映像化は比較的簡単な部類だと思う。本作の続編である
「魍魎の匣」なんかも、評判はあまり良くないが映画化を果たしている。
だが、映画化とは、言ってしまえば作品の「要約」もしくは別の付加価値を与えることだ。
正直読んでいて思うことは、この作品には一部の隙すらない。要約もできないし、付加価値のつけようもなく完成されている。
もしくはあったとしても、一般人に穴をつくことは到底不可能なのだ。世界がどこまで「敷衍」されているから、おなじだけの敷衍をもって証明されなければ、たちまち袋小路に陥る。抗わないほうがいい。行き止まりの通路でそのまま腰を降ろして読み耽るほうがよっぽど健全に思う。
ああ、それに尽きるかもしれない。
もう読みながら、諦める。
心を渡して、ただ物語を味わう。
色眼鏡を外すとは、つまりはそういうことなのだろう。
まんまと中禅寺の言う通り、姑獲鳥の夏は終わりを迎えてしまった。
そんな読書体験だった。
あとがき:読書感想文はかけない。
読書感想文というのは、つまるところ「要約」
そこに幾ばくかの心情をのっけて世間に発信することに付加価値を見出し、誰かの購買意欲をそそるのが読書畑の人間にとって正しきカタチなのかもしれません。
あるいは、誰かの書きたい欲を刺激することで、この仕組み自体が小説界隈を発展させるたための燃料なのかもしれない。
しかし、京極先生は物事をどこまでも「敷衍」している。話を展開しながら横に横に、広く広く。そうして広がりきったピザ生地を、書籍という狭い穴にギューギューと詰めていく。奥に奥に、深く深く。
一般的な小説や純文学は、削って、カットして、加工して、仕上げていった先の輝く宝石、といったイメージ
であれば「姑獲鳥の森」は貪欲に磨き上げた宝石を加工しないままにこれでもかと詰め合わせたみたいな作品だ。
速筆で有名な京極先生が、人生に横たわるテーマを余さず詰め込みようやくできあがった厚み。素材の味を楽しむ、といった観点でいうならば、この小説は感想文にまとめ上げてはいけない。
どれだけの熱量をもった読書感想文が世に溢れたとしても「本著を読め」という、もう取りつく島もないような感想が唯一の正解になってしまうからだ。
そうして開かれてしまった百鬼夜行シリーズへ続く道を、人は沼という。
姑獲鳥の夏は、その始まりの物語にすぎない。

「この世に不思議なことなどない」と、中禅寺は言い放ちますが、一つ、私には疑問に思うことがある。
「なぜこのシリーズの凄まじさを、みなが声を大にして伝えないのか」
これが不思議でなりません。
みなさま、ぜひともお手に賽子を。
めくるめく京極夏彦ワールドへ落ちて参りましょう。
🐈️気に入りましたら、ぜひサイトマップも覗いていってくださいな🐈️
📕他の読書感想文も一緒にいかが?📕
🎉Kindle本*エッセイ集、出版しました!🎉
著・猫暮てねこ『恥の多い人生を書いてまいりました』
ネコぐらしは『文字生生物』を目指して、毎日noteで発信しています。📒
※文字の中を生きる生物(水生生物の文字版)🐈
あなたのスキとフォローが、この生物を成長させる糧🍚
ここまで読んで頂き、ありがとうございます✨
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

