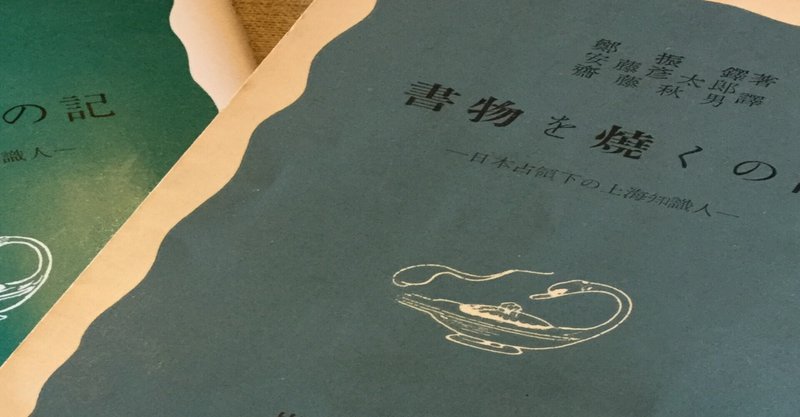
水の温度を知る魚ー戦時下の知識人と本の運命ー
立春前に家の大掃除をした。年末は忙しくてできなかったのだ。今年は久しぶりに本棚の整理もする。狭い家なので、たまにやらないと新しい本が入らない。
片付けているうちに、夫の蔵書の中に、同じ本が2冊あるのに気づいた。岩波新書の青版。1冊は1954年の第1刷で、紙が茶色くなっている。破れているページもあった。もう1冊は1991年の第3刷で、こちらは比較的新しい。夫に「何で2冊もあるの?」と尋ねると、古い方は父親の蔵書だったものだが、大好きな本なので学生時代に自分でも買ったのだという。へえ、それは面白そうだ、と思って新しい方を手にとり、軽い気持ちで読んでみた。そして読み終わった後、私は思わずアマゾンでその本をカートに入れそうになっている自分に気づいた。自分用にもう1冊買いそうになる気持ちを押しとどめるのに必死だった。
まったくもって、素晴らしい本だったのだ。
☆☆☆
鄭振鐸(ていしんたく)の『書物を焼くの記―日本占領下の上海知識人―』(安藤彦太郎・斎藤秋男訳、岩波新書)は、副題の通り、日本占領下の上海で身を潜めていた中国文学者、鄭振鐸(1898~1958)のエッセイである。戦後まもなく「蟄居散記(ちっきょさんき)」というタイトルで雑誌に連載された文章をまとめ、翻訳したものだ。
まず驚かされるのは、その抑制された筆致である。当時の上海の混乱や、困難の多い自身の生活を描いているのだが、表面的にはとても静謐な文体なのだ。もちろん訳文によるところも大きいとは思うが、作者の声が静かであればあるほど、彼のはげしい怒りがダイレクトに伝わってくる。ページをめくるたびに、敵である日本軍、そしてその手先となった「漢奸(かんかん…対日協力をした中国人)」たちへの深い憤りが、にじみ出てくる。
☆☆☆
堀田善衛の短編小説「漢奸」は、日本占領下の上海で、新聞の文芸欄を担当する中国人前衛詩人が、日本の敗戦を迎え、裁判を受けるまでの様子を描いた作品だ。私は個人的にこの作品は堀田善衛の最高傑作の一つではないかと思っているのだが、あくまでも日本人知識人の目から見た「漢奸」、それも前衛詩人というかなり特殊な事例を描いたものだ。それに対して『書物を焼くの記』は、中国人知識人、つまり同胞から見た「漢奸」のすがたを描いている。私にとって「漢奸」についての新たな見方を与えてくれる作品だった。
興味深かったのは、鄭振鐸が、ひとがなぜ「漢奸」になるのかという問いを立て、分析している所だ。中国には長い官僚政治の歴史がある、と鄭振鐸は言う。そして、一度その中で役人になった者は、死ぬまで役人根性から抜け出せないと。
「このような官僚どもは、毎日、手づるをもとめ、使い手をさがし、主人をたずねてまわる。主人が眼をかけて、そばにおいてくれて、高い役目と、よい給料の餌をくれさえすれば、ぺこぺこと、なんでも言いつけをまもるのである。その主人がどんな種類の人間であるかについて、考えてみようともしない」(p.121)
彼らはよく「占い」や「人相見」に頼る、と鄭振鐸が喝破しているのも面白い。鄭振鐸によれば、彼らには、民衆の生活はどうでもよく、ただ個人の立身出世だけが問題なのだ。こうして彼らは占領者に阿り、協力する。しかし、それは漁師に操られる鵜になることにすぎない。頭がなく、魂がなく、思想がないために、自分が漁師にとって単なる道具であることすらわからない鵜に。
本書の全編をとおして、鄭振鐸は彼らの存在に憤り、嘆く。と同時に、信念を曲げず、占領への抵抗を続けた人々のエピソード紹介も怠らない。拷問されても、処刑されても仲間を売らなかった男性たちと女性たち。彼らへの最高の敬意が存分にこめられているのも、この本の特色だ。戦争というものが、平和な時には巧妙に隠されている一人一人の、人間としての地を露わにしてしまうこと、そしてその苦しさに、これほど思いを至らされたことはなかった。
☆☆☆
というわけで、本書では多くのページが作者の周囲の知識人の動向をしるすことに当てられているのだが、おそらく読書家にとって最も胸をうつのが、タイトルにもなっている「書物を焼く」話から始まる、占領下における本の運命を語った三つの節だ。
作家でもあり、文学研究者でもあった鄭振鐸は、当然のことながら多くの蔵書をもっていた。戦争が始まると、それが「焼けて」しまう。第6節「書物を焼くの記」にその顛末が記されている。
まずは戦火で書店が灰燼に帰し、預けていた本が焼ける。しかし鄭振鐸にとって、それはあるていど覚悟していたことだった。彼にとって本当の試練は占領が始まってからだ。「抗日的な本は焼くか、届けるように」という知らせがくる。日本軍による家捜しが一軒ずつ行われるという噂が飛びかいーそれは抗日的な本が見つかれば家主が逮捕されることを意味したー鄭振鐸は心を鬼にして、自らの愛する蔵書を焼くのである。
何が抗日と見なされるのかがわからないなか、人々は新聞、雑誌も含め、あれもこれも懸命に焼いた。「書物の焼くの記」ではその時の鄭振鐸の煩悶が、例によって押さえられた、淡々とした文章で綴られる。結局、一軒ずつの家捜しは行われず、焚書騒動は一ヶ月ほどで収まったのだが、この時の経験が彼にとってふかい心の傷となったことは想像にかたくない。
次に来る試練は資金繰りのために本を売ることである。占領下で身を潜める困難な生活、食べものを買うためには金がいる。第7節「書物を売るの記」だ。
「本を売る話になると、わたしの心は急に曇ってくる。一冊、一冊とあつめた本は、みんな、この本はどこの店で買った、あの本はどうやってみつけたと、それぞれの歴史をもっている。ちょっと躊躇しているあいだに買われてしまい、その後、ふとしたことから探しだしたのもある。また、揃いの書物のうち一、二冊だけが手に入り、その後、苦心惨憺のすえ、古本屋の山積みのなかからみつけて、完全なものにしたのもある。完全に揃ったときの嬉しさは、どうだったろう。なかには永久に揃わないものもあるが、そうなると手にいれた分はますます貴重なものになる。(中略)こういうふうに、書物それぞれには、みんな、わたしの感情がこもっているのである。魚が水の温度をよく知っているようなものだ。こんなに苦心して得たものを米に代えてしまうなど、だれが想像しただろう。さらに一冊、一冊と買って、ようやく一揃いになり、それがまた書棚に積まれるようになったのを、ひもでくくったり、箱に詰めたりして、売りあるかねばならぬと、いつ想像したことがあったろうか」(p.57-59)
魚が水の温度を知っている、というのは不思議な表現だ。鄭振鐸は魚、彼にとって本は水なのだ。その貴重な、生きるためにどうしても欠かせないもの、大切な叢書類や、石刻本、明代や清代の本を、彼は手放していく。本を売るか餓死か、と迫られれば、本を売るしかない。そのあまりの苦しみに、鄭振鐸は、自分はなぜ本を買ってしまったのだろう、とまで考える。何でもいいから他のものを買っておけば良かったのだと。自分の命そのものでもある本。それを売らなければならない時の、情けなく、みじめな気持ち。おそらく国や時代は違っても、愛書家であれば思いは同じであろう。心を打たれずにはいられなかった。
☆☆☆
ここまでの節も十分に味わい深いものだったが、続く第8節「書物の運命」が、私にとっては一番印象深かった。戦時下で紙が不足しだすと、本は紙の原料として買い取られるようになる。全て溶かし釜に放り込み、再生紙にするのだ。本屋も、古書は、いつ来るかわからない買い手を待つようなことをせず、すぐに紙屋に売ってしまう。その方が手っ取り早く金になるからだ。紙屋が見るのは秤の目盛りだけ。すなわち、よほどの稀覯本でもない限り、「本の価値は重さ」ということになるわけだ。
鄭振鐸は本屋で、貴重書が紙屋に売られそうになっている現場を目撃し、金を払って買い取ったこともあったが、彼一人で全ての古書を救えるわけではない。
「永久にかがやく名著や、苦心をこめた大作も、その日かぎりの新聞や号外といっしょに、紙屑として釜にいれられてしまうのである。文献の災厄こんにちより甚しきは無しだ。見るだに心の痛くなる光景で、書店のまえをとおりすぎることさえ忍びがたい気持ちがしてくる」(p.71)
戦時下に本がたどった運命を、それまであまり考えたことがなかった私には、この節の内容は驚くことばかりで、読み進めるうちに自分の不明を恥じずにいられなかった。戦争における人間の運命については、それなりに学んできたつもりだった。しかし戦争とは、本をも処刑するものだった。ただの紙ではないはずの本を、ただの紙にしてしまうものなのだ。本書は全部で22節から構成されており、どの節も大変に読み応えがあるが、私にとってはこの第8節が、一番インパクトが大きく、戦争、そして占領が本質的にいかなるものなのかを考えさせてくれたように思う。
☆☆☆
私が上海に初めて行ったのは1991年1月、まだ学生の時だった。人々が、大学で習っていた中国語(普通語)とは違った言葉を話していて、少し寂しい気がするものの、街に漂うどことなくモダンな雰囲気が心地よかった。友人とバンド(外淮)、豫園、租界といった観光地をたのしく歩き回り、はじめての中国旅行を満喫した、という記憶がある。
しかし今ふりかえると、たかだかその46年前まで、日本軍による占領と、『書物を焼くの記』で描かれた状況があったわけで、何というか、無知というか、無邪気に上海の地に降りたってしまっていたなあと、反省する心がわき起こってくる。
それだけではない。上海にはその後3~4回訪れたが、そのたびに経済的に発展していく様子に眼を奪われるばかりで、占領時代の出来事に真剣に思いを馳せたことは正直あまりなかった気がする。機会があるかどうかわからないが、今後もし再び上海の地を踏むことがあったら、その時は鞄の中に本書を入れていたい。『書物を焼くの記』は、そんなことを願いたくなる本だった。
今はない岩波新書の青版。今回手にとった第3刷も旧字だが、活字は大きくて大変読みやすかった。実は今回の大掃除で、他にも青版の古い中国文学の翻訳ものが何冊か見つかったので、時間を見つけておいおい読んでいきたいと思う。
(この文章は2020年2月に書いたものです)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
