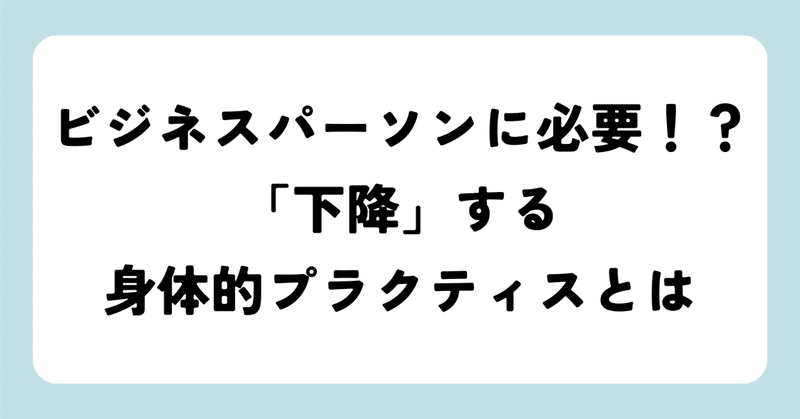
ビジネスパーソンに必要なのは「下降」する身体的プラクティス?
はじめに
2020年に「肚の叡智をつかって失われた直感と洞察を取り戻す」というコンセプトのオンラインプログラム『ガット・ウィズダム』を学びました。
ここで学び、実践するプラクティスとは、心身をアスリートのように鍛えていく方向性を「上昇」と表現するならば、「下降」と表現する方向性なのではないかと個人的には思っています。そして、多くのビジネスパーソンにとって重要なのがこの「下降」の方向性の身体のプラクティスなのではないかと思うのです。
今回は上記のオンラインプログラムで紹介されていた「人間のパーソナリティに関するモデル」がとても興味深いと共に、多くの人にとって価値あるものだと感じたので紹介したいと思います。
ボディサイコセラピー(身体心理療法)とは?
「ガット・ウィズダム」の講師をされていたのは贄川治樹さんという方で、ボディサイコセラピストをされています。私はそういう分野があることを当時初めて知りました。今回紹介する図と関係が深いものでもあるので、贄川さんの言葉を紹介する形で説明します。
概要
・ボディサイコセラピーは、「からだ」を導入した心理療法
・大きな特徴として、胎生学に基づいているということがある。言語のみを用いる心理療法は、言葉を発する時期までしかさかのぼることしかできないが、ボディサイコセラピーでは、子宮内の胎児期にまでさかのぼり、トラウマを解消し、もともと持っている美質や本質を取り戻すことができる
・ジグムント・フロイトの弟子であるウィルヘルム・ライヒが起源とされている
・精神分析の対象関係学派、発達心理学、胎生学、神経生理学、運動生理学などの幅広い領域を取り入れて進化し、ヨーロッパ、アメリカ、南米などで広がり、社会的に認められている
どういうことを行うのか?
具体的に行うことは、多くの理論と技法をたずさえて、目の前にいる人に同調し、身体感覚、動き、感覚器官、呼吸、情動や感情、言葉やイメージ、関係性で起きていることなどに意識を向けながら、クライアントと一緒に内面の旅を歩んでいく
ボディサイコセラピーで捉える人間のパーソナリティとは?

上記の図は、プログラムで紹介されたものを私が作成しなおしたものとなります。個人として理想的なバランスになっている場合は上記のような三角形になっているそうです。
それでは、図の内容について紹介していきます。
・この図でいう一番下には自然環境がある
・自然環境(大地)に一番近いところに位置するのが身体のプロセス。このプロセスは、自律神経系ととても関係が深い。自律神経系は脳の中で一番深いところにある脳幹と関係が深い。
・これが土台となって、その上に情動や本能的な衝動が出てくる。
・情動や本能的衝動の上に今度は感情や意志の力が働き出すようになる。
・その上に言葉がのって、思考(大脳新皮質の部分)がくる。
・そういった自分を客観視している自我の部分が出てくる。
私たちは、生まれてから、図の下から上に向かう「ベクトル」によって発達していくそうです。
多くの人は逆三角形になっている
本来あるべきバランスは上記で紹介した図ですが、現代人の多くの方の状態は逆三角形になってしまい、一番上にある自我・セルフイメージが肥大化してしまっている、頭でっかちになっていて、そのために本来は土台であるはずの身体プロセスを感じにくくなっている。また、それに紐づいて本能的なものや感情も感じにくくなっている。とのこと。

MYコメント
この状態には私自身も大いに心当たりがあります。今でこそ、三角形のバランスで生きられているように感じますが、少なくとも社会人になってから1、2年は自分の感情が分からなくなっていました。(そもそも感情は感じるものなので、分からないという用語を使っている時点で思考優位になっていて、問いを通じて出口のない迷路に入ってしまっていると言えますが、あえて使っています)
セルフイメージが肥大化していることにより、イメージに合わないものを抑え込んで、ないことにしようとする。その結果、どんどん自分の体と心が分かれる、自分のイメージだけが大きくなっていく。合わせて、周囲からの承認を得ようばかりしてしまう。そういったことが起こりやすくなるそうです。これは言い換えれば、自然・大地と切り離されていっているとも。
思い出したこと「上虚下実」
この三角形・逆三角形の図を見た時に思い出したことがあります。それは、その昔、ハワイ島のオーガニックファームで生活していた時に毎朝ヨガをしていた時に教えてもらった「上虚下実(じょうきょかじつ)」という言葉です。
当時してもらった説明については忘れたので、ネットで検索し、近しい意味だと思えるもの「しゅとう整体」さんのHPで見つけたので紹介します。
上虚下実とは、上半身の力が抜けていて、下半身が充実していること。虚は、余分な力が抜けていてゆるんでいること。実は、力がそこに集まっていて、張りがあること、を意味している。
また、その状態だと何がいいのでしょうか。
人間の身体は、上半身の力みが抜けてくると、骨盤の中に力が集まり、重心がよってきて、足腰がしっかりとしてくる構造をしている。
重心が骨盤の中に落ちてくると動くときに軸がブレにくくなり、余分なエネルギーを使わないために疲れにくくなる。
また、腰がしっかりすると姿勢がよくなり、視野が広がります。また、胸郭が緩んで広くなり、呼吸もしやすくなる。
成人発達理論とのつながり
この傾向は成人発達理論の後期合理性段階(オレンジ)における弊害に通ずるものを感じます。
自身が生身の人間であることを忘れてしまい、自己の体や心を恣意的に「改革」し、「改造」し、「変容」させようとしたり、あるいは、その限界まで酷使したりしてしまう
」p309から引用
自己の信奉する構想や理念を実現するうえで不都合となる自己の人格の側面や要素を積極的に排除・抑圧する心理的な作用を生み出すことになる。そしてそうして排除・抑圧された人格の側面や要素は無意識化されて意識の外に追いやられていくことになる。
p310から引用
これは言い換えれば、都心部で暮らす多くの人にとって、ビジネスフィールドに最適化するために成長していく・能力を伸ばしていく、ということは、同時に上記でいう後期合理性(オレンジ)段階の持つネガティブな側面が育まれてしまうということでもあると思えます。
どうすればいいのか?
では、どうすれば適切なバランスへとシフトしていくことができるのでしょうか。
プログラムの中ではいくつかのワークが紹介されていました。自身の体を丁寧に観察するであったり、丹田呼吸的なものだったり、横隔膜を刺激するもの、膝などにアプローチするもの、などなど。
それらを抽象化して、ずばり「どうしていけばいいのか?」には言及されていませんが、私なりに解釈すると、今回紹介した三角形・ピラミッドでいう「土台(身体プロセス)に直接・意識的にアプローチをすることを通じて、その上に座している情動・本能、感情・意志を取り戻していく、育んでいく」ことでしょう。
さいごに
自分の経験を振り返ってみると、今回の図でいう自我が、苦しみを感じるだけではなく、その苦しみが閾値を超えるようなものになっていた状態から気持ちや意識が解放されていった時にはいつも集中的な「身体のプロセス」への取り組みがあったように思います。
古くでいえば、高校生の時に硬式テニス部に入り、テニススクールに入るぐらい夢中になり、毎日のように練習していた時が思い起こされます。
実は、それよりも前の小学校3年生から中学校2年生頃まで、転勤などのきっかけによりイジメを受け、精神的に、時には肉体的に痛みを感じ、昔の自分からすると暗黒時代と呼びたくなるような時期がありました。
その暗黒がすっかり晴れたことは、高校でそれまでの友人関係が大きく一新されたと言う意味で生活環境が変わったことも大きかったと思いますが、先に述べた硬式テニスに夢中になったことが情動・本能を取り戻す上では大きかったように思うのです。(その分?それまで無意識に抑圧していた怒りの感情が大きく出たことにより、親を含め色んな人に迷惑をかけましたね 汗 ただ、ああいった歪でも表現していかなければ、発達していかないのだろうなぁと感じます。)
今回、こういう記事を書いてみましたが、せっかくの機会なのでプログラムを学んでいた頃よりも心身についての解像度が高まるように、関連する情報にも触れて学びたいなと思っています。
おまけ
「ガット・ウィズダム」を受けての学びについて書いたものだったり、その他の身体知性にまつわる記事をまとめているマガジンはこちらからご覧いただけます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
