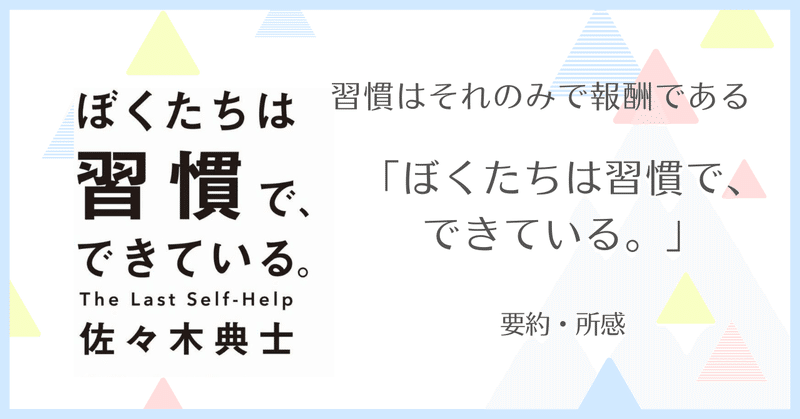
習慣はそれだけで報酬である「僕たちは習慣で、できている」要約・所感
おはようございます。本日は佐々木典士氏著書の「僕たちは習慣で、できている」を取り上げたいと思います。
皆さんは習慣とについてどのようなイメージがありますか?私の中での習慣とは「何か好ましい行為を本人の強い意志のもと、少なくない我慢を強いて身に付けるもの」というイメージがありました。
本書を読むと習慣と意志力の関係性が分かり、意志力が弱くても習慣は身に付けることが出来ると理解できます。
人の行動の45%が習慣でできていると言われています。睡眠が30%近く占めるので、好ましい習慣を味方につけることにより人生の大半は近くは上手くいくでしょう。良い習慣を身につけてより良い人生を送れるように本書から学んだことを以下にまとめておきます。
1. 習慣とは何か。なぜ習慣は難しいのか
本書では「習慣とはほとんど考えずに行う行動」としています。好ましい行動であろうと悪い行動であろうとほとんど意識せずに行動している状態です。逆もしかり、悪い行動をしていない事も習慣といえます。
なぜ私たちは好ましい行動を習慣化することが難しいのでしょうか。習慣化されていない行動は意識や認知が及んでいる状態になります。これらは大脳で制御しているため感情に左右されやすく、不安や自己否定感にさらされると途端に遂行が難しくなります。
人は目の前の報酬を過大評価して将来にある報酬や罰則を過小評価してしまう性質があります。これを行動経済学では双極割引と呼びます。
さらに大脳での制御、認知においては計画的な嘘や自分にとって都合の良い解釈を容易に作り出せるのです。感情、性質、認知これらが習慣へ壁となり私達の前に立ちはだかります。
私達の習慣対する誤った認識もその障壁の1つと言えます。10㌔ランニングしたり、お酒をやめたといった一見するとストイックな習慣を持っている人がいます。すると周りの人は「あの人は志が高いわね」と意志力の高さを理由にしがちです。しかし、これは間違いです。
「習慣が守れる=意志力が強い」ではなく「習慣が守れる=そもそも誘惑されていない」が正しい解釈です。行動に悩みがある時点で意識が呼び出されているのです。繰り返しですが、習慣とはほとんど考えずにする行動です。
また、毎日走るような習慣がある人はそれ自体が懲罰ではなく報酬に置き換わっているのです。運動自体に身体的爽快感や陶酔感を感じることが出来ますし、自分で設定して決めルールを遂行できると自己肯定感が高まります。習慣とは好ましい行動を報酬に書き換える技術とも言えそうです。
習慣は「トリガー」「ルーチン」「報酬」の3つの要素から成り立っています。行動の引き金となる物は何か、その行動は何によって構成されているか(弊害となっているものは何か)、その行動によって自分が得られるものは何か。この3つのを自分の中できちんと把握して整理して設定する。これが出来れば習慣化は一気に近づきます。習慣は意志力ではなくスキルと言えるのです。
2. 習慣を身につけるための工夫
・とにかくハードルを下げる
車輪は動き始めるときに、一番大きい力を要します。電車は動き出したらあとは惰性で走れるし、ロケットの発射直後のエネルギーはその後の80万キロよりも大きいのです。習慣もこれと同様で回すには動き始めの大事なところで出来るだけ邪魔を取り除くことが重要です。
つまり、ハードルをとにかく下げて始めやすくします。腕立て伏せはいきなり10回ではなく1回で良いのす。その代わり必ず毎日行います。10回に設定してできない日があると、自己否定感を抱いてしまうのが人間のです。例え1回でも達成し継続することで自己肯定感と効力感を積み重ねていくことのほうが大切なのです。
・キーストーンハビットをつくる
その習慣によってドミノのように好循環を生み出していく要の行動をいいます。早起きや片付けなどがその代表でしょう。
著者の佐々木さんは「早起きは先鋒であり大将でもある」このことばを心に刻んでいるそうです。早起きはいちばん最初に出てくる先鋒であり、負けてしまうと後の習慣も崩れて立ちいかなくなる大将でもあるという意味です。一日の始まりの早起きが成功すれば、自己肯定感の連鎖がはじまります。
・毎日やる方が簡単
何かをやめるときは完全に断つ方が簡単なのです。何かを身につけるときはその反対で毎日やる方が実は簡単なのです。週に1回、3日に1回ではやるために意志の呼び出しが必要となります。毎日には選択肢がなく迷いがありません。下げていいのは難易度であって頻度ではありません。
・とにかくやってみよう
やる気とはじっと待って自然に湧いてくるものではありません。やり始めないとやる気は出ません。脳の側坐核が活動するとやる気が出るのですが、側坐核は何かやり始めないと活動しないからです。とにかくやってみようは脳科学的にも根拠があるのです。
3. 習慣を味方にするマインドとは
・成長を報酬にしない
好ましい行動をくり返すことに対する報酬を「自己成長」にすると実は上手くいきまん。なぜなら、成長とは分かりやすく右肩上がりで順調に上がっていくものではないからです。
成長とは習慣を地道に積み重ねていくと、いずれ何処のタイミング(多くは突如として)で目に見える形で自覚するものです。これをブレイクスルーといいます。よって成長をモチベーションとしていると続きません。継続する為には報酬を成長ではなく行為自体の中に見つけだすことが大切です。
・既に身についた習慣がご褒美になる
習慣にさえなれば走る行為自体からも報酬があるとは先に述べました。日記を付けることも、はじめは何を書いていいか分からず苦労するものです。しかし、習慣となってしまえば書くこと自体が自分の思考整理となったり、発散の場としてプラスに働く機会となるのです。
・努力と我慢を分けて考える
努力は支払った代償に見合った報酬がしっかりとあること、我慢は支払った代償に対して正当な報酬が無い事としています。努力による報酬は自分自身の基準で良いのです。あなたが自分で身につけて獲得した習慣の報酬はあなたが決めていいのです。
・センスと才能を分けて考える
センスとは習得するスピードのこと。才能とは継続した結果、身につけたスキルや能力。同じ経験をしたとしてもそれをたし算でしか積み重ねていけない人がいます。一方で掛け算のように素早く結果に到達できる人がいます。センスがあるとかけた労力に対して成長の割合が高くなります。たとえ、センスがなくても諦めずに継続していればたし算でもいつか同じスキルや能力、つまり才能にたどり着く事ができるでしょう。
習慣には応用力があります。私達の生活は習慣のあつまりに過ぎません。誰かの習慣をそのまま移してもうまく行きません。一番大切な事は自分で考えて設定して実行することでしょう。
所感
習慣について学びました。私自身は現在自分で決めている習慣は平日の早起きと読書、朝の15分散歩、そしてこのnoteの投稿です。当然私には持って生まれた文章書くセンスはありません。よって掛け算ではなく足し算になりますが、それでも一つずつ積み上げていくことは可能です。いつかブレイクスルーすることはあるのでしょうか。あまり期待はせず書く事自体に楽しみを見つけていこうと思えました。
それ以外に本書読んで自分でも実感している事があります。それは自分で決めたことをきちんと遂行していると不思議と自己効力感が湧いてきて1日を気分良く過ごせるということ。反対にやる気がなかったり何かにイライラしてしまう日を振り返ってみると朝の習慣が守れていなかったりします。キーハビットをしっかり守るだけで報酬として気分の良い1日が貰えるのです。習慣はノーリスクハイリターンの投資と言えそうです。皆さんもまずははじめてみましょう。
より詳しく知りたい方は是非手にとって読んでみてください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
