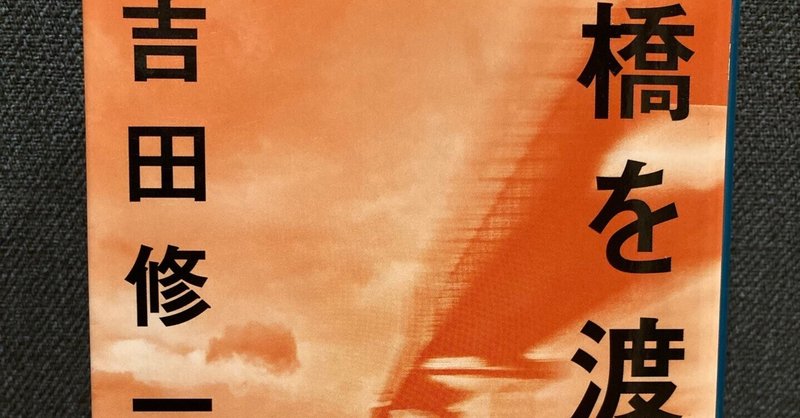
【作品#35】『橋を渡る』
こんにちは、三太です。
学期末が近づいてきました。
3学期の百人一首大会に向けて、国語の授業で百人一首を行っています。
生徒は例年以上に楽しんで取り組んでくれています。
こちらも間を置きながら、読むのを楽しんでいます。
今年度は、五色百人一首で導入をしたのが良かったのかなと思います。
では、今回は『橋を渡る』を読んでいきます。
初出年は2016年(3月)です。
文春文庫の『橋を渡る』で読みました。
あらすじ
2014年の東京。
まずは3人の男女の視点で物語が紡がれます。
一人目はビール会社の営業課長の明良。
二人目は都議会議員の妻、篤子。
三人目はテレビ局の報道ディレクターの謙一郎。
三人はそれぞれに性、不正、罪の問題を抱えています。
この何の関わりもない三人を貫くのが2014年の東京の状況。
本書は当初週刊文春に連載されたものであり、その当時(2014年)の時事的話題が物語にも大きく影響しています。
そして三人の視点が描かれたあとに突如現れる70年後の日本。
サインと呼ばれる人間の細胞から生まれたクローン人間など、そこには2014年当時から想像される未来の世界が描かれます。
その70年後にタイムスリップしてしまったのが謙一郎です。
2014年とこの70年後の未来がどう関わっていくのかが本書の読みどころです。
公式HPの紹介文も載せておきます。
ビール会社の営業課長、明良。
部下からも友人からも信頼される彼の家に、謎めいた贈り物が?
都議会議員の夫と息子を愛する篤子。
思いがけず夫や、ママ友の秘密を知ってしまう。
TV局の報道ディレクター、謙一郎。
香港の雨傘革命や生殖医療研究を取材する。結婚を控えたある日……
2014年の東京で暮らす3人の選択が、
未来を変えていく。
出てくる映画(ページ数)
①「戦場のメリークリスマス」(pp.429-430)
現在の師団に配属された直後、響は東アフリカの紛争地に派遣された。ここで響たちの部隊が他の同盟国の兵士たちと共に担当したのが捕虜の監視だった。収容所の捕虜のなかにはもちろんサインもいた。(中略)
この収容所で流行っていた百年前の日本映画がある。「戦場のメリークリスマス」という作品で、当時人気のあったデビッド・ボウイというロック歌手が演じるイギリス兵が、日本の捕虜収容所で拷問され、生きたまま土中に埋められる。
今回は1作のみでした。
感想
初読ではSFのような展開に戸惑いましたが、今回、再読して未来と現在の繋がり、未来への想像力をとても楽しめました。
それには映画をずっと見てきた効果もあるのかなと思います。
例えば、タイムスリップできる場所として「見知らぬ赤い荒野の風景」というのが出てくるのですが、これはどこかスタンリー・キューブリックの「2001年宇宙の旅」の映像を思い起こさせます。
ただただ荒唐無稽ではなく、つながりを感じられて、面白さが増したのだと思います。
本書では、「夢」と「声(あるいは音)」というのが何度も出てきます。
まず夢についてです。
「罪を犯した夢をよく見る明良(p.55)」、「嫌な夢を見る篤子(p.231)」、「土を掘る夢を見る謙一郎(p.353)」と3人の視点それぞれで夢が出てきます。
そして70年後の未来では、「ブレインシネマ」という自分の夢を映像で見られる装置(p.410)が開発されているのです。
夢の内容を読んでみたら、謙一郎の夢で出てくる謎の男と未来の世界のサインである響が少しつながるように思えました。
「逃げないほうが安全」という夢の言葉はそのまま未来のサインの状況に当てはまります。
と考えるなら、おそらくこの夢が何度も出てくるということは、現在と未来をつなぐ潤滑油のような働きをしているのではないかと思いました。
このつなぎがないと、未来の登場にあまりにも唐突感が出てしまうのではないかということです。
もう一つの声についても見て見ましょう。
「声で満たされた明良と真沙のセックス(p.126)」、「太鼓の音に満たされる謙一郎(p.380)」と声あるいは音に関して特徴的なシーンが出てきます。
こちらも未来との関係で考えられればいいのでしょうが、ちょっとそこまでは考えられませんでした。
しかし、特に篤子のパートで大きく問題となる2014年の問題、都議会のセクハラヤジ問題には声が大きく関係すると思いました。
まさにヤジが声ですし。
いずれにせよ「夢」、「声(あるいは音」は象徴的に使われており、そこからさらに意味を引き出せそうに思いました。
本書では70年後の未来と、そこまで描かれてきた2014年の3人のパートが絶妙につながっていき、そこを読み取っていくのも大きな醍醐味だと感じました。
山眠り70年を夢の橋
その他
・明良のパートで、吉尾健一という吉田修一さんを思わせるような小説家の登場人物が出てくる。
以上で、『橋を渡る』の紹介は終わります。
再読で改めて良さを感じられた作品でした。
では、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
