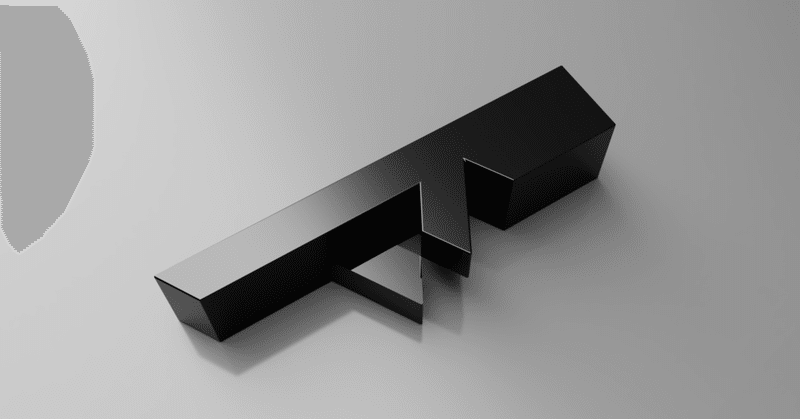
いま知っておきたい霊魂のこと 正木晃
お世話になってる方から勧められた本。自分ではなかなか手に取らなかっただろう本、ということをおそらく見越して勧めてくれた本で、自分の宗教観にはない視点を示してくれていて、自分の立ち位置を俯瞰することができる良書でした。
著者は研究者の方ですが、歴史的な文脈から身近な幽霊やドッペルゲンガー、憑依などの話題まで、霊魂に関する話題が幅広く盛り込まれとても読みやすい内容です。日本の霊魂観を知る上で非常に勉強になりました。
ちょっと笑ってしまったのですが、最後に著者自身が、研究者として一線を超えてしまったかもしれない、それでもよかった、と回顧しているように、今まで仏教界からもタブー視されていた「霊魂」について真正面から肯定的且つ平易に論じてくれています。
文化的な植民地精神から脱却しようという気運が高まりつつある(気がする)日本で、素直なありのままの感覚を意志を持って表現するような一周回ったラディカルさが刺激的です。また同時に明治以降近代化の中で日本の仏教が手放してきたものを明らかにしてくれています。
一寸の虫にも五分の魂、山川草木悉皆成仏という風に、日本人は森羅万象に霊魂があるという立場を取ってきました。霊魂の存在を前提としたうえで、葬送儀礼が営まれてきました。従って霊魂を前提としない葬儀などは意味がないというのが本書の立場です。
しかし、正直に言えば、僕自身「霊魂」という言葉を真剣に考えたことはありませんでした。というよりそもそも考える発想を持っていませんでした。墓参りをしてもそこにいるような感覚はなかったですし、お盆に山から祖霊が帰ってくるとか、そんな風に感じたこともありませんでした。あくまで自分の心の中に存在するものという感覚です。ディズニー映画のリメンバーミーの世界観です。記憶から消えてしまったものは2度目の死を迎え、無になってしまうという感覚でしかありませんでした。
だから忘却は、自分の起源を忘れてしまうことであり、それこそ祖先への冒涜のような感覚がありました。私たちはどこから来てどこへ行くのか。良くも悪くも、自分の中に両親や祖先がどう生きているか、彼らの辿った足跡を訪ね、それと重ね合わせることで自分を見つける行為、それが死者との繋がりでした。そして、その繋がりによって今の自分が存在できることに対し、心の内で感謝し静かに内省する行為でした。もし仮に彼らの中に何か後悔があったとしても、自分はそれを乗り越えて生きていくことが、自分を生んでくれた彼らへの最良の慰めであるという感覚。つまり、簡単に言えば、よりよく生きることが祖先への手向けという感覚でした。葬儀にしても自分の中の故人の存在を現象学的に強く感じられる装置ではあっても、霊魂ということについては考えたこともなかったというのが正直なところです。
だからこそ、墓を作る立場の人間としては、自分の中に、それを前にした人に、どう不在者の存在を感じさせるかということについて腐心してきたのかもしれません。
だから本書で批判的に書かれている「お葬式は、亡くなった方のためではなく、のこされた方々のためだという理屈」は、自分自身も特に疑いなく依拠する理屈でもありました。これまでにも本などで葬式は死者のためのものであるという主張は聞いたことはありましたが、ずっと腑に落ちませんでした。本書によれば、この考え方は近世か近代になってから考え出された理屈にすぎず、そうとうに無理があると書かれています。この理由に関しては本書では詳述されてはいませんが、社会的な背景要因としては、明治になって仏教がヨーロッパの思想の影響を受けたことで、仏教を哲学として捉える仏教学が隆盛し、それまで肯定していた霊魂を一転して否定するようになったという経緯があるようです。
また、本書の他の箇所で、葬式で神懸かり状態になってしまった参列者に対応する際、一番悪質なパターンは仏教を思想や哲学だと言っているお坊さんだというくだりがあります。前述の葬式を残された人のためだという理屈を持つお坊さんと同様に、仏教を思想や哲学だと考えるお坊さんは霊魂を前提にしていません。つまり、極端に言えば、喪失感に苛まれ、精神的に不安定な状態である人に対し、ただ共感を求めているだけの彼女にアドバイスする彼氏みたいに内省的な解決を求めようとするのかもしれません。しかし、あくまで行っているのは葬儀、つまり故人を送り出すとともに遺族がお別れする儀式であり、そして何より相手にしているのは人間だということです。本書の冒頭に「霊魂の存在をみとめたほうが、みとめないよりも、人はずっと幸せに生きられるという立場をとっています。」と書かれていますが、確かに現場での喪失感に哲学は役に立たなそうです。死を前にして論理的な正しさは無力なのです。だから仏教学としての哲学的側面と、葬儀などの民衆に対して担ってきた儀礼的側面とは分けて考える必要があります。
私たちは近代を経て科学的な思考を身に付け、死後も肉体は違う分子となって地球に還っていくと知っていても、死は理屈抜きに絶望的で、言葉にならない喪失感に覆われて、ただただ悲しいものです。だから、それに対処するために「霊魂」という概念を前提にすることが、ヒトが長年かけて生み出した知恵だということが本書の重要な主張です。
これは自分にとって非常に重要な指摘でした。僕は恥ずかしながら、この歳までそんなことを考えたこともなかったのでした。確かに、遺族の想いに寄り添う時、いかにその人が遺族のことを考えていたとしても、亡くなった人を死後の世界に送り出すことに対し、霊魂を前提にしない場合は「本気であること」ができません。故人を送り出すことに本気であることができないということは、胸に手を当てて考えてみれば、厳密にはどこかで弔っているフリになってしまうということです。本書ではおそらくそういう意味で、生きている人のための葬式という理屈を掲げるお坊さんはおざなりであることが多いと言っているのでしょう。
ただ、個人的には霊魂という考え方は、一定の合理性があるにせよ、なかなか急にしっくりくるものではないのが正直なところです。ましてや人生100年時代で不遇の死の少ないかつてない長寿命社会においては、霊魂という概念の出番もそれほど多くはないような気がしています。かつて墓や仏壇や山などに霊魂を見出す感覚は、霊魂が荒魂や和魂のように恐ろしいものである一方で大切なものであるという相反する要素を同時に含んだものだったからだと本書でも書かれています。その結果、霊魂は普段は遠くにあって、お盆などに時折帰ってくる存在になりました。そして個性を失い安定した状態になっていきます。ですが、現代では手元供養などの葬法が生まれ、距離が格段に近くなっています。それは経済的な変化や住環境の変化もありますし、核家族化、少子化の影響もあるでしょう。繰り返しにはなりますが、女性87歳、男性81歳という平均寿命もあるでしょう。いまや不遇の死どころか、20年30年にも及ぶ長い老後をどう生きるかという不安が生じている時代です。現世に未練を残した霊魂は格段に減っているはずです。ちなみに僕は自宅用の墓を作っているので、近くにあって良いという考え方です。少なくとも死者を恐れる感覚はありませんし、前述のように、忘れるべきではないと思っています。もっと言えば、自身の変化と共に新しい故人を発見していくべきとさえ思っています。また、メメント・モリではないですが、死を意識して生きる方が後悔なく生きられると思っているからです。緑と光が溢れる霊園が溢れ、平均寿命50歳の頃には考えられないくらい死が遠くに行きました。葬送儀礼が簡略化する中、もう少し身近にあっても良いという考えです。少々話が逸れましたが、従って霊魂という考え方はどんな状況で亡くなったかによってその作用は変わってくるように思います。なので、本書にもあるように、東日本大震災や今回の石川の地震などの天災、事故や病気など不条理な死に対しては、霊魂が心を救ってくれることも多いはずです。
最後に改めて確認しておきたいことは、著者自身、「霊魂の存在をみとたほうが、みとめないよりも、人はずっと幸せに生きられるという立場」、「立場」と言っているように、近代以降、科学的な方法論に基づいて生きている私たちが、合理主義的な発想に基づいてプラグマティックに思考した結果、霊魂がある方がよいと結論づけているということです。私たちはシャーマンのように無邪気に霊魂を信じることもできないし、合理的だからという理由で遺体をゴミ箱に捨てることもできません。本書を読んでひとつ思ったのは、霊魂に肯定的か否定的か、葬儀は生きている人のためか死んだ人のためかという風に、図式的に見るべきではないようには思いました。簡単にどちらと言える話ではありません。葬儀の場面では霊魂を肯定することで救われる人がいるでしょうし、日常においては仏教学が持つ理論的な展開が人を救うこともあります。踏み絵を踏むことで神の声を初めて聞くロドリゴのように、何が優先されるべきかは常に問う必要があります。
自分自身、現代アートを志して、その流れの中で葬送儀礼に興味を持ってお墓を作りだした経緯があります。アートは感じて考える場を提供します。葬送儀礼も似たところがあります。喪失は極めてつらい体験ですが、葬送儀礼も感じて生き方について考える側面があると思っています。その点で、僕はアート作品のように現象学的に、感覚と思考を連動させるものとして、お墓もまた、色、形、空間、時間を組み立てることができるという考えに基づいてデザインし、制作しています。しかし、そうした経緯で始めたことであるが故に、自己表現として始まったところも正直ありました。だから喪失という極めて辛い体験がもたらす感情を、どのようにケアできるかは自分自身どれほどわかっているのかは不明瞭な部分もありました。
それは今も勉強中ですが、そんな自分にとっては、死という体験の根本を気づかせてくれる非常に素晴らしい本だったことは間違いありません。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
