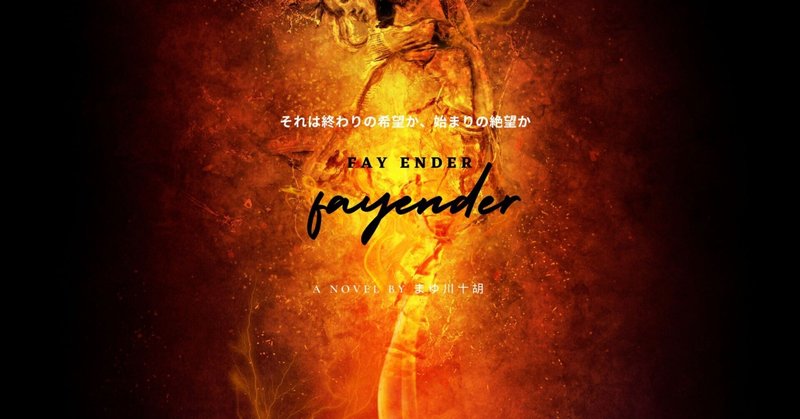
fay ender ⑦【本格ファンタジー小説】第一章 異能の者「1-3 月夜の麗人③」
第一章 異能の者
1-3 月夜の麗人③
(前作1-2 月夜の麗人② のつづき)
少しでも襲撃者たちから遠く逃れようと、岩場を歩き続けたが、とうとうベヒルが負傷した足首の痛みに耐えきれず、音を上げた。
岩に座らせて僧服をめくってみると、右の踝辺りが二倍の太さに腫れ上がっていた。
フィオランは舌打ちして、辺りを見回した。
こんな石灰岩だらけの不毛な土地では、腫れを取る薬草など生えてもいない。
歩けないのなら、自分が背負っていくしかないのだ。
起伏が多く、足場の悪いこの台地を。
無言で背を向けてしゃがみこみ、ベヒルの腕を肩へ担ぎ上げる。
されるがままのベヒルは、口が利けないくらい驚いていた。
痩せこけた体はそれほど重さを感じず、楽に立ち上がる事が出来た。
それでも、人を一人背負っての岩山下りは大層骨が折れる。
徐々に息が切れて一息つこうと立ち止まったとき、前方の岩陰から例の不思議な女が姿を現した。
さきほどベヒルが痛みで行軍から脱落した際、振り返る事なく歩き去ってしまったので、ただの行きずりの縁だったかと溜息をついたばかりである。
それが戻ってきてくれたとあって、正直ほっと安堵もし、喜んだ。
「その坊さんを降ろせ。足を見る」
女はぶっきらぼうに指図をした。
フィオランはなんて口の悪い女だと内心呆れるが、言われたとおりにベヒルを岩の上へ座らせた。
女が凄まじい能力者だということは、さきほどの立ち回りで嫌というほど見せつけられているので大いに期待した。
ところが、ベヒルの足下に跪いて、革袋から取り出した物はただの薬草であった。
「……なんだ?」
折れそうなほど細い足首に、石で叩いて磨りつぶした草を貼り付けながら、女は顔を上げずに尋ねた。
不満そうな空気を敏感に察したのだろう。
フィオランは珍しく口ごもりながら頭を掻いた。
「いや……。ついさっきみたいに、何かこう見事な魔法でパパパパーっと治すかのかなと」
「傷や怪我を魔術で治せる人間がいたら化け物だろう」
「いや、あんた充分化け物……っと。ちょっと期待しちゃってさ。さすがに都合良すぎだな」
うっかり失言しそうになって、愛想良く笑ってごまかす。
ここでもまた、人好きのする好青年といった仮面を被りだした。
「わたしは魔法など使ってはいない。これも歴とした薬草学から学んだことで、この先の岩の切れ目から採ってきたものだ。磨りつぶして患部に貼り付けておけば、腫れも痛みも和らいでくるだろう」
「あ、ありがとうございます」
石膏のような白い手で手当をされ、ベヒルは顔を赤らめながら礼を言った。
「『母の手』と呼ばれる野草だ。割とあちこちで自生しているから知っているだろう。こんな台地でも、大きな岩の割れ目にひっそりと生えていることがある。これを朝になったら、また磨りつぶして貼るといい」
女は、両の掌一杯ほどの野草をベヒルへ手渡した。
「そんなにたくさん、月明かりがあるとはいえ、暗い岩場でよく見つけられたな。それもやっぱり魔法かい? あんたは数少ない異能者(サイキッカー)の一人なのか?」
フィオランは女への興味が抑えられず、不躾に尋ねてしまった。
女はやっとフィオランの方へ振り向き、月明かりを受けて仄かに煌めく銀色の双眸をじっと注ぐ。
その透明な視線をまともにくらい、フィオランは身の内でざわめくものを感じ取った。
女はフィオランの視線を捉えながら、ゆっくりと言った。
「この世に魔法なんてものは存在しない。世界中の人間が異能者(サイキッカー)と呼ぶ人種は、普通の人々が使いこなせていない、ある一部の脳の使い方を知っているだけだ。すべて理の範疇で起こしている現象だ。おまえは勘違いをしている」
「普通の人間である俺たちにとっては、理の範疇も魔法も違いなんてわからないのさ」
初対面の、しかも若い女におまえ呼ばわりされたのは初めての経験で面食らったが、不思議な事にさほど勘に障らなかった。(イアンの時とは違って)
あまりにも自然な口調だったせいか、それとも落ち着き払った女の堂々とした態度に嫌味がなかったせいか、自尊心の強いフィオランにしては珍しい事であった。
「あんたは面白いことを言うな? そんな説は初めて聞いたぜ。ダナー正教会の坊さん方がそれを聞いたらなんて言うかな? 教会がお抱えの異能者軍団は、ダナー神が遣わされた神の手足とされているようだぜ」
「フィオラン、不謹慎だよ」
ベヒルが表情を曇らせて話を遮ろうとした。
その集団の存在は、正教会の陰の部分である、布教に伴った軍事政策に深く関わってきた歴史があり、人々は禍を恐れて彼らについて無闇に語る事を憚る。
「彼らもまた、理というものを誤解しているのさ」
ただただ静かに語る女に、フィオランは強烈な興味を抱いた。
麗しい容貌以上に、女が持つ佇まいそのものに妙に気が惹かれるのだ。
他人に個人的な関心を抱く事にブレーキをかけていたのに。
「……あんた、名前は? なんて呼べばいい?」
女は長いこと黙っていたが、やがて簡潔に答えた。
「ヴィー」
本名か?
疑問を抱くフィオランをよそに、ベヒルが律儀に名乗っている。
女は相槌を打っていたが、大して興味もなさそうな態度で辺りを点検し始め、適当な場所で腰を降ろした。
体に厚手のマントを巻き付け、皮袋を枕にそのまま横になってしまうので、二人は戸惑った。
「ここで眠るのかい?」
フィオランに声をかけられ、女は億劫そうに答えた。
「直に夜明けだ。今眠らなければ、明日身が持たない。場所など構っていられないだろう」
女が休んでいた快適な場所に降って湧いて、追い出してしまったのは自分たちであったことに、遅ればせながら思い至った。
そういえば、助けられた礼もろくにしていない。
「悪かったな……その、色々と世話になってしまって」
女は何も言わず、早々に眼を閉じてしまっている。
「俺たちもここで休んでもいいかい? どうせこいつは動かせないし」
「好きにすればいい」
本当はもっと聞きたい事があったのだが、女にここで終わりと態度で打ち切られて、フィオランも引き下がった。
しかし謎めいた女である。
歳の頃は二十代後半か?
自分より年上なのは確かだろう。
まだ若い美貌の女が、人生経験を豊かに積んだ老年期の人間のように落ち着き払っているのが、アンバランスといえばアンバランスだった。
口を開けば、不遜ともいえる独特な話し方で、反論があってもうっかり引きずり込まれてしまう。
口数は少ないのに、説き伏せられてしまうような凄味があった。
大体、若い女がこんな人里離れた不毛の台地を一人彷徨っていること自体、異様であった。
しかも岩場だらけの地面を寝床にして、平気な顔で眠っている。
いかにも旅慣れた強者といった様子だ。
「……変な女だな。美女なのに」
隣でベヒルが奇妙な声を出した。
慌てて口を押えているが、目を剥いてフィオランを窺っている。
「なんだよ?」
不機嫌に眉を顰めると、ベヒルは精一杯声を潜めて言った。
「男の人じゃないの?」
「はあ?」
フィオランは更に不機嫌になって、ベヒルの顔をまじまじと見つめた。
「男だよ。信じられないくらい綺麗だけど、どう見ても男の人だ」
「おまえの目、どうかしてるんじゃねえのか?」
背が高すぎるが、どう見てもあれは女だろう。
大体、マントを羽織る前に露わになっていた体の線が豊かな曲線を描いていた。加えて、風に乗ってかすかに感じ取れた匂いは、決して男のものではなかった。
フィオランは旅人の方へ再び目を向けた。
岩の陰になって、姿は黒い塊でしか判別がつかない。
隠された姿をもう一度思い返してみる。
「おまえ、当の本人にその発言が届いてみろ。間違いなく、朝目覚めたときは、この世でなくあの世だな」
自信を持って、そう断言した。
~次作 「1-4 月夜の麗人④」 へつづく
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

