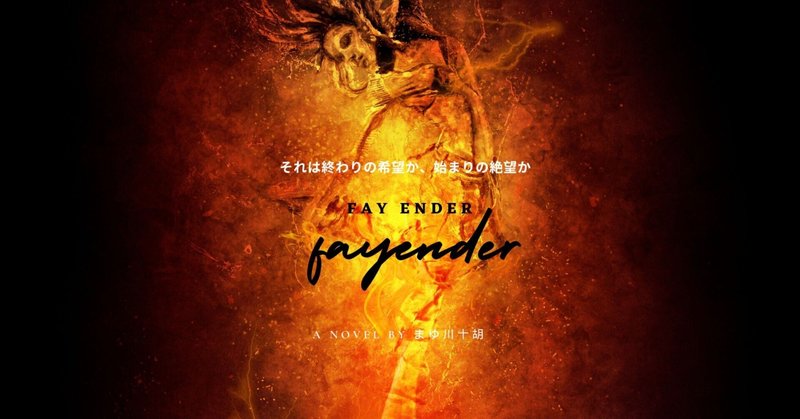
fay ender ㉖ 【本格ファンタジー小説】第四章 血の絆 「4-4 滅びの淵」
第四章 血の絆
4-4 滅びの淵
(前作 「 4-3 女伯の恋 」 のつづき )
ラダーンの王宮は王朝開闢以来、五百年の長きに亘って黒鳥宮と呼ばれ、世に名高い。
王宮自体が両翼を大きく広げた形となっており、宮殿内部の装飾をほとんどを黒曜石で造作しているため、この名がついた。
その左翼に当たる、王家の私的な居住空間となっている奥宮に王太子の居室がある。フィオランが療養している部屋とは目と鼻の先の近さであった。
エリサに支えられながら、白く光沢を放つ絨毯の上を歩いていく。
見事な彫刻を施された重厚な扉の両脇には近衛兵が屹立していたが、エリサの目配せを受けて恭しく扉を開けた。
三間続きの部屋であった。フィオランが寝かされていた部屋も立派であったが、その豪奢さは比較にもならない。
二人の突然の来訪に、前室にいた侍従らしき男が慌てて飛び出し、フィオランの行く手を遮った。何やらもごもとと囁かれたが、衰弱しきった体でどこにそんな力が残っているのか、不思議なほどの力で侍従を押し退けた。
目当ての相手は最奥の寝室にいた。
天蓋付きの大きな寝台に、立ち枯れた木のような痩せ細った身体が埋もれている。いつか視た、エリサの映像そのままであった。
明らかに重篤の病人であるその人は、押し入ってきた相手を見てはっと起き上がった。そして傍らで付き添うエリサへ非難めいた視線を送る。
無言の叱責を受けて、エリサはあえて言い訳をせず目を伏せた。
フィオランは深く息を吸い、吐いた。激情を抑えるためだった。
「王太子殿下―――ネイス。それともお兄様。一体どう呼べばいいんだろうな」
「どれでも好きなように、フィオラン」
亜麻色の髪に縁どられた顔は、より一層痩せこけたようであった。
頬骨が痛々しいほど突き出てすっかり面変わりしてしまったが、それでもその髑髏じみた顔に宿るふたつの強い光が、唯一彼の生命力を感じさせた。
薄い青の瞳だけは、まだ知性と生きる情熱を失ってはいなかった。
「聞きたいことは山ほどある」
「わかっているとも」
「本当にそうか? 俺がどこまでこの大層な茶番に気づいているのか、
あんた本当にわかっているのか? 首謀者は誰だ。あんたか? 国王か?
それとも………そこに隠れているヤツか?」
フィオランの口調にはっとしたエリサは視線を辿って、顔を顰めてしまった。書斎へと続く入口の陰から現れた人間を見たからだった。
鉢合わせをするのに、これほど間の悪いことはない。
「俺があんたに気づかないとでも思ったのか? ヴィー」
腰まで届く長い黒髪に、すっぽりと外套を身に纏った黒ずくめの格好。
白と金で統一された室内に、夜の使者が訪れたような趣きでひっそりと彼らの前へ現れた。
その星のように煌めく双眸が、今は鈍い灰色の光を放ってフィオランを見つめている。
「あの頭のイカレた坊主に痛めつけられて以来、どうも神経過敏になっていてな。目を瞑っていても物は見えるわ、めっぽう地獄耳になっているわ、
嗅覚だって狼どころか熊並みだぜ。あんたの匂いぐらい、とっくに嗅ぎ分けていたんだ」
言葉は冗談めいているが、その緑の眼は鬱屈した怒りで黒ずんでいた。
「まさかあんたまで片棒を担いでいたとは、さすがに気づかなかったぜ。
どこの世界にも属さない本物のさすらい人だと畏敬の念を払っていたんだが、とんだ勘違いだったな。結局あんたも損得で動いていたってわけか。
それとも、王家の手飼いにでも成り下がってるのか?」
言葉を選ばないフィオランの激しい攻撃にひと言も反論せず、ヴィーはただ見つめ返すばかりであった。
「誰に頼まれたんだ? 国王に金でも積まれたのか? それともこの王太子に泣いて縋られたのか? 偶然を装って俺に近づいて誑しこめと?
十分に油断させて力をうまく引き出した後は、敵だか味方だか知らないが、正教会の連中へ餌を投げ与えたってとこか? 俺を絶望のどん底に突き落として痛めつければ覚醒するとでも思ったのか? ところが、筋書きに反して俺は覚醒しなかった。大した誤算だったよな」
「フィオラン、違う。そうではない。彼はどこにも属してはいない」
「信じられるかよ、ネイス」
寝台から下りた王太子へ、フィオランは皮肉たっぷりに言った。
「レンティアの塔で正体を名乗りでなかった人間の言うことなど信じられるか。儀式に立ち会うことを強要されたんだろうが、あんたも俺の力を当てにしていたのには違いないはずだ」
病の治療と恐らく人質の意味も兼ねて、王太子は長らくあの大僧正の牙城へ捕らわれていたのだろう。
長年に亘り、大僧正と確執の関係にあった国王は、フィオランという存在を使ってその確執に終止符を打とうと画策したに違いない。
そうなると、自分と王太子は正教会潰しのネタという役割で、あの場で覚醒に至らぬことは最初から分かっていたとも考えられる。
どこまでが人の作為が絡み、どこまでが偶然なのか、疑い出すとキリがなくなってきた。
「相当重いんだろう? 正教会の医術でも手に負えないほど、しぶとい病気なんだろうが。素直に言えよ。火山が噴火だ、国の存亡に係るだの御大層なことを言ってくれるが、本当は自分が生き延びたい。ただそれだけのことなんじゃねえのか」
「それだけのことですって?」
フィオランを支えていたエリサが、それ以上耐えきれずに声を震わせた。
「滅亡の危機に晒されている国を前にして、日に日に衰弱して無力に死んでいくしかない身を、それだけのことと言うの?」
「火山噴火なんていう天変地異には、どんな人間だって無力だろう」
鼻で笑ったフィオランへ、エリサは激しい眼を向けた。
「この方は王太子なのよ。国土がどんなに荒廃しようとも、その先の国の行く末を導かなければならない方なのよ。全国民に対して保護を与え、その責任を負わなければならない方なのよ」
「まだ言うのか? それを。大義名分なんてどうでもいい。本音を言えよ。
どいつもこいつも、綺麗事ばかり並べ立てやがって嘘八百だらけじゃねえか。まったく俺をとことん馬鹿にしてやがるぜ。いいか、俺は物を入れておくだけのただの器じゃねえんだ。ちゃんと意思もあれば、感情もある人間なんだぜ。俺をどうこうしたいんなら、俺の胸にずしんとくるまで納得させてみせろ! 上っ面の弁解ばかりで人の心を動かせるか!」
「その通りであるな」
部屋の隅々にまで響き渡る、厳めしい声が響いた。
振り向くと、応接の間からいつの間にか人が数人入ってきていた。
アーネス・ラムトン子爵に付き従われた、年老いた人物を誰かと問わずともひと目でわかる。
ラダーン国王スタフォロス四世。
王冠こそ戴いてはいないが、琥珀色の貂の毛皮で縁取りされた暗緑色の外套を肩へ掛け、金と黒曜石で象嵌された腰帯を嵌めた贅を尽くした姿。
乾ききった灰色の肌に、彫りの深すぎる目元。年老いた猛禽類を思わせる容貌のうえ、奥まった眼から放たれる強い眼光は相手を圧倒するほど威厳に満ちている。
大僧正ホスローの狡猾な威圧とはまったく違った、為政者としての静かな迫力。だがその眼差しには、血を分けた息子に対する情愛は微塵も感じられなかった。
「あんたが俺の親爺か」
簡潔明瞭にこれを挨拶代わりとしたが、侍従長はこの態度に色を成し、アーネスは相変わらずといった具合に苦笑した。
親子の情など湧かないのは、フィオランも同様である。
スタフォロス四世は、自分とは似ても似つかない青年をじっくりと観察し、再び口を開いた。
「………母親に似ておるな」
「始末し損なった妾を覚えているのかい」
「そなたは何もわかってはおらぬ」
王は言下に切り捨て、言い募ろうとするフィオランを目で制した。
「そなたが持つ力を欲したのは余だ。余は、そなたの力もそなた自身も欲しい。二十三年前、その力が及ぼす影響を恐れて、そなたを遠く手放そうとし、望まぬ惨劇を生んでしまった。その余の誤りが今悉く報いとなって受けておる。余は長らく判断を誤っていたのだ。そなたが持つ竜の力とは、過去永きに亘り、人力の及ばぬ災厄に出現していたものであった。決して人間ごときの私利私欲のために宿り、遣わされたものではないと知るべきであった」
王が何を言わんとしているのか。不本意ながらフィオランは大人しく聞く耳を持つことにした。
「ラダナスは臓器が正常に働かないという業病に冒されており、もう長くはない。子を望もうにも、子種さえもはや作れぬ。それが明確になった時点で、余はそなたの捜索を決心した。王家を断絶させるわけにはいかぬ。ラダナスを諦め、そなたに王位を継承させるか、そなたを犠牲にしてラダナスを生かすか二つに一つ。王として余はそのどちらも望んだ」
ネイスこと、ラダナス王太子は複雑な表情を浮かべていた。王家存続のためだけに己の命運を見限り、レンティアの塔へ従順な患者を装って治療へ赴いた事が真実のすべてではない。
ただ言えることは、王と王太子ぐるみで大僧正をうまく利用し、失墜させる口実を作ったことだけは確かだった。
「それに加えて、千年に一度といわれるタルル山の噴火。それはラダーン王国の滅亡を意味する」
陰鬱な呟きに、室内にいるラダーンの人間たちはぞくりと鳥肌を立てた。
その暗い事実を誰もが極力考えまいと、隅に追いやってきたのだ。
「もはや王位継承どころの問題ではない。気が狂わんばかりに悩む余の元へ助言をしに来た者がいたのだ」
王の視線の先にヴィーがいた。
「ラダーン王家の古き知恵者。この世を永劫に渡り歩くさすらい人。五百年の長い歴史の中、ラダーンの歴代の王は有事の際には必ずその助言を受けている。現に余が幼き頃に、先の王は西域への、特にモーラの扱い方を彼に尋ねていた。いずれ、モーラとの婚姻が必要になると、わが王家へ勧めたのは彼だ」
フィオランは手が震えるのを感じた。
自分の与り知らぬどころか、到底手の及ばぬ次元で運命を決められていたことを知り、言いようのない虚しさが黒々と体の中に広がった。
不信の塊りとなったフィオランを、王はあえて直視して言った。
「竜の目は、この未曽有の災厄に対して最後の防波堤となり得る。それだけの力を秘めているという予言を余は信じた。
そなたの目覚めを余は審判と受け止め、座して待つ。覚醒を果たさぬのなら……その時は余の――それがこの国の運命なのであろう。
甘んじて受け入れるしかない」
自分を支えるエリサの震えが、密着した身体を通して伝わってくる。
フィオランは大声で喚き、暴れ出したくなった。
我知らず歯軋りが漏れ、それを真下から見上げるエリサの必死の形相。
その縋りつく眼を通して、声にならぬ言葉が強引にフィオランへ流れ込んでくる。
殿下を助けて――――!
エリサの心には、ただそれだけの一念しかなかった。
噴火や国家の命運などどうでもいい、ただラダナスの命だけを狂おしく望んでいた。
酒場でフィオランの胸を打った唯一の映像。
ラダナスへの一途な愛を知り、フィオランはこの女とラダーンへ興味を持った。それがラダーン行きの決心にも繋がったのだ。
青い眼を覗き込みながら憐憫の情を催した。
望みのためなら悪魔に身も心も売り渡してでも叶えようとする執念。
それが愛であっても権力であっても、人間の身勝手な欲には変わりはない。
そのためには相手を苦しめ、犠牲にすることも厭わず、その結果露呈した己の醜さを肯定さえしだすのだ。この王と同じように。
フィオランは、むずかる子供を宥めすかすように優しく言ってやった。
「俺には何もしてやれることはない。何も、だ。噴火を防ぐことも、この国を救ってやることも、ましてやあんたの大切な王太子を生かしてやることも」
エリサの口元が大きく戦慄いた。その口から絶望の声が迸ろうとしたその時。
地の底から巨大な突き上げが起こった。
その場にいた全員が一瞬にして宙に浮き、壁や床へ激突した。亀裂が生じた壁や天井が崩れてくる。
床に這いつくばって頑丈な柱がある部屋の隅に移動した彼らは、壁の一部が崩れて見通しが良くなった外の景色を見て愕然とした。
遠く山裾を広げて聳える山が、どす黒い巨大な黒煙を遥か上空にまで噴出させている。
タルル山の大噴火が始まった。
~次作 「第五章 宿命を終わらせる者 5-1 覚醒」 へつづく
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

