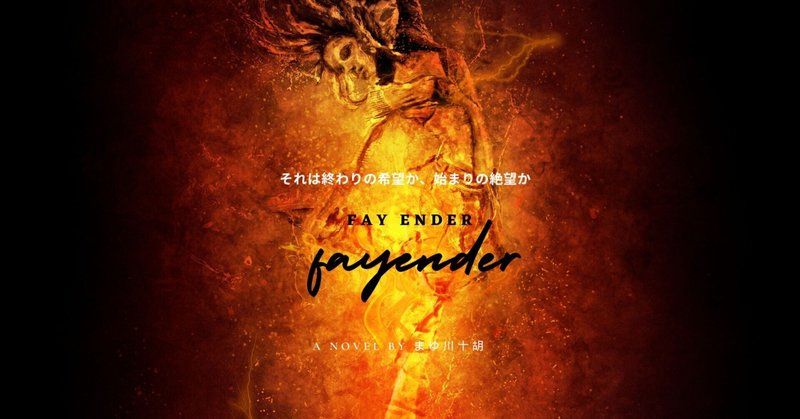
fay ender ⑧【本格ファンタジー小説】第一章 異能の者「1-3 月夜の麗人④」
第一章 異能の者
1-3 月夜の麗人④
(前作1-3 月夜の麗人③ のつづき)
岩と岩の隙間から差し込んだ朝陽に顔を照らされ、フィオランはようやく目が覚めた。
頭を巡らすと、ベヒルが涎を垂らしながら自分の胸元で眠りこけている。
思い切り顔を顰めて、麦色の頭を払いのけた。
拍子に、背中や尻がずきずきと痛む。
おまけに体が冷えて寒い。
震えて体をさすりながら起き上がると、腰が軋んで悲鳴を上げた。
流浪生活が長かったとはいえ、こんな所で装備もなしに野宿をしたのはさすがに初めての経験であった。
はっとして、岩場の窪みに視線を走らせる。
あるのは灰色の岩だけで、肝心の女の姿がどこにもない。
野営した岩場の上によじ登り、辺り一帯を見回した。
東の方角を一望する。
石灰岩の台地は徐々に岩の数も少なくなって、緩やかな傾斜で平原へと続き、白い風景から緑溢れる色彩へと変化していっている。
その台地を四方ぐるりと見やっても、人影一つ見当たらなかった。
行ってしまったか。
フィオランは溜息をついて、ベヒルの元へ戻った。
冷たい岩へ頬をつけて、死んだように眠るベヒルをつま先で小突いた。
「おい、起きろ。いつまで寝てやがんだ」
「ひあ?」
「変な声出すんじゃねえ。涎を拭け、みっともねえ」
寝ぼけ眼のベヒルが、慌てて口元に手を当てた。
「餓鬼の頃から、そのだらしのねえ寝方はちっとも変わっちゃあいねえな」
恥ずかしそうに、そっと口元をぬぐう姿を憐れみながら眺める。
頭が正常に働き出したベヒルは、女がいないことに気がついたようだった。
「あれ、あの人はどこへ?」
「とっくに行っちまったよ。おまえ、この世で目覚められてよかったな」
「だからあの人は男だって」
食い下がるベヒルを無視して、フィオランは怪我の処置に取りかかった。
夕べ、女からもらった野草を石で磨り潰して。
「何だか人間離れした人だったよねえ……。この土地の精霊だったりして」
それもあり得るかもしれない。
ここは玄関口とはいえ、西域だ。
何せ、太古の昔は魑魅魍魎が跋扈していたという伝説があるくらいだ。
そうフィオランも胸の内で考えた。
ラダーン王国への道程は果てしなく遠い。
まずは大陸を網の目のように縦横する街道へ出て、隊商宿で足となる乗り物を確保しなければならない。幸い、旅行客相手に荒稼ぎした儲けを懐へ残したままなので、路銀は十分にある。
街道はもう目視出来るほどの距離にあり、街道にさえ出て平野を跨ぐ森を抜ければ、隊商宿が一件あるはずだった。
目標が間近に迫って、ベヒルを背負うフィオランの足も速まった。
太陽が中天を過ぎ、徐々に近づく街道を小規模の隊商が通過していく。
左手へ西進しているということは、西域中央の各商業都市へ向かうのだろう。
それを目で追い、ふとある一点に視線が止まる。
隊商が通過した後に、黒っぽい塊が三つか四つ残されていた。
何だろうと目を凝らす。
大きな塊が三つと細長いものが一つ。
その場から動きもしない。
じっとその対象に視点を合わせながら、足が更に速まった。
時折、陽炎となってゆらゆらと塊りが揺らいで視力を翻弄する。
やがて背負われたベヒルも気がついたようだった。
「あれ? フィオラン、まさかあれあの人じゃ……」
半刻ほど歩き、互いの姿形の判別がつく距離に迫って、フィオランはぽかんと口を開けてしまった。
間違いなく、夕べの女が立っている。
それも三頭のラクダを連れて。
「あんた……ヴィー? そんなところで一体何を――」
人を背負って岩山と台地を下ってきたお陰で、干からびた声しか出ない。
女は微かに笑顔を浮かべて出迎えた。
「やっと来たな。待ちくたびれたぞ」
「えっ?」
あまりにも意外な言葉に、フィオランは虚を突かれた。
知り合いでもない行きずりの自分たちをなぜ待つ?
「そのラクダは? まさか俺たちのために用意してくれたなんて言うんじゃあ……」
「その通りだよ。そら、受け取れ」
もう至近距離までやって来たフィオランへ、女は手綱を寄越した。
ラクダがのそりと体を揺すって近づいてくる。
ベヒルがフィオランの背の上で仰け反った。
「わ、わあっ! ぼ、僕はラクダが苦手で……」
相変わらず空気を読まないベヒルの太股を思い切りつねり上げながら、尋ねた。
「どこからこんな三頭ものラクダを? さっきの隊商から譲ってもらったのか?」
「いや? そんな金は持ち合わせてはいない」
「だったらどこから」
「呼んだのさ。わたしの声に彼らが応じて駆けつけてきてくれた。ただそれだけだ」
「呼んだって……」
さすがにフィオランも絶句した。
女の会話についていけない。
いとも簡単に、当たり前の顔で説明してるが、全く理解の外であった。
気を取り直して、三頭のラクダをよく見てみると、どれもきちんと鞍や轡、手綱まで立派に付いている。
肉付きも良く、毛並みもいい。野生では決してない。
自然に、襲撃された夕べの記憶に導かれ、ラクダの群れを見て羨ましいと思った感情まで思い出した。
そこで、導き出された答えを恐る恐る口にしてみた。
「まさか、さ。こいつら、あのイアンとかいう異能者集団からかっぱらったものじゃないよな?」
「呼んだと言っただろう。彼らが自ら己の意思で応じてくれたんだ。わたしがわざわざ盗みに行ったわけではない」
「……そうかい」
それ以上なんて言ったらいいのかわからなくなり、フィオランは黙って手綱を受け取った。
ベヒルは今の会話にというよりも、ラクダの存在に全身を強張らせている。
「ラクダには乗ったことはあるか?」
「ああ、昔何度か。馬よりはうまくねえけど」
「彼らはよく調教されているから心配ない。前足を軽く叩いてやると座ってくれる」
女が実践してみせ、フィオランもそれに習った。
なるほど、ラクダは気が荒いとよくいうが、このラクダは大人しく、大きな体を静かに地面へ沈めてくれた。
「ぼ、僕は遠慮するよ。このケダモノに乗るくらいなら、這ってでも自分の足で歩くつもりだ」
「いい加減にしやがれ。年甲斐もなく、それ以上好き嫌いをほざきやがったら殴るぞ」
「き、きみは知らないんだ。こいつらがどんなに凶暴なのかを。気にくわない人間には徹底して攻撃を仕掛けてくるんだぞ。唾を吐きかけたり、尻尾で頭を叩いたりするのは序の口で、酷いときは小便を引っ掛けるわ、蹄で蹴るわ、最後に追いかけてきて頭を噛んで髪をむしり取るんだ!」
「おまえどんだけ嫌われてんだ」
ラクダにそこまで嫌われる人間も珍しい。
ベヒルは半狂乱になって訴え続ける。
「そのうち僕はこいつらに噛み殺されるだろう!」
「いいから乗れ、鬱陶しい」
聞く耳持たず、ベヒルの体をどしんとラクダの瘤と瘤の間に乗せてやった。
乗った途端、ラクダがのそりと立ち上がり、ベヒルは魂消るほどの悲鳴を上げた。
「ふたこぶラクダに乗っておいて、贅沢言うんじゃねえ。一番楽でありがてえ乗り物じゃねえか」
そして女の方へ改めて向き直る。
「心から礼を言うが、どうしてここまで良くしてくれるんだ?」
女に対して変わらぬ興味はあるが、今は警戒心の方が強かった。
人は誰でも面倒事を察知すれば、巻き込まれぬよう避けて通るはずだ。
しかも初対面で、ここまで親切にされる理由が分からない。
「したくなったから、そうした。自分の行いにいちいち理由づけをした事はない」
ヴィーという女は、おかしなことを聞いたという表情を浮かべる。
「街道へ出ようと歩いていると、風に乗ったラクダたちの話し声を聞いた。耳を澄まして聞いている内に、彼らが夕べの馬鹿どもの所有だと分かった。
わたしはこの先に控える長旅のために、次の隊商宿で乗り物を買う予定だったので、彼らに話しかけてみた。所有者を変えてみないか、とね。ついでに足のない、負傷もしているおまえたちの事も頭をよぎった。全員が応じてくれたが、三頭だけこうして来てもらったんだ。理由というならこれが理由だ」
「ついで……。それはどうも」
本当に気まぐれから来るただの親切らしい。フィオランが考えるような裏はなさそうだった。正直、女の話の内容をいちいち吟味する気力が今はない。
岩場の行軍で疲労困憊しているフィオランにはそれ以上構わず、女はラクダの背に乗り込み、手綱を持った。
走り出そうとする相手を、フィオランは慌てて引き留めた。
「ま、待ってくれ……ヴィー!」
手綱を引き絞られ、ラクダは足を止めた。
「長旅のためにと言ったよな? どこまで行くんだ?」
「ラダーンだよ」
これは一体どういう巡り合わせだ?
一瞬、言葉が詰まった。
「……行商人にも見えないけど、商売はなんだい?」
「質問が多いな。しかも回りくどい。もっと単刀直入に尋ねたらどうだ?」
ずばりと切り込まれてフィオランはたじろぎ、とりあえず探りを入れる態度はやめた。
「こんなド辺境から、はるばる大国まで行く理由を知りたいんだ」
答える義理はないが、女は少し間を置いた後、口を開いた。
「知り合いに呼ばれたのさ」
簡潔に終わらせ、再びラクダを走らせようとしたが、ふと女は思いついたようにまた足を止めた。
「どこへ行くのか知らんが、街道は使わない方がいいぞ。また襲われたくなければな」
「そう思うかい」
「ああ。宿場を通れば確実に足跡が残り、容易に後を追える。その逆も充分あり得る」
女が言わんとすることを敏感に察する。行動を読まれ、途中先回りし、待ち伏せする事も可能だろう。
フィオランは眉根を寄せて考えた。
「あんたなら、どう東へ向かう?」
女は少し訝しむように小首を傾げた。
「かなり旅慣れているようだから、是非助言を受けたい。この先のサジェットを通らず、東の領域へ入るには、あんたならどう辿る?」
「おまえたちはどこへ行きたいんだ?」
「あんたと同じ、ラダーンだよ」
女は少し眉を跳ね上げた。
フィオランは、先程から頭の中を巡っていた考えにとうとう決断を下した。
「つまり、あんたを旅先案内人として雇いたい。街道を通らず、なるべく人目にもつかず、その上普通の人間は選ばないような道筋ならなおいい」
思いがけぬ事を言われて、女は目を丸くした。
「それだと生きて辿り着く見込みはほとんどないな。自殺志願者か?」
からかうような口調は明らかに脈薄だった。
だが、フィオランは大真面目である。
「あんな奴らとは金輪際顔を合わせたくないんでね。自然と選択肢も狭まるということだ。別に好きこのんで地獄行きを希望しているわけじゃねえ。だが俺たちは、正規の道以外ではサジェットより東へ行った事がない。できれば信用のおける旅慣れた案内人がぜひとも欲しい」
「信用されているとは光栄だ。おまえは口説き慣れているな」
「それはどうも。……聞けば行き先も同じだ。これは何かの縁だと思って、俺たちを連れて行ってくれないか?」
縁という言葉に女は反応し、低く笑い声を漏らした。
若さに似合わず超然とした女が初めて人間的なところを見せ、フィオランは目を惹きつけられた。
「わたしに、古代の苦行者のような旅へ付き合えというのか? 物見遊山で快適に進める道のりをわざわざ捨てて?」
「悪いがあんたには似合わないと思うぜ、そんな生ぬるい旅」
「言ってくれるな」
「そうじゃないから、あんな岩場で野宿してたんだろう?」
人目を避ける事情でもあるのか、そう聞くにはまだ親交を深めていない。
だが意味は充分伝わっている。
女はラクダの上でかなり長く沈黙をした。
それを見上げ、じっと待ち続ける姿勢もまた辛い。
首の痛みを堪えて、フィオランはひたすら待った。
「条件がいくつかある」
ほっとフィオランは胸を撫で下ろした。
「なんだい? なんでも聞くぜ」
「自分の身は自分で守れ。わたしの助けは当てにするな。勝手な行動は禁止。それと、行き倒れたらそこが墓場だ」
「承知した」
内心、これはとんでもない女だと腰が引けたが、おくびにも顔には出さなかった。
「彼は無理だろう」
女は街道から外れて、草原をうろうろ歩いているラクダへ目を向けた。
前瘤にしがみつき、ベヒルが青い顔で悲鳴を上げ続けている。
「そうだな……」
自分に付き合わせてしまったせいで危険な目に遭わせ、怪我まで負わせてしまった。
前途洋々な若き司祭のためには、ここで解放してやった方がいいのだろう。
「それでどんな道筋を?」
女は、東へと伸びる街道から大きく外れた南の方角を指し示した。
その指差す方角を見て、フィオランの顔が強張る。
「南下するのか? でもあそこは……」
てっきり北を迂回するのだとばかり思っていた。
南回りで東の領域へ入るなどと、正気の沙汰ではない。
「人跡未踏の地だ。覚悟しておけ」
女は不敵な表情で微笑む。
これは決して誇張ではない。
自分は命を懸けた肝試しを買って出てしまったことを、フィオランは悟った。
しかも格好付つけて拝み倒した以上、今さら引っ込みはつかない。
この高原を境にし、南には大山岳地帯が延々と広がっている。
その先には広大な南海があるはずだが、いまだかつて山を越えて海まで生きて踏破した者はいない。
その自然環境の厳しさもさることながら、大昔は火山帯だったという一帯は、毒ガスを噴出する穴や毒性の強い川などが至る所に存在し、生き物を全く寄せ付けないのだ。
そんな土地へ、わざわざ踏み込もうというのだ。
まさに古代の苦行者の旅そのものであった。
~次作 「第二章 力の発現 2-1 地獄の一丁目」 へつづく
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

