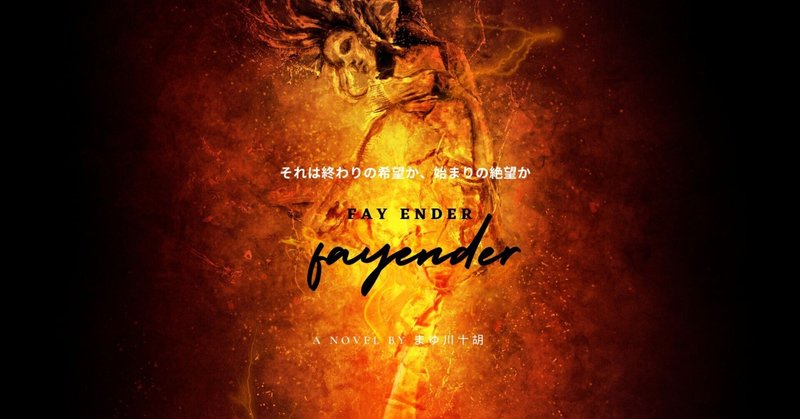
fay ender ㉙ 【本格ファンタジー小説】第五章 宿命を終わらせる者「5-2 恋焦がれる②」
第五章 宿命を終わらせる者
5-2 恋焦がれる②
( 前作 「 5-2 恋焦がれる① 」 のつづく )
「………今さら否定しても無意味であろう。だが、余はそなたも、そなたの母も、亡き者にしようと思ったことは一度もない」
今のフィオランには、目を覗きこむだけで、相手が頭の中に思い描く心象を読み取ることができる。
嘘をついているか否かはすでにわかっていることであったが、あえて王の口から聞き出したかった。
「そなたらの存在をこの国から抹殺せざるを得なかったのは、余の過失だ。ホスローが赤子のそなたを狙っていると気づいたときには、すでに手遅れであった。あの忌まわしい惨事が起き、混乱に紛れてあやつの手がそなたらに伸びるのを恐れた。そなたらを、唯一生き残っていた巫女メリュジーヌへ預け、国外へ逃がした。だが、ラダーン王宮で起きてしまったモーラ使節団の殺戮は、もはやどうにも言い逃れなどできはしない。結果、怒り狂い蜂起したモーラ一族を徹底的に征伐するしかなかった。ただせめてもの償いとして、そなたとエーティンの足取りを消し、ホスローの捜索の目から絶えず隠す工作だけはし続けてきたのだ」
ホスローとは真逆のことを王は語った。
フィオランは真実をその口から聞きたかっただけであった。
モーラが滅び、西域で利を得たのは正教会であり、ラダーンではない。
二十数年前の惨劇以来、西域でのラダーンの評判は表には出さずとも、呪詛と唾棄すべき対象と化している。
その一方、モーラ滅亡と共に西域からは太古の昔から続いた異教が排され、正教会がそれに取って代っていった。
洞窟でエリサが語った、フィオラン親子を王は守り続けてきたという話は本当だったのだ。
「なぜ、俺の命を助けたんだ? 怪物の俺が忌まわしくはなかったのか?」
言葉にするにはあまりにも葛藤がありすぎたのだろう。王は答えず、ただ必死に見つめてくるだけであった。
「………許してくれ、フィオラン」
落ちくぼんだ眼窩から覗く眼の中に、母エーティンの姿を見つけた。
赤子に乳をやるエーティンから、十歳ほどの少年へと風景が変わる。
亜麻色の髪の、利発で大人びた顔をした少年が後の王の心を占めていった。
フィオランはそれらの映像を断ち切るように、きつく眼を閉じた。
次に眼を開けたときには、心を決めていた。
「あんたには最初から息子は一人だけだったんだな。直に話してそれがよくわかったよ」
「余は―――」
「まあ、最後まで聞いてくれよ。俺は別に家族の再会を期待して、旅してきたわけではないんだ。俺が知りたかったのは、なぜこんな境遇で生きなければならないのか。それだけだったんだ。途中から、自分は果たして人間なのか? という疑問が加わったけどな。思いも寄らない形だったが、結局欲求はまあまあ満たされて、こんな有様でも俺は結構今の自分に満足しているんだ。今さら、あんたに息子として可愛がってもらおうなんて、これっぽっちも思っていねえ。ただ、な……」
老いても頑健であった王が弱々しく横たわる姿を、少し憐れんだ。
「あんたが俺の母親を愛していたとは少し驚いたぜ」
沈黙する王からラダナスへと視線を転じた。
「たしかに病を治しただけじゃあ、あんたの体は王位に就けないだろうな」
ラダナスは苦い笑いを口元へ浮かべた。
「そのことはとうに諦めている」
子を成せない王子は王位継承の資格を剥奪される。それをスタフォロス四世がひた隠しにし、完全に望みが消え去るまで事あるごとに、あらゆる治療法を試みてきたのだった。
フィオランは無言で部屋を移動し、ラダナスの傍へ近寄った。
おもむろにその両手を掴むと、掌を自分の胸へ押し当てる。そして自分の両手も同じようにラダナスの胸へと当て、そのまま動かなくなった。
王やカランドリエが息を潜めて見守る中、二人はお互いの顔を飽くことなく見つめあった。
(これは癒しの目だ)
特にこれといった感情もなく瞬く緑の眼は、ラダナスへ阿片とは違った心地よさを与えた。
別段、身体に変化は何も感じられない。電流が流れるとか、劇的に身体が楽になるとかそういった変化は一切訪れなかった。
やがて、ラダナスから手を離してフィオランは後退した。物言わぬラダナスとは違い、背後から山のように問いかけたがっている王の気配を感じて、フィオランは面倒くさそうに口を開いた。
「病の根っこを無くしてやっただけだ。病気そのものを治してやったわけじゃあない。病を完治させることができるかどうかは、これからのあんたの努力次第だろう。今までとは違って、もっと自分を大切に扱ってやればよくなるんじゃないのか? えらく時間はかかるだろうがな」
阿片漬けになっていることを、暗に匂わせた。
ラダナスはただただ絶句し、複雑な表情をしている。たまらず、王が咳き込むように訪ねてきた。
「治してくれたのか? これでラダナスは死なずにすむのか?」
「そんなこと、神のみぞ知るだ」
ここで本来の天邪鬼な性格が顔を覗かせる。
「言ったろう? 完治するかどうかは本人次第だと。俺は完治しやすいよう、厄介な根元をやっつけてやっただけだ。それ以上のことはいくらなんでも手に余る。この世にはな、出来ることと出来ないことがあるんだぜ」
黄泉の番人ラミアの受け売りだったが、自分で言った言葉にはっとした。
代価は払わねばならぬ。
その意味を、あの時に無償に気になったのだ。だからこそ、こうして王宮へ戻ってきたわけなのだが………。
「ところで、俺の仲間は………あいつはどこにいるんだ?」
ベヒルは市民たちと共に、王宮で避難生活を送っているのはわかっている。
もう一人、フィオランの相棒とも呼ぶべき、新しい存在となったヴィーのことだ。
大気と化して漂っている間も、ずっとヴィーの存在を感じていたのですっかり安心しきっていたのだ。フィオランの疑問には、意外にも王が答えた。
「彼のさすらい人のことか?」
王は言い難そうに、しばしためらった。何か隠している、そうフィオランは直感した。思考を読もうとしたが、曖昧な靄に阻まれた。
「王宮の外におる。恐らく東の庭園のどこかに」
なぜそんなところに?
胸騒ぎがした。フィオランの視線を受けて、王は言った。
「人に自分の姿を見られたくないと言っておった。そなたが戻ってきたら、居場所を教えてやれと頼まれた」
「なぜ早くそれを言わねえんだ!」
怒りに任せて叫び、同時に王の哀しいまでの身勝手さを知った。
最後の最後まで、王は自分よりラダナスを優先させたのだ。
「あんた、とことん俺を利用したんだな」
腹の底から吐き捨て、フィオランは元来た方法と同じやり方で忽然と姿を消した。
王たちの目の前で、空中に溶けこむように突然体が消えてなくなった。
王たちとは違い、超常現象に免疫のないカランドリエは魂消て腰を抜かした。
「な、な、な、何なんですか、あの人は! ば、化け物―――」
騒ぎ始めたカランドリエへ、王太子は厳しい顔を向けた。
「この場で見聞きしたことは一切の他言無用。わたしはそなたが賢明であることを信じているよ」
言葉は優しいが、動揺したカランドリエの神経を鎮めるほど、その口調にはひやりとしたものが混じっていた。カランドリエは緊張を強いられっぱなしで、噴き出した額の汗を拭いながら立ち上がり、居ずまいを正した。
「……もちろんです。王太子殿下。私は決して殿下のご信頼を裏切りはいたしません」
再び大気と化したフィオランは一陣の風となって、東へと広がる広大な王宮の庭園を駆け巡った。市街と同じように、ここもほとんどが火山灰によって真っ白に覆われていた。
ヴィーは楓の林の中にいた。雪のように白く降り積もった地面へ、ひと際大きな木の幹に背を持たれて座っている。不思議なことに、周りにはたくさんの動物が集まっていた。
その姿を見て、フィオランは血の気が足元まで引く音を遠くで聞いた。
ヴィーは、人の気配を感じてうっすらと眼を開けた。
蜘蛛のように細くて長い手足に、赤い髪を振り乱し、緑の眼を血走らせているフィオランを見つけた。蒼白になった顔にそばかすが細かく浮いていて、頼りない子供のように見えた。
ヴィーは微笑をうかべた。
「ど、どうしたんだ……どうしてこんな姿に…………」
狼狽えたフィオランは傍によって膝をつき、震える手を伸ばした。
ヴィーに寄り添っていた動物たちがぱっと離れ、遠くで様子を窺っている。
灰色やどす黒く変色した皮膚へそっと触れた。
衣服から覗く手も首も、その美しい顔さえも、腐敗しかかって無残に変貌している。フィオランの顔を見上げてくるが、その銀色の眼がはたしてちゃんと見えているのかどうかさえ疑わしかった。
フィオランは瘧のように身体が震えだし、傷つけてしまうことを恐れて自分で自分の手を掴み、引っ込めた。
「俺の………俺のせいか? 俺が目覚めたばっかりに、あんたの命を奪ってしまったのか?」
だったら、こんな力なんかいらねえ!
言葉にならない叫びが眼から迸り、ヴィーはただ慰めるように微笑した。
「力は無尽蔵ではないと言ったのはこのことか? 代償を払うってのはあんたのことか? なんでだよ! 俺の力の代償がなんであんたなんだ!
俺の落とし前は俺自身がつけるべきじゃねえのか? あの化け物の女があんたを選んだのか?」
ヴィーは土気色の唇を開いた。
声を出すのもやっとらしく、最初は息だけが弱々しく漏れていった。
「わたしが決めたことだよ。自分で選んだ死だ」
フィオランは耳をそばだてて、声を拾った。そうしないと小さすぎて聞こえなかった。
「俺は、あんたとこれから一緒に生きていくことを楽しみにしてたんだ。
勝手に決めて、勝手に納得して死んでいくなんて酷すぎねえか?
俺をこんな風にしておいて、自分だけさっさと逝っちまうのかよ。無責任すぎるぜ」
「長すぎる生に幕を下ろす。おまえが産まれたとき、そう自分で決めたのだ。おまえがこの世に必要とされ、目覚めたその時こそ、今度は自分が眠る番だと。幾たびも生まれ変わり続けながら、おまえは短命で散っていった。
その度にわたしは取り残され、ひとりで彷徨い続けてきた。もう終わりにしたい」
すまない、とヴィーは弱々しく笑った。
フィオランは胸がつかえたが、想いのたけを絞り出した。もう格好つける余裕もなくなった。
「なんでだ! 俺がいるじゃねえか! 長すぎるっていうんなら、せめて俺が耄碌するまで待ってくれたっていいじゃねえか!」
「―――疲れたんだ」
吐息なのか、言葉なのかわからない声だった。
「もう、待つのは疲れた。わたしは気が狂うほど長い時をかけておまえを待ち続けた。わたしに………死をもたらしてくれる者の誕生を」
どれだけの時をたった一人で生き続けてきたのか。どれほど孤独であったのか。それはフィオランの理解を遥かに超えていた。
じっと耐えるような、何かを待ち侘びる視線をどれほど旅の間に感じていたか、思い出した。
生き続けてくれと願うのは、永劫の時を生きてきたヴィーにとっては無慈悲であり、残酷なことは百も承知であった。
「あんたは俺に一生かけて償わなきゃならない借りがあるんだぞ。自分が死ぬために俺をとことん利用したってことだ。お陰でえらく痛い目に遭って、何度も死にかけた。悠長に死んでる場合じゃねえんだぜ」
恨み言を並べてみても、もう訪れている死は止められない。
フィオランのふざけた文句に、ヴィーは薄く笑った。
笑みを浮かべた顔が崩れ始めた。フィオランは咄嗟にヴィーの顔を掌で包み込んだ。身体の崩壊を少しでも食い止めようと。
見送られるというのはいいものだ―――。
それが最期の言葉となった。
必死にこの世に繋ぎとめようとする努力も虚しく、ヴィーの身体は一瞬にして崩れ去り、細かな塵となって大気の中へ消えていった。
永劫の時を生きてきた者にとって、死とは消滅を意味した。本来、遙か昔に土に還っているはずの自然の摂理が働いたのだ。
広げた掌にはもう何もない。温もりさえ残っていない。
怒りも悲しみも感じられないほど麻痺した耳に、鳥が羽ばたく音が聞こえてきた。
噴煙に朦朧と霞んだ月を背景にして、怪鳥が飛んでいた。
高みから射貫くようにフィオランを一瞥した後、ひと声鳴いて霞の中へと姿を消した。
~次作 「 5-3 さだめの終わり 」 へつづく
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

