
窪美澄『水やりはいつも深夜だけど』【#読書の秋2022】
僕はスーパーでレジ打ちのアルバイトをしているので、それはもうたくさんの学生、社会人、ご年配、カップル、夫婦、子供連れ、家族連れの接客をすることになる。僕がバイトを始めてからはまだ1年半ほどしか経っていないが、始めた頃はベビーカーに乗っていた赤ちゃんが今はよちよち歩いていたりする。自分の親の少し上くらいの世代の人が急に赤ちゃんを抱っこしていたりして、お孫さんなのかな〜と思ったりする。この前までポイントカードを持っていなかった若めの男女2人組が、いつの間にかポイントカードを作っていたりもする。少し前お腹の大きかった妊婦さんが、抱っこ紐をして来たりする。子供の名前を呼びながら店内をキョロキョロするお母さんを見て、多分さっきポテトチップスがある通路に入っていった子だよなぁと思ったりもする。
たった1年半という期間でも、何人もの"生活の変化"を垣間見ることができる。
この小説を読んで、お客さんを見る目が良くも悪くも変わってしまったような気がしている。執拗に人間の関わり合いとネガティブな部分が見えてきてしまう。
この小説に出てきたものでも「ママ友グループの仲」「出産後の夫婦関係」「夫婦の子供への考え方」「愛人(の一歩手前)」「親の再婚相手と連子」「嫁姑問題」。バイト先でこれらがチラついてしまう。
巻末に掲載されている加藤シゲアキさんと窪美澄さんとの対談の中にもあったことだが、僕も「結婚はあくまでスタートである」というのを感じた。結婚して、子供が産まれて、その子供が幼稚園に通いだして、さまざまなコミュニティが築かれ始め、子供の成長と共に起きる問題がそれはもうたっっくさんあって、次第に夫婦仲にも変化が起きて、離婚・再婚・不倫という結果になる人たちもいる。結婚の前と後では後のほうが良くも悪くも出来事が多いと思う。それに伴って関わる人の数も当然増えるわけで、産まれてくる子供や配偶者はもちろんのこと、新たに入っていかなくてはいけないコミュニティの中でたくさんの人と助け合わなくてはならないのだ。
ちらめくポーチュラカ

「人の親になる」ということを、自分の親も含めた多くの人がこなした結果が今である。産まれてくる子がどんな人間に育つかわからない中での期待と不安の入り混じりは、一人の大学生でしかない僕には想像が及びもつかない。
「どんな子に育ってほしいか」という問いに対する親の答えに、自分は沿えているのだろうか。
この話の語り手である”杉崎”は学生時代に女友達からいじめを受ける。そんな「女の世界」を抜け出すために大学の男子の多い学科に入り、そこで出会った人と結婚をし、就いた仕事も空気が合わずに退職し、子供を授かった結果、自身は「ママ友」という女の世界に戻ってしまった。息子の”有"が自分と同じ道を進まないように、杉崎は子育てをする。
結局、そんなことは"杉崎"の取り越し苦労であった。”有"の方は男の子でまだ5歳であるが、親の思い描くレールなんて走っていなかった。
「自分がされて嫌なことは他人にしない」という考えには欠陥がある。単純な話、他人は自分ではない。自分にとっては「されたら嫌なこと」でも、他人からしたら「してほしいこと」かもしれない。
僕は「髪の毛切ったんだね」「メガネ変えたね」とか言われるとなんとも言えない気分になる。これらの言葉も、なんてことない雑談とそのきっかけにすぎないということも十分理解している。その上で、「自分という人間が、他人の世界にも存在している」という当たり前の事実が重くのしかかってくるのだ。共感されたことは一度もないが、「俺って見られてるんだ…」とテンションが下がる。僕は「髪の毛切ったんだね」と言われるのが好きではないが、言われたい・気付いてほしい人もいるであろう。
自分が親にしてもらって嬉しかったこと。自分が親にされて嫌だったこと。色々思い返してみる。
俺は親に車で送り迎えされるのがあまり好きではなかった。
受験期に塾から帰ってきてラップに包まれたチャーハンが机に置いてあった時、すごく嬉しかった。
どれが自分がされて嬉しいことで、されて嫌なことで、理想なのか。どれが任意の他人がされて嬉しいことで、されて嫌なことで、理想なのか。
自分がされて嬉しかったことをするのが正解とは限らないし、その逆も然りである。とある子供にとって完璧な親がいたとして、その子が完璧な親になれるとは限らない。
そんな期待と不安を抜けた人々が、僕のバイト先には来ている。そう考えると、見る目が変わってしまう。
僕がもし親になるなんてことがあれば、「アンパンマンの歯ブラシが急に使いたくなくなる瞬間」を理解できる親でありたい。
言語化したくないようなレベルの理由があるということが、俺にはよくわかる。
サボテンの咆哮
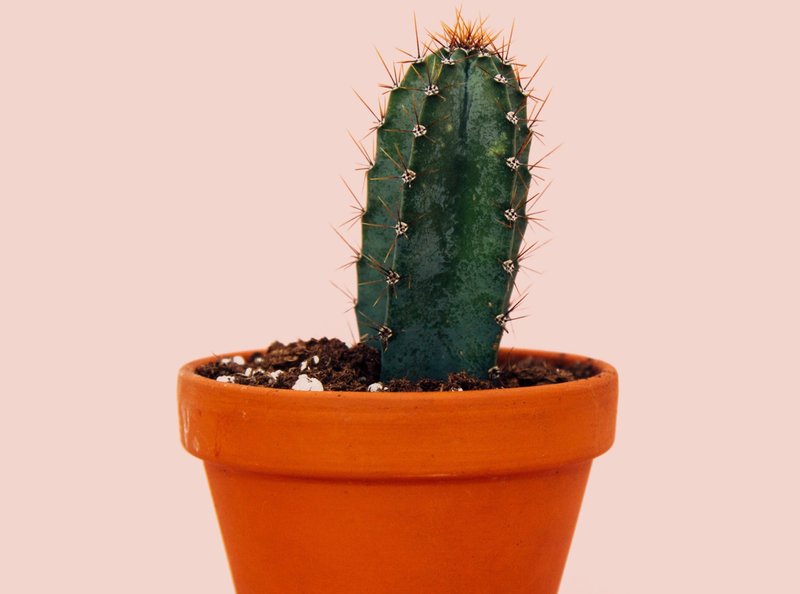
(ちなみに、この物語の語り手”武博"の妻である”早紀"は髪型を変えたことを言わないとヘソを曲げるタイプである。)
アホみたいですけど、会話って大事なんですね。
ゲンノショウコ

小説を読んで、久しぶりにボロボロ泣きました。
"風花"ならなれる。僕もそう思います。
砂のないテラリウム

この物語の語り手の"片岡"には「素知らぬ顔をして、自分が誰かから好かれているという満足感に浸りたい」という願望がある。程度の差こそあれど、多くの人が抱く種類の願望だろうと推察する。結婚前の付き合っている段階の時には現在の妻から向けられていたそれらが、出産などを経てなくなってしまった。
他者評価や自分に需要を感じてくれる人に依存した自己肯定感は、その他人の消滅と共に消えてなくなる。他者との関係がただの恋人関係なのであれば、別れれば良いだけの話である。これが夫婦関係となると全く別の話で、「サクッと離婚する」なんて選択はできない。話し合いをする雰囲気がなかったり意地が邪魔をしてきたりで価値観をもう一度すり合わせるという行為にはなかなか至れないのだろうと思う。
満たされない願望を、”片岡”は愛人で満たしてしまいたくなる。「自分に会いたいと思ってくれる女性」という存在がそれを実現に近づける。
最後に踏みとどまった”片岡”と、子供の勘のようなもの。寂しいのは自分だけじゃないのだという、わかりそうでわからない当たり前のこと。何が寂しいのかは、人によること。何に幸せを感じるかも、人によること。
"片岡"一家が、「『自分は寂しい』で良い」と僕の背中にスッと手を添えてくれた気がした。
一家が微笑ましく晩御飯を囲む姿が、僕の脳裏に浮かんでくる。
かそけきサンカヨウ

「自分のさ、一番古い記憶って覚えてる?」と僕が聞かれたら何を答えるんだろうなぁと考えてみた。
何歳の頃かあまり覚えていないが、祖父母が引っ越しをすることになった。後々聞いた話を整理すると、家の老朽化による建て壊しらしい。祖母がよく見せてくれるアルバムに写っているその家の記憶はほとんどないが、祖父母の家のトイレが紐を引いて流すタイプで音がとてつもなく大きかったことだけは何故か覚えている。祖父母の家が建て壊されている期間に祖父母に会いに行ったことがある。そこから自宅へ帰る途中、建て壊し中の家を夜中に車で見に行った記憶もある。窓を開けて眺めている時、犬が遠吠えしていたのも覚えている。
僕には場所も情景も全部頭に思い浮かんでいるんですけど、読んだ人からしたらどうでも良いですよね。
ノーチェ・ブエナのポインセチア

語り手である”陸”が言う「カタチ」という言葉がすごく腑に落ちた。
生きていくことの本質なんて、ほとんどそれだなと思った。
まだ、自分の「カタチ」を主張できるような立場ではない。
”陸”が抱えている「心臓のカタチ」。
僕も一つ、歪んだ「カタチ」に身に覚えがある。
ただ、それは誰にも言わない。信用ならないから。
それと、僕と違って”陸”は考え方がやさしい。だから、羨ましい。
#313 窪美澄『水やりはいつも深夜だけど』
#読書の秋2022
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
