
日本創生神話 伝説時代 その2 ~古代豪族~大和朝廷の成立まで つづき
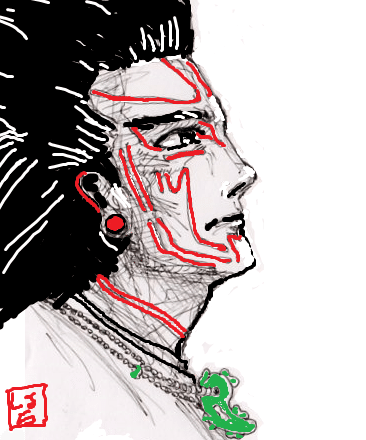
<イザナギの身体から誕生 「三貴子」> 参家の紀氏?もしくは磯城。

↓○天照大御 ノ神(アマテラスオオミカミ) 大日霎貴・オオヒムチ。イザナギの左目から生まれる。左手の白銅鏡から。イザナギから生まれた「三貴子」のひとり。イザナギに「高天之原を統治せよ」と託される。葦原中国に保食神の存在する事を知り、月読命を派遣する。のち月読に代えて天熊人を派遣する。
↓○月読 ノ命(ツクヨミノミコト) 月弓尊・ツクユミノミコト。イザナギの右目から生まれる。右手の白銅鏡から。弟に蛭児とも。イザナギから生まれた「三貴子」のひとり。イザナギに「日に並んで天事を知らしめよ」と託される。天照の命で葦原中国の保食神の下に使いするが保食神を殺害する。天照の意に反したことから追放される。
<「白村江の戦い」に唐の捕虜となった九州の王の存在で、九州王家が没落し、畿内の大王に権力が集中して大王から天皇家に脱皮したとすれば、新たな権威付けのために、九州王家の月王朝の存在は否定され、太陽王の大和政権となったと考えられ、そのため月の神の存在が希薄となってしまったのでは?>
⇔↓○建速 須佐之男 ノ命(タケハヤスサノオノミコト) 素戔嗚尊・スサノヲノミコト。イザナギの鼻から生まれる。右手の白銅鏡から。兄に蛭児とも。イザナギから生まれた「三貴子」のひとり。イザナギに「御青海之原を統治せよ」と託される。
≪個人的感想≫ イザナギ、「三貴子」に高天原を託し「淡海の多賀」に眠る(末子相続の先例となるか)。「通い婚」であることを考えれば、イザナミが畿内系、イザナギが九州系か。イザナギのケガレ落としの地となった、九州がもともとの本拠地であり、日向国の高天原を天照大神に託し、筑国を月読神に託し、海原にむかう地をスサノオに託し、スサノオは出雲に向けて旅立っていったと解釈しました。
イザナギ後裔の九州王家の政略結婚による、領土拡大、畿内進出までの長い過程を、または、天照後裔の天ノ一族の畿内入りと、統一政権設立までの繰り返しが、神話になっていると考えます。
のちにイザナギ後裔が進出した近江(滋賀県)の多賀に「古代の都」があるのでしょうか。イザナギの名を冠して、畿内国名は ⇒イシナギ⇒イソキ:磯城⇒シキ:信貴⇒志紀へと変遷するか。
磯城とわざわざ難しい漢字をあてるのは、磯=イソ と表現したかったのでは。物部守屋の根拠地「稲城:イナキ」の「城:キ」の意味も、関連があるのではないでしょうか。

【九州王朝の系譜】
稲作の伝来とともに急速に勢力を拡げ、畿内に進出するか。
アマテル 太陽神
↑[天照ノ大御ノ「神」](アマテルノ オオミノ「カミ」)
・/amateru no oumi no 「kami」。・天照皇大御「神」・アマテラス・天照坐皇大御「神」。太陽神。イザナギ後裔の三貴子のひとり。高天原を統治する。弟:須佐之男ノ「命」(スサノオ)との息に天ノ忍穂耳ノ「命」(オシホミミ)。天之菩卑(アメノホヒ)、天津日子根(アマツヒコネ)、活津日子根(少彦名・イクツヒコネ)、熊野久須毘(クマノクスビ)。
<八咫烏の系譜上でいくと、天櫛玉の父・天神魂(伊久魂・生魂)の祖・神皇産霊高魂ということになります。><神皇産霊は女神で少彦名の親。天照の先代とでも考えた方が良いのか・・(妄想。>
▽思 金 ノ「神」(オモイ カネノ「カミ」)
・/omohi kane no 「kami」。・常世ノ「神」/tokoyo。思金「神」・八意思兼「神」。知恵の神。高皇産霊神の息。天照を補佐。天孫降臨に天ノ手力雄、天ノ石別(天ノ火明)とともに従う。葦原中国に天穂日、天稚彦を派遣。建御雷の出陣要請に天ノ迦久を派遣する。息の天ノ表春、天ノ下春はともに邇邇藝命を補佐。<天ノ手力男と対をなす智の神。><大伴系の祖のようです。><「天ノ熊人」と関連するか、同一人物なのか・・。それとも「保食神」そのものか。><「思金」=シキン=磯城・「しき」に通じるか。>
▼活津 「彦」 根(イクツヒコネ)
・/ikutu 「hiko」 ne。・生根彦。天照とスサノオの息。誓約の五柱。事跡不明。
<天津彦根の流行する前は「活津」が重要な名前だったのでしょうか。><文章上で活津彦根の次に続く野夫須美神。本当は活津彦根ノ野夫須美で一人格で、「クマノ」が先入観に有り、いつのまにか別人格として分割されたのでは><活津ノ夫須美(イクツノブスミ)と結びついて熊野奇日で、双子神の熊野忍踏の存在が重複するものとして消されたのでは。><後世の誤解による文書の分割から変な感じで5柱となっているのでは?。><「彦」=官位名、根=「禰宜」など神官を現す詞では・・。>
⇔▼熊野 擬樟日(クマノ クスヒ)
・/kumano kusuhi。・熊野久須毘・熊野奇日・野夫須美大「神」・(熊野忍踏、弟神とも?)。天照とスサノオの息。誓約の五柱。
<『日本書紀』では熊野忍隅(オシホミ)命と双子神。もともと二神だったものが一つになってしまったのでは。><出雲の熊野から紀伊の熊野(牟婁郡那智)へ移住。><のちに天孫族として(大伴ノ)高倉下が紀州にいることに繋がるのでしょうか。><のちの神武世代で「奇日」の名をもつ磯城黒速との繋がりも気になります。><天ノ手力雄が天孫降臨に従い伊勢佐那県に鎮座しますが、関連ありでしょうか。「手力雄」は天ノ石別神(天ノ火明)とともに畿内に基盤を築いた重要人物のような気がします。>
▼天ノ 尾羽張(アメノ オハバリ)
・/ameno ohabari。・天之・伊都之尾羽張・「十拳剣」・稜威雄走「神」。イザナギの息。迦具土神を討つ。天ノ安河をせき止る役割を持つ。息に建御雷神。
<大陸との往来を監視する北九州の王でしょうか。「天ノ安河」=対馬あたりなのでしょうか。><のち山幸彦が十拳剣を継承し、海幸彦に「釣り針」を返す為に献上。王位に関する何かだったのでは。><動物が喧嘩の際に尾や羽が張る姿をみて、威を張る人のことを尾羽張と読んだのでしょうか。>
《個人的感想》 イザナギが黄泉の穢れを落とす。筑紫国の橘日向の小門の阿波岐原(アワキバラ)。天照の在地故郷は素直に九州なのかなあ~。参考までに、邪馬台国周辺で使用されていたとされる官位と、妥当とされる読み。
「大率」=オトド/otodo(各地に派遣される<臣従した在地の?>王)→のちのオオド?もしくは大伴の姓につながる「オオト(意富)」?、小国の「守護」みたいなものでしょうか。のちのオオタタネコや、オオノヤスマロ、それなりの王族の家系なのでは・・。
「卑狗」=ヒコ/hiko(大率の下の官位)→よくある「彦」?、名前の前に付く「彦」パターンの彦火明などの彦は「守護代」的な官位かもしれませんね。
「爾支」=ネギ/negi(大率の下の官位)→宿禰・足尼/sukuneにつながる?「支」の字が鉄剣のワカタケルの字にでてきますが、読みの「支」=「ケ」は妥当なんでしょうか。家宰や執事という感じでしょうか。
「多模」=タマ/tama(大率の下の官位)→そういえば「魂」とか「玉」のつく人物名ありますね。
「弥弥」=ミミ/mimi(大率の下の官位)→「耳」、末尾にミミのつく人物名ありますね。神武の息子達など「耳」がつくので「方面軍旗頭」的な官位なのでしょうか。
「弥馬升」=ミマ(メ)ト/mima(me)to(次官)→倭王「師升」は読みがスイショウなのに升=「ト」の読みでいいのでしょうか。地名にすれば「ミマナ」とか読みが近いかもですね。「ヤマト」でもいけそうな気がします(汗。官位ではなく役所名か。
「弥馬獲升」=ミマ(メ)ワケ/mima(me)wake(次官)→「獲升」で「なんとかの別(ワケ)」につながる言葉なのでしょうか。それとも、「ミマカナ」や「ニンナカヤ」に近い読みの気もします。役所名か。
「奴佳提」=ヌカデ/nukade(次官)→もしくはnakate?、「奴」は「ナ」の当て字でしょ
うか?。役所が地名になり、「ナガト」とか・・(妄想。もしくは「ヌカシ=ぬし=主」として残存する言葉の語源でしょうか。
「記紀」では官位がそのまま人名にとりこまれている場合があるような気がします。口頭伝承の聴き写しだから、書記した人の表現力、漢字のボキャブラリー等の問題もあるのではないでしょうか。後世の人がいろいろ解釈を加えて、同一人物が複数になったり、複数がひとりに集約されたり、現在では繋がらないものに変容してしまっているのかもしれません。

天照ノ大御神(アマテラス)→ 天ノ忍穂 耳ノ命(オシホミミ)→ 邇邇藝命(ニニギ)
①~天孫降臨の順
①はスサノオ。須佐之男ノ「命」(スサノオ)
勝速日/katuhayahi・忍穂耳ノ命 /osiho mimi no mikoto(以下、命・尊:ミコトの敬称略)
天津国(高天原国) 北九州(筑前・筑後あたり?) 筑紫?それとも 海の向こうの対馬国?狗邪韓国(金海)?
オシホ(オシオ)
②天ノ 忍穂 ノ 「耳」(アメノ オシホ ノ 「ミミ」) ・/ameno osiho no 「mimi」。・正勝吾勝・勝速日・押穂「耳」・。高天原の神。天照の息。葦原水穂ノ国に向かうが、国津神・道速振(チハヤフル)に撃退され天ノ浮橋(橋立?)から引き返す。弟の天ノ穂日、天津彦根は出雲入り。息に天ノ火明、邇邇藝。
<葦原水穂ノ国(近江?)から撤退。><大伴ノ天雷、紀ノ多久豆玉と同世代で対比されるようです。><「押穂」の名で「ミミ」は官位を表す言葉では。><八咫烏の系譜上でいくと、天櫛玉の父・天神魂(伊久魂・生魂)ということになります。><熊野ノ忍隅命(忍踏・オシホミ)との関係も気になるところです。紀伊国と関連をもつのでしょうか。「神武東征」以前に畿内への進出を試みていたのではないでしょうか。>
↑▽高皇産霊 ノ 「神」(タカミムスビ ノ「カミ」) ・takamimusubi no 「kami」。/・高御産巣日・高木ノ「神」。高天原の神。天照を補佐。娘(萬幡豊秋津師比売・栲幡千千媛)婿に忍穂耳(オシホミミ)。雉(きぎし)鳴女を派遣するが天稚彦に討たれる。天稚彦を討つ。娘・萬幡豊秋津師比売の婿に忍穂耳。
<九州の王?><大伴系の祖のようです。><高魂命-伊久魂命-「天押立命」に至る系譜の高魂命の一代前が高皇産霊ノ神なのでは。春日ノ津速産霊と同一人物では。その系譜を引くものにより天ノ穂日の息・天ノ稚彦が討たれたのでは。>

ヒアケ(ヒアキ)
<邇邇藝の弟の系譜>
③↓▼天ノ 火明(アメノ ヒアカリ) ・/ameno hiakari。・(大伴ノ日明)・彦火明「命」・安国玉「主」・天ノ石門「別」・天ノ押立・天ノ忍立。高天原の神。忍穂耳の息。高皇産霊神の孫。邇邇藝に先立ち天孫降臨。室に大国主の娘・天道媛。息に天ノ香語山。忍穂耳により葦原中国(近畿?)の春日ノ市千魂に代わり国主として派遣される。
<大伴の祖となります。><「彦火明命」と同一人物?大国主の娘婿か。><この人物が海部、尾張氏の祖の彦火明命(彦火照命)とすれば『海部系図』の天火明命との矛盾もすっきりでは?><ならば、息に大伴ノ天香語山・高志神彦火明命。孫に天村雲、大伴ノ高倉下。大伴、海部(アマベ)氏、尾張連の祖。><最初の遠征で父の撤退後も天ノ橋立に残されるか?><それとも父のルートとは別に南海道を東征して天津国(畿内)に降臨?。><押帯や足帯やらに通じる名を冠して、大王だったのではなかろうか、という人物です。><ニニギの別名・天ノ火照(ニギハヤヒ・物部祖)と、天ノ火明(ヒアケ・大伴祖)は別人かと。>
天ノ火明の五伴(五重臣)
▽天津 赤麻良(アマツ アカマロ) ・/amatu akamaro・あかまら。天津勇蘇(アマツユソ)・天曾蘇・天蘇蘇・アメノソソ。筑波蘇蘇の息。天ノ火明の五伴(家臣)。同僚に天津赤星。
<笠縫部の祖。><アカマロ=赤銅らしいです。神武の大和入りに赤銅八十師が登場しますが・・。子孫か。>
↑▽天津 赤星(アマツ アカホシ) ・/amatu akahosi。(古葛城)・葛城ノ赤星。葛城一言主の息。葛城勝手の弟。天ノ火明の五伴(家臣)。同僚に天津赤麻良。<天津甕星と関連ありか。>
▽天津 麻良(アマツ マロ) ・/amatu maro・まら。物部。叔父に天津羽原。天ノ火明の五伴(家臣)。
<物部氏・大庭造の祖。><子孫がニギハヤヒと縁を結ぶか。>
▽天津 富々侶(アマツ ホホロ) ・/amatu hohoro。天津羽原・十市羽原・天津真浦・十市真占/toimaro。甥に天津麻良。天ノ火明の五伴(家臣)。
<十市部の祖。富々侶=トトロとも読めなくもないw。><物部と十市の先祖の血が近いということでしょう。>
▽天津 赤占(アマツ アカウラ) ・/amatu akaura・あから。為那都比古/inatubiko。天ノ火明の五伴(家臣)。
<為奈部の祖。>
《個人的感想》 大伴氏の祖「天押立」の系図をたどると、安牟須比命ー香都知命─天雷命─天石門別(安国玉主)。天石門別は天ノ火明とも。ここで問題なのが、安牟須比命と(金海伽耶・首露王第五王子。母許黄玉)が同一人物説があるということです。
あちらの金海王家の系図をみてみたいものです。日本の方は単純にオムスビとか和風なところからきてたりして・・。それが何かの事情で結びついたりとか・・。前方後円墳とかの関連も有りますけど。
そもそも、新羅(ワイ・カイ族)により追われた百済(旧・辰族)の民が渡来していたのなら、現在の南半部にいる人達は何処から来た人なのだろうという、根本的な疑問が解消できていません。
─大伴氏が朝鮮半島にいつのまにか地盤をもってることが矛盾がなくりますが、では古代朝廷の王族は金海が本拠?発祥地?ということになってきますね・・。
始祖・首路王が0世紀の人物なら、日本の神話時代が限定されてきますが、そんなに新しいところで日本神話が始まるもんだろうか・・と思わなくもないです。縄文時代は1万年前くらいから始まってますし・・・。稲作は0世紀よりもっと早いし、国は既にできて乱立していたでしょうし。
在地の王と外来の王の婚姻で、血を結んで王権が強化されたのでしょうか。
しかし、金海伽耶や首露王と世代をあわせようとすると、大国主17代と、時代(世代)にかなりの無理が生じるような気がします。安牟須比命=首露王第五王子というのも具体的すぎて、どうかな・・。やはり異国のものを持ち込むと混乱しますね。根本的に時代・世代が違うのではないでしょうか。大国主が17代も相続されていたとすれば、スサノヲの時代はもっと古い神話なのでは・・。>

▽「建」 御雷(タケ ミカヅチ) ・/「take」 mikazuchi。・「武」 甕槌・(大伴?)・「建」御雷之男「神」・鹿島「神」。高皇産霊神の系譜。イザナギに十拳剣で刺されたカグツチ神から誕生する(馬術師範・天ノ尾羽張(伊都尾羽張神・稜威雄走)の息)。忍穂耳(オシホミミ)の将。天ノ迦久が出陣要請の使者。伊那佐之小浜に上陸。信濃諏訪にて建御名方との戦いに勝利し、父の大国主からの国譲りを実現。ニニギが降臨する。のち鹿島ノ神。
<子孫の大伴ノ高倉下のもとに剣のことを知らせる。><大伴氏の祖ということになりそうです。><子孫は神武から大々杼の姓を与えられる。><「鹿島ノ神」=常総地方の中臣氏の氏神。出雲振根の討伐で常総の兵士が活躍したのが後世、経津主の軍功を横取りする結果となったとか・・(妄想。><山陰道を東征?><分身は十握剣とも。><分身は佐士布都神という神剣とも。下の経津主の事でしょうか。><大伴=中臣=物部は長い歴史の中で婚姻関係を重ねているため、ほぼ一門一家ということでしょう。他の豪族では、あの蘇我と 物部でさえ縁戚ですから(汗。><天ノ岩戸の神、伊都尾羽張神の息。大伴の祖と関連がありそうです(妄想。><天ノ安川の地で水を塞き止め往来を支配する。>
▽天ノ 迦久(アメノ カグ) ・/ameno kagu。・天ノ香具。天照に出仕。建 御雷の元に出雲出陣を促す使者。
<天ノ香語山と関連がありそうな名です。迦具土神は天ノ尾羽張により討たれ、迦具土神から御雷神が生まれ、御雷神を説得できるのは天ノ迦久のみ。迦具土と迦久に特別な関係がありそうです(妄想。>
▽「建」 経津(タケ フツ) ・/「take」 futu。・「武」経津・「建」布都・(大伴?)・香取「神」。高皇産霊神の系譜。イザナギに十拳剣で刺されたカグツチ神から誕生する。忍穂耳(オシホミミ)の将。大国主の国譲りを実現させた。妹(浅香媛)婿に春日ノ居々登魂。甥に春日ノ押雲。
<御雷ノ神は布都主の武将のようです。タケミナカタとの決闘でミカヅチの活躍のみが有名になったようです。石上神宮に布都御魂。><「十拳剣」=別名・天之「伊都之尾羽張」=九州伊都の王もしくは尾羽張から、東海道の王を指すか。><海神・豊玉彦の息が振魂命。フツ、フルに通じるものを感じます。>
▽天ノ 鳥舟(アメノ トリフネ) ・/ameno torifune。忍穂耳(オシホミミ)の将。出雲平定に派遣された三神将のひとり。
<「鳥」の名をもつ王家の祖でしょうか。天ノ夷鳥(出雲国造の祖)との関係が気になります。>
▽「建」 葉槌(タケ ハヅチ) ・/ameno haduchio。・天ノ羽槌雄(アメノ ハヅチオ)・天ノ羽雷・天ノ羽富・倭文神(シトリノカミ)・はつち。天ノ日鷲の息。忍穂耳(オシホミミ)の将。建御雷の跡を受けて常陸の邪神・↓天津甕星(香香背男)を討伐。
<倭文と、渡来系の西文(西漢文)、東文(東漢文)の意味は。のちの坂上田村麻呂とのつながりが気になります。><鹿島神と中臣の縁を考えると、大伴氏が常陸まで遠征していくなかで、宇佐・春日・鹿島の神事で春日系中臣氏が重要な位置にあったのでしょうか。><大伴氏の先祖に天ノ雷命がいますが、雷を名に持つ人物は、なにか関連があるのでしょうか。><天ノ日鷲は神武期の将ですので世代が合わないです。日鷲を古い時代の人物とみて、神武期に天羽槌雄とみるべきか。><「羽」の字を持つものとして、建御雷神の父・天ノ尾羽張との関連も気になるところです。><足名椎、手名椎の系譜の人物でしょうか。>

(壱岐・一志国)宇佐神宮へ
月 夜見(ツク ヨミ) ・/tuku yomi。・月 読・宇佐・(筑 夜見)・月弓・月夜見尊。天照の弟神。スサノオの兄。「保食神(ウケモチ)」を殺害し穀物を得るが姉「天照」に行状を非難され追放される。
<稲作の伝来に係わる人物なのでしょうか。><月読命─伊吹戸主命─宇佐津彦命─「宇佐津姫」・春日ノ種子へと繋がるようです。><月(ツキ)で筑紫(ツクシ)と関係ありかも。><夜は、「邪」や阿夜の当て字なのでは、見は官位の「耳」に通じるもののような気がします。>
<月支国に関連する神か・・。ツキとヨミの2国を統括する神だったのでは・・。アマテラスに従い、出雲地方の様子を監督に行ったのか。ヨミに対抗する勢力で当時の出雲は二分されていたのでは・・。>
(葦原中国)畿内の土着神。
葦原水穂国の「穂(保)」に、食(しょく)=磯城(しき:三輪の豪族)、その先祖では。
保食神(ホノシキノカミ) 穂ノ磯城ノ神・ほのしきのかみ。別名:宇氣母知能加微 ( うけもちのかみ )・宇都志枳阿鳥比等久佐 ( うつしきあおひとくさ )。イザナギ・イザナミ意外の神を産む創造神。天照神の統治する高天原のライバル、葦原中国の主神。雑穀の神々を産む。
<「大宜都比売(オオゲツヒメ)」の伝承と重複する神。イザナギ・イザナミの後裔どうしで、王位継承の騒乱があったということか。><古事記と日本書紀により保食の神の名が違います。>
飯神(メシノ カミ) 目支ノ神。
<「大宜都比売」の兄「飯依比古」に通じるか。>
魚神(ウオノ カミ) さかなのかみ。
<「鮭・サケ」の神なのでしょうか。>
毛鹿毛柔神(エミカエミニノ カミ) 恵美ノ邇ノ神。
<音的にはミカヅチに通じる名のように聞こえます。>
供神(トモノ カミ) 饗神。
<供する⇒大伴氏に通じるか。>
牛馬神(ギュウバ) 保食神の頭頂(頭髪)から生まれる。
<「牛頭天王」の意味か。>
粟ノ神(アワ) 保食神の頭から生まれる。
<葦原中国の影響力は四国・阿波に及んでいたということか。>
稗ノ神(ヒエ) 保食神の頭から生まれる。畑作の神。
<九州の火ノ神に通じるか。穀物名は、各地域の主力生産物の意味か。>
麦ノ神(ムギ) ばく。保食神の頭から生まれる。畑作の神。
豆ノ神(マメ) ず。保食神の頭から生まれる。大豆・小豆の神。
蚕ノ神(カイコ) さん。保食神の頭から生まれる。養蚕の神。
≪個人的感想≫ 日本書紀の編纂者が朝鮮語に通じ、順番と肉体の部位を対応するように表記したとありますが、
古事記の方でアイヌ語などとは検討してみたことはあるのでしょうか。なにかしら相違があるような気がします。
そもそも、日本語で記されたものを外国語で読む必要があるのか?という、疑問が湧きますし、度々の戦争によって人も行き来してますし、自然にあちらに日本語が残る場合もありますが、それは考慮されているのでしょうか?。前方後円墳の様に残された言葉もあるのでは?
古代朝鮮語と、今の朝鮮語って断絶せずに繋がっているのでしょうか?。
百済や伽耶の人々が生き残っているでしょうか? 北のカイ・ワイ族に飲み込まれてしまっているのでは?
単純には言い切ることが出来ない言葉の歴史があるんじゃないでしょうか?
天熊人(アメノクマヒト) 天ノ熊人・あめのくまひと。天照神の重臣。月読神の失脚後、使者として葦原中国に派遣される。保食神から穀物の種実を授かる。高天原に持ち帰り稲作を伝える。
<熊襲の人の意味か。山神に通じる熊人か。それとも熊彦という人物か。>
「顯見蒼生」現世に神が現れた。
天邑君(アメノムラキミ) 天ノ邑君。イネの栽培に成功し、天狭田(アメノサナダ)にて人民を統治する。
<天ノ狭田は、天ノ真田・神田とも。天ノ長田とも。>

《個人的感想》 『古事記』の読み方は、根本的に間違っているのではないのか。王統の系譜を本来は表したかったのに、のちの読者が
物語調に解釈して、意味をはき違えているのではないのでしょうか・・。
記憶術の中で、良く知る言葉の音にのせて暗記する方法を、阿礼が行っていて、安麻呂は、意味を考えてくれと、
子孫に託しているのではないでしょうか。
現在に伝わる江戸時代からの『古事記』研究の解釈方法ではなくて、根本的な内容の検討・研究方法に立ち返らないといけないのではないでしょうか。
読みを学ぶのではなく、意味を考える学問に立ち返る時期かと・・。
また、「天ノ邑君」とはまさに「阿毎君(天皇家の祖)」のことではないのか。
穀物神の神話が、記紀で神名の記載が違うのは、ふたつの王朝の都合上。
『古事記』にあることがオリジナルで、『日本書紀』にあることが王朝交代の正統性を主張するために作為的に付加されたものではないだろうか。
「粟」と、「稲」。伝来の重さは、古代王家にとって重要なのでは。
古事記では粟、日本書紀では稲に置き換えられているのでは?
畿内「大国主」の系譜は、九州のものへと入れ替わり、その後、
天孫降臨後、王の変遷は、関東に逃れた建御名方→これを追討した建 御雷→天津甕星(香香背男)→天ノ羽槌雄ということでしょうか。
滋賀県でのオルドス短剣鋳型の出土は、ある伝説を裏付けるものでは・・。
(装飾がシンプルなことから否定する意見もありますが、可能性としてあげておきます。)

重要人物⇒呉太伯 (*)姫・泰伯。周の古公亶父(周文帝の祖父)の長子。弟・虞仲と共に周を出奔し句呉国を建国。<周は文公の息子・武帝の代に殷を倒す。呉に出奔した太伯の後裔は倭に渡るとも。太伯兄弟が周朝を継げなかったのは、母系に異民族の血があるためか、殷(商)、三苗族の血のなにかしら理由(末子相続の風習?)があるのでしょう。呉の一般人は夏王朝に追われた元黄河流域の先住民・三苗族。モンゴロイドの深い歴史の闇があるような・・。滋賀県の続報が気になりますね。>

【畿内王朝の系譜】国津神:畿内から以東
(刺ノ国) 山陰地方伯耆国から因幡の近隣?とりあえず出雲よりも東の国でしょう。
《個人的感想》 出雲の根・枝(刺と同義?)からきてるとすれば、紀州の木など木に関連する信仰を象徴する国名でしょうか。刺=sasi=高志とも似た言葉です。神武の命で越に大伴氏が攻め入ったという伝承につながるか。
もしくは、サシノクニ=サ行のスとして解し諏訪(スワ)・信濃国(シナノノクニ)、二国を刺ノ国と範囲と考えます。
▲刺国 大「神」(サシクニ オオ「カミ」) ・/sasikuni ou「kami」。娘婿に天ノ冬衣神。孫に八十神、大国主。
<生駒や信貴山のオオカミ信仰とかにつながるのでしょうか。>
天ノ 冬衣(アメノ フユギ) ・/ameno fuyugi。出雲、スサノオ系の神(大国主の系譜の5世)。淤美豆奴神(大国主の系譜4世)と布帝耳神(布怒豆奴神女)の息。室に刺国若媛(佐志久斯和可媛)。息に八十神、大国主(オオナムチ)。
<大伴氏の関係者か。><母に布怒豆奴神女、「神女」きたっ!><父・淤美豆奴神は「近江津ノ神」とでも読めるか、母の布怒豆奴神女は「布都津ノ神女」などでしょうか。>
[刺国 若(媛)](サシクニ ワカ(ヒメ)) ・/sasikuni waka(hime)・刺国稚姫。大国主の母。神産巣日神、五十猛とスサノオに大国主を預ける旧縁を持つ。
<信濃国諏訪に墓地。>
▽刺国 ノ 八十「神」(サシクニ ノ ヤソ「ガミ」) ・/sasikuni no yaso「gami」。大国主の兄。因幡の八神媛に求婚。伯耆国西伯郡の手間山にて赤猪の大石を用い大国主を討つ。
<八十神はたくさんいる兄のことらしい。>
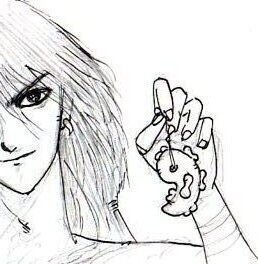
⇔↓▽大国 「主」(オオクニ 「ヌシ」) ・/oukuni 「nusi」。・大穴牟遅/ounamuchi・オオナムチ。・大己貴・刺国ノ大汝・葦原志挙乎・伊和大「神」・(「八島士奴美」、敬称?)。スサノオの子孫・天ノ冬衣「神」(大国主の系譜5世)と刺国若媛の息。因幡八上媛の婿(息に木俣神)。兄・刺国八十神に追われ出雲(根国)入り。スサノオ系の豊葦原水穂之国(近畿・近江?)、葦原中津国(出雲?)の神。スサノオ直系のスセリ媛の婿となり葦原ノ色許男・宇都志国玉とも呼ばれる。大国主の系譜6世。のち高志(越)国の沼河媛を室に迎えるとも。息に事代主、建御名方。
<分身は「国平の鉾」。><出雲の神というよりは出雲を足場に畿内に国を築いた王のように思えます(妄想。><初代大国主の名「八島士奴美(ヤシマシヌミ)/yasima sinubi」の名は、近江源氏の八島荘の地名として残るのでしょうか。>
以下、心苦しいですが、「神(かみ)」や「命・尊(みこと)」など尊称、敬称できるだけ略させていただきます。
弥生時代後半というよりは、許されるなら象徴的なもの青銅器・銅鐸時代と呼んでもよさそうな感じです。
天孫降臨までの出雲・大国主系の神話は・・ 北の国の神話 クルの神々 奥州蝦夷の豪族と軍団

ここから先は
¥ 100
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
